こんにちは、筆者です。
みなさんは自分の「信念」というものをもっているでしょうか?
今回の記事は「信念をもっている人」に向けたものではありますが、これから信念をもとうとしている人も、今はまだ「信念」というのがなんなのかわからない人にも参考になると思います。
仕事を行っている中で、自分の「信念」というのを貫くことが困難に感じる時があります。
そんな時に、「信念を貫く」方が良いのか、「信念を諦める」方が良いのか、迷うと思いますが、筆者はどんな状況でも、自分の人生の中で見つけた”信念”を諦めるべきではないと考えます。
この記事では、そんな仕事の中で自分の「信念」が揺らぎそうになった時にみて欲しい記事になっていますので、ぜひ、参考にしてみてください。
この記事でわかること
・自分の信念を貫くのが難しいと感じた時に参考にした方が良い人物
・ある実業家の人生
・信念を貫いた人の名言

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験
- 吃音症歴20年
- 元オートローン営業マン
- 元オーダースーツフィッター
- 元百貨店販売員
- 現Webマーケター
- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味
- 酒は飲めない、よく体調崩す人
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
自分の”信念”を貫くのが難しいと感じたら

仕事の中ではよく、自分の人生を通して得た「信念」を曲げなければいけないのではないだろうか?と思ってしまう状況がでてきてしまいます。
・会社の方針が自分の信念に反するものになってしまった
・上司から指示されたことが自分の信念に反すること
・営業成績のために自分の信念を曲げなけれいけないのか
など
仕事において「雇われ」という立場の場合は特に、自分の信念を揺るがすほどの圧力がかかる時があります。
ただ、このような状態であっても、曲げようにも曲げたくないものが、それまでの人生経験を培って得た、信念というものです。
この”信念”を貫くのが難しいと感じたら、一人の、”信念を最後まで貫き通した人物”を思い出してみてください。
”金”よりも”人”を重視した実業家

ある一人の、信念を貫き通した人物とは、「出光佐三」さんという実業家です。
この方は、ガソリンでお馴染みの「出光石油」の創業者であり、戦後の日本を復興した第一人者です。
筆者が「出光佐三」さんを知ったのは、小説の「海賊とよばれた男」を読んだのがキッカケです。
この小説は、「出光佐三」さんと「出光石油」の半生をフィクションを絡めながら、ドラマティックに書かれているものなのですが(ちなみに映画にもなりました)、筆者が車屋さんの社長から勧められて読ませていただいて読んで、ものすごく感動した本です。
何が感動したのかというと、のちほど詳しく紹介しますが、「出光佐三」さんの大事にしていた”考え”と、その”考え”に基づいた”行動”が、まさに筆者自身が漠然と思っていた、大事にしていきたい価値観と同じだったことです。
この本に書かれてある出光佐三さんの「考え」というのが「信念」だったのです。
筆者が同意して、紹介したい出光さんの信念の中に、「金よりも人を重視する」ことを基盤としたものがあります。
現代の実業家といえば、「金持ち」というのが大きなイメージですが、そのイメージとは大きく乖離する信念は、果たして実現可能だったのかという疑問を感じますが、出光さんはそれを最後まで信じ、さらに、体現しています。
そんな、出光さんの人生で起こった出来事の中で、特に「信念を貫く」ということが出来ることと、信念を貫くことの大切さを実感できるものをピックアップして紹介していきたいと思います。
出光佐三さんの人生

出光佐三さんの人生は、まさに波乱万丈と表してもおかしくありません。
小説や映画ではフィクションも含まれていますが、現実の出光さんの人生は、小説や映画で表現する以上に、様々な出来事が起こっており、「出光さんは自分の信念を貫けるの?」と疑問に思ってしまうような境地にも何回も陥っていることがわかります。
そんな出光さんの人生から、「信念を貫く」ことが出来ることと、貫くことの大切さについて知ってもらえれば嬉しいです。
以降の記事は本「出光佐三 反骨の言霊-日本人としての誇りを貫いた男の生涯- 著:水木 楊」を参考に執筆します。
ハンデを背負った人生の始まり
出光さんは生まれながらに、病弱で、薬を飲んで医者通いが多かったそうです。
病弱であるが故に、体育の授業では集団から遅れ、ついていけなかったり、学校の出席日数も足りなかったりしたそうです。
そして、人生通してハンディキャップとなる出来事にも遭遇してしまいました。その出来事とは、小学2年生の頃に目を傷つけてしまったという出来事です。
草の葉で瞳孔を傷つけてしまい、そこから菌が入ってしまい、どんどん視力が落ちてしまったそう。
視力が落ちたために、普通の子のように読書をすることができなくなってしまったらしく、勉学に支障をきたすこととなってしまっただけではなく、その後の人生にも影響する大きなハンディキャップを負ってしまったのです。
当の学問はというと、当時の教室の座席順は成績の良い順だったらしいですが、出光さんの悪さから、いつも後方になってしまっていたそうです。
当時、小学校卒業後は、父親が働かせようとしていたそうですが、出光さんは小学校卒業後、商業学校へ進学を希望したそうで、父親の反対を押し切り、福岡商業に合格。晴れて、福岡商業の学生となったのです。
勉学で不利なハンディキャップがあろうとも、自分が望む道を実現するためにハンディをもろともしない精神は、この後の「自分の信念を貫く」に繋がっていくと感じました。
「商売は金儲けではない」ということを学んだ学生時代
出光さんは、福岡商業へ入学したのち、1年生の頃は成績が2番、2年生の頃はトップ、3〜4年生の頃は3番目という小学生時代とは比べ物にならないほど、好成績を収めています。
これは何があったのかというと、本が読めないから、本に書かれてあるほんの少しの内容をヒントに「考えに考えて考え抜いた」そうで、記憶力が抜群であったということもあり、好成績を収めたそうです。
そんな好成績を収めてはいましたが、当時の福岡商業内での「身分差別」に辟易していたそうです。
そうして、出光さんは福岡商業卒業後、神戸高商へ進学し、この学校の校長先生である「水島銕也」先生から、出光さんの生涯を通して信念となり、実現していくこととなる、「黄金の奴隷になるな。士魂商才をもって事業を営むように」ということを学びました。
当時は、日露戦争に日本が勝利して、経済的にバブルの状態であり、あちこちに成金趣味があったり、株価が高騰しており、拝金主義が蔓延っていたそうです。
神戸高商に商工会議所の会頭が講演に来た際に、「商売とは金儲けであり、金がなければ商売は成り立たない。金がなければこの社会では何もできはしない。儲けること、それが全てだ。」ということを出光さんは聞いて、憤慨したそう。
そして、「黄金の奴隷になるな」「士魂商才」という信念以外にも、水島先生からは、水島先生の生徒への献身的な態度から、「人間尊重」を学んだと言っています。
もう一つ、出光さんが生涯を通して、実現しようとする”信念”の一つである、「生産者と消費者を直結して、相手の利益を考えながら物を配給する」というものも、神戸高商時代に、これは「内池廉吉」教授から出光さんは学んでいます。
これらの神戸高商で得た信念を元に、出光さんは卒業論文で当時主流だった石炭を元にするエネルギー生産に対する「石油の可能性」を示唆していたのです。
神戸高商卒業後、出光さんは他の生徒が有名企業や今後成長するであろう商社に就職を決める中で、なも知らぬ零細企業で「丁稚」から仕事を始めることにしたのです。
これにはちゃんとした背景がありました。
それは、将来の独立独歩のためと、独立後に仕事をこなせるように、仕事を一から覚えるため、さらに、卒業論文で書いた「石油」に少しでも触れるため。という思惑があったのです。
出光さんが決めた企業である「酒井商店」では主に小麦粉と機械用の円滑油を取り扱っていた。
この一連の出光さんの学生時代の出来事から、自分の「信念」を見つけることと、その見つけた信念を「どう実現していくか」を実際に考え、行動に移しているということを学ぶことができます。
つまりは、「信念」を諦めるのではなく、「信念」をどう実現していくか?に注力していたことがわかります。
会社創業時の倒産危機
出光さんは、酒井商店で働いたのち、27歳で「日田重太郎」さんの力を借り、独立しました。
この「日田重太郎」さんとは、どういった関係だったのか?といいますと、出光さんが独立をするための資金を提供してくれた人なのです。
日田さんとは日田さんの息子さんの家庭教師を出光さんが勤めていたという接点がありました。
日田さんは出光さんの真面目でたくましいさま、ストイックな雰囲気を気に入って自分の息子の家庭教師をお願いしたのです。
そして、日田さんは出光さんに6千円、現代でいう8,000〜9,000万円ほどのお金をあげたのです。
その時に、日田さんはお金を渡す代わりに「従業員を家族と思い、仲良く仕事をして欲しいこと」「自分の主義主張を最後まで通すこと」「自分が金を渡したことを誰にも言わないこと」の3つの条件を提示したそうです。
ここで大事なのが、日田さんが提示した1つの条件が出光さんが学生時代に得た価値観と一致していたということです。
そして、「自分の主義主張を最後まで通すこと」ということが、さらに出光さんの「信念」を通して、自分のするべきことに向き合うということに拍車をかけたことがわかります。
ただ、その確立された信念、日田さんからの援助はありつつも、事業はなかなかうまくいきませんでした。
次第に日田さんからもらった6,000円も減っていき、そこを尽きつつあり、商売を諦めつつあったといいます。
ですが、日田さんからは「初心を貫け」という言葉をもらい、そして、言葉だけではなく、その後、出光さんのために、さらなる資産を提供したり、保証人になったりと、まさに奉仕の精神で出光さんに尽くしたといいます。
この出来事が、のちに出光さんが信念の一つとする「陰徳の精神」を確立し、日田さんとの約束の一つである「資金を投じたことを他言しない」の約束を破りながらも、従業員に語り継いだといいます。
出光さんは独立後の店の存続の危機に瀕死ながらも、日田さんの助けを借りつつ、日田さんから「信念を何があっても貫くこと」を学んだ出来事だったのではないかと感じます。
戦後、信念の体現
戦後、出光さんは各戦地から引き揚げてくる、約千名の全社員を一人も「馘首」つまり、”クビ”にしないという決断をしたのです。
内地はほぼ更地になっており、事業を再開しようにも、戦後ですからそう簡単にはいかないですし、やすやすと仕事が転がっている時代ではないにも関わらず、社員を一人もクビにしなかったそうです。
出光さんはこの苦難な状況の時も、役員から猛批判をくらいながらも、ずっともっている「人間尊重」の信念を曲げない、貫き通すことを選んだのです。
この時の出光佐三さんの年は「61歳」。ここにきて全くの0からのスタートになってしまった、いえ、むしろ、仕事がないのにも関わらず約千人の社員を養わなければいけないのですから、マイナスからのスタートと言ってもいいでしょう。
そんな苦境でも出光さんは「人間尊重」の信念を貫いたのです。
日章丸事件
昭和24年1月、将来的な石油販売の自由競争のため、石油配給公団という石油の卸売業務を行っていた政府機関を解散させる方針を固めました。
これにより、当時の卸売業者、つまり、元売り業者は民間企業に引き継ぐことになったわけですが、この時に「元売り業者」になるには、「太平洋沿岸にタンクを持つ会社に限定する」という条件があったのです。
出光さんは、学生の頃よりもっている信念の一つに「生産者と消費者を直結して、相手の利益を考えながら物を配給する」というものがあったため、この石油の「元売り業者」になることは、必須であり、これを実現できなければ自分の”信念”を現実化することができなかったのです。
ただし、出光さんは、この時戦後の影響もあり、タンクを購入する資金が全くない状態。そんな会社存続と、自らの信念の実現が叶いそうにない境地に立たされていながらも、なんとか資金を調達し、タンクを購入することができたそうです。
ですが、また、新たなる壁が誕生しました。それが、GHQが打ち出した「消費地精製主義」というもので、これは、「日本に原油の形で持ち込み、国内の精油所で精製して製品にして販売する仕組み」です。
で、この時は、国内の石油会社は出光以外の大多数の企業が外油の傘下にあり、さらに、原油は海外から調達することもあり、完全に、外国至上主義の国内石油会社にすごく不利な主義だったのです。
この新たな逆境に、出光さんはどう立ち向かうかを思案した時、「タンカー建造」に至ったのです。
これが、映画「海賊とよばれた男」でも登場した「第二日章丸」です。
「第二日章丸」を建造する上でも、海運会社とタンカー建造権利を巡ったり、国内の石油会社からの批判を受けながらも、出光さんが信じ、実現しようと考える「生産者と消費者の直結」を実現しようと奮闘しました。
「第二日章丸」ができてからというものの、海外からの石油輸入はうまくいき、「元売り業者」としても運営することができるようになった矢先、またも外部からの妨害があります。
その妨害者が「外油企業」です。「外油企業」は出光の石油輸入を妨害して、原油を輸入させないようにしていましたが、出光さんはこれをうまくかわすために、ゲリラ的に原油を輸入することをやって、またしても、自分の信念の実現のために行動したのです。
そして、ここでやっと「日章丸事件」に触れてきます。
「日章丸事件」のことの発端は、イランより出光に直接「イランの石油を輸入してくれないか」という提案を受けたことがことの始まりです。
この時、イランとイギリスは大きな対立をしていました。
その対立とは、イギリスがもつイラン国内の石油産出地をイランが国有化してしまったという事件が対立の原因となっています。
当時、イギリス人のウイリアム・ダージーという人が、イラン国内で原油を掘り当て、その原油を元に「アングロ・ペルシャ石油会社」(アングロ・イラニアン社)を設立。
このアングロ・イラニアン社は後に世界第三位の石油会社にのしあがり、イギリスに国有化されました。
ですが、この後、イラン国内でクーデターが起き、モハメド・モサデクが政権を握り、このイギリスが国有化している会社の原産地を国有化してしまったのです。
つまり、「イギリス人がイラン国内で掘り当てた原油で大バズりして、とてつもない石油会社を設立し、それをイギリスが国有化したんだけど、イラン国内の政権が変わって、その石油産出地をイランが国有化してしまったよ」という事件が起こり、イギリスとイランの対立が起こってしまったのです。
これは一見すると、「イギリス人が掘り当てた石油産出地なんだから、イランの国有化はおかしい!」と見えてしまいますが、イランがなぜ国有化してしまったのかという背景には、イギリスの過度な「搾取」が原因だといわれています。
この搾取により、国内の生産物からの利益のほとんどをになっている石油からの利益が大きく減ってしまい、イラン国内では栄養失調者が多数発生してしまったこと、国民の大きな経済格差を生み出してしまい、イラン国内は瀕死の状態に陥ってしまっていたのです。
このような状態があり、イランは出光に「石油を輸入して欲しい」ということを頼んだのです。
そして、出光さんはイランの悲惨な状況と、あらゆる根回しを通して、イランからの石油輸入を勧めたのです。
出光さんはこのイランからの石油輸入が実現できたなら、国際外油会社の市場の支配から抜け出し、自由競争により、消費者に利益をもたらすことができる、つまり、「生産者から消費者へ」という出光さんの信念を通すことができると考え、イラン石油輸入に奔走しました。
ただし、この事業には大きなリスクがありました。それがイギリスからの妨害です。
当時、イギリスはアングロ・イラニアン社を巡り、イラン近辺の海岸に艦隊などを配置し、イランから石油を輸入しようとするものを拿捕したり、曳航したりして、かなり緊迫した状態でした。
この状態で日章丸をイランに向かわせるのは大変な困難と、社員の身に危険を晒してしまうことになり、最悪、出光自体がなくなってしまう、そんな恐ろしい賭けだったのです。
ですが、この状態でも、出光さんは自身の信念を曲げず、日章丸をイランに送り、イランから石油輸入を実現させました。
この事件から、出光さんの信念を通そうとする執念を感じます。
信念を貫くには”困難”が生じる

今回は、出光さんの人生の中の出来事の一部を抜粋して紹介してみました。
出光さんが生まれた家は決して恵まれた家庭環境ではありませんでした。
ご実家では、貧困に瀕しており、出光さん自身、養子に出されてしまいそうになってしまう時もありました。
その前提があり、出光さんが学生時代の日露戦争勝利後のバブルによる「拝金主義」に憤りを覚えており、学生時代出会った信念である「黄金の奴隷になるな」「士魂商才」「消費者至上主義」「大家族経営」「他者を助ける」などを確立しており、その信念を現実化していくために周囲の反対や妨害がある中で奮闘していました。
自分の信念を貫くには必ず障壁が目の前に訪れます。
信念を貫くには、出光さんの人生を通してわかるように、”困難”が生じるのです。
ただ、人生を通して、信念を貫く時に訪れる困難を乗り越えた時、筆者のように体現した信念に共感してそれを世の中に広めようとしたり、出光さんの人生を通して出光さんの信念を受け継ぎ、新たな事業を勧めたりと、人々、はたまた、世の中に大きな影響を及ぼすことになります。
信念を貫こうか迷っている人は、迷わずに信念を貫くことを選ぶのが出光さんの人生からわかることです。
出光佐三さんの名言

自らの信念を貫いた出光佐三さんが残した名言を紹介したいと思います。
紹介する名言を通して、信念を貫くモチベーションにしていただければ幸いです。
・黄金の奴隷たるなかれ
・順境の時こそ悲観せよ、逆境の時こそ楽観せよ
・働いて、自分に薄く、その余力をもって人のために尽くせ
黄金の奴隷たるなかれ
これは出光さんが学生時代に「水島銕也」校長先生から得た信念からくる言葉です。
水島先生は「金の奴隷になるな、士魂商才をもって事業を営むように」と学生らに説いていました。
つまり、「金に振り回されないで、武士の心、礼儀礼節、他者を尊重し、自己利益には知らずに合理的な商売をする」ということです。
この名言は筆者も大事にしている言葉です。
たとえ自分が実業家や経営者でなくても、他者からお金をいただく立場であれば、「自分さえ良ければ良い、自分の利益が第一」という思考で仕事に取り組むのではなく、「道徳に沿って、他者のことを第一に考え、他者の利益を追求する」ということを忘れずに仕事をしていく。
これが、黄金の奴隷にならずに、士魂商才で仕事を行うということなのではないでしょうか。
順境の時こそ悲観せよ、逆境の時こそ楽観せよ
この名言は「順調な時ほど、未来の苦難に備えておき、逆境の時は”なんとかなる”という気概をもっておく」という意味の名言です。
仕事に限らず、何事も順調な時ほど足元をすくわれやすいです。逆に、苦難に対面している時は、ついつい「なんとかしなきゃ」という気持ちになり自分を追い込んでしまい、正常な判断や行動をすることができなくなってしまいます。
ですから、順調な時は、気持ちや頭の中に余裕があるうちに、未来に来るであろう困難に的確に備えておき、困難な時は、気持ちを注ぎすぎないで、「天命に任せる」くらい流れに身を任せるくらいの方が良いということですね。
仕事でも人生においても大切にしておきたい信念になりそうなのでピックアップしました。
働いて、自分に薄く、その余力をもって人のために尽くせ
出光さんは「他者のこと」を第一に考えていました。
出光さんが海の上の船を相手に「軽油」を売り始めて、周囲の同業者から「海賊」などと呼ばれ反感を受けようとも、その行為は出光さんが思っていた「消費者のため」というものがありました。
船の燃料には当時、「灯油」が使われていましたが、「灯油」は価格が高く、燃料費が影響して市場に出回る魚の価格が高騰していました。
確かに、この行為によって、出光さんの会社は儲けたかもしれませんが、その儲けを決して自分たちだけのためには使いませんでした。
この後も、政府の石油統制機関の市場独占、石油の質低下、石油価格の固定に反旗を翻し消費者第一主義を掲げたり、国内の石油配給の安定化と低価格で石油を消費者に提供するためにタンクを製造したり、タンカーを用いて独自で海外から石油を輸入したりとしています。
また、戦後に仕事がなく、雇用していた約千人ほどの社員に対しても、多くのお金を送ったり、自分の大事なコレクションを売って雇用できるようにお金を確保していたということもあります。
このように、出光さんは出光さんの人生を通して「働いて、自分に薄く、その余力をもって人のために尽くせ」ということをやり続けていたのです。
この名言という信念は、現代の「資本主義社会」に欠けていることだと筆者は考えています。
人としての在り方は本来、人と人が手を取り合って己の人生を全うするということが、個々人の幸福につながっていたのではないかと考えます。
「自分さえ良ければ良い」
「自分が得をするにはどうしたら良いか」
「簡単に儲けよう」
「人を騙して儲けよう」
そうではなく、「働いて、自分に薄く、その余力をもって人のために尽くす」ということが、回り回って自分の幸福を上げることになり、世の中がより良く、暮らしやすい世の中になっていくのではないでしょうか。
さいごに
少し長くなりましたが、今回は「出光石油」の創業者「出光佐三」さんの人生を通して、「信念を貫く」ことについてお話ししていきました。
今まさに自分の信念を貫こうか迷っている人に、少しでも勇気と希望を出光さんの人生から汲み取っていただけたのであれば幸いです。
筆者も出光さんの信念をもとに、引き続き、読者の皆さんに役に立つであろう記事を提供できるように奮闘していきたいと思います。
この記事も役に立つかも

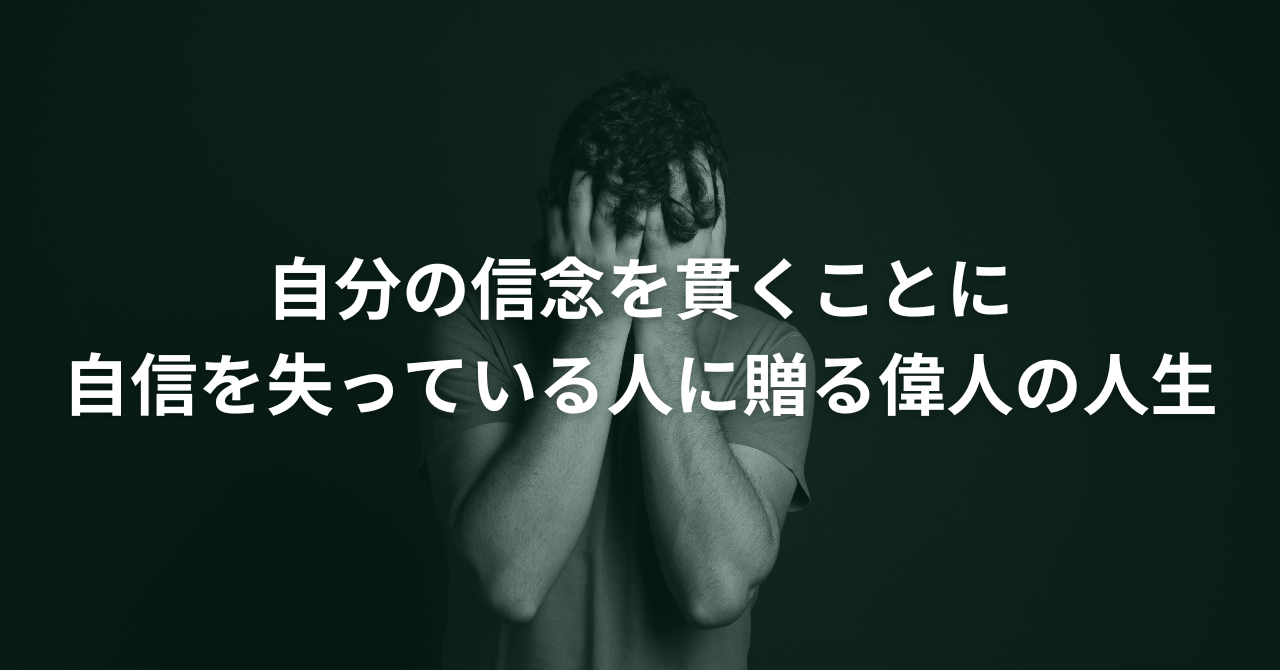
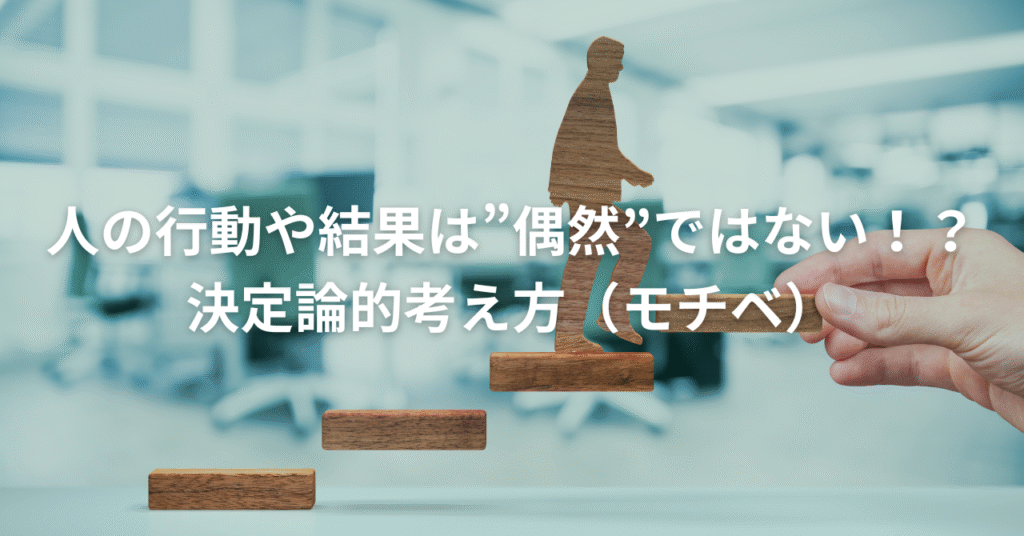
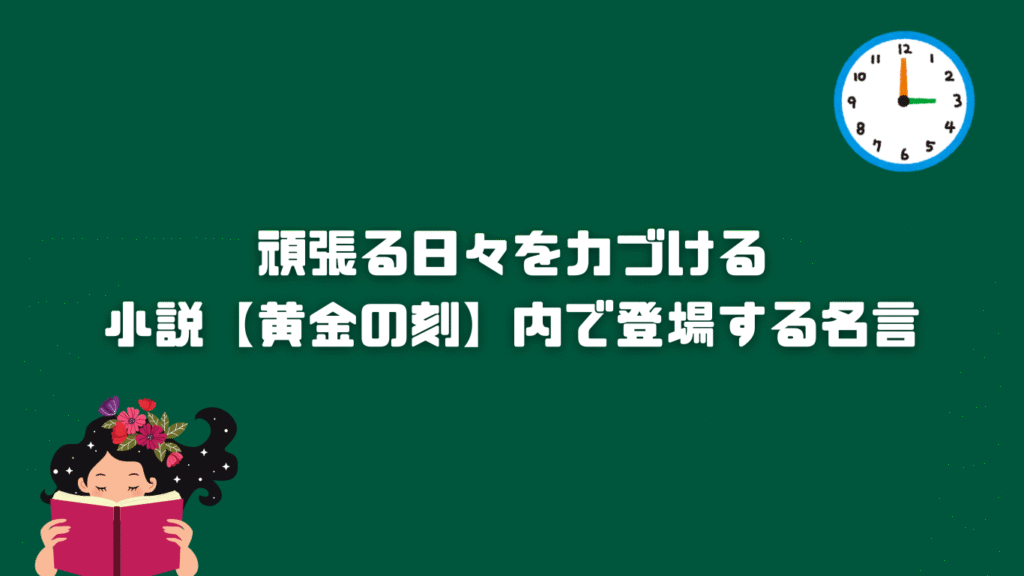
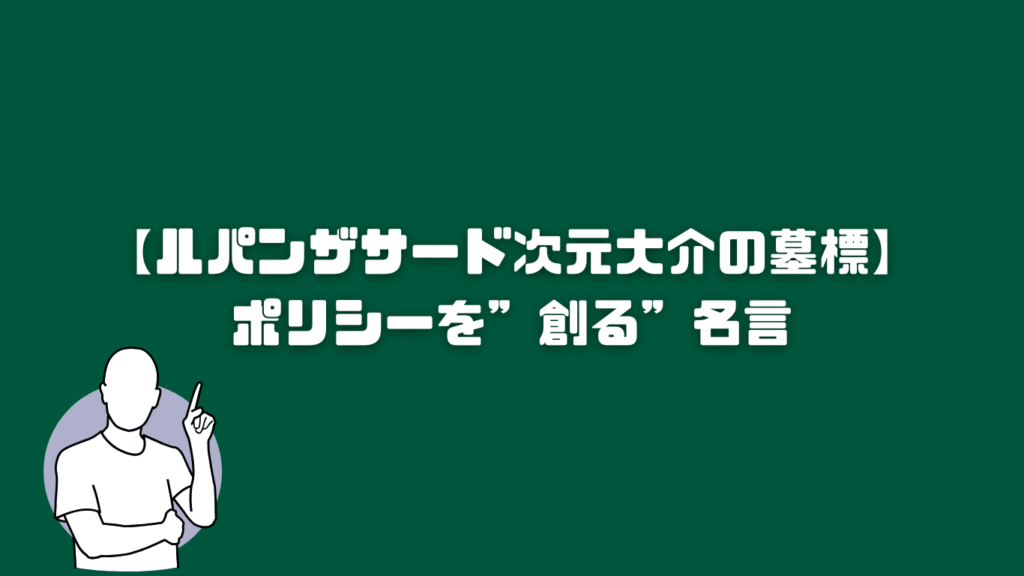
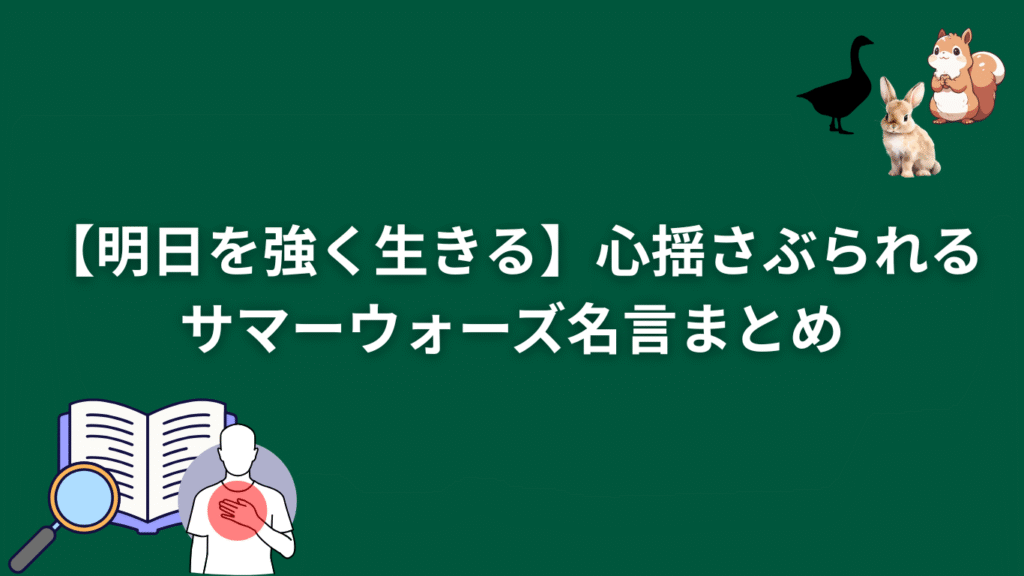
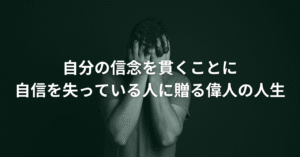

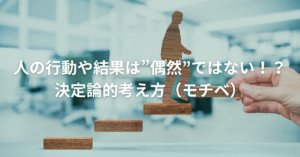

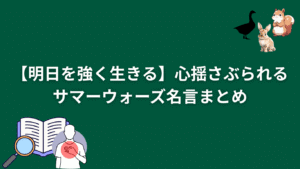
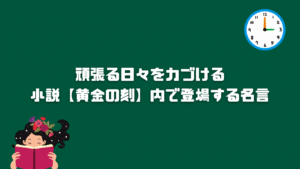
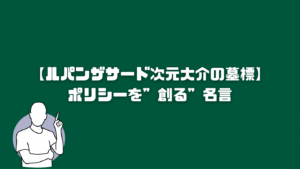
コメントする