こんにちは、筆者です。
今月(2025年9月)の中ごろに、ヤフーニュースさんにて「『前にも言ったよね?』が致命傷 Z世代の約6割がやる気を失った上司の一言」という、ちょっと気になる記事を見つけました。
今回は、この上司や先輩というマネジメントを行っている人が言ってしまいそうなワードである「前にも言ったよね?」というフレーズは言わない方が良いんじゃないか?という視点で筆者の見解をご紹介していたきたいと思います。
もし、今後輩などに「言ってしまっているな…。」と身に覚えがある人はぜひ参考にしてみてください。
参考元:Yahoo! ニュース 『前にも言ったよね?』が致命傷 Z世代の約6割がやる気を失った上司の一言
この記事でわかること
・「前にも言ったよね」は言わない方が良いのか?
・「前にも言ったよね」を言わない方が良い理由
・「前にも言ったよね」以外にどうしたら良いのか?

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験
- 吃音症歴20年
- 元オートローン営業マン
- 元オーダースーツフィッター
- 元百貨店販売員
- 現Webマーケター
- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味
- 酒は飲めない、よく体調崩す人
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
「前にも言ったよね」は言わない方が良いのか?
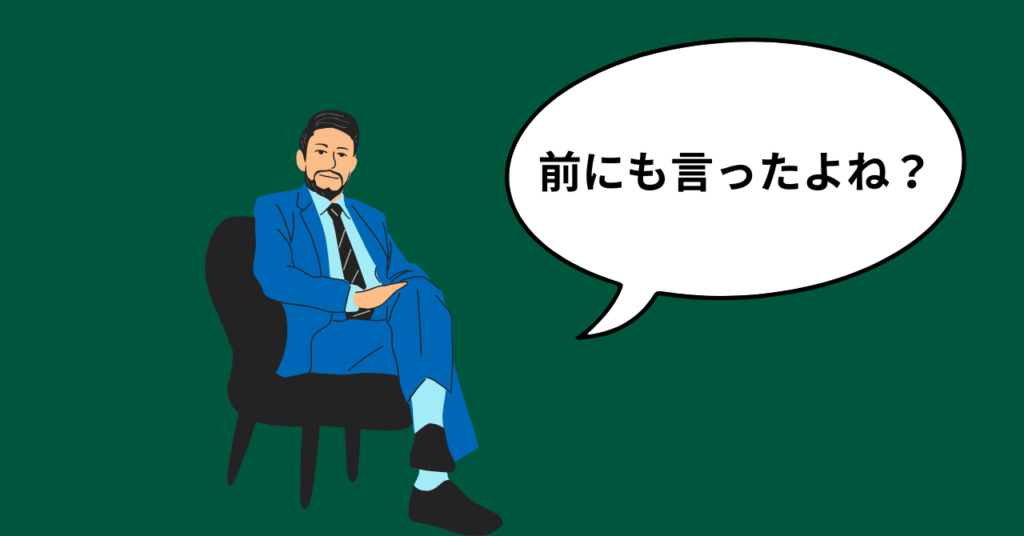
「前にも言ったよね」というフレーズは、上司や先輩という、仕事上で新人を教育する立場、つまり、マネジメントをする立場の人は言わない方が良い。というのが筆者個人的な見解です。
Yahoo!ニュースでも「前にも言ったよね」は言わない方が良いということを論理的に主張しています。
Yahoo!ニュースでは、Z世代(1990年代〜2010年初頭に生まれた世代のことをさす)を基準として、「前にも言ったよね」について解説しています。
Yahoo!ニュースによると、Z世代の若手社会人316名を対象とした、「Z世代と上司のコミュニケーションに関する実態調査」というペンマークとアルバトロスの調査に注目し、Z世代の約6割が「上司の何気ない一言」で仕事への意欲が低下した経験がある。という結果を提示しています。
この「上司の何気ない一言」というのが、今回のテーマにおける「前にも言ったよね」という一言であり、この調査の結果から、特にZ世代の若手社会人のやる気を削ぐことに繋がってしまうというということがわかります。
筆者はこの調査結果の背景には、「前にも言ったよね」という一言の危険さを知ることができると感じました。
「前にも言ったよね」は若手社会人のやる気を削いでしまう、という調査結果をYahoo!ニュースの記事から読み取ることができますが、その他にも「前にも言ったよね」という何気ない上司の一言から生じる影響はあると考えます。
次は、その「前にも言ったよね」という一言を言わない方が良い理由を考えていきたいと思います。
「前にも言ったよね」を言わない方が良い理由

上司や先輩といった、下の人を指導する立場の人が「前にも言ったよね」という一言を言ってしまうと、たとえ、Z世代ではなくとも、様々な悪影響を及ぼしてしまうことが考えられます。
具体的に「前にも言ったよね」という一言は次の4つの悪影響を及ぼしてしまうのではないでしょうか。
・プレッシャーを与えてしまう
・モチベーションを落としてしまう
・嫌悪感を抱くキッカケになってしまう
・コミュニケーションが取りづらくなってしまう
プレッシャーを与えてしまう
仕事上で、上司や先輩といった、下の人を指導するような立場の人から、教えてもらったことが一回でできなかった時、「前にも言ったよね」と言ってしまうと、指導される側の人からしたら、「やばい、ちゃんとやらないと」というプレッシャーを元にした、強迫観念にかられてしまうと考えられます。
もちろん、何回も言っても、何度も同じミスをしてしまい、ついつい「前にも言ったよね」という言葉を言ってしまうというのは、しょうがない部分もあると思います。
指導する人の側からしたら、何度も同じミスをされてしまい、上の立場の人からマネジメント不足だと怒られてしまうことがあるかもしれませんからね。
ただ、それでも、「前にも言ったよね」という一言は、指導される側からすると、”圧”を感じてしまう一言になってしまい、それにより、プレッシャーを感じ、また同じミス、ないしは、別のミスを引き起こしてしまう。
そんな風に負の連鎖になりかねません。
時にはプレッシャーを与えて、ミスを出さないようにするという指導も、必要な時はありますが、仕事上、絶対やってはいけないミスや道徳に反すること、人の命に関わること以外の、いたしかたないミスに対して「前にも言ったよね」という一言を投げかけるのは、違うミスを引き起こしてしまうトリガーになりかねないのです。
モチベーションを落としてしまう
上司や先輩といった、指導する側の人が「前にも言ったよね」と指導される側の人に言ってしまうと、指導される人のモチベーションを落としてしまうことに繋がります。
これは、Yahoo!ニュースでも主張されている、調査通りのことなのですが、筆者は別の視点から見てモチベーションが下がってしまうと考えられます。
筆者の視点は2つです。
1つが「図解 モチベーション大百科」から抜粋した、「学習動機」というモチベーションを形成する心理的作用に反してしまうということです。
「学習動機」というのは「相手の気持ちに寄り添うと、動いてもらいやすい」という人の行動意欲を示したものです。
「相手の気持ちに寄り添うと、動いてもらいやすい」という心理的作用があることがわかっており、この時に「前にも言ったよね」を考えてみると、この一言には「相手の気持ちに寄り添う」という意図が全くなく、相手のやる気を削いでしまう行為だということが分かります。
2つ目の視点ですが、こちらも「図解 モチベーション大百科」から抜粋させていただきまして、「道徳的行動」を促す心理的作用を参考にします。
この「道徳的行動」というものは、「人を褒める時と叱る時に、相手の意識をどこに向けさせるかが、その後の行動を促すことに重要である」という内容です。
人の意識には以下のような階層があるといいます。
・存在(自分自身)=自分自身に与える影響が非常に強い
・価値観(大切にしていること)=影響が強い
・能力(できること)=影響がやや強い
・行動(やったこと)=影響が弱い
・環境(人、場所、道具)=影響が非常に弱い
褒める時は、影響が非常に強い、「存在(自分自身)」に結びつけた方が、影響を強く与え、その後の行動に作用するというもので、逆に、叱る時は、影響が非常に弱い、「環境(人、場所、道具)に結びつけた方が、その後の行動に良い作用をもたらす。
というものです。
つまりは、「前にも言ったよね」という叱り方は、「何で言ったことができないんだ」という”人格”に注目しており、「存在」に結びつけた叱り方なので、指導される側の人のモチベーションは落ちてしまう。という考え方です。
この2つの視点から見て、「前にも言ったよね」は指導される人のモチベーションを削いでしまう一言だと考えます。
嫌悪感を抱くキッカケになってしまう
「前にも言ったよね」という一言は、前項で述べた通り、「教わったことをできないのはなぜですか?」という、人格を否定してしまうようなニュアンスが含まれた一言であり、人は誰しも、嫌な気分にさせる人のことを嫌悪してしまうものですから、人格を否定してくるような人に対して、嫌悪感を抱いてしまう恐れがあります。
この嫌悪感がキッカケとなり、人間関係に亀裂が生じ、仕事をしにくくなってしまう。という業務上において、悪影響を及ぼしてしまうことが考えられます。
組織で行う、会社の仕事というのは、どうしても横や縦の連携が必須ですから、少しでも人間関係で亀裂が入ると、やりにくくなってしまうのがネックなところ。
「前にも言ったよね」という一言は、この人間関係の亀裂のキッカケとなってしまう恐れがあるのです。
コミュニケーションが取りづらくなってしまう
会社は組織で動く以上、横と縦の人間関係を円滑にしておく必要がある、ということを前項で少しお話ししましたが、人間関係を円滑にしておくには、「コミュニケーション」が必須です。
コミュニケーションをしっかり、良好にとることで、良好な人間関係と、仕事のしやすさに直結します。
ただし、「前にも言ったよね」という一言は、この”良好なコミュニケーション”をとる時の障害となってしまうのです。
「前にも言ったよね」という一言は、言い方にもよりますが、言われて良い気分はしません。
言われて良い気分はしない一言を受け取ることで、「この人とは会話しにくいな」「この人怖いな」「また怒られるんじゃないかな」といった、負の感情や負のイメージを指導される人に植え付けることになってしまう恐れがあるのです。
この負の感情や負のイメージは、良好なコミュニケーションを取りづらくしてしまい、結果的にどんどん、人間関係が悪くなり、仕事がしにくくなってしまう。
そういった悪影響を及ぼすことが考えられます。
「前にも言ったよね」は何の解決策にもならない
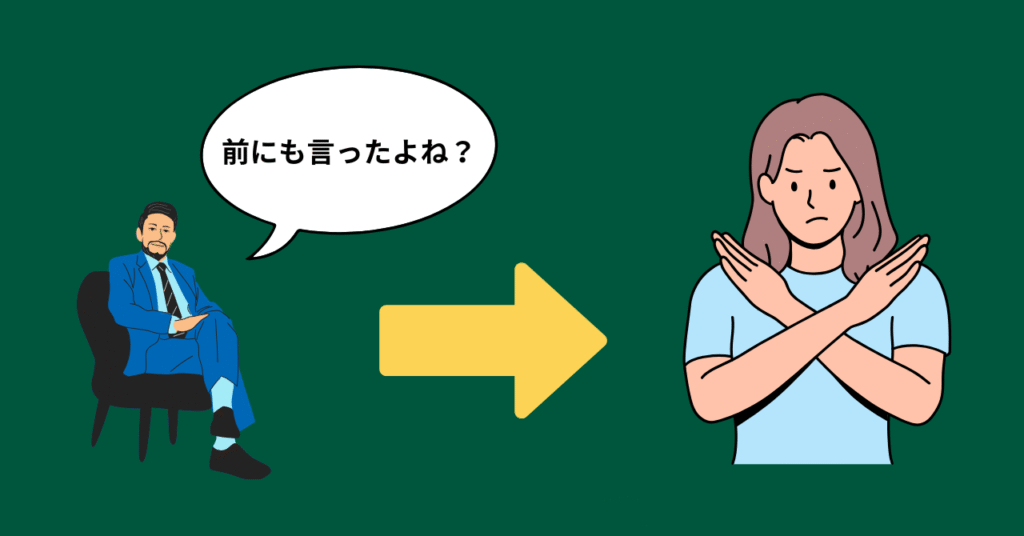
以上により、「前にも言ったよね」という一言は、色々な悪影響を及ぼしてしまうということの中身を紹介していきましたが、筆者個人的には「前にも言ったよね」という一言は何の解決策にもならないと考えています。
この「前にも言ったよね」という一言のニュアンスとしては、「教えたことを何でできないんだ」とか、「何度同じことを言わせるの?」とか「こっちの労力も考えてよね」というような、指導する人の個人的な気持ちが背景に隠れていることが予想できます。
つまり、自分の感情を言葉にして相手に伝えているだけ。なのです。
これでは、相手も嫌な気持ちに陥るか、気分が落ち込んでしまい、モチベーションが低下するかという、いずれにしても良い結果にはなりません。
ここで本来の”目的”を思い出してみてください。
本来の目的は、「教えてもできない人をどう指導して、できる人にするか」というのが目的です。
教えたことをできさえすれば、指導する人にフラストレーションは溜まらないので、「前にも言ったよね」という相手に悪影響を齎すであろう一言を言わずに済みます。
この本来の目的というのを忘れないことが、「前にも言ったよね」という一言を言わないようにする方法の一つだと筆者は考えます。
覚えてもらうには具体的な案を提示した方が良い
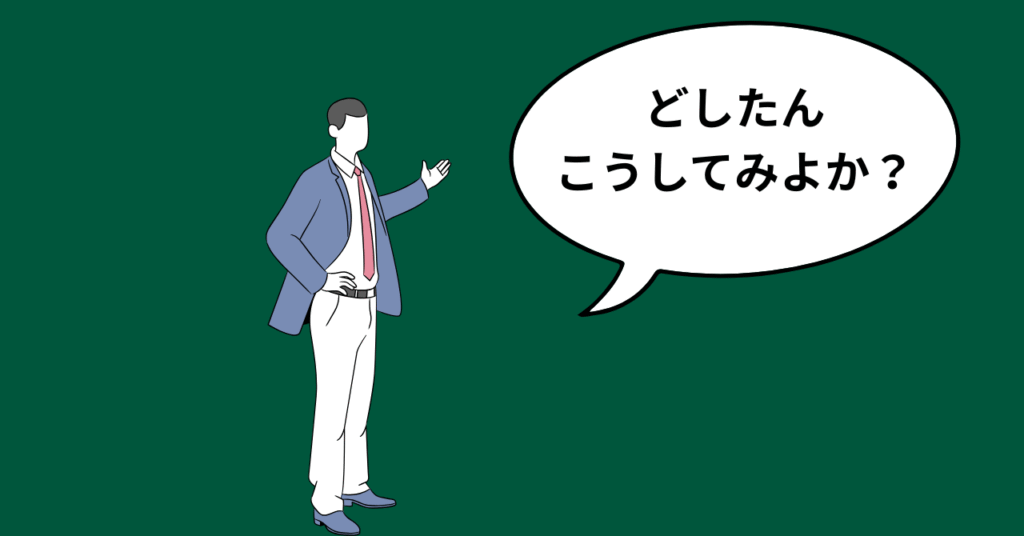
では、実際に本来の目的である、「指導される人を仕事ができる人材にする」ということを実現するにはどうすれば良いのか?ということですが、筆者が考える方法として「具体的な案を提示する」というのが適切な方法だと考えます。
ただし、ここで注意したいのは、これは「仕事を覚えてもらう」という目的を達成する方法だということです。
「仕事を覚えてもらうために指導される人のやる気を上げる」という目的達成ではアプローチの方法が変わってくると考えます。
「仕事を覚えてもらう」には、「前にも言ったよね」という一言を投げかけるのではなく、「じゃあこうしてみようか」「こうすれば分かりやすいかな?」という具体的な改善案を提示することが、問題解決に繋がるのではないでしょうか。
また、ミスをしてしまった内容が重要なことだった場合は、その重要度を論理的に説明してあげることが、指導される人の腹に落ち、具体的な改善案を受け取ることができます。
もし今、実際に教えてもできない後輩がいるのであれば、「前にも言ったよね」という一言を飲み込んで、代わりに、具体的な改善案を一緒に考えてみるのはいかがでしょうか。
さいごに
今回は、Yahoo!ニュースでみた「『前にも言ったよね?』が致命傷 Z世代の約6割がやる気を失った上司の一言」の記事に感化されて、「前にも言ったよね」といってしまうことで生じる悪影響について筆者なりに考えてみました。
人に物を教えるということは非常に難しいですよね。
筆者も教えるということは、あまり得意ではありませんし、自分に自信がないということもあり、教えること自体、周囲の目を気にして憚られる行為だと思っています。
ですから、まず指導する側でいるだけでも、すごいことだと思いますし、たとえ、今回紹介した「前にも言ったよね」という一言を言ってしまって、「やっちまったなぁ」と悲観していても、そんなに気に病むことではないと思いますし、改善していく余地はあります。
そして、指導する人は指導する人になるだけの経験と、知見があると周囲からも認められているということを自覚して、自信を持って、後輩さんを助けてあげると良いのではないでしょうか。
筆者ができないことをやっている人に尊敬を込めて。
この記事も役立つかも

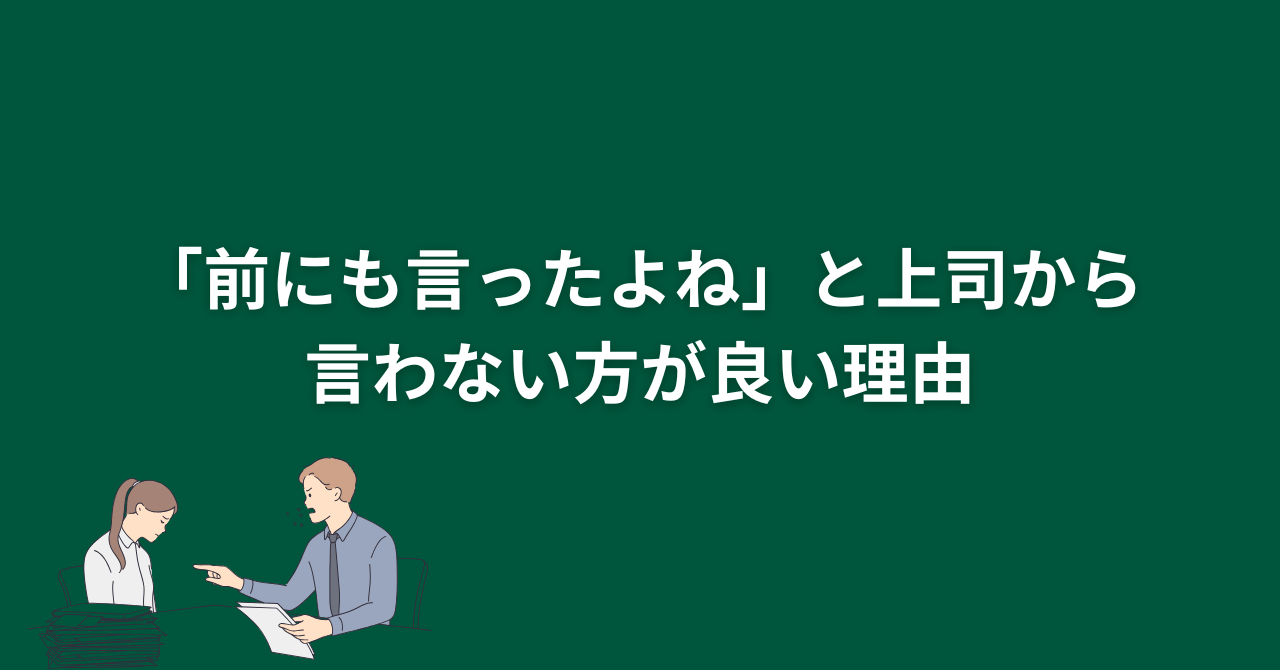

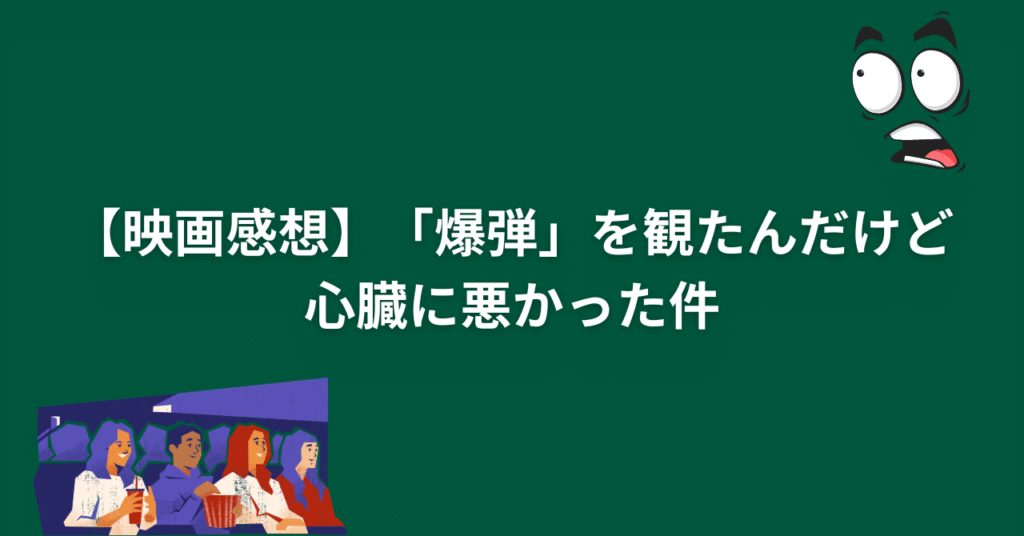
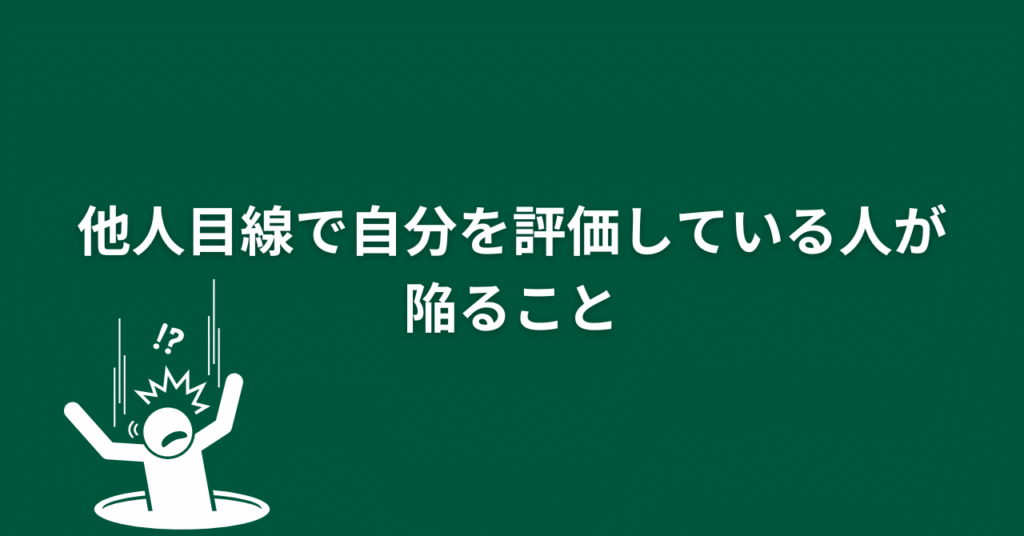
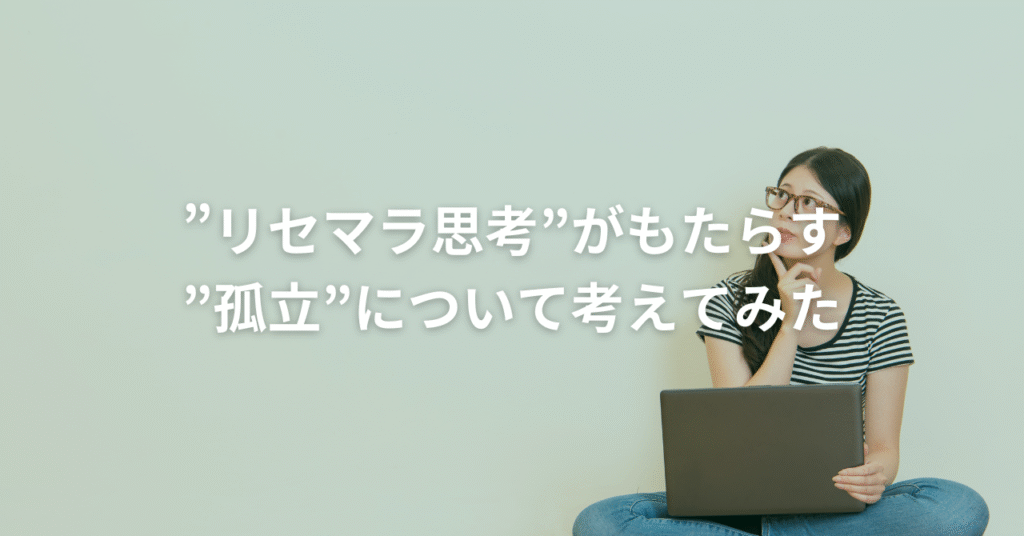
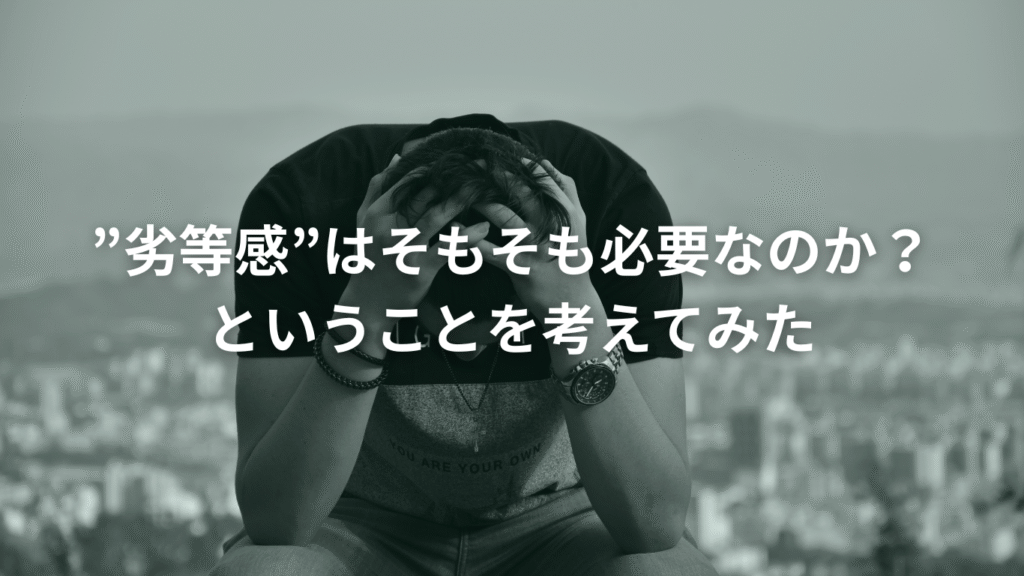
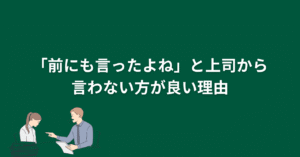

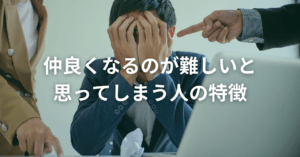

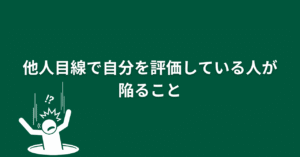
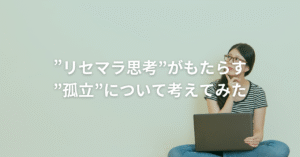
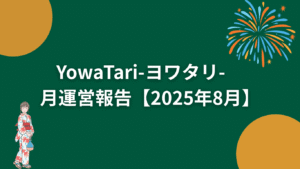
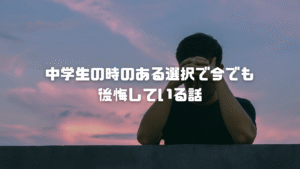
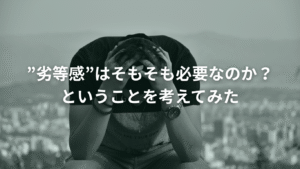
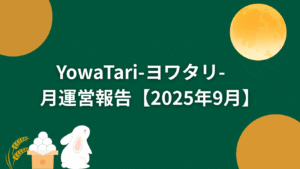
コメントする