こんにちは筆者です。
仕事上で上司や取引先との会話の中で「わからないこと」があった時、「わかりません」と伝えることが良いように思えますが、実はこれだと相手に「不信感」を抱かさせてしまうかもしれません。
もちろん、わからないことに対して「わかりません」と素直に言うことはとても大切であり、この言い方でも十分相手に失礼なく伝えることができます。
ですが、もっと良い「わかりません」の言い方・言い換え方があります。今回は「わかりません」を上司や取引先に伝える時に失礼にならない言い換え方を紹介していきたいと思います。
この記事でわかること
・「わかりません」の相手に失礼にならない言い方
・「わかりません」の言い換え方
・「わかりません」の実践例

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験
- 吃音症歴20年
- 元オートローン営業マン
- 元オーダースーツフィッター
- 元百貨店販売員
- 現Webマーケター
- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味
- 酒は飲めない、よく体調崩す人
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
「わかりません」をストレートに言ってしまうと…

仕事上で上司や取引先との会話の時に、わからないことがあったとき、ストレートに「わかりません」と言ってしまうと、言い方によっては不躾で、淡々としており、「やる気があるのだろうか?」というマイナスの印象を与えてしまうかもしれません。
このように上司や取引先にマイナスな印象を与えないためには、上手く「わかりません」と言う必要があるのです。
ただ、「わかりません」でも言い方によっては全く問題ありません。実際に「わかりません」の失礼にならない言い方をみていきます。
「わかりません」の失礼にならない言い方
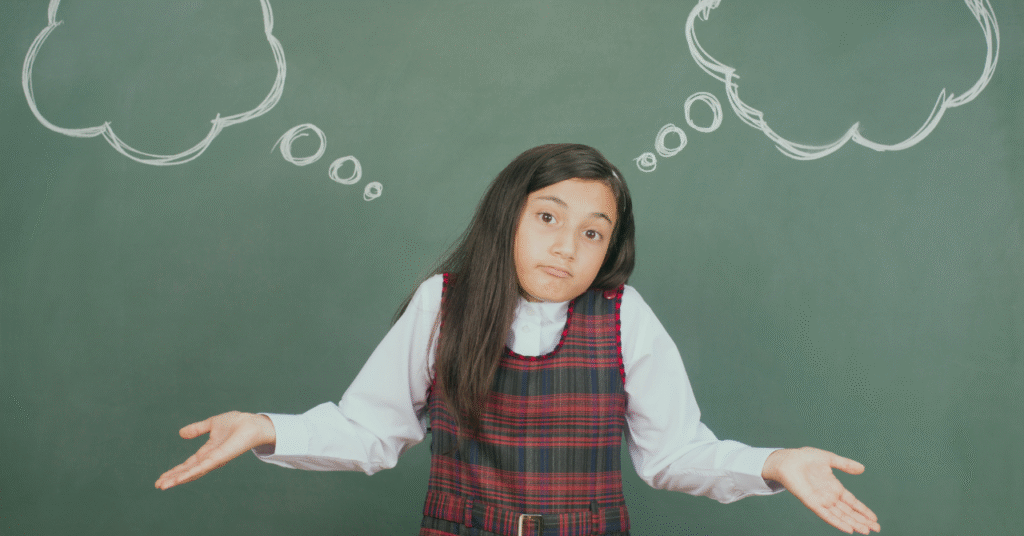
「わかりません」の上司や取引先に失礼にならない言い方は
「申し訳ございません、言っていただいた〇〇という部分がわかりません。ご教示いただいてもよろしいでしょうか?」
このように「わかりません」を言うことで相手には失礼にならず、むしろ、「ちゃんとわからないところがわかっていて、それを解消しようとしていて誠実な子だな」という印象を相手に与えることができます。
後ほど”言い方”については注意点をまとめていきたいと思います。
「わかりません」の言い方を変えれば、十分に上司や取引先の人に失礼なく伝えることができますが、「わかりません」そのものを言い換えることでも相手に失礼な印象ではなく、丁寧で、意欲が感じられる良い印象を与えることができます。
その言い換え方については次の項目を参考にしてみてください。
「わかりません」の失礼にならない言い換え方

「わかりません」の相手に失礼にならない言い換え方は以下の6つになります。
参考にしてみてください。
・存じ上げません
・存じません
・わかりかねます
・勉強不足で申し訳ございません
・お答えいたしかねます
・寡聞にして存じ上げません
存じ上げません
これは「わかりません」の謙譲語表現での言い換え表現です。
謙譲語表現とは、自分を謙り、相手を敬う表現の時に用いる敬語表現です。
存じ上げませんを使う時は必ず、主語を”自分”にすることです。主語を自分にしなければ、「自分を謙り、相手を敬う」ということができないからです。
まあこれは「わかりません」という主語が自分の表現を言い換えるものなので、この部分に関しては問題ないと思います。
あとは「存じ上げません」というのは「謙譲語I」に該当しており、「謙譲語I」は”対象が明確である場合”に使う謙譲語です。
例えば
取引先「競合他社の〇〇さんって知っていますか?」
自分「いえ、申し訳ございませんが、存じ上げません。」
このように聞かれたことが”明確である物事”の時に、「わからなかった」場合、「存じ上げません」を使うと良いでしょう。
存じません
これも「わかりません」の言い換え表現の一つです。
前項の「存じ上げません」と何が違うんやってことですが、これは「謙譲語Ⅱ」に該当するという部分で異なる謙譲語表現の言い方といえます。
これも自分を謙り、相手を敬う言葉になるので、表現上で言えば相手に失礼に思われることがありません。
「謙譲語Ⅱ」は、「謙譲語Ⅰ」とは違い、敬う対象が明確でなくて良く、特に何が敬う対象なのかを指定せずに使える謙譲語です。
例えば
取引先「今朝の仕事関連のニュースみた?」
自分「申し訳ございません、それらのニュースは存じていません。」
このように、対象が曖昧なものに対しては「わかりません」を「存じません」とすると良いです。
わかりかねます
「わかりかねます」は
品詞に分けると
わかる=動詞
かねる=動詞につく連用形
ます=連用形につく語
このようになり
意味に分けると
かねる=〜できない、〜することが難しい
ます=丁寧語
ということになる、いわゆる「わかることができないです」という意味を持つ丁寧語です。
分解するとちょっと難しいですが、意味としてはシンプルです。
ただ、この語を使う場合、以降に紹介する”注意点”を踏まえないと、逆に相手に少し冷たい印象を与えてしまいかねない言い換え方となっていますので、扱いには要注意です。
勉強不足で申し訳ございません
上司や取引先との会話でわからないことがあった時、そのまま「わかりません」と言うのも素直で誠実さを与えることができますが、誠実さにプラスして”意欲”を伝えることができる言い方が「勉強不足で申し訳ございません」という言い換え方です。
「勉強不足」ということを言えば、「これから勉強する意欲がある」「普段から前向きに仕事に取り組んでいる」というニュアンスを伝えることができます。
そして、「知識が足りなかったこと」に対して、「申し訳ございません」という謝罪の一言を加えれば、相手に良い印象を与えることができます。
お答えいたしかねます
これも「わかりません」の言い換えになります。
「その問いに答えることができない」という意味を丁寧に伝える言い換え方です。
ただ、これは「本当なら知っているが、会社の規則などで答えることができない」というニュアンスにも聞こえる可能性があるので、慎重に使用する必要があります。
寡聞にして存じ上げません
「勉強不足」ということを意味する言葉で”寡聞”(かぶん)というものがあります。
この語は、知識が乏しいこと、知識が少ないことを意味している語であり、「知識が乏しい」ということを「存じ上げません」という謙譲語表現で相手を敬うように表現した言い換えです。
「勉強不足で申し訳ございません」をより丁寧に伝えたいのであれば「寡聞にして存じ上げません」を使ってみると良いです。
「わかりません」の失礼にならない使い方【対面例文】

上記で説明した「わかりません」と「わかりません」の言い換え言葉を実際の対面シチュエーションで使う例を紹介していきたいと思います。
以下のそれぞれの文面を参考にしてみてください。
わかりません
取引先の場合
取引先「いただいた書類の〇〇という部分について知っていますか?」
自分「申し訳ございません、わかりません。」
上司の場合
上司「営業で大切な5つのポイントについて知ってるか?」
自分「いえ、わかりません。」
存じ上げません
取引先の場合
取引先「御社が取り扱っている商品の原材料の生産場所はご存じですか?」
自分「申し訳ございません、原材料の生産場所については存じ上げません。」
上司の場合
上司「なんでアポイントをとらないといけないか、知っているか?」
自分「すみません、存じ上げません。」
存じません
取引先の場合
取引先「競合他社の〇〇会社さん何か問題起こったらしいんだけど何か知ってる?」
自分「そんなことがあったんですね。いえ、そのようなことは存じません。」
上司の場合
上司「この件について〇〇社の方針は知ってる?」
自分「申し訳ございません、その点につきましては存じません。」
わかりかねます
取引先の場合
取引先「この価格でご対応いただけますか?」
自分「申し訳ございません、誠に恐縮ですが、その価格だと個人で判断していいのかわかりかねますので、一度社内に持ち帰らせていただき判断させていただきます。」
上司の場合
上司「この数字の誤差がわかる?」
自分「現時点では、はっきりとわかりかねます。至急調査いたします。」
勉強不足で申し訳ございません
取引先の場合
取引先「御社の販売商品の意図について詳しく教えていただけますか?」
自分「勉強不足で申し訳ございません、すぐに調べさせていただき、回答いたします。」
上司の場合
上司「このシステムの更新履歴の重要性はしっかり把握しているか?」
自分「いえ、まだ把握できていません。勉強不足で申し訳ございません。速球に確認します。」
お答えいたしかねます
取引先の場合
取引先「競合他社さんの動向について教えていただけますか?」
自分「申し訳ございませんが、把握しておらずお答えいたしかねます。」(そもそも知らない場合)
自分「申し訳ございませんが、他社様に関する情報についてはお答えいたしかねます。」(知ってるけど言えない時)
上司の場合
上司「新しい社内チャット機能の導入日って知ってるか?」
自分「申し訳ございません、その件につきましてはお答えいたしかねます。リリースはまだだと思います。」
寡聞にして存じ上げません
取引先の場合
取引先「最近導入された〇〇っていうサービスについて知っていますか?」
自分「いえ、寡聞にして存じ上げません。調べてみます。」
上司の場合
上司「新しい商材について〇〇っていう部分がわからないんだが、知ってるか?」
自分「申し訳ございません、寡聞にして存じ上げません。商材を考えた人に聞いてみます。」
「わかりません」の失礼にならない使い方【メール例文】

もし、メールで「わかりません」を使わないといけない時があれば、以下の2種類の言い換え方の例文を参考にしてみてください。
・存じ上げません
・不勉強で申し訳ございません
存じ上げません
取引先の場合
件名:〇〇につきまして
株式会社〇〇
〇〇様
平素よりお世話になっております。
いただいておりましたお問い合わせの件だったのですが、申し訳ございません、私自身も存じ上げておらず、一度こちらで調べさせていただいて再度ご連絡させていただければ幸いでございます。
引き続きよろしくお願いいたします。
上司の場合
件名:〇〇について
〇〇部長
お疲れ様です。
先ほどご連絡いただきました〇〇につきまして、申し訳ございませんが私も存じ上げません。
もし必要であれば、私の方でお調べさせていただきますがいかがされますか?
ご検討のほどよろしくお願いします。
勉強不足で申し訳ございません
取引先の場合
件名:〇〇の回答について
株式会社〇〇
〇〇様
平素よりお世話になっております。
先ほどご質問いただきました〇〇につきまして、勉強不足で申し訳ございません。すぐに正確なご説明ができませんでした。
早急に調べ、資料を整えご案内させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。
上司の場合
件名:〇〇
〇〇部長
お疲れ様です。先ほどご指摘いただきました点につきまして、勉強不足ですぐに回答できず申し訳ございません。
調べさせていただき、後ほどご連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。
「わかりません」を使う時の注意点
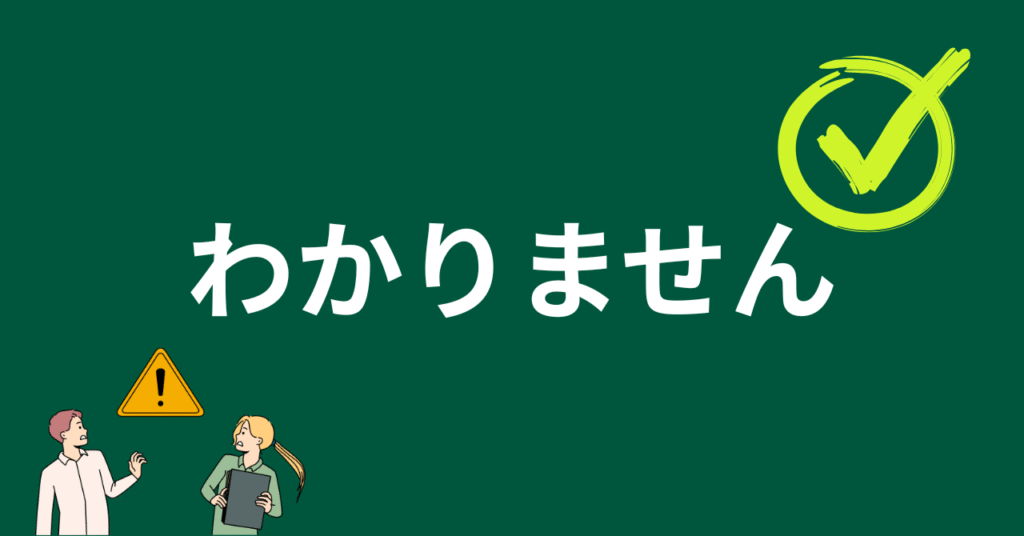
「わかりません」を仕事上で使う場合、3つの注意点があります。
上記の例文にも含まれているものがあるので、気になった人はもう一度例文をみてみてください。
クッション言葉を使う
「わかりません」を言う前に”クッション言葉”を入れてみると相手に失礼なく伝えることができます。
このクッション言葉というのは、相手に”配慮”をした言葉です。
例えば
・申し訳ございません
・すみません
・大変恐縮ですが
など
「わからなかった」という事実に対して「すまなかった」という相手への配慮を含んだ言葉のことを言います。
この”配慮”の言葉を入れることで、配慮を受け取っている分、相手が「しょうがないか」と思ってもらいやすくなり、失礼に思われる確率が低くなります。
何が”わからないのか”明確にする
”何が”わからないのかを明確にすることで、相手に「無責任さ」を与えないで「わかりません」と伝えることができます。
”何が”わからないのかがわからないで、相手に回答してしまうと、相手には「この人真剣にうちとの取引を考えてくれているのかな?」だったり、「真面目に仕事をしていないのかな?」といったマイナスな印象を与えてしまいます。
「どこの部分がわからないのか」というのを会話の中で明確にして、相手に「これがわからないです」としっかり明示できるように気をつけてみてください。
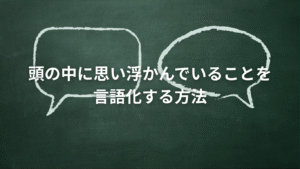
使いすぎると信用を無くす
仕事上で上司や取引先とのやり取りの中で「わかりません」を使いすぎていると、「本当に真剣に仕事に取り組んでいるのかな?」と仕事に対しての姿勢に疑いの目を向けられてしまいます。
なるべく仕事上で聞かれるであろう事柄、インプットしておきたい情報は事前に知っておくことで「わからない」を減らすことができます。
「わかりません」の使いすぎには注意してみてください。
「わかりません」を使うリスクとメリット
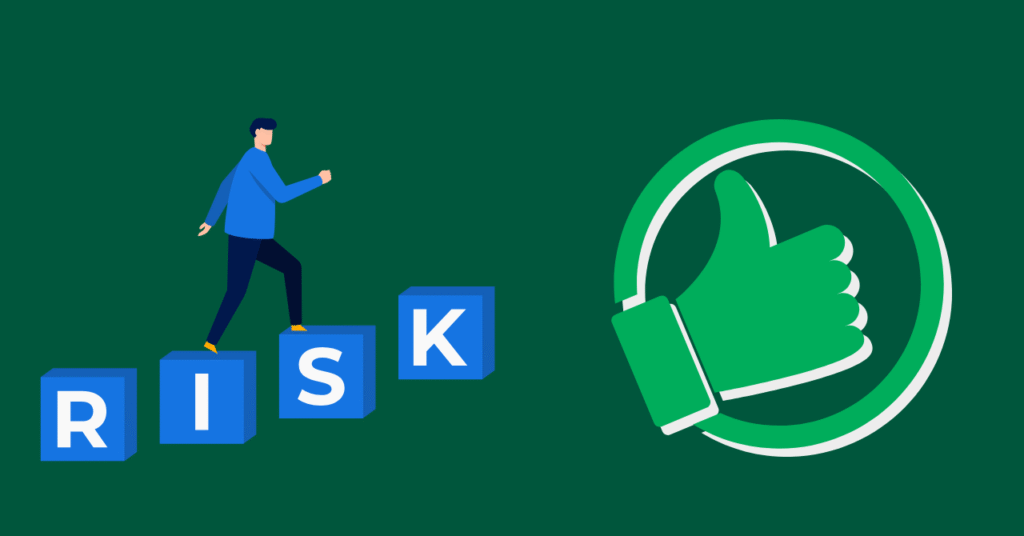
最後に「わかりません」を使うリスクとメリットについてお話ししていきたいと思います。
実は「わかりません」には良い面、悪い面があります。これを知っておけば、上手く言葉を使って、仕事上、相手と良好な人間関係を作ることにも繋がります。
信用を積み上げられる
まずはメリットです。
「わかりません」を使うことで、上司からも取引先からも「信用を積み上げる」ことができます。
これは「わからないことは正直に聞き、わからないを解消する」という誠実さと意欲という前向きな印象を与えることができるからです。
筆者は新社会人の頃、逆にわからないことを人に聞かないで自分でなんとかしようとしてしまう性分だったので、信用を積み上げるのにかなり時間がかかりました。ですが、今ならわかります。
わからないと思ったタイミングで聞いた方がよほど早く信用を積み上げることができますし、わからないことの回答も早く得ることができます。
わからないと思ったら、”すぐに聞く”これが大切であり、「わかりません」を使うメリットといえます。
同じ物事に対して使い続けると信用を無くす
「わかりません」を使いすぎると「意欲がない」とみられてしまい、信用を失ってしまう恐れがあるということを解説しましたが、これはより具体的なリスクです。
「わかりません」を多用しても別の物事についてのことや、まだ入社したばかりで間もないという状況では、そこまで上司や取引先からの信用を落とすことはありませんが、何回も同じ物事に対して「わかりません」を多用しているとこれは信用をなくすキッカケとなってしまいます。
同じ物事について何度もわからないということは、それを覚える意欲がないとみられてしまいかねないからです。
もちろん、なかなか仕事が覚えられないという人であればしょうがありません。少なくとも筆者は覚えるまで同じことについて解説する根気はあります。
ですが、世の中にはそんな人だけではありません。
「一回覚えたら覚えろ」と言う人もいれば、「仏の顔は3度まで」という人もいます。
ですから、出来るだけ同じ物事についての「わかりません」の多用は信用を落とすリスクがあるので避けた方が良いです。

まとめ
今回は仕事で「わかりません」を使う時の相手に失礼にならない言い方について解説してみました。
特に社会人になって最初の時期や、転職して間もない人であれば、わからないことは多くあり、良く使う文言の一つになります。
その時に、自分の知らず知らずのうちに上司や取引先の信用を落とさないよう、上手く「わかりません」を使うことが大切です。
今回の内容を簡単にまとめると
・「わかりません」はそのまま使ってもOK
・失礼にならない言い換え方もある
・わからないことを素直にわからないと言うことは大切
・だが多用は信用を落とすリスクがある
これらをおさえて「わかりません」を使ってみてはいかがでしょうか。
この記事も役立つかも

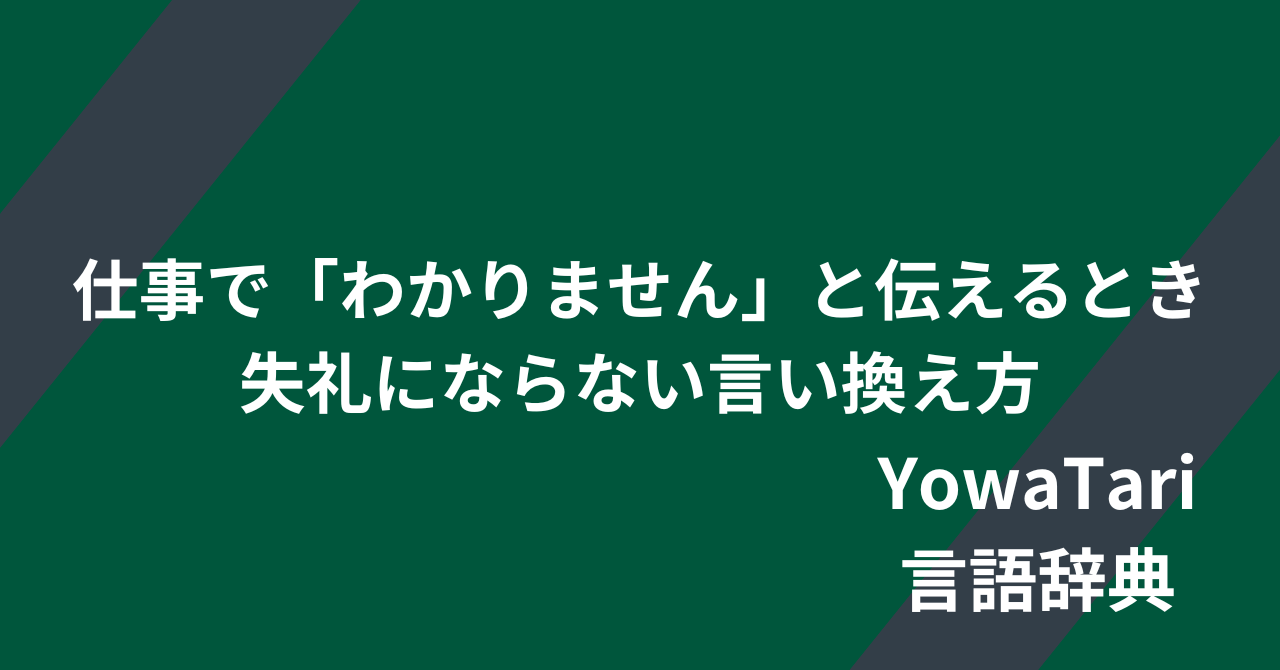
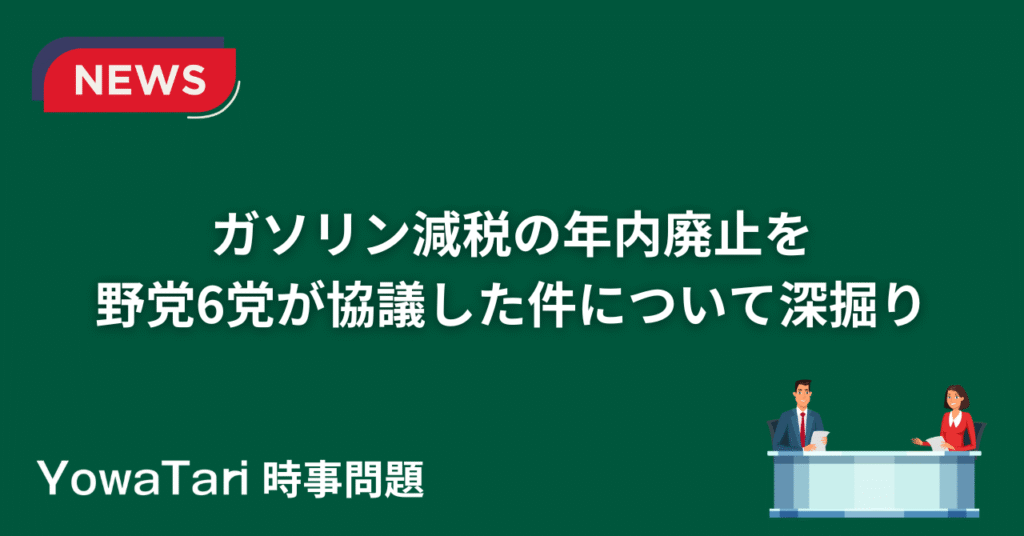
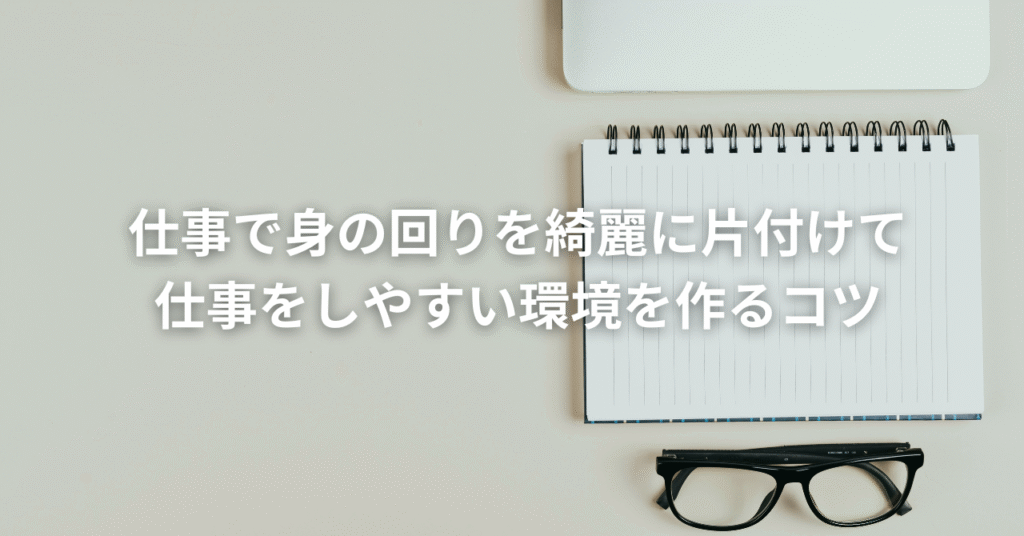
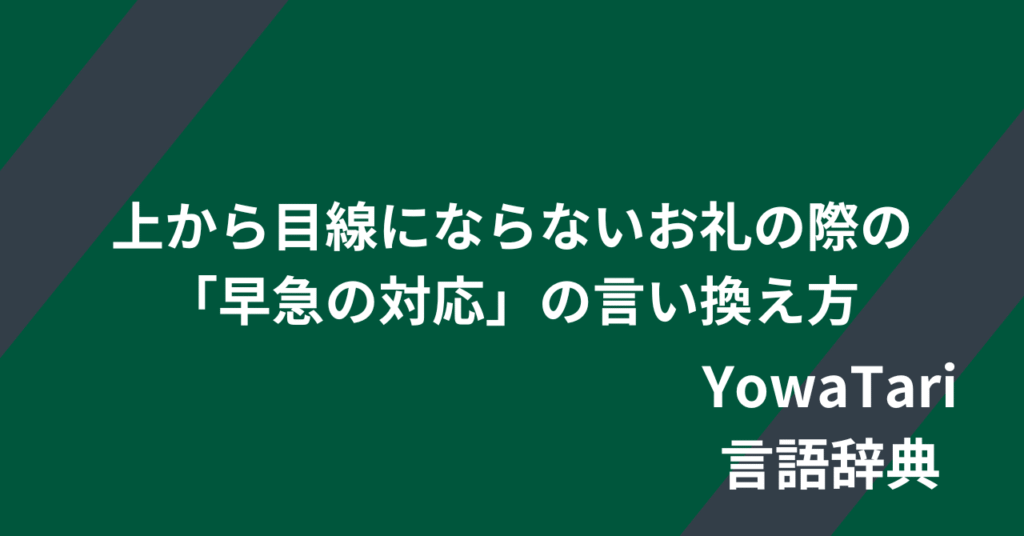
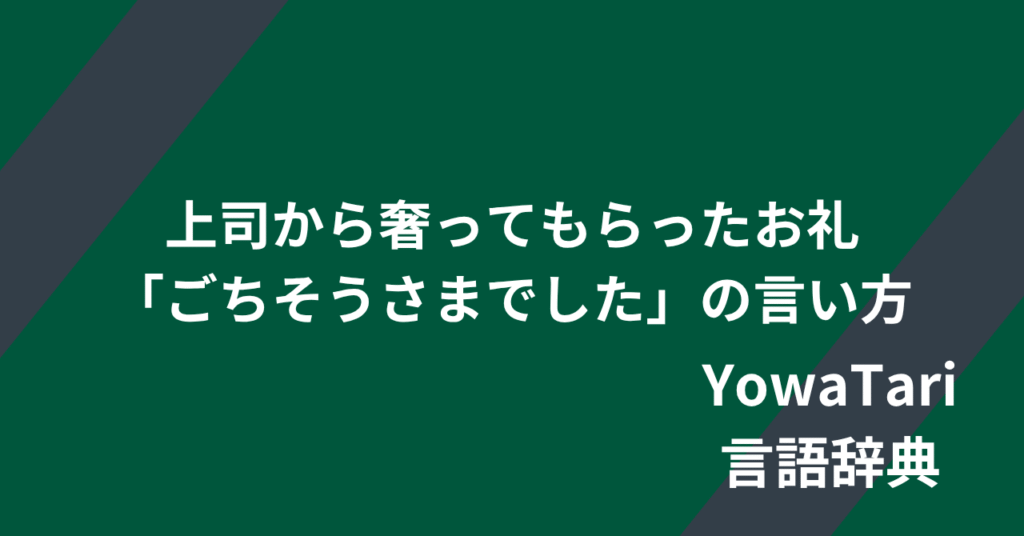
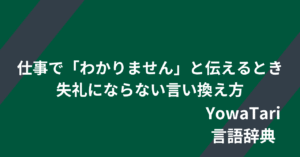


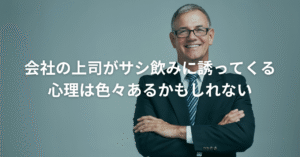
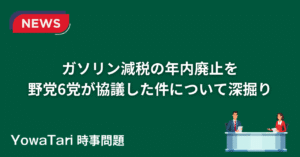
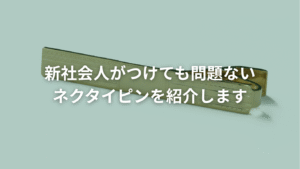
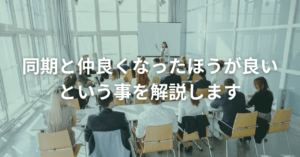
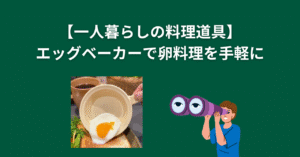

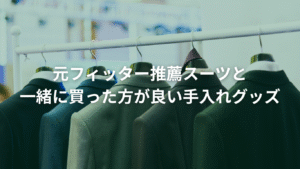
コメントする