最近、愛知県豊明市で、何やら気になるニュースになっていたものがあった。
「スマホ条例」
何やら、子供のスマホ利用に制限をかけようとする条例を国、正しくは地方自治体が出したそうなんだが、この条例についてちょっと居ても立っても居られなくなったので、筆者の考えについて語っていきたいと思う。
これが”世渡り”と何の関係があるのかということについてだが、世をうまいこと渡っていくには社会情勢にも目を向けないといけないと思ったりしているので、何か社会について考えるきっかけとなれば良いと思い、1エンタメとして届けられれば良いと思う。
「スマホ条例」についての筆者なりの考えは”いらない”だ。
なぜ「スマホ条例」はいらないのか、紐解いていこうと思う。
この記事でわかること
・スマホ条例について
・海外の条例の動き
・なぜスマホ条例はいらないといえるのか

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験
- 吃音症歴20年
- 元オートローン営業マン
- 元オーダースーツフィッター
- 元百貨店販売員
- 現Webマーケター
- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味
- 酒は飲めない、よく体調崩す人
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
「スマホ条例」はいらない

「スマホ条例」。この地方自治体が考えた、子供のスマホ使用を制限する条例だが、はっきり言って、いらないだろう。と筆者は思う。
あとから、いらない理由について深掘りしていきたいと思うが、ここでは簡単に「いらない」とだけ言っておく。
ま、一つの意見として聞いてほしいところではあるが、スマホって一個人が使う自由な行為だと思うので、その自由を制限しようとする地方自治体、国に対して筆者はどうも違和感を感じざるを得ない。
もしこの記事を読んでいる方が、まさにスマホ条例を考えた人だったら、本当に何と言ったら良いか申し訳ないが、筆者は側から見てていらないと感じてしまった。
「スマホ条例」どんな条例か

では、実際、「スマホ条例」というのはどんな条例なのか、色々なニュースからみていきたいと思う。
長くなりそうなので、以下の2つの項目にまとめてみた。
そもそも条例とは
そもそも、「条例」というのはなんのなのか?効力は強いのか?ということを考えていきたいと思う。
法律とかそこらへんの知識はド素人なので、多少の情報の齟齬はごめんなさいなので、参考程度にみてほしい。
Wikipediaの情報によると、条例とは地方公共団体が国の法律とは別に定める自主法という。
条例は日本国憲法を根拠とし、地方自治法に基づいて制定されることから、日本国憲法を頂点とする国内の法体系の一部であって、法の形式的な効力の意味においては、法令に違反できないものであるという。
つまり、法的には破っちゃいけない法だよってことにはなっているらしい。
条例は基本的に、制定したその地方(都道府県や市区町村)でのみ適用されるけど、一部その地域以外のところでも関連する条例については他の地方でも効力をもつということ。
今回の「スマホ条例」は愛知県豊明市が可決したから、豊明市での適用になる。
ちなみに、条例を破ってしまうと、地方自治法14条第3項の規定により、2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収(以上刑罰)又は5万円以下の過料に制限された罰則を課せられるそう。
参照元:Wikipedia
スマホ条例とは
以上の条例の基本を踏まえて、今回の「スマホ条例」についてみていこう。
詳しくはこの愛知県豊明市公式が発表している「豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例案」を気になった人はみてほしい。
この条例の注目されている部分は「市内に在住又は在学する18歳未満を対象とした、スマホを使用するのは1日あたり2時間以内を目安とする」という部分だ。
世間ではこの部分が取り上げられて、物議を醸してる。
さらに、注目したのは条例案の中の「余暇時間におけるスマートフォン等の使用について、小学生以下 は午後9時、中学生以上は午後10時を目安」という部分だ。
こうしてみると、結構ターゲットを絞って、かなり限定するような形で記載されていることがわかる。
ただ、豊明市は「子どもの健やか な成長と、市民全体が健全に暮らせる社会の実現に寄与すること」を目的として本案を制定していることから、いたずらに考えているわけではないということがわかる。
この部分に関しては、筆者も激しく同意したい。
確かに、スマホがもたらす時間の浪費と、それに伴う睡眠時間の減少、コミュニケーションの減少という問題はあると考えるので、それを防ぐための条例と考えてみると、条例について完全には「いらない」とはいえない。
また、この条例を地方自治体が定めることで、「スマホの適切な使用方法の啓発」「スマホの過度な使用による問題の相談支援の体制を整える」という公的な動きを促す役割を担うと書かれている。
これも”確かに”といわざるをえない。なんか段々と筆者の意思が揺らいできてしまっている。
海外でも国からの”制限”ルールはある

ちなみに、海外でも豊明市のようなスマホ条例と似た国が定めるルールのようなものが存在することを知っているだろうか?
中国・アメリカ・オーストラリアの3カ国の例をみていきたいと思う。
中国のゲーム規制
これは、2021年の記事の「未成年の「ゲームは1日1時間」+「金土日だけ」=「週3時間」 揺れる中国、その影響は?」を参考にしていきたい。
中国政府が突然「18歳未満のオンラインゲームは金、土、日、祝日の午後8〜9時しかやってはいけない」というゲームのプレイを制限する規制を発令したらしい。
ゲーマーの筆者からすると、これは耐えられない規制だ。
アメリカフロリダ州でのSNS規制
アメリカのフロリダ州では、14歳未満のSNSアカウントの開設を禁止する法律が制定されているらしい。
なぜこのような法律が制定されたのかというと、アメリカの保健福祉省の医療総監が「SNSには若者のメンタルヘルスに悪影響を及ぼす重大なリスクがある」と警鐘を鳴らしたという背景がある。
これは確かにといえる。
SNSは非常に悪影響だとは筆者も思う。
・匿名性が高く攻撃的になりやすい
・言葉の暴力を受けやすい
・時間を奪うコンテンツがたくさんある
・他社を基準として自己判断をしてしまいやすい
など
SNSに触れているとこのような悪影響があると考えられることから、筆者もSNSの危険性というのは広めたほうが良いとは思うが、”規制”にすると少しやり過ぎ感を感じざるを得ない。
参照元:子どもへのSNS利用規制は必要か 海外の禁止法案から考える
オーストラリアの16歳未満のSNS利用の禁止
また、オーストラリアでも、16歳未満のSNSの利用を禁止する法案が可決されたそう。
この法律は「若者をソーシャルメディアの害から守る」という観点から支持されていて、主に企業に対して法的処置をとるような法になっている。
16歳未満にアカウントをつくらせてしまったら企業に対して罰金が最大で約50億円かさられるみたいだ。
一方で、この法案は安易なものであるとの声もあがっている。
・規制を避けてアカウントを作ることはできる
・多様な価値観に触れる機会を奪っている
・SNSを奪っても子供たちの間で起こるイジメ問題はなくならない
このような視点から法案の安直性を指摘しているみたいだ。
これは難しい。確かに筆者が16歳未満だった頃はまだSNSもそこまで普及しておらず、SNSがないからと言って不幸だったのかというとそうではなかった。
確かにSNSから受ける害というのは多いと思うが、筆者はそれ以上にこの世の中、特に社会に存在する大人たちのモラルの欠如が子供達を暗黒面に引き込んでいるんじゃないかと思ってるので、SNSの話ではないと思ったり。(もちろん良い大人の方々も多くいる)
豊明市のスマホ条例は世界の流れに沿った条例にみえる

豊明市の「スマホ条例」はこうした海外の動向の影響を受けて考えられた法案なんじゃないかななんて思ったりして。
SNSの普及と、普及に伴うSNSから受ける害の可視化というのは最近多くなってきていると肌感覚と、実際の研究からも言われているそう。SNS依存とかね。
このような現状を打破するために世界でもスマホの利用を制限したり、ゲームを制限したり、特定のアプリ(SNS)を規制したりしている。
このような世界の流れに乗って、日本国内でも「スマホを制限する条例があっても良いんじゃないか?」ってな感じで考えられてそう。
でもやっぱり、スマホ条例っていらないよなって筆者は思う。
なぜ「スマホ条例」はいらないと思うのか

なぜ「スマホ条例」をいらないと筆者は思っているのかについてお話ししたいと思う。
筆者が「スマホ条例」をいらないと思っている理由には以下の4つの理由がある。
・禁止されると逆にやりたくなるから
・”国”が人の自由を制限するルールを決めるのは悪手
・たぶんもっとやることがある
・今後”親”に責任追求がいく可能性がある
禁止されると逆にやりたくなるから
心理学の一つに「心理的リアクタンス」という心理作用がある。
これは、「禁止されるとやりたくなる」という、あの心理状態を説明するものだ。
人間は本来あるべき選択や行動の自由を制限されてしまうと、その自由を取り戻そうとする心理が働く。これが心理的リアクタンスだ。
つまり、この「スマホ条例」というものは、本来誰にも邪魔されずに操作することができるスマホの操作を条例により禁止することによって、その制限されたスマホの操作という自由を取り戻すために、その条例に抗おうとする心理が働くということだ。
何が言いたいかっていうと、「条例で定めてしまうと、もっとやりたくなるよね」っていう話だ。
親にゲームなんかするんじゃないといわれると、もっとやりたくなる時みたいに。だから、スマホを制限したいなら、制限しないほうが良いのだ。
”国”が人の自由を制限するルールを決めるのは悪手
”国”という一つの巨大な存在が、国の中にいる人々という小さな存在に対して、その人々の自由を制限するルールを定めることは悪手だといえる。
スマホ条例でいうと、決して強制性は強くないにしろ、地方自治体という大きな団体が、国のルール(憲法)にのっとり、ルールを決めているということは、「力あるものが弱きものの自由を制限する」というような支配感を感じてしまう。
なんなら、ちょっと大袈裟かもしれないが、日本国憲法で保証されている「基本的人権」の「自由権」(表現・思想の自由)を侵害しかねないことなんじゃないかとも思う。
昔であれば、アナログで表現や思想の自由を語っていたが、今ではデジタルで語れる世の中になっており、その権利はたとえ子供だろうが、侵害されるべきものではない。
こうやって、憲法とか思想とからめるとスマホ条例に対する問題っていうのは難しくなってくるよね。
たぶんもっとやることがある
たぶんスマホ条例よりも、もっと力を入れるべきものがあると思う。
確かに、子供たちの健全性を守るということは大事なことだし、蔑ろにして良いっていうわけではないけれど、強制力はないけどスマホ条例を制定して、相談支援できる環境だったり、スマホによる健康被害の抑制を測ります!っていうのは、なんか違うと思う。
アプローチを間違えてる。
あくまでも地方自治体は、その街で過ごしやすくする環境を整える機関だと思うから、「何かを禁止・規制」するのではなく、それを民事的に行っている企業や団体を「支援」することが必要だと思う。
あと、豊明市では他にも「人口の減少・少子高齢化」「子育て世代の転出増加」「空き家の多さ」「道路の整備の遅れ」など様々な問題があるっぽい。
「スマホ条例」を制定して、はい終わりだとこれはなんの対策にもなっていないしパフォーマンスになってしまう。
そうではなく、今ある問題を精査して、より緊急性の高い問題に着手していかないと街がなくなり条例だけが残るということにもなりかねないのではないだろうか。
参考元:豊明市が抱える課題の整理
今後”親”に責任追求がいく可能性がある
例えば、「お酒は20歳」からという法律で決められているものがあるが、あの法律自体は良いのだが、「この法律があるからダメだよ、法律を破っている子供を叱らない親はダメ」という責任追求が”親”にいってしまうというのが怖い。
お酒に関しては、確かに法律で全国で決められているルールであるから、納得はするが、強制力がない条例とはいえ、地方自治体が定めているからダメだよというのを子供ではなく、親に向けて伝えようとすると、どうしても親の責任という風潮が広まってしまうのではないかと思う。
筆者が想像しているのは、この条例が「外堀から埋めていこうか」というようなルールにならないかが心配ということだ。
「スマホを条例に基づいた時間以上子供に見せているのはダメですよ」という圧力を親にかけることにより、その条例を破る子供は、親が悪いみたいな思考になり、親を総叩きするような風潮にならないかという懸念がある。
「スマホ条例」は「ブラック校則」みたい

以上のような「スマホ条例はいらない」理由が筆者にはある。
よく考えてみたんだが、「スマホ条例」って学校の”ブラック校則”と似てはいないだろうか?
・パーマ禁止
・耳にかかる髪は禁止
・ジャージ登校禁止
・帰りの買い食い禁止
など
目的がよくわからないし、もし目的があったとしても納得できない校則がブラック校則というやつだ。
「スマホ条例」もそれに似ている。「スマホ条例」は確かに、明確な目的(子供の県税制の保護)があるが、ビジネスで”エビデンス”(証明するもの)といわれるものがない。
つまり、「本当にスマホを制限することが子供の健全性を守れるのか」という問題に多くの根拠を明言していないのだ。
だから、「何この条例、本当にいるの?」というようなブラック校則に対して感じる感情と同じものが沸き起こってくる。
腑に落ちるところもあるけどもっと良い方法はあるはず
今回は「スマホ条例」について筆者が感じたことを長々と綴ってきた。
読者の皆さんは、「スマホ条例」に対してどう思っただろうか?
「スマホ条例」の中身を見てみると、確かに腑に落ちる部分はある。(子供の健全性を守るなど)
腑に落ちる部分はあるけど、同じことになるが、もっと良いアプローチ方法があるはずだ。権力を握っているように見える地方自治体が自由を制限するような条例を制定してしまうと、まさに自由を制限しているように感じられ反発につながることは火を見るよりも明らかだ。
問題が起きている部分に制限を設けるのではなく、問題の外側の部分に視点を置いてみることで、新しい解決策が見えてくるかもしれない。
まぁこのような問題は難しく、なかなか答えの出ない問題なので、筆者がこうやって一方的に話しているのは、ほぼ解決にはつながらないと思うから、この辺で終わりにしたいと思う。
この記事が読者の皆さんの何かの興味に繋がったら嬉しい。
この記事も役立つかも

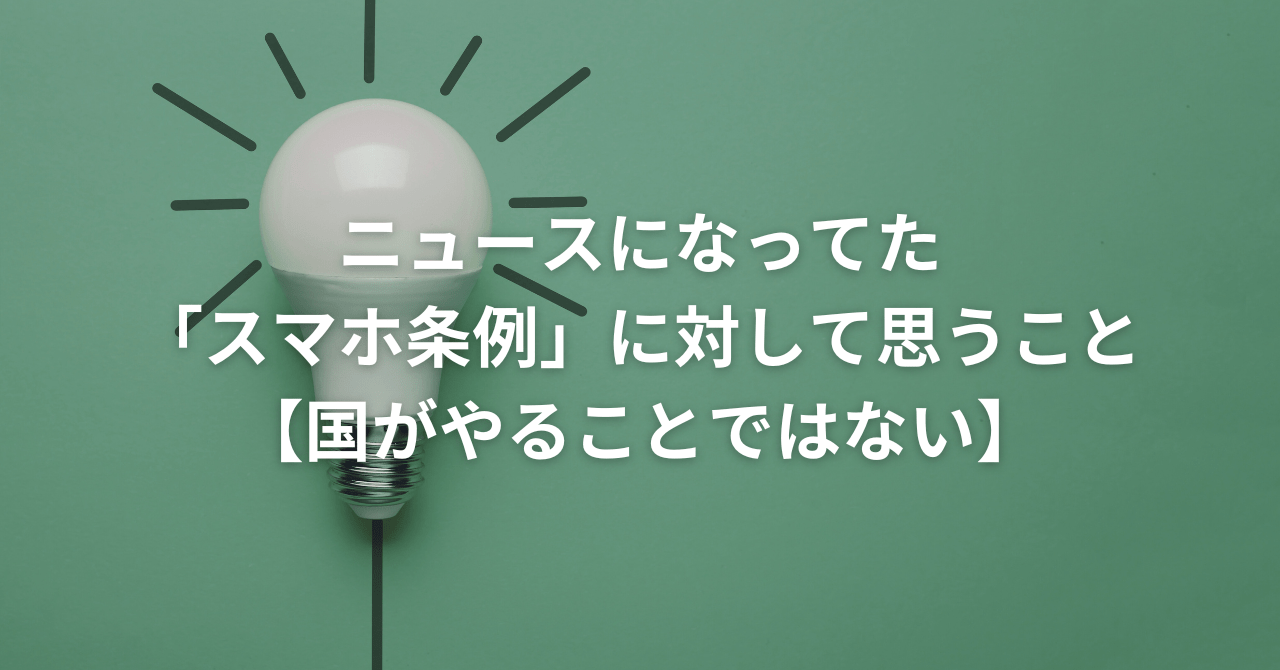
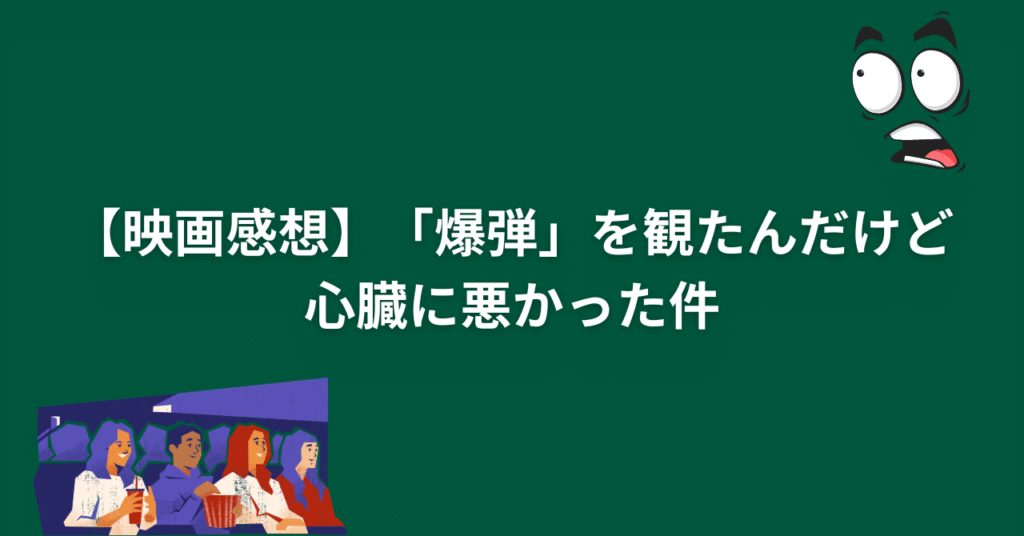
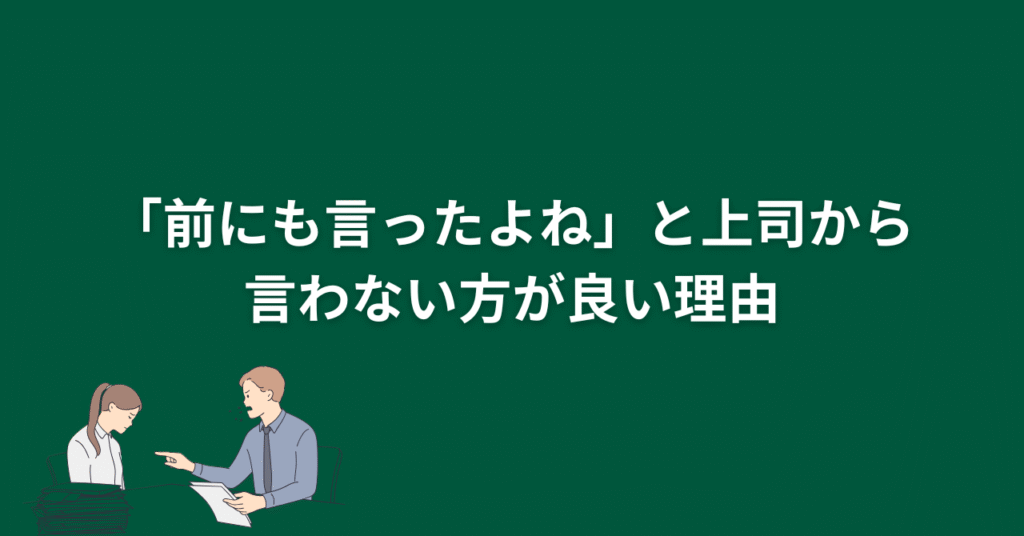
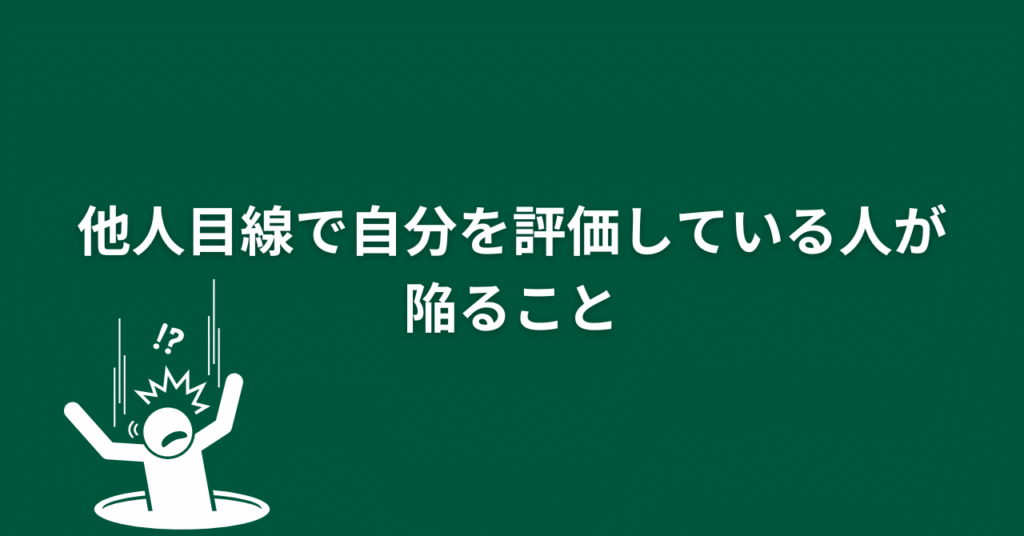
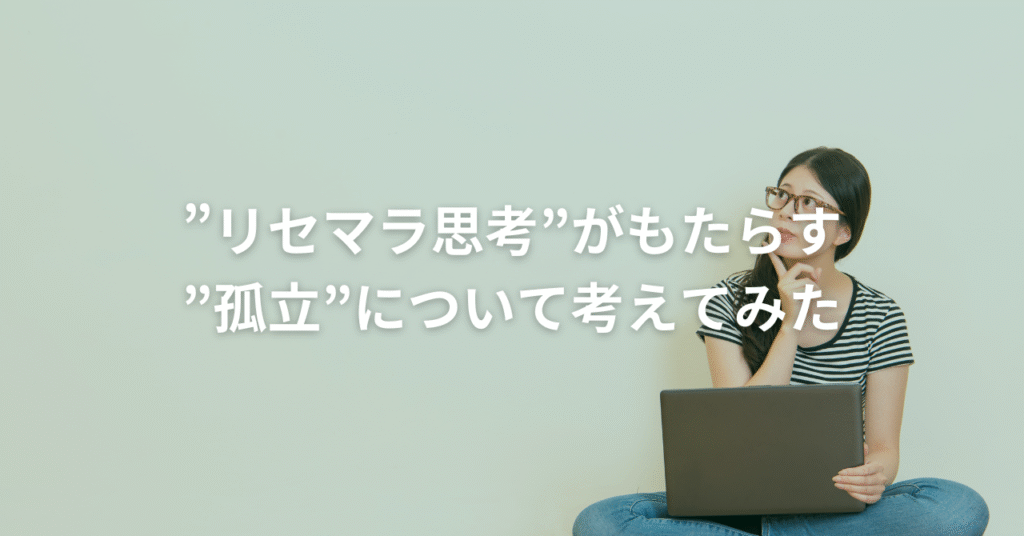
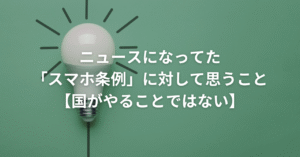

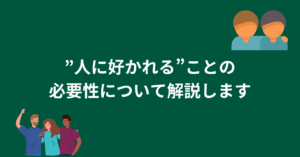

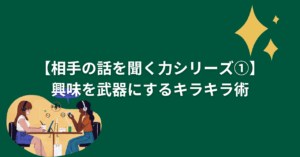
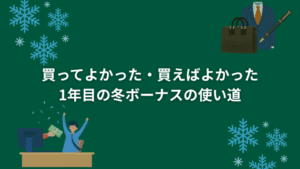
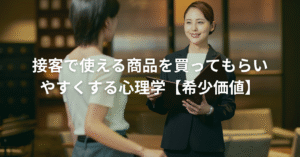
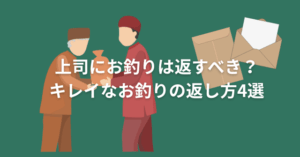
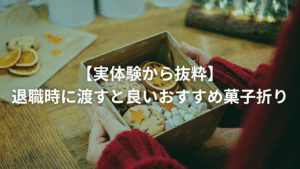

コメントする