こんにちは筆者です。
皆さんは大手時計メーカー”セイコー”の創業者である「服部金太郎」の人生を物語を描く「黄金の刻」という小説をご存じでしょうか。
本小説は、史実を元にしたフィクション小説ではありますが、人生において学べる名言がたくさん出てきます。
筆者は実際に本書を読んで、多くのことを学べ、「なぜセイコーがここまで大きくなったのか」ということが何となくですが分かった気がしました。
この点において
・今何かを頑張っている人
・20代社会人で日々の仕事で悩んでいる人
・達成したい目標がある人
そんな人に参考になる小説なんじゃないかと思ったわけで、ぜひ皆さんにも小説「黄金の刻」を読んでみて欲しいなと思い、「これは学びになるな」と感じた”名言”を一部お届けし、「少しの気づき」を得てもらい、本書に興味を持ってもらうという意図で記事をお届けします。
この記事でわかること
・頑張る日々を力づける名言
・何かを取り組む時に大切な考え

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験
- 吃音症歴20年
- 元オートローン営業マン
- 元オーダースーツフィッター
- 元百貨店販売員
- 現Webマーケター
- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味
- 酒は飲めない、よく体調崩す人
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
【黄金の刻】内で登場する筆者が感じた名言を一部紹介

本記事では、小説【黄金の刻】の中で登場する、実際に筆者が読んでみて「すごく良いな」と感じた名言を紹介していきたいと思います。
ただし、小説内にある全ての名言をこちらで紹介してしまうと、これから本書を読む方の楽しみや、無駄な認知バイアスに繋がってしまうので、あくまでも本書に登場する名言の一部を紹介させていただければと思います。
それと各名言について筆者自身が感じたことを付け加えさせていただきますので、それが認知バイアスにならないように、一つの”解釈”として楽しんでみてください。
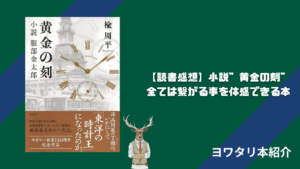
作品内の名言
ここから作品内の名言を紹介していきたいと思います。
筆者が抜粋した名言は以下の10個です。もし、本書が手元にあれば、自身でも探しつつ参考にしてみてください。
日頃の生活ぶりが、どうして分かるのかと君は思うだろうが、見ている人は見ているものだし、聞こえてくるものは聞こえてくるのが世の常というものでね
これは本書のp24で主人公の「服部金太郎」が最初に丁稚奉公として働いていた「辻屋」の相談役の蒲池が主人公に向かって言った一言です。
何か物事に対して頑張っていると、誰かに力を誇示するために頑張っているわけではないが、頑張っている姿を少しは認めて欲しい、そんな気持ちになる時があります。
そんな時に思い出したい名言といえます。
人の頑張りは見ている人は見ています。筆者もこれは実際に経験しました。
アルバイトの頃、忙しくて毎日が必死でした。ある忙しい日になかなか上手く仕事ができなかった時、そのバイトの先輩から「ちゃんとやっているのは見ている」という励ましの言葉をもらいました。
この経験からも本書に登場するこの名言は本質をついた名言なのではないかなと個人的に感じました。
参照元:「黄金の刻」p24
いいえ…それは、暇を頂戴してから探すのが筋だと思いまして…
主人公が丁稚奉公として働いていた「辻屋」を自らの夢のために辞める時に、相談役の蒲池に次の勤め先について聞かれた際の一言です。
現代では「現職で働きつつ裏で転職活動をする」ということが普通であったり、安全といわれています。確かに、働きつつ生活のためのお金を得ながら、収入を途切れさせずに次の職へ就くというのが実に合理的で、生活を守ることができる選択であることは間違いありません。
ですが、それまでお世話になって社会人としてのマナーや、仕事に対する姿勢などこの先役に立つ知恵をお金と共にくれた会社に対して行うこととしては少し”不義理”にも感じてしまうもの。
これは筆者も同じように考えており、実際に筆者は1社目をやめた頃は似たような辞め方をしました。
ただ、これは「在籍時の転職活動は不義理だからダメ!」ということではありません。むしろ、働きながら転職活動をした方が生活が安定するので良い選択です。
それとは反対の主人公の発言ではありますが、この考え方も筆者は一理あると思います。実際に筆者も一社目からの縁が今でも繋がっていますし。
今就いている会社の辞め方の一つの選択肢としてこの名言は参考になるのではないかなと感じました。
参照元:「黄金の刻」p53
自分もそうして一人前になった。だから弟子にも同じ苦労をなんて、そんなもん、修行でも何でもねえよ
主人公が兄弟子に技術について何も教わることができず、むしろ不遇を受けていたことを知っていたという親方との会話にて登場する名言です。
これも筆者の心に刺さりました。
筆者も本当に申し訳ないと今でも思っていますが、これと似たようなことを社会人になって2年目の後輩ができた時にやってしまいました。
筆者は結構見て覚えて自分なりに考えて実行して失敗して改善してというタイプだったので、後輩にもこのやり方を推奨してしまった結果、筆者に相談することができない状況を作ってしまいました。
この経験から、自戒も込めてこの名言が心に刺さったわけです。
「自分も苦労したから後輩、教えを乞う人にも自分と同じ経験をさせて覚えさせよう」というのは、単なる思考の停止であり、面と向かって教えることから逃避するのと同じことです。
もしこれから後輩が入ってくるのであれば、この言葉を忘れないようにしてみてはいかがでしょうか。
参照元:「黄金の刻」p60
お前はこれから先、様々な人間と交わることになる。中には、お前を利用しようとか、騙そうとか、下心を持って近づいてくる人間もいるだろう。お前が、大きくなればなるほど、必ずその手の人間が近づいてくる。世の中は善意の人間だけじゃねえってことを学んだだけで十分だろう。
これも主人公と、兄弟子から不遇を受けていることを知っている親方との会話の中の一節です。
人には色々な人がいます。
純粋で良い人もいれば、自己利益しか考えず、どう搾取するか考え近寄ってくる人間もいます。決して良い人だけではないのが世の中です。
そのことを改めて教えてくれる名言だなと筆者は感じました。
特に社会人になるとこれが顕著に現れてきます。
あなたに色々と良くしてくれていた人が、自分の利益にならないことを知った瞬間に、あなたとの関わりがなくなる、そのようなことが起きます。
ですが、逆に自己利益がなくてもあなたを良くしてくれる人も必ず現れます。そんな人を大切にしていきたいと思える名言だと感じました。
参照元:「黄金の刻」p64
約束通り返せなきゃ、どんなにいい人間関係でもあっという間に崩れちまう。それが借金だ。だから借金をするやつは、返せなくなって縁が切れても構わねえ、要はどうなっても構わねえってやつのところへ行くんだよ。だから、身内でも親、兄弟のような、何があっても縁が切れねえところは後回し。親しい仲でも、本当に大切に思っている人間のところへは、行かねえもんなのさ。
これは主人公が働いていた時計屋の亭主が兄弟子からの借金の連帯保証人にさせられ、結局兄弟子がとび、主人公が働いていた時計屋の亭主がその借金を肩代わりすることになった時、借金取りが亭主に向け言った一節です。
まさに「金の切れ目は縁の切れ目」ということわざを使うのがピッタリといえるでしょう。
そして、この一節から感じ取れることはそれだけではありません。
「約束通り返せなきゃ」の”約束”ということが大切なことではないでしょうか。もちろん、お金が介在する関係になってしまうと、人間関係が途切れてしまうということもあります。
もう一方で、「約束を破る」ということにおいても良い人間関係を壊す原因になります。
いくら「あの子は遅刻してくる人だから」とキャラで片付けられる時があっても、それが度重なると、人間と人間の間にある信頼は失墜していきます。
そのうち良い人間関係だったものも壊れて縁が切れてしまう。そんなことがあります。
どんなに小さな約束だろうと、約束したからには”約束を守る”ということが良好な人間関係の継続には必要なんじゃないかと感じた名言です。
参照元:「黄金の刻」p75
財産の一切合切を失った主を前にして、給金を要求する。その心情が金太郎には理解できなかった。そして人間の奥底に潜む、冷酷さ、醜さをまざまざと見せつけられた気になった。
これは主人公が働いていた時計屋の亭主が借金取りからお金などを全て回収されてしまった時の情景を表た一節です。
”名言”ではありませんが、この一節も筆者の心に刺さったので紹介させてください。
今までお給与だけではなく、ご飯をもらって従業員みんなで和気藹々と食べたり、色々な雇い主と従業員という壁を越えて色々なお世話をしてもらっていたのにも関わらず、給料が支払われないとなった時に急変して亭主を責め立てる従業員らの姿を主人公は目にしました。
これには筆者も理解ができず、憤りまで覚えました。
利害関係を越えて心情で繋がっていると思った関係を、たかが自己利益のみを考えた人間に壊されてしまう。こんなに悲しく、無情なことはありません。
最近、ネットなどでついつい目にしてしまうのは「自己利益」を優先した思考が蔓延っていることです。「自分さえ良ければ良い」「自分の好きなことをやろう」このような思考は解釈次第で良薬にもなりますし、毒にもなります。
確かに「自分を大切にすること」は大事なことです。しかし、人と人が繋がってできている世の中において、他者を蹴落としてまで自分の保身を考えたり、自己利益を考えたりするのは、相手の情を裏切ることです。
そんな考えが増えてしまったら、まさに競争社会、弱肉強食社会、弱いものは蔑まれて当然な社会ができてしまいます。そんな格差がひどい世の中の何が楽しいのでしょうか?
情報が簡単に手に入る現代だからこそ、このような「自己利益最優先思考」にならないようにするポリシーや、考え方が回り回って自分を豊かにするために必要なのです。
参照元:「黄金の刻」p80
若輩者がいっても説得力に欠けますが、何をやろうと、どんな目に遭おうと、中途半端ってのが一等悪いと思うんです。だってそうじゃありませんか。堕ちるところまで堕ちれば、それ以上堕ちる心配はしなくていいんです。少しずつでも、這い上がっていけば、それだけ物事は好転していくんです。そんな日々を送り続けて行けば、振り返って見たら、こんなところまで昇って来たかと思える日が、きっと来るんじゃないでしょうか。
これは主人公が全てを失ってしまった雇用主である時計屋の亭主に言うセリフです。
人生には良いことも悪いことも起きます。これは自我を持ち、”進路”を考える時期になる中学生の頃から少しずつ感じることです。
山あり谷ありの人生の中、現実が上手くいかない時、それが続いてしまうと「自分はダメなんじゃないか」「自分にはセンスがないから諦めよう」そんな地の底で”行動”という乗り物から降りてしまいそうな時があります。
この時、地の底である”谷”で現実を好転させようとする”行動”を辞めてしまうと、そのまま現実は何も変わりません。
この時にどれだけ谷から這い上がるかというのが、人生を好転させるには大切です。
谷の底はもうありません。そこから上手くいくための”行動”をし続けることが、その苦しさから逃れる方法の一つであるということをこの一節から学びとることができます。
参照元:「黄金の刻」p86
まず、本人の修理を身につけようという意志と熱意。次に熟練の技を持った職人の修理をどれほど見るか。その上で、基本技術を徹底的に繰り返し、指先が自然に動くまで体に叩き込む。そして、修理する時計がどこを、どう直してほしいのか、時計の声を聞く。つまり、想像力と勘を鍛えることだ。
主人公が時計の修繕所を創業した時、請け負った修理の出来についてある人が店に来店した時の、そのある人との会話です。
この一節がなぜ筆者に響いたのかといいますと、「なぜ好きなことをした方が良い」ということを多くの人が言うのか少しわかった気がしたからです。
仕事でもプライベートでも”好きなこと”をした方が良いと多くの大人たちに言われますが、これは、「好きこそ物の上手なれ」だからではないかと思いました。
好きなものだからこそ、没頭することができ、好きなものに関する知識を好んで収集することができ、好きなものの技術なり、知識なりを向上させるために意欲的に学び続けることができる。結果、それが大きな力となり自分自身に宿る。
このサイクルを実現するのに必要なのが「好きなことをする」ということの背景だと筆者は感じました。
ですが、生活のために行うことが多い”仕事”において「好きなこと」を追求することは難しいものです。この時に役に立つのが「好きな作業を見つける」ということだと筆者は考えます。
・資料作り
・パワーポイント作り
・数字管理
など
仕事の中で自分が好きな作業に焦点を当てることが、この名言が活きてくるのではないかと感じました。
参照元:「黄金の刻」p95
それに、人に教えるってのは、案外難しいもんでな。一つのことを教えるにしても、どう表現するか、どんな言葉を使うかで、相手の分かりが早くもなれば遅くもなる。実際、一人で仕事をするようになってから、ああ、師匠は、あの時こういうことをいいたかったのかって、後になって腑に落ちることが山ほどあったからな。だから、教わる方にも才が必要だが、教える方にはもっと才がいると思うのさ
こちらも主人公とある人との会話において展開される一節です。
人に教えるというのは一見すると、簡単そうに思いますが、実際はそうではないということに気がつく言葉です。
自分が教えたいことと、違う認識で教えられた人は受け取ってしまうこともあります。
これはこの一節の通り、「教える方の技量」が大事だということだと思いました。
筆者も実際に後輩に仕事を教えた時に自分が伝えたいことをなかなか伝えることができなかったという経験があります。
「教えられる方が覚えが悪い」と胡座をかくのではなく、「相手にどう言えば伝わるのか?」「どういう教え方が相手の腹落ち度合いが高いのか」ということを意識して”人に伝える”という行為をしていきたいと、この名言を読んだ時に感じました。
参照元:「黄金の刻」p97
金額の多寡じゃねえんだよ。世の中ってのは世知辛いもんでな。特に自分の利害が絡むと、人の道に外れるようなことも平気でやるやつが滅法多いんだ。坂田さんにしてみりゃ、あんたが仏に見えただろうし、世の中、まだまだ捨てたもんじゃねえと、希望と生きる勇気をもらったと思うよ
こちらもある人と主人公の会話の一節で、主人公にある人が言ったセリフです。
この名言でも「自己利益至上主義」について考えさせられました。
確かに筆者も、社会人になって、自分の利益が損なわれた人が豹変して暴言を吐いたり、態度が悪くなって強くあたられた経験があります。
そして、筆者自身も自分に大きな損が降りかかった時についつい心の中で「どうして自分だけこんな目に遭わないといけないんだ」「相手がそうならこちらも同じ対応をしてやろう」とそんな負の感情が湧いてきてしまいます。
ただ、この時に大切なのは「どれだけ負の感情が湧いてきてもその感情に流されないこと」ということで、何よりも「人の道から外れない」つまりは、”人情を大切にする”ということを忘れないようにしようと、この名言から学びました。
参照元:「黄金の刻」p98
本書から学ぶこと
本書からは、「人生において”社会”という名の人と人との繋がりの中で生きる時に忘れてはいけないこと」を学びました。
この学びは本記事の冒頭でお伝えした
・今何かを頑張っている人
・20代社会人で日々の仕事で悩んでいる人
・達成したい目標がある人
など
主に自分を含めた働く社会人の方々にとても役に立つものなのではないかなと感じます。
人と人はたとえ”物”や”サービス”が介在したとしても、大切なってくるのはやはり”情”です。
どんなに良いものを扱っていようが、接客が悪かったり、営業態度が悪かったりすると、貴重なお金を払おうとは思いませんし、その人と長く付き合っていたいなという利害関係を超えた関係性を作ることはできません。
利害関係を超えた”情”で繋がる人間関係を作るということにおいて、とても重要な学びを得ることができる、そんな一冊なんじゃないかと筆者は感じました。
さいごに
今回は小説「黄金の刻」に登場する、筆者が学びになった名言を紹介してみました。
本記事が、今を頑張る人たちの活力となれば幸いですし、小説「黄金の刻」に少しでも興味を持っていただいて、実際に自分で読んで、筆者とは違う視点の学びを得て、現実でより良い日常を過ごすために活用してもらうということが理想であります。
今後とも学びになった書籍を紹介していきたいと思います。
この記事も役に立つかも

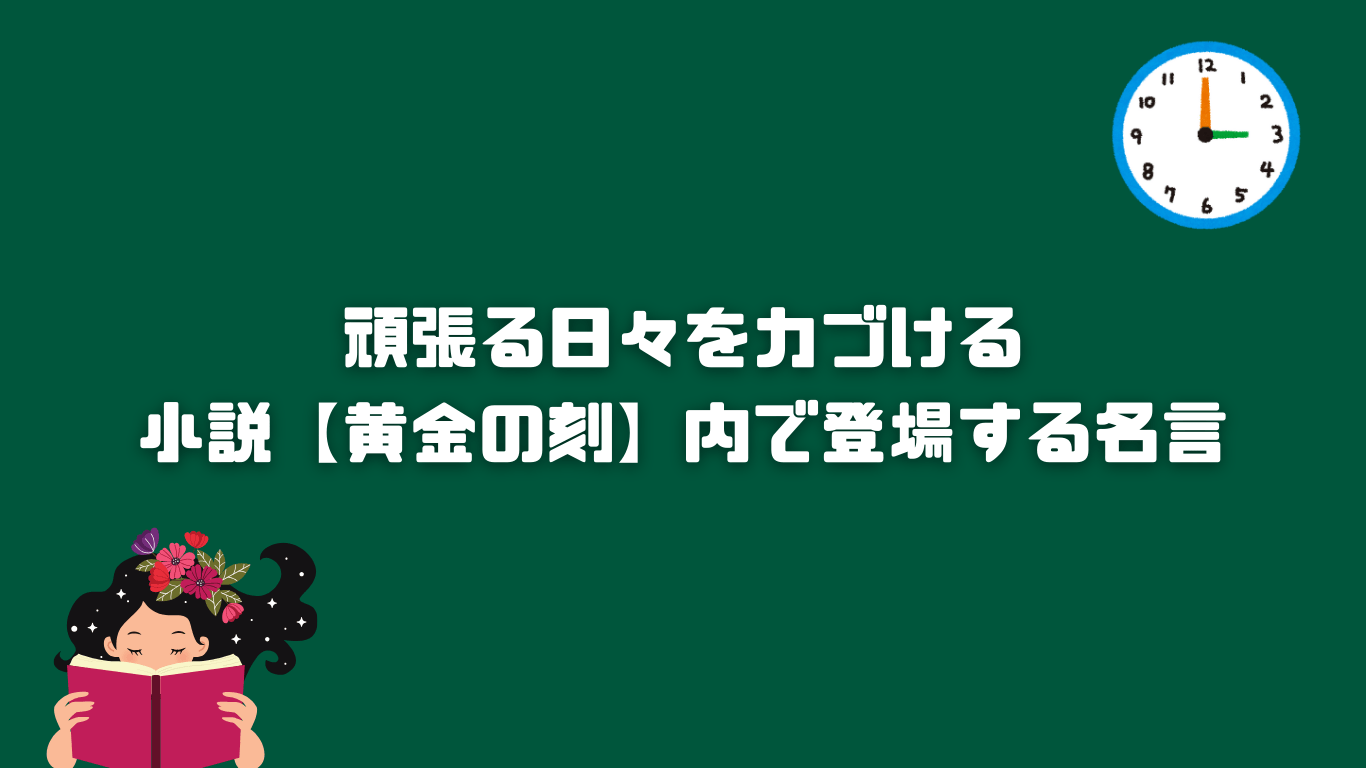

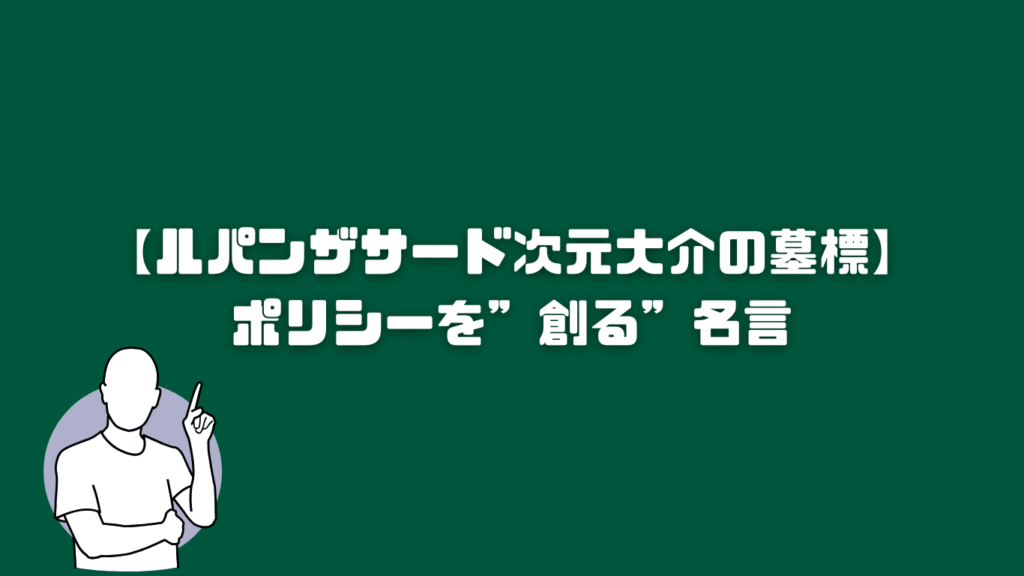
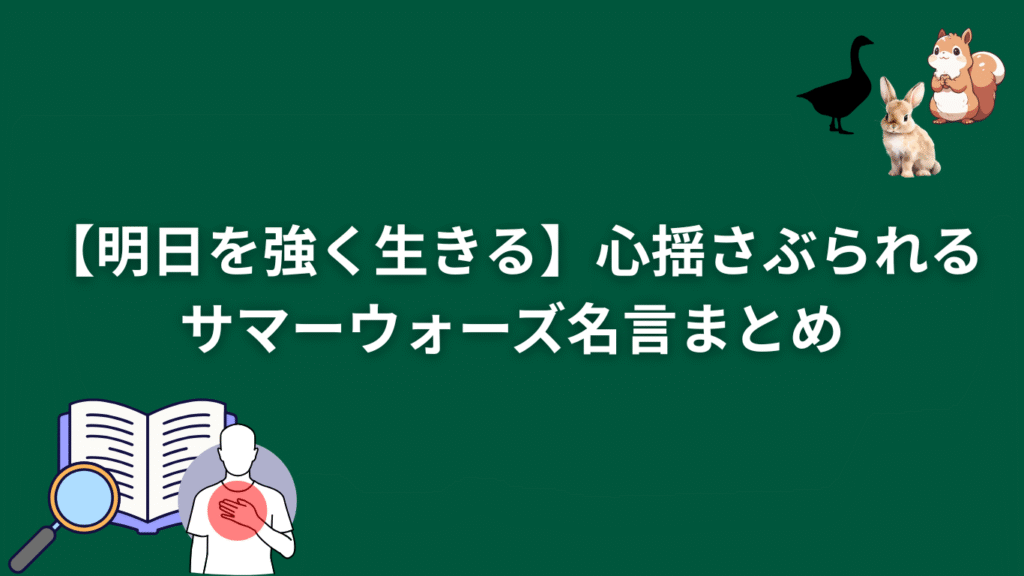
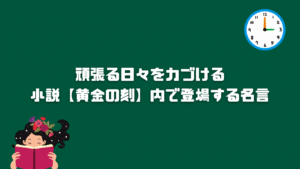

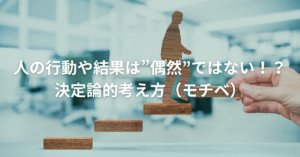
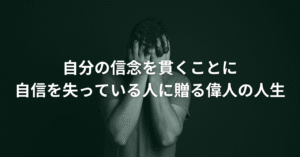

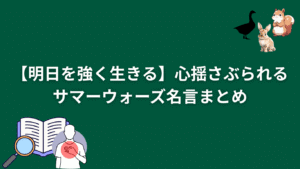
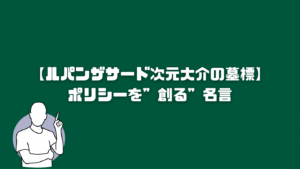
コメントする