筆者だ。
仕事上、分からない事があったり、アドバイスを貰いたい時、先輩に質問を行わないといけないタイミングってありませんか?
特に、社会人になりたての頃は、まだ直属の先輩と仲が深まっておらず、質問をするのに躊躇しがちです。
「仕事を円滑に進めたい気持ち」と「先輩に質問したいけどしにくい気持ち」そんな気持ちのジレンマに陥っている方に、今回は「失礼にならない先輩への質問方法」を例も合わせて紹介していきたいと思います。
筆者自身、会社の先輩たるものを経験していること、他に先輩を経験している人から聞いた話をもとに今回記事で紹介していきたいと思います。

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験
- 吃音症歴20年
- 元オートローン営業マン
- 元オーダースーツフィッター
- 元百貨店販売員
- 現Webマーケター
- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味
- 酒は飲めない、よく体調崩す人
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
質問する時の事前準備
先輩に失礼のないように仕事関連の質問をする時にやっておくと良い”事前準備”を紹介したいと思います。
事前準備は2つあります。
・まずは自分で考える
・5W1Hを利用して質問を整理する
まずは自分で考える
意外と社会人経験が長い人でも「まず自分で考える」があまり得意ではない人が多いです。
・取り組んでいる仕事の中で、つまずいているのはどういうところか?
・分からないのはどこの部分なのか、解決するにはどんな知識・理解が必要なのか?
このように”まずは自分で考える”癖をつけることで、つまずいている原因が判明した時に理解がしやすくなり、教えてもらったことが定着し、同様のミスをしにくくなります。
一旦自分で考えることは、先輩の質問を身につける上で重要な事前準備となるのです。
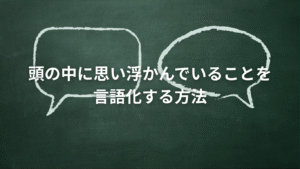
5W1Hを利用して質問を整理する
英語の授業で習ったことがある人もいると思いますが、復習も兼ねて振り返ってみましょう。
5W1H
Who 誰に
What 何を
When いつ
Where どこで
Why なぜ
How どのように
この5W1Hを元に、「自分が取り組んでいる仕事」を分析してみます。
Who :取引先に
What :見積書を
When :一昨日
Where :取引先の会社で
Why :取引先の要望で
How :他の商品の比較表も乗載せてとの要望
このように仕事の内容を当てはめてみることで、漠然とした”わからない”から脱却することができます。
どこの部分が分からないのかを先輩に質問をする前に明確にしておくことで、的確な回答を貰うことができます。
質問する時の失礼にならないコツ
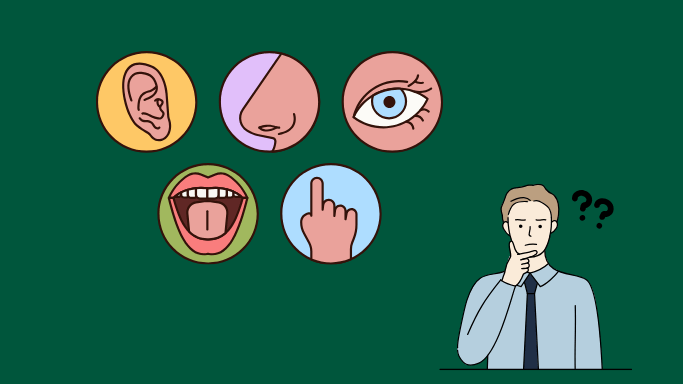
先輩に質問する時に、一歩間違えてしまったら失礼な質問方法になってしまうことがあります。
少なくとも以下の点をおさえておけば、先輩が失礼に感じることがなくなります。
①状況と考えを伝える
②結論から話す
③”聴く”姿勢をとる(メモ)
④質問は端的に
⑤ビジネス枕詞を入れる
⑥相手に許可をとる
①状況と考えを伝える
現状どうなっているのか?現状に対してどう考えているのか?を先輩に伝えることで、的確な回答をしやすくします。
・今どんな状況なのか?
・その状況に対してどう考えているのか?
この2つがわかっていなければ、先輩からしたら「何をどう回答すれば良いのかわからない」ということになりやすいです。
というのと、状況に対して考えがなければ、回答をもらっても身につきにくく、同様のミスを再発しやすくなってしまい、同じ質問を先輩にしないといけなくなってしまう可能性があります。
これらを防ぐためにも、状況と自らの考えを伝えると良いです。
②結論から話す
「結論から話すこと」は先輩の仕事の時間を最小限いただく、ということに繋がります。
質問やアドバイスを求める時に、結論から話すことで、先輩は話の要点を最初におさえることができ、瞬時に回答することができるからです。
要点に付随する話を省くことで、質問やアドバイスの回答に迅速かつ的確に回答でき、先輩の仕事時間を減らさなくてすみます。
忙しそうな先輩であれば、特にこのコツは意識して取り組むと良いでしょう。
③”聴く”姿勢をとる(メモ)
足伸ばして腕組んで背もたれに深く腰掛けている状態で話を聞かれたらどうでしょう?
あまり良い気持ちにはなりませんよね。
先輩に失礼にならない回答を聴く姿勢は以下の4つを意識すると良いです。
・体を向ける
・目または眉間を見る
・軽く前のめりになる
・メモをとる
体を向けることであなたに注目してますというシグナルを発信し、目または眉間に視線を向けることで真剣に聴いていることを伝え、軽く前のめりになりあなたの話に興味津々ですという姿勢を見せるのです。
さらに大切なのは、「メモをとること」です。
メモをとるという行為は、話をしっかり記憶しておこうという姿勢に映り、先輩に対して失礼な印象を与えることが少ないです。
④質問は端的に
質問が長いと時間がかかってしまう他に、話の内容が複雑で理解が難しくなってしまい、的確な答えを考えるのが難しくなる。と言うデメリットがあります。
ですので、先輩に質問やアドバイスを求める時は、なるべく端的な文章を構成すると、先輩からして分かりやすく、解析度が高い回答を考えることができ、回答しやすくなります。
⑤ビジネス枕詞を入れる
ビジネス枕詞というのは、本題に入る前に入れる
・今お時間よろしいでしょうか
・お忙しいところ大変申し訳ございません
などのワンクッション言葉です。
これが入ることで、相手へ気遣いをしていることのアピールになり、不快に思われにくくなります。
⑥相手に許可をとる
ビジネス枕詞と内容は重なりますが、質問をする前に「今お時間よろしいでしょうか?」と質問を許可する構文を入れると、相手の状況を確認しているという配慮になり、先輩は不快に思いにくくなるでしょう。
さらに、踏み込むと、「今お時間3分ほどよろしいでしょうか?」と”時間”を明確にすることで、仕事に追われている先輩でも、”どれだけ時間がかかる”か知ることができ、時間に追われることがなくノンストレスで質問に回答することができます。
質が高い回答をしてもらうためにも、相手の状況を把握するようにちょっとした気遣いの言葉を言うことが大切です。
先輩に質問するタイミング
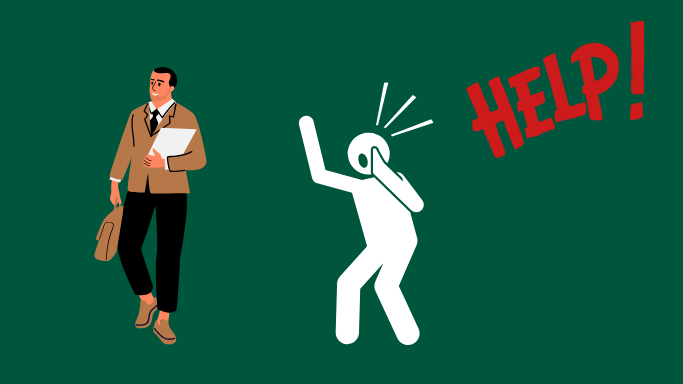
先輩に質問するタイミングによっては、忙しかったり、他の仕事で手いっぱいになり頭がいっぱいで余裕がない状況のときがあります。
そうした中での質問は的確な回答を聞き出せないどころか、先輩に対して失礼にあたってしまうかもしれません。
良いタイミングを見極めることが大切です。
実際に後輩がいる社会人にも聞いてみました。
・前後に会議がないタイミング
・朝一番
・業務が一段落していそうな時
・一対一のミーティングの時
前後に会議がないタイミング
実際に後輩がいる社会人に聞いてみました。
仕事上会議が多い部署とのことで、前後に会議があるときに少し複雑な質問を受けてしまうと、会議の事前準備などに支障をきたし、質問に答えにくいとのことでした。
これを意識すると、全く会議がない日が限定されてしまい、質問をできる時が限られてしまいます。
ですので、あくまでも参考程度にとどめておき、もし、会議の前後に質問をする必要があるのであれば、ビジネス枕詞を用いて先輩に話しかけると良いでしょう。
朝一番
朝一番に質問やアドバイスを求めると良いです。
なぜならば、朝一番はまだ仕事にとりかかる前であり、頭の中がクリアになっていることが多いからです。
一日の時間で一番余裕があるタイミングで質問やアドバイスを求めることで、先輩にかける負担が少なくなり、余裕がある分、回答の質も高いものを期待することができます。
業務が一段落していそうな時
先輩の業務がひと段落していそうな時も質問やアドバイスの回答を求める絶好のタイミングです。
やはりこのタイミングも、先輩の頭の中がクリアであり、余裕があるという理由から適切だと言えます。
・伸びをしている時
・飲み物を買いに行った時
・周囲の人と雑談している時
などが仕事が一段落したタイミングを見分ける行動です。
一対一のミーティングの時
先輩が仕事上のメンターやトレーナーであるのであれば、一対一のミーティングの機会があることが多いです。
ミーティングのタイミングで、普段仕事上の質問や、より良いパフォーマンスをすることができるようなアドバイスを求めるということが適切だと言えます。
もし、別に議題があるのであれば、そのテーマが終わってから先輩に聞いてみると会話の流れもスムーズになるので、良い回答が得られることに繋がります。
シチュエーション別具体的質問例
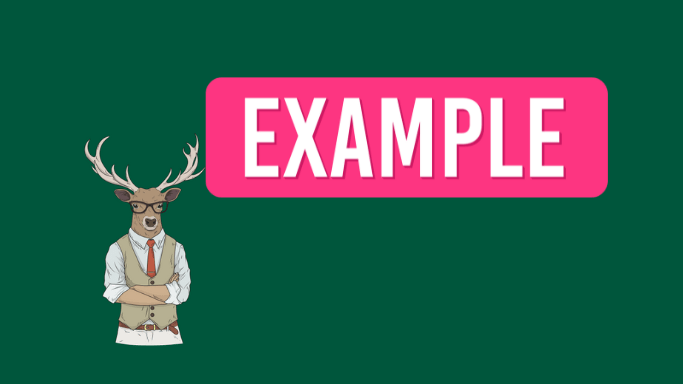
ここでは、具体的な先輩への質問の例を紹介していきたいと思います。
具体例を知ることで、「どう質問すれば良いだろう?」という疑問を解消することができます。
3つのシチュエーションと「デキる新社会人と思わせる質問」でまとめてみました。
忙しい中での質問例
先輩が忙しい中、質問やアドバイスを求めたい時、”ビジネス枕詞を忘れない”というのが大切です。
「忙しい中すみません、今よろしいですか?」
文の頭に「忙しいのはわかっているんですけど、本当申し訳ない質問に答えてくれ」という気持ちを込めた「忙しい中すみません」という”配慮の言葉”をいれることで、先輩に回答してもらいやすくします。
だいたい何も問題なく質問を聞いてくれます。
「〇〇さん今お時間〇〇分ほどよろしいでしょうか?」
こちらも前の例と同様に「先輩への質問のコツ」で紹介した、「まず許可をとる」という質問方法の具体例です。
文の冒頭に先輩の名前を入れることで”ネームコーリング効果”という、好感を上げる心理的作用も用いることで、先輩に失礼に感じられずに質問をすることができます。
また、具体的に質問の回答に要する時間を伝えることで、質問に答えてもらいやすくします。

「今よろしいでしょうか?ご相談がございまして…」
相談があることを丁寧に伝えることで相談に乗りやすくさせる手法です。
「何か重要なことなんじゃないか?」
と先輩に感じてもらうことで、「忙しいから後にして」という断りの言葉を封じる狙いがあります。
プラス文の冒頭で許可をいれることで先輩の仕事の状況を確認できる・配慮の言葉になるというメリットがあります。
「〇〇の件は〇〇でよろしいでしょうか?」
これも質問のコツの1つ「確認する」です。
要件の正か誤りを聞くだけなので相手もYes or Noで答えることができるシンプルな質問であり、時間を取らないと言うことがポイントです。
質問がシンプルで回答に時間がいらないと分かることで、先輩から要点のみを失礼にならずに聞き出すことができます。
会議中の質問例
会議中に分からないことがあったら、先輩に聞いておかなければ、仕事の円滑性に支障をきたしてしまいます。
会議中に先輩に失礼にならずに質問をする時は以下の例文を参考にしてみると良いでしょう。
「確認なのですが、〇〇は〇〇ということでよろしいでしょうか?」
これも質問のコツ「確認する」です。
「自分の認識は合っているか」ということを確認する質問です。
冒頭に「確認なのですが」と入れることで、「YESorNO」の回答の質問だと分かり、回答を引き出しやすいですし、事前準備で紹介した「自分で考える」ができているので、質問としての質が高いです。
「〇〇という案はすごく理解できました。もう少し〇〇に焦点を当てるのはいかがでしょうか?」
会議中に自分の意見を伝えたい時、発言者の意見を肯定して質問することで意見が聞かれやすくなります。
これがもし、「その意見はいけません。私の意見はいかがですか?」と言われたらどう思うでしょうか。
「なんだこいつぅ!」と白鳥警部のような声がでてしまうほど怒りを覚えてしまうかもしれません。
 たくしん
たくしん蘭さんを離せぇ、離さないと撃つぞぉ!参照
自分の意見の提案をする場合、先輩やその周囲にいる人に不快感を与えないために、まず発言者の意見を肯定することが重要です。
「大変申し訳ございません。〇〇という部分を理解することができませんでした。もう一度ご説明いただいてもよろしいでしょうか?」
冒頭に「大変申し訳ございません」という謝りと謙遜表現を入れることで、自分の落ち度を認め、丁寧にもう一度説明して欲しいというお願いをします。
このように質問をすることで「しょうがないな」と言う心理になりやすく質問に答えてもらえる確率も高いです。
先輩と2人っきりの質問例
特に新社会人で配属されたばかりで、先輩とはまだ親密度が浅い状態で2人っきりの状況になると、なかなかのキツさがありますよね。
そんな時にどう先輩に質問をすることで、あの重苦しい雰囲気から解放されるのか、具体的な質問例をあげていきます。
参考にしてみてください。
「週末は何されてるんですか?」
これは質問する方・答える方とも答えるのが簡単な質問の仕方です。
もし例え「寝ている」というたんぱくな答えが返ってきたとしても「どのくらい眠るんですか?」という”どのくらい?(How)”である5W1Hで話を深掘りすることができます。
また、関係が浅い初期の状態こそ、「何をしてるんですか?」よりも「何をされているんですか?」の方が文章的に丁寧な表現になり、失礼のない質問をすることができます。
「今週末は何されるんですか?」
前の例文とほぼ同じですが、これは直近の予定を失礼なく質問する文です。
やはりここも、文章を丁寧にすることが大切です。
「何されているんですか?」と丁寧な言葉にすることで、先輩から違和感なく情報を聞き出します。
また「今週末」というのも重要です。
「普段何しているのか?」よりも、近々の状況に関する情報であるがゆえ、先輩に興味を持っているという印象を与えやすくなります。
「今日の〇〇のニュース見ましたか?」
その日のニュースをみましたか?という質問は、時事問題に興味があることをアピールすることができ、真面目さの印象を先輩に与えることができます。
また、先輩がどう言うニュースに興味を持っているのかということも聞き出すことができ、先輩を知ることもできます。
「仕事はどうやればうまくいきますか?」
仕事に対してアドバイスを貰いたい時、先輩から上手くアドバイスを聞き出すことができる質問です。
この文のポイントは「素直さ」にあります。
素直にストレートに「仕事はどうやれば上手くいくか」ということを聞くことで、先輩に「やる気」や「ハングリー精神」など真面目で根性があるという印象を与えることができます。
変に笑いながら聞くよりも、真面目な声のトーンで、真剣に聞くことで先輩から的確なアドバイスをもらえることに繋がります。
デキる新社会人と思わせる質問例
「こいつ……デキるッ!」と先輩に印象付ける時の質問もあります。
ここで大切なのは、「質問の事前準備」と「質問のコツ」を徹底するということです。
「私はこう考えているのですが、いかがでしょうか?」
質問のコツの1つ「まず自分で考える」にあたります。
コツでも解説しましたが自分で考えて行動できる会社員さんは多くありません。
上司や先輩の言うことをただそのまま聞き続ける。
これだと長い目で見た時に自分自身も成長しにくいですし、年齢が上がっても同様のことをしていると、受動的にみられてしまう場合もあります。
ですので、自分で考えられるだけでデキる新社会人と見られやすいのです。
自己思考力をつけるには、読書が有効な手段です。
社会人になって仕事に繋がる何かをしたいと感じたら読書をしてみるのはいかがでしょうか?


「一度自分で試してみたのですが、合っていますでしょうか?」
こちらは「自分で考える」をした上で、実践してみた結果を踏まえて、先輩にやり方が正しいのか聞く質問例です。
考えた上で一度試してみる。
試してみることは大きなことでなくて大丈夫です。
「エクセルの表を作ってみました」など難易度が比較的易めの業務で大丈夫です。
ただ、この質問をしすぎると「そんな聞いてこなくて良い」となるので、挑戦するものの難易度はどんどん上げていくと良いです。
「こちらの件は〇〇ということでよろしいでしょうか?」
「確認する」という行動が、”デキる新入社員”と認められやすくなります。
指示を受けたことを確認することで、「任せても大丈夫だ」という気持ちにしやすいですし、「しっかりと要点を抑えている」アピールにもなります。
先輩の信頼を得るための質問方法です。
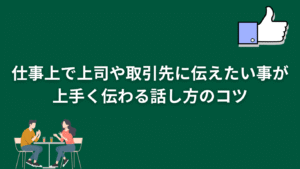
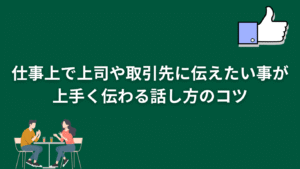
質問後の先輩に失礼にならない行動
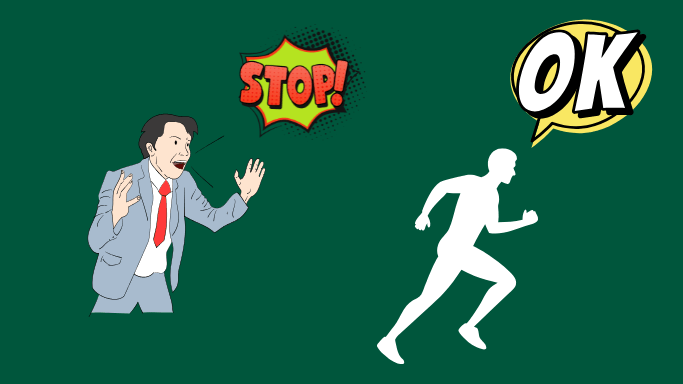
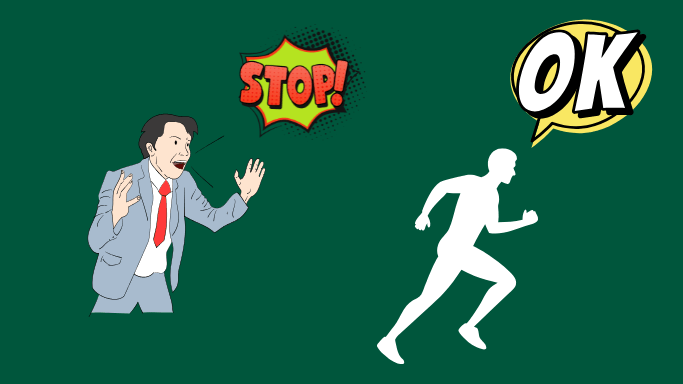
質問やアドバイスを先輩に求めた後に、とっておきたい失礼にならない行動を紹介します。
これを知っておくことで、質問のみならず、その後の行動でも先輩から信頼を得ることができます。
・相槌をとる
・復唱して確認
・感謝の言葉を忘れない
・解決後はフィードバック
相槌をとる
先輩への質問の回答をしてくれている時に、しっかりと、相槌をとることで、「ちゃんと話聞いてますぜ」というアピールになります。
無反応で話を聞かれるよりも、相槌というノンバーバルコミュニケーションを相手にわかるようにとることが信頼や親密度を上げる大切なポイントです。
復唱して確認
先輩からの回答を復唱して、自分がしっかり理解できているか確認します。
この作業を行うことで、先輩には「しっかり聞いていました」ということと、「情報が正しく伝わっているな」という安心感を与えることができます。
これにより、先輩に、また別の質問に答えてもらえる機会を得ることができます。
感謝の言葉を忘れない
感謝することは当たり前だと思うかもしれませんが、何回も先輩に質問をしていると、流れに慣れすぎて、感謝の言葉を忘れてしまいがちになります。
親密度が高くなったとしてもあくまでも仕事上の先輩ですから、「親しき中にも礼儀あり」という言葉通り、感謝の言葉を忘れずにしましょう。
それが、親密度を強固にするポイントです。
解決後はフィードバック
先輩のアドバイスを受けて、改善したものがあるのであれば、先輩のアドバイスを受けた後、どうなったのか?ということをしっかりとフィードバックすることが大切です。
このフィードバックがあれば、「回答は役に立ったのか?」ということが先輩に伝わり、先輩の回答の質が向上することに繋がります。
また、先輩の回答で上手く仕事が完了したのであれば、それは、あなたの成功体験と同時に先輩の成功体験になります。
あなたと先輩の自信を作ることに繋がりますし、なによりも、仕事がうまくいったという安心感も先輩に与えることができます。
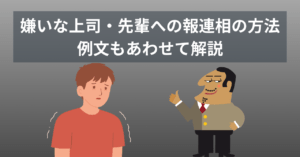
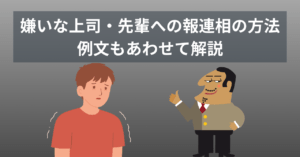
先輩へ質問する時に注意したい点
最後に先輩へ質問する時に注意したい点を3つ紹介して、今回のテーマを終わりたいと思います。
先輩へ質問する時に注意したい点はこちら
・知ったかぶりをしない
・敬語をしっかり使う
・普段仲良くても仕事では真面目に
知ったかぶりをしない
「先輩が忙しい」と思ってしまうと、遠慮しがちになり、せっかく質問できても先輩に手間をかけさせないように、回答の中で分からないことがあっても分かったフリをしてしまいがちです。
これでは、長い目で見た時に、再度同じ質問をしてしまうことに繋がってしまい、結果的に先輩に無駄な労力をかけてしまうことになります。
自分のためにも、先輩のためにも知ったかぶりをしないということが大切です。
敬語をしっかり使う
これまた、親しき中にも礼儀あり。です。
新社会人になって、配属されはじめの方であれば、先輩に礼儀をもって接することができると思いますが、これが、仕事に慣れてくるとおざなりになりがちです。
その中で、敬語がだんだんと崩れてしまって、不意にタメ口を言ってしまうという関係を悪くさせてしまう失言につながりかねません。
普段から敬語に意識を向けると良いでしょう。
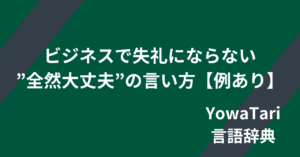
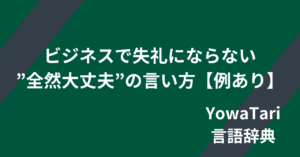
普段仲良くても仕事では真面目に
こちらも前の項目と同様ですが、先輩と仕事上で接する時は、いくら仲が良くても”目上の人”として接することで、先輩以外の目上の人にも礼儀正しく接することができます。
”慣れてきたな”と思っても、しっかりとメリハリを持つことが大切です。
失礼のない質問は良好な人間関係を作る”配慮”
先輩に対して失礼のない質問やアドバイスを求めることは、人間関係での”配慮”に意識を向けているという証拠です。
人への配慮を意識することで、相手との信頼感や親密度を上げることに繋がります。
今回紹介した質問方法を駆使して、ぜひ先輩と良好な関係になってもらえれば幸いです。
この記事も役に立つかも

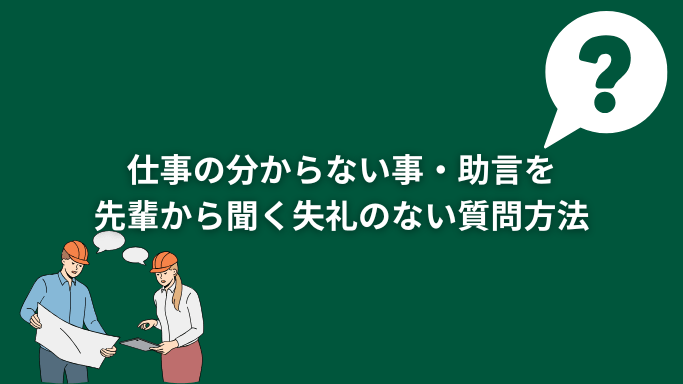

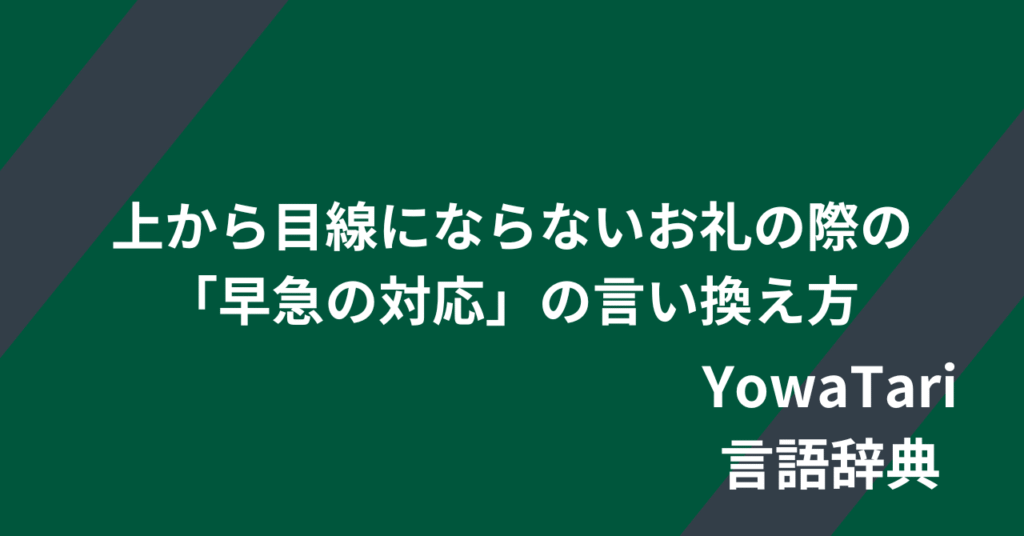
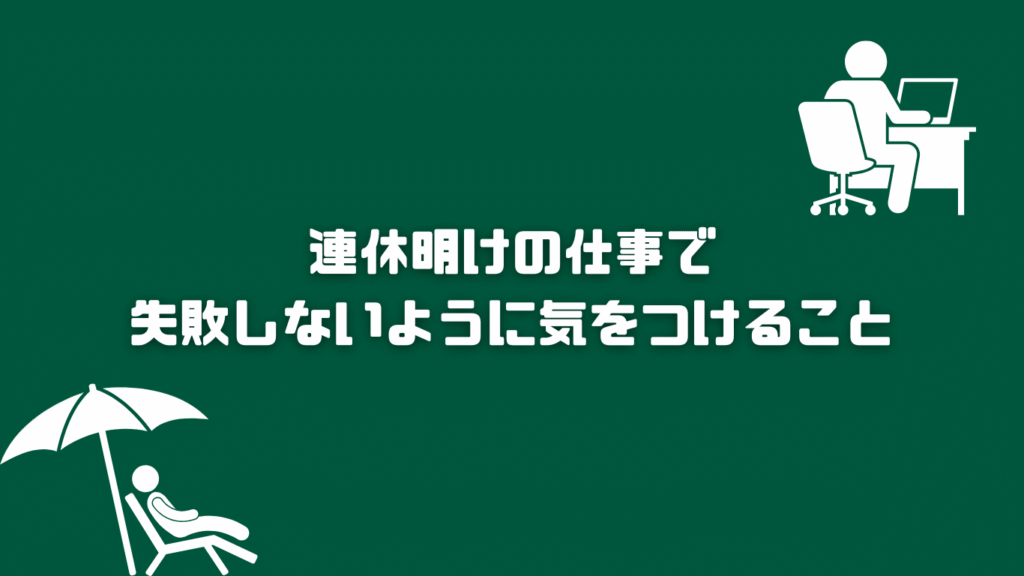
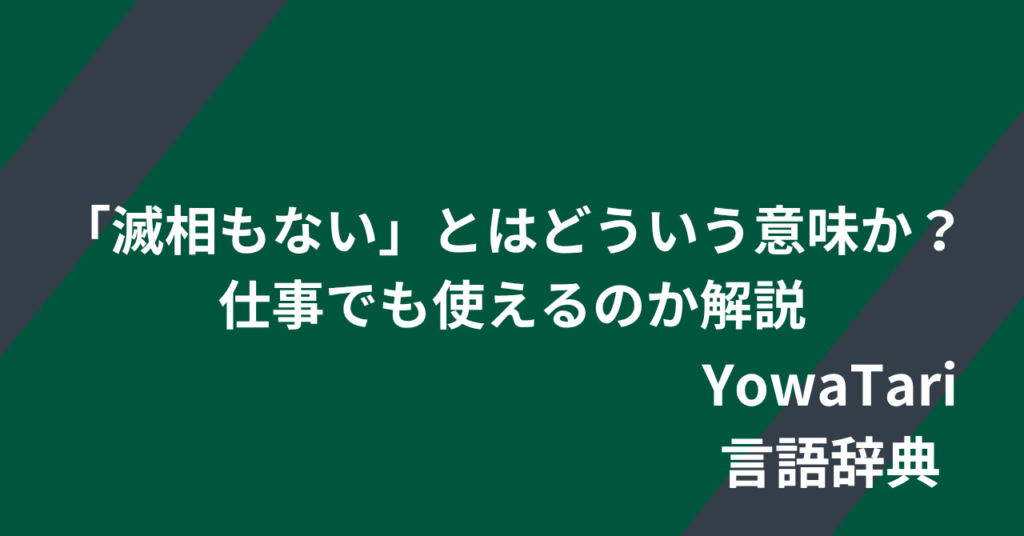
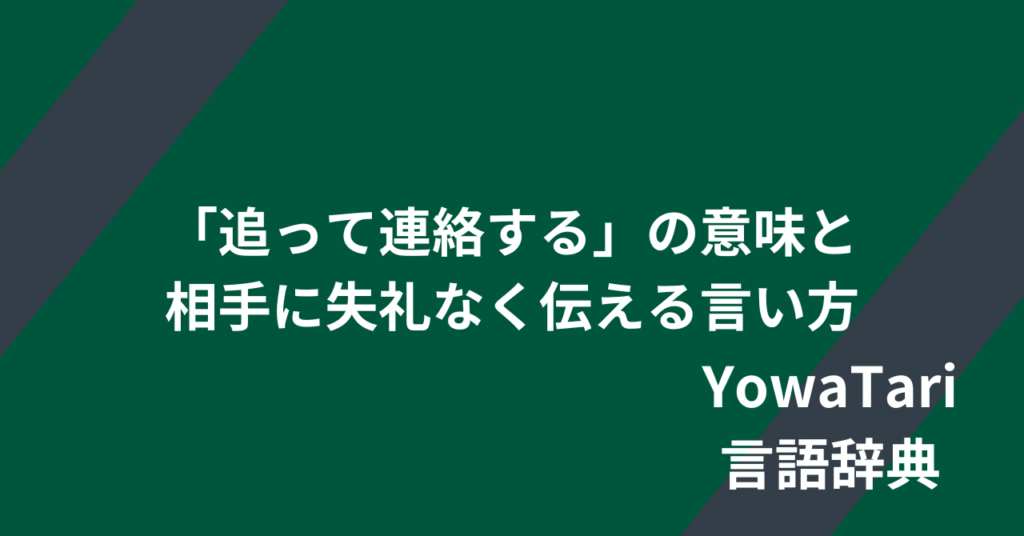
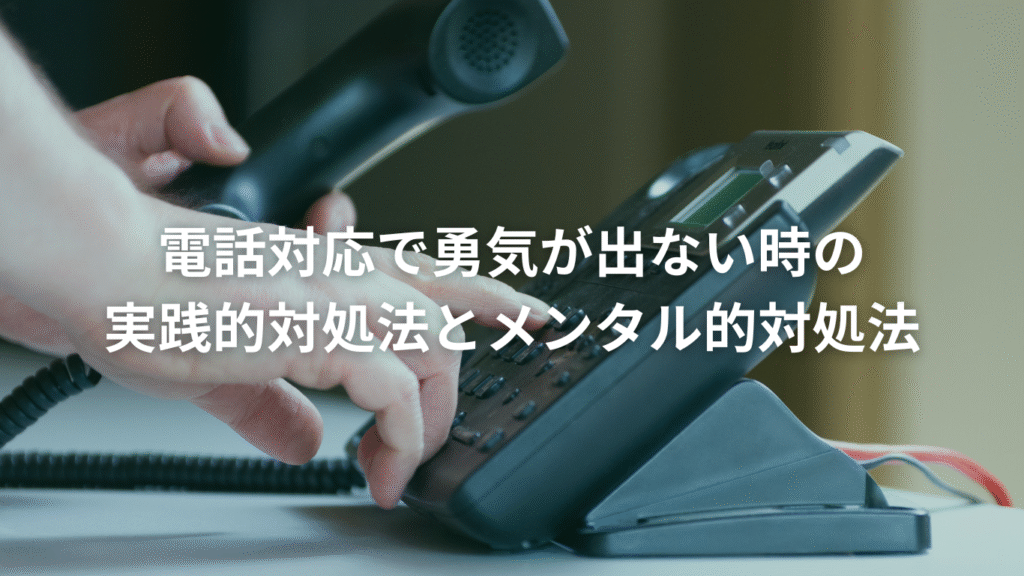
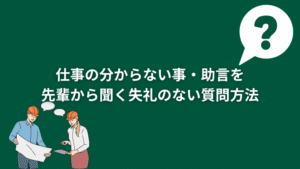

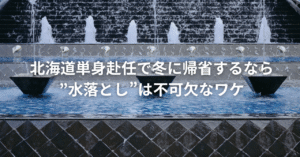
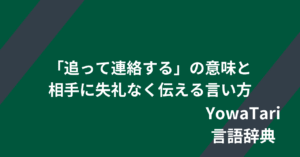
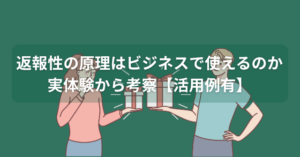
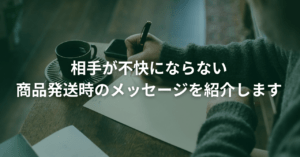
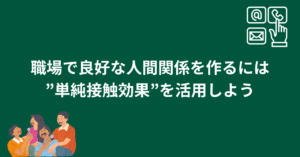
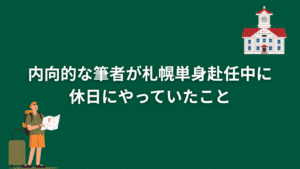
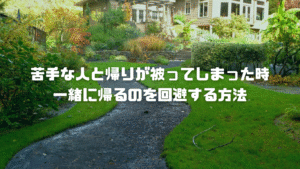
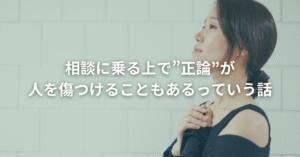
コメントする