筆者だ。
ビジネスには「会社と会社」のやり取り、「会社と個人」のやり取り、主にこの2つの業種がありますが、そのどちらの仕事内容にも欠かせない業務が「電話対応」です。
「電話対応」の業務の中で、無事に取引先やお客様に電話が繋がれば良いですが、そう思うようにはいかず、電話が繋がらないときがあります。
その時に必要とされるのが「留守番電話を残す」という業務です。
今回の記事では「ビジネス上の取引先やお客様との電話対応時の留守番電話の失礼のない残し方」を解説していき、「留守番電話を残す」という業務をやりやすくできればと思います。
取引先との連絡の時の留守番電話、お客様との連絡の時の留守番電話それぞれの視点からも解説していますので、ぜひ実践で活用してみてください。
この記事でわかること
・ビジネス上の留守番電話の基本構成
・留守番電話のコツ
・留守番電話の例文

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験
- 吃音症歴20年
- 元オートローン営業マン
- 元オーダースーツフィッター
- 元百貨店販売員
- 現Webマーケター
- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味
- 酒は飲めない、よく体調崩す人
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
留守番電話の基本構成
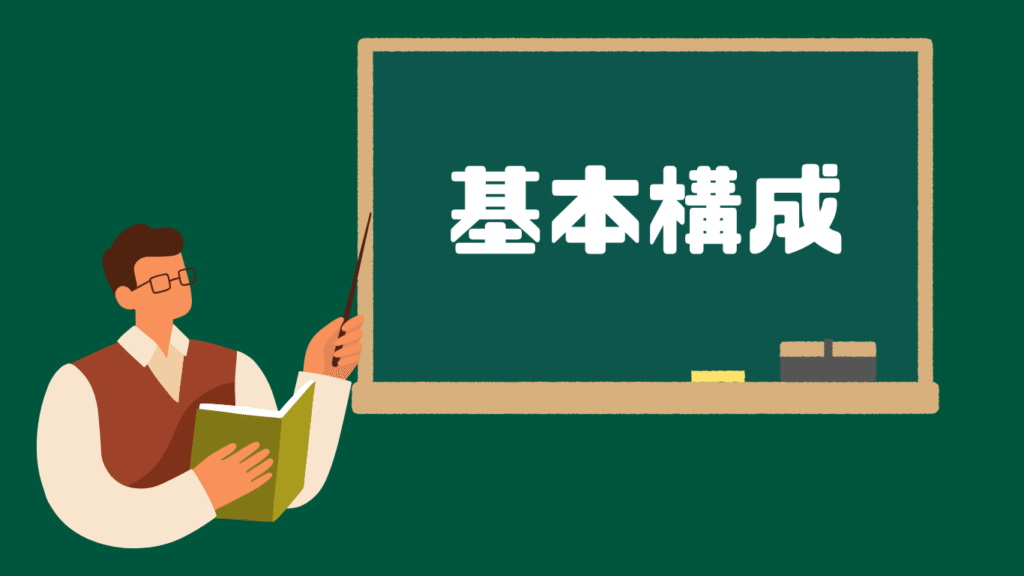
ビジネス上で、取引先・お客様双方に留守番電話を残す際は、相手に必要な情報が簡潔かつ正確に伝わるよう、留守電の基本構成を意識することが大切です。
主に以下の4つの要素をおさえると良いです。
①どこの誰なのか名乗る
②何の用件か伝える
③相手にどうしてほしいのか伝える
④締めの一言
①どこの誰なのか名乗る
まず最初に、必ず自分が「どこの誰なのか」を名乗ることが相手の不信感を抱かせないためのポイントです。
・会社名
・所属部署
・氏名
この3つをはっきり伝えることで、相手がすぐに発信者を特定でき、「仕事ができるな」と思われるようなキッカケになり、信頼感を高めることに繋がります。
特に関係性が浅い・初期の取引先や初めてのお客様、リピーターになりかけているお客様には、会社名から丁寧に名乗るのが相手も安心感を抱きやすいです。
この”どこの誰なのか名乗る”ということが不明瞭だと、相手が折り返しをためらう原因にもなり、連絡遅れなどに繋がってしまうので注意すると良いです。
②何の用件か伝える
名乗った後は、簡潔に用件を伝えることが大切です。
・「〇〇についてご連絡しました」
・「〇〇の件でお電話しました」
など
要点を端的に述べることで、「どんな留守電なんだろう?」と疑問に思う気持ちを払拭することができます。
用件が複数ある場合も、できるだけ一つにまとめるか、最も重要な内容を優先して伝えるのがポイントです。
用件をまとめるとき
・「〇〇のバージョンの費用と〇〇のバージョンの費用について連絡しました」
→「ご検討いただきたい費用についてご連絡させていただきました」
最も重要な内容を優先して伝える時
・「納期の件と費用の件と商品の概要の件につきましてご連絡しました」
→「費用の件につきましてご連絡しました」(もし費用が相手の要望だった場合)
あまり用件が長いと留守番電話の録音時間内に収めることができなくなってしまいます。「相手がわかりやすくすること」と「録音時間」の観点から見て、「何の用件か伝える」ようにしたほうが良いです。
③相手にどうしてほしいのか伝える
用件を伝えた後は、相手にどのような対応をしてほしいのかを明確に伝えると良いです。
例えば
・「お手すきの際に折り返しご連絡いただけますと幸いです」
・「ご確認の上、メールでご返信ください」
など
「相手にしてほしい具体的なアクション」を示すことで、相手がこちらが残した留守番電話に対応しやすくなります。
また、折り返しを希望する場合は、連絡先や希望する時間帯も添えると相手に無駄な労力をかけさせずにすみますので、相手が親切に感じることに繋がります。
このようにし「折り返したけど繋がらない」ということになる可能性が低くなることで、自分自身も余計な仕事を増やさずに、なるべく早く仕事を進めることができるので、楽になります。
④締めの一言
留守番電話の最後に、感謝やお詫びの気持ちを込めた締めの一言を添えると印象良く留守番電話を終わらせることができます。
・「お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします」
・「ご不在のところ失礼いたしました」
など
相手への配慮を言葉で示すことで、相手に「丁寧な印象」を与えることができるのです。
また、より相手に丁寧な印象を与えたい場合は、再度、「どこの誰なのか名乗る」ことで、相手の聞きそびれを防ぐことができ、「気が使えるな」と相手に思わすことができます。
ビジネスシーンでは、こうした細やかな気遣いが信頼関係の構築に繋がることがあるので、忘れずに伝えると良い人間関係を構築するキッカケになります。
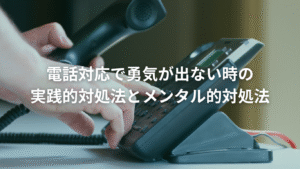
おさえておきたい留守番電話の注意点

ビジネス上、取引先やお客様に電話をかけて、電話に出なかった場合、留守番電話を残す際には、いくつかの注意点をおさえておくことが大切です。
・簡潔に留守電を残す
・慌てなくて大丈夫
・雑音を入れない
・基本的は1日2回
これらのポイントを意識することで、留守番電話一つとっても相手に好印象を与えることができます。
簡潔に留守電を残す
留守番電話は、録音時間が限られているため、できるだけ簡潔に要点をまとめて伝えることが大切になってきます。
長々と話すと途中で切れてしまったり、相手が内容を把握できずに留守番電話が終わってしまい、結局「何をどうすればよいのか」がわからなくなってしまうなんてこともあります。
伝えるべき情報(どこの誰なのか・用件・相手にどうしてほしいのか・締めの一言)を事前に整理し、なるべく簡潔に話すと無駄な労力にもなりずらく留守番電話を残せるので良いです。
慌てなくて大丈夫
筆者は良く「早く言い切らなきゃ」と考えてしまい、早口になりがちで呂律が回らなく、カミカミになってしまうなんてことがあります。
留守番電話を残す際、筆者のように緊張して早口になったり、言葉が詰まってしまうこともありますが、慌てる必要はありません。
一呼吸おいてから話し始めることで、落ち着いた印象を与えられ、スムーズに留守電を残すことができます。また、事前に話す内容をメモしておくと、「あれも言わなきゃ」と迷うことがなくなるので、内容もシンプルになり簡潔に伝えられることに繋がります。
慌てず、丁寧に話すことがポイントと言えるでしょう。
雑音を入れない
留守番電話を残す際は、周囲の話し声や作業音などの雑音が入らない静かな場所でかけることが大切です。
雑音が多いと、相手が内容を聞き取りにくくなり、誤解や伝達ミスの原因になってしまい、相手に”情報が伝わらない”という最悪のことに繋がってしまうおそれがあります。
特に外出先やオフィスの騒がしい場所では、できるだけ静かな場所に移動してから電話をかけると良いです。また、マイクに鼻息などの「自分が不意に出す音」がかからないよう注意し、相手が聞き取りやすい音声で伝えることを心がけると良いです。
基本的は1日2回
ビジネス上で取引先やお客様に留守番電話を残す時は、相手に「しつこいな」と思わせないようにすることを考慮し、1日に2回までを目安にすると良いです。
何度も連絡すると、相手に「しつこさ」を感じさせてしまうだけではなく、「早く連絡しなきゃ」というようなプレッシャーを与えてしまうことがあります。
1回目の留守電で折り返しがなかった場合、2回目は「何度もご連絡して申し訳ございません」と”配慮”の一言を添えると丁寧です。
それでも連絡が取れない場合は、メールや他の手段も検討してみると良いです。
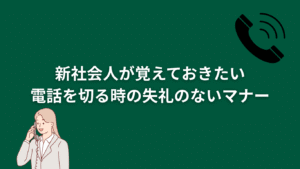
留守番電話の相手別例文
ビジネスシーンでは、相手によって適切な留守番電話の内容や言い回しが異なります。
この項目では、法人営業(取引先)と個人営業(お客様)それぞれのケースで使える例文を紹介します。
状況に応じてアレンジし、相手に合わせた丁寧な対応を心掛けると良いです。
・法人営業の場合(相手が取引先だった場合)
・個人営業の場合(相手がお客様だった場合)
法人営業の場合(相手が取引先だった場合)
法人営業で取引先に留守番電話を残す場合は、会社名・氏名・用件・相手にどうして欲しいのか・締めの言葉を明確に、かつ端的に伝えることが「相手の忙しさも考慮した上での留守番電話」となり大切です。
以下のように留守番電話を残してみてください。
例文
「お世話になっております。株式会社〇〇の〇〇でございます。〇〇の件でご連絡いたしました。ご都合がよろしい時に、折り返しご連絡いただけますと幸いです。失礼いたします。」
このように、ビジネスマナーを意識した、なるべく丁寧な言葉遣いを心がけると相手に失礼な感じを与えることがない留守番電話を残すことができます。
また、期日があるものであれば、「〇〇日までに折り返しご連絡いただけますと幸いです」という「いついつまでに」を入れておくことも”配慮”の一つです。
もしそれでも出来るだけ返事を急がせたいのであれば、「メールにてご連絡ください」というメールでの連絡手段も選択肢として提示しておくと良いです。
個人営業の場合(相手がお客様だった場合)
個人営業でお客様に留守番電話を残す場合は、より親しみやすく、かつ丁寧な言葉遣いを意識すると、相手は「大切にされているな」という感覚を得ることができ、失礼に思われにくい留守番電話を残すことができます。
例文
「〇〇様、いつもお世話になっております。〇〇会社の〇〇でございます。ご注文いただいておりました商品の件でご連絡いたしました。またお時間を改めてこちらからご連絡させていただきます。お忙しい中失礼いたしました。それでは。」
ここでのポイントは「お客様の名前を最初に言うこと」です。
お客様の名前を最初に言うことで、「自分の名前を覚えていてくれた」というような良い印象を与えることに繋がりますし、「ネームコーリング効果」という心理学的観点からみても親近感を与えるという効果があります。

そして、大切なのは「なるべくお客様から連絡させない」という配慮の言葉をつけることです。「お客様のお手をわずらわせない」というのが個人営業では大切になってきます。その配慮を含めた言葉が「こちらから連絡する」という文言なのです。
最後に「お客様が電話に出れないくらい忙しい時に電話をしてしまいすみませんでした」という意味を含めた「お忙しい中失礼いたしました」という文言を入れ、「失礼します」を重複させないように「それでは」という締めの一言を加え録音を切る。というような流れとなっています。
このようにみると、また取引先と電話をする時とは違うニュアンスが込められた言葉で構築されていることが分かります。
留守番電話を残す時のイレギュラーの時の対応
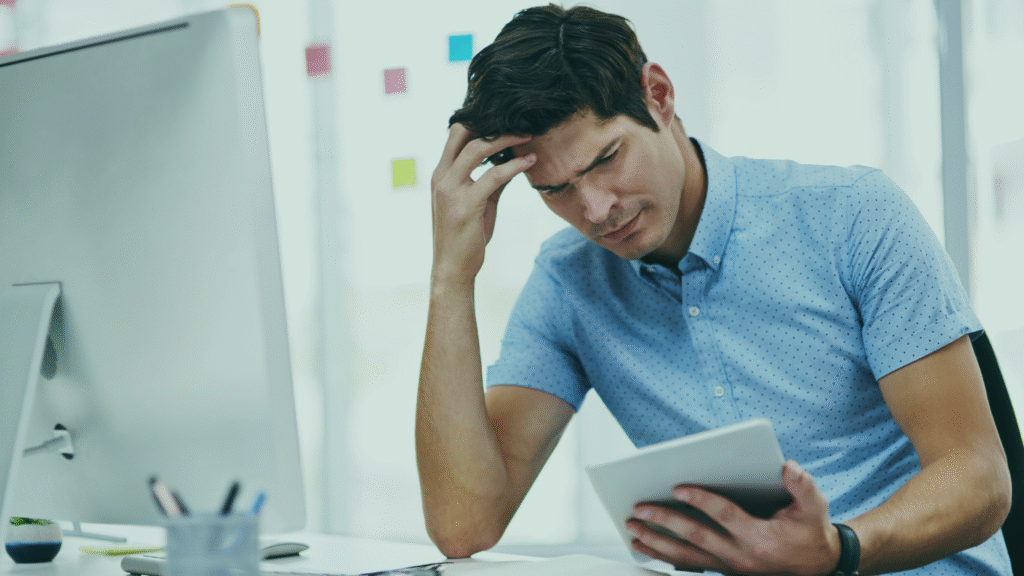
ビジネス上で留守番電話を残す時には、予期せぬイレギュラーな状況が発生することもあります。予期せぬイレギュラーが起きたとしても、慌てず冷静に対応することが相手との信頼関係の構築に繋がります。
それぞれのケースごとに適切な対応方法をおさえておくと良いです。
・留守電を残している時に電話が繋がったら
・途中で録音時間が切れたら
・2回目以降の留守番電話の場合
・留守番電話による相手からの折り返しに出られなかった時
留守電を残している時に電話が繋がったら
留守電を録音している最中に相手が電話に出た場合は、すぐに挨拶をして状況を説明すると良いです。
「お忙しい中失礼いたします、〇〇会社の〇〇です」という挨拶をした後に、「ちょうど留守番電話にメッセージを残しているところでした」と一言添えると、相手も状況を理解しやすくなり、電話終了後にもし留守電が残っていても、気にすることがなくなります。
挨拶と状況説明後に、通常通り用件を伝えれば問題ありません。慌てず、落ち着いて対応することが大切です。
途中で録音時間が切れたら
録音時間が途中で切れてしまった場合は、再度電話をかけ直し、簡潔に要点だけを伝え直しをすると「相手に情報が伝わらない」ということが防げるので安心です。
また再度留守番電話を残す際に「先ほど留守番電話が途中で切れてしまい、失礼いたしました」と一言添えると丁寧になります。録音時間を意識して、次回はより簡潔にまとめることを心がけると良いです。
ただ、ここで注意したい点があります。
それは「相手がしつこい」と感じてしまう可能性がある。ということです。
・会議中でポケットに携帯をしまっている
・相手はそもそも留守番電話を聞かない人
このような状況下で「留守番電話が録音できなかったから再度留守番電話を残す」という目的で電話をかけると相手は「しつこいな」と感じてしまう可能性があります。
このような時は留守番電話が時間内に録音できなくても、時間が経った後に再度電話をかける。というようにすれば相手に「しつこい」感を感じられずにするポイントです。
「相手の性質」「相手の状況」に合わせて選択すると良いです。
2回目以降の留守番電話の場合
2回目以降の留守電を残す場合は、相手の都合を考慮し、必ず「何度もご連絡し、申し訳ございません」とお詫びの言葉を添えると相手に嫌な思いをさせません。
また、前回の連絡内容を簡単に振り返り、今回の要件や相手にして欲しい対応を明確に伝えることがポイントです。
・1回目の電話内容
・折り返しが欲しいのか、再度こちらから連絡するのか
このような点をふまえると良いでしょう。
留守番電話による相手からの折り返しに出られなかった時
留守電を残した後、相手から折り返しの電話があったにもかかわらず出られなかった場合は、できるだけ早く再度連絡を入れることがポイントです。
その際、「先ほどは折り返しのお電話をいただきながら、出られず申し訳ございません」とお詫びの言葉を添えると相手に失礼な感じを与えません。
また、メールなど他の連絡手段も活用し、迅速な対応を心がけることが大切です。
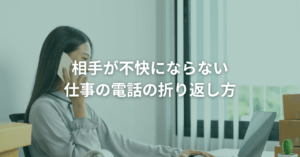
留守番電話を残す時の+αの配慮
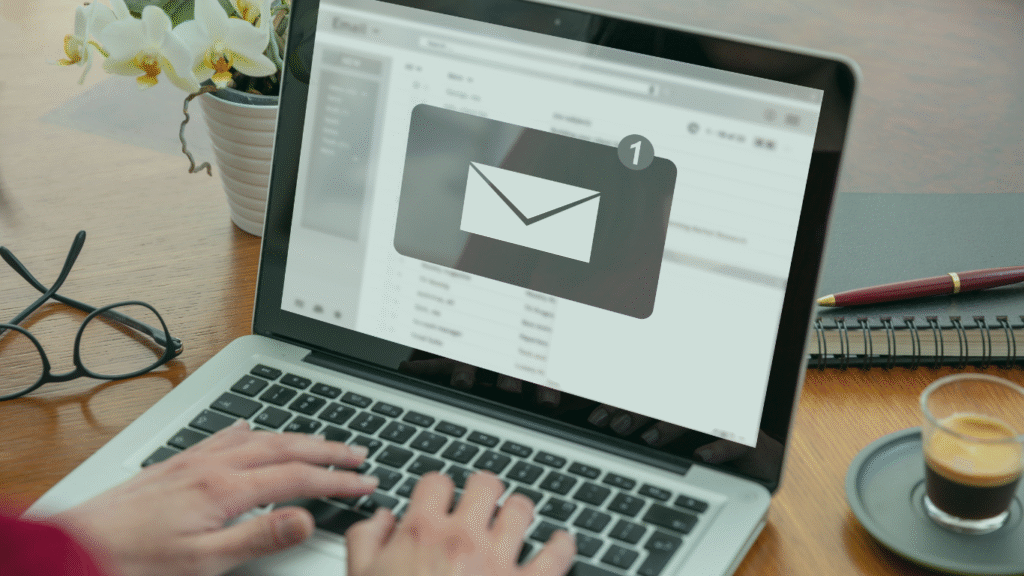
ビジネス上での「留守番電話」という業務では、基本的なマナーを守るだけでなく、+αの相手への配慮を加えることで、より相手からの”信頼”を得ることができると考えられます。
以下の2つの+α配慮をおさえてみてください。
・留守電に追加してメールを送っておく
・他の人にも共有しておく
留守電に追加してメールを送っておく
留守電だけでは伝わりきらない場合や、確実に連絡を取りたい場合は、メールを併用することがおすすめです。
メールで要件や連絡先を明記しておくことで、相手も確認しやすくなりますし、メールは記録としても残るため、後から内容を見返すことも可能になり、情報伝達漏れを防ぐことができます。
取引先とお客様、それぞれに適したメール例文を紹介します。
取引先の場合の追加メール例
件名:お電話の件につきまして
〇〇株式会社
〇〇様
いつもお世話になっております。株式会社〇〇の〇〇です。
本日お電話いたしましたが、ご不在でしたので留守番電話に〇〇の件でメッセージを残させていただきました。
ご都合がよろしいお時間に、ご返信いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
株式会社〇〇
担当 〇〇
お客様の場合の追加メール例
件名:先ほど差し上げたお電話の件につきまして
〇〇様
いつもご利用いただきありがとうございます。
〇〇会社の〇〇です。
本日お電話いたしましたが、ご不在でしたので留守番電話にご注文いただいた商品の件につきましてメッセージを残させていただきました。
お時間を改めまして再度、こちらからご連絡させていただければ幸いです。
なお、もしご都合のよろしいお時間の希望がありましたら、こちらのメールにてご連絡をいただけますと幸いです。
お忙しい中大変恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
〇〇会社
担当 〇〇
他の人にも共有しておく
留守番電話を残した場合は、社内の同僚や上司にもその内容を共有しておくと安心です。
情報共有を徹底することで、万が一自分が不在の際にもスムーズな対応が可能となるからです。
特に複数人で対応する案件や、緊急性の高い連絡の場合は、メールやチャットツールを活用して速やかに社内に情報共有すると良いです。
まとめ
ビジネス上での留守番電話は、基本構成と相手への配慮となるマナーを守ることが、相手に失礼に感じ取られずに留守番電話を残すことができることに繋がります。
今一度、留守番電話の基本構成を振り返って見ましょう。
①どこの誰なのか名乗る
②何の用件か伝える
③相手にどうしてほしいのか伝える
④締めの一言
さらに、追いメールや社内共有、イレギュラー対応など様々な対応を頭に入れ、実行することで、相手から信頼されるビジネスパーソンを目指すことができます。
ぜひ、本記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。
この記事も役立つかも

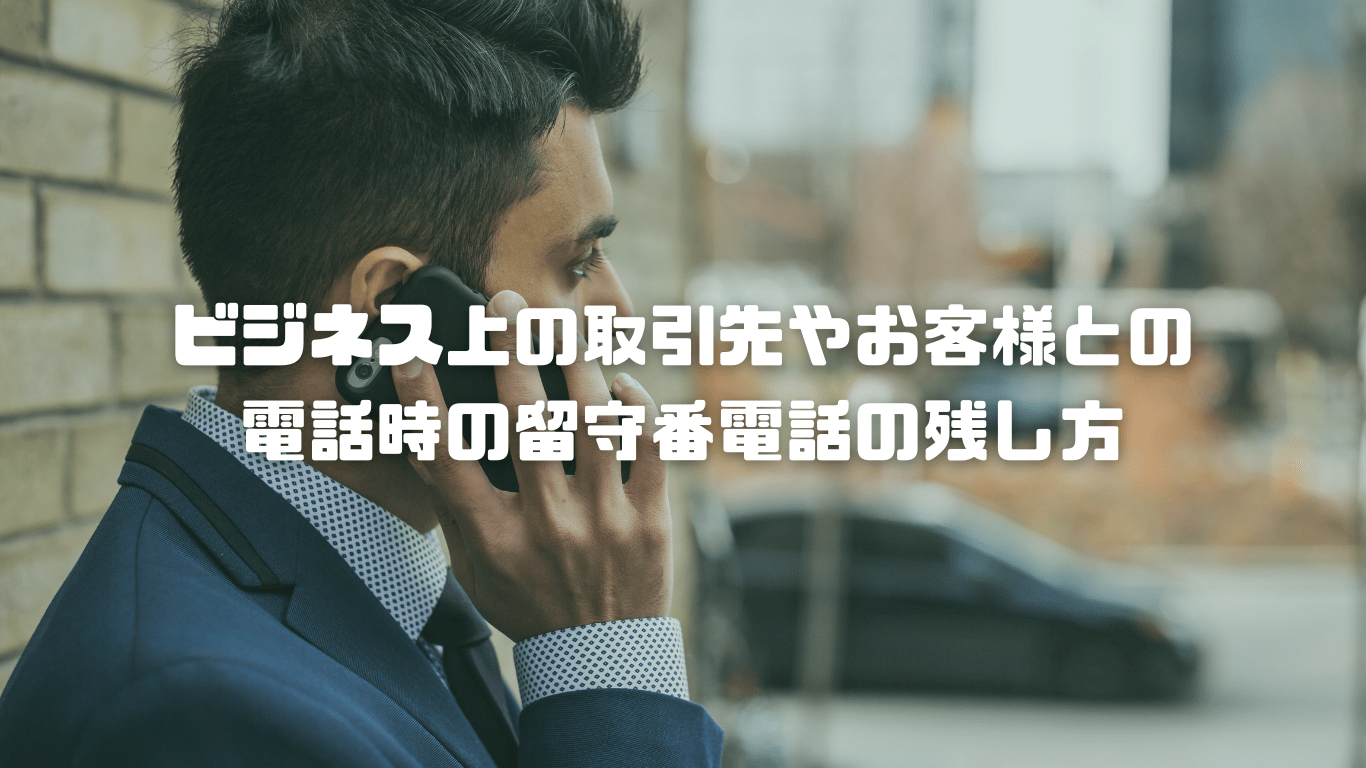
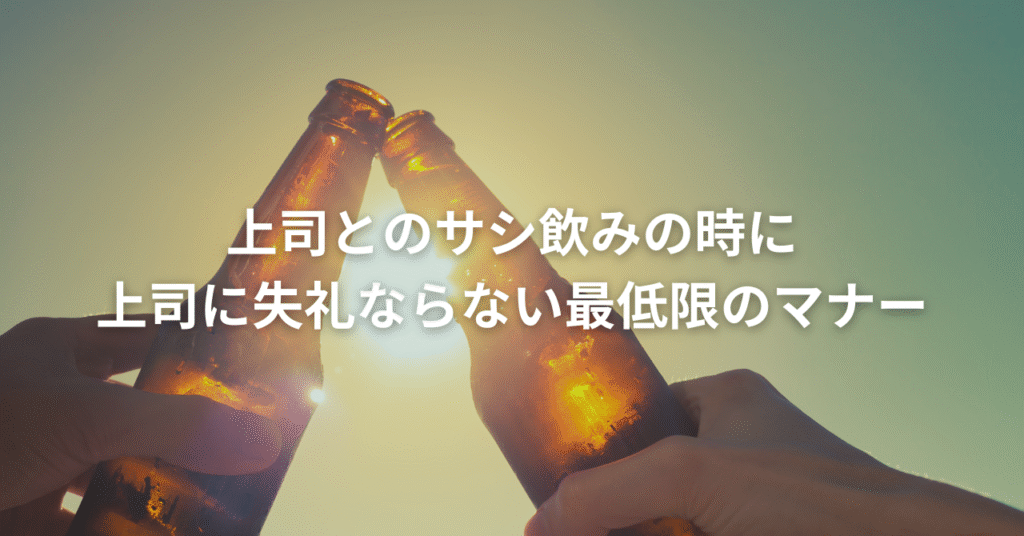
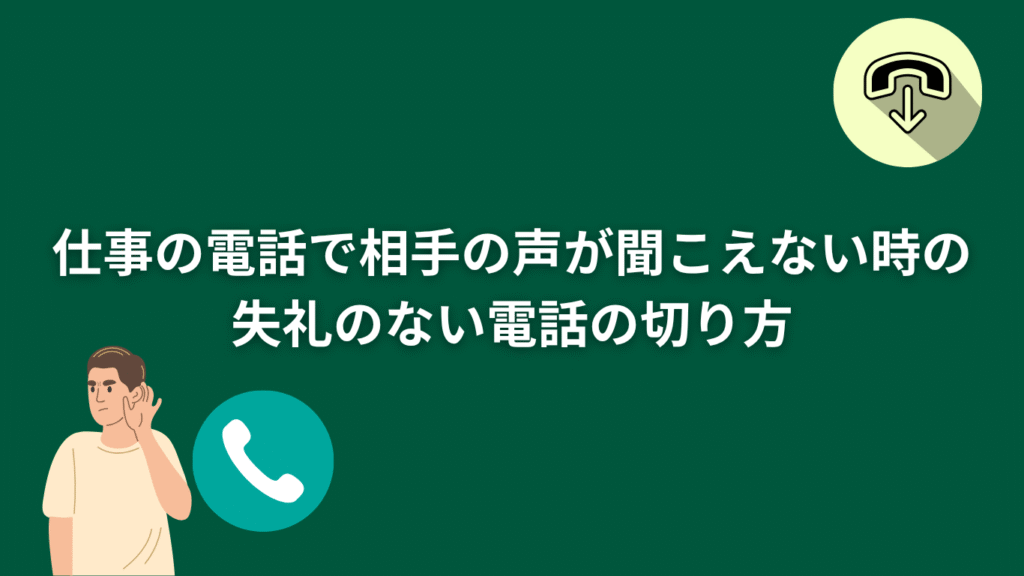
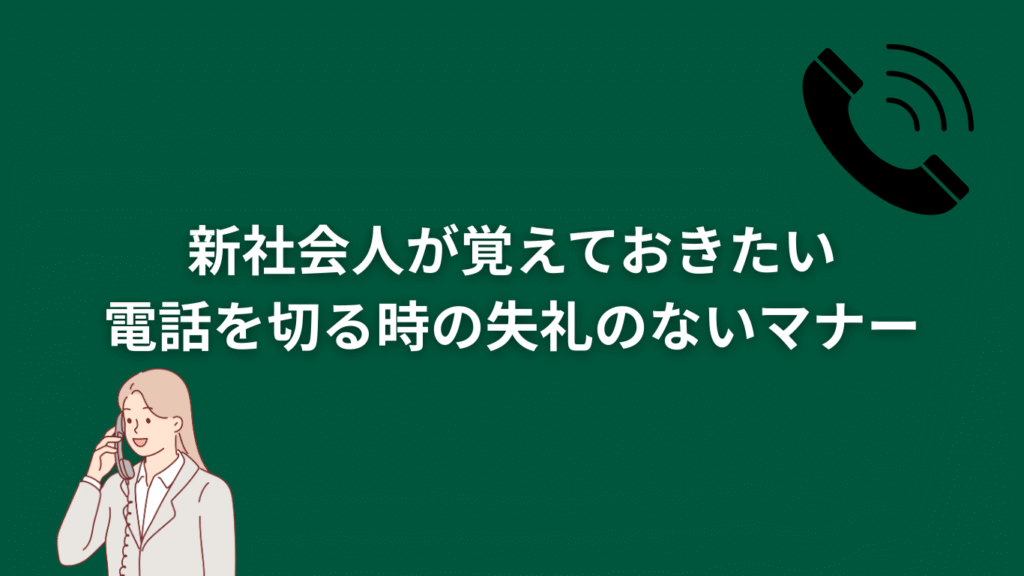
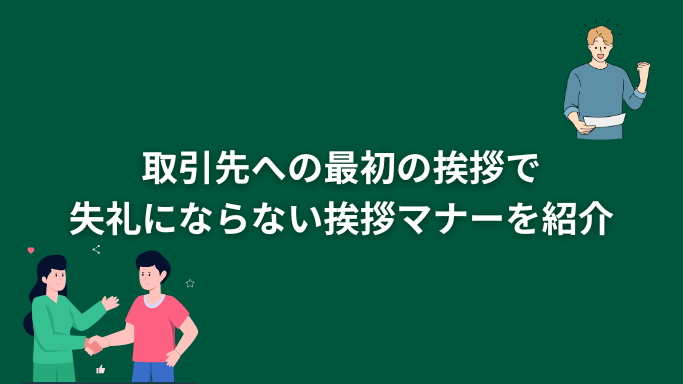
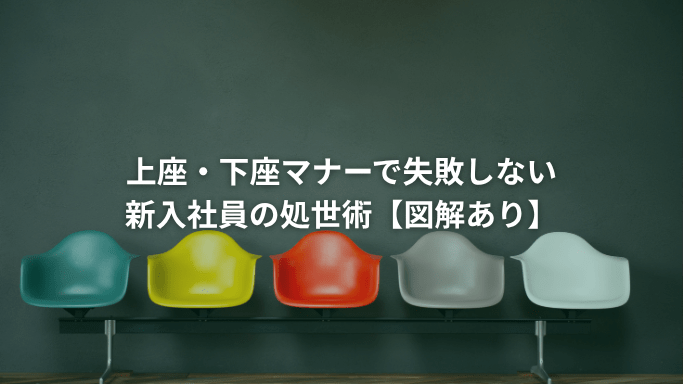
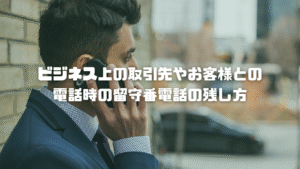

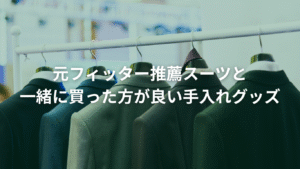
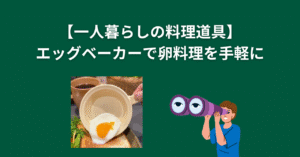
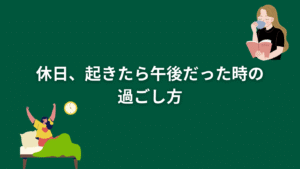
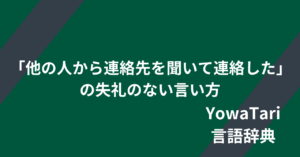
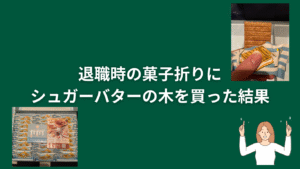

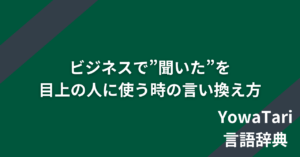
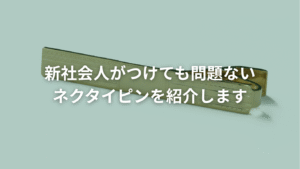
コメントする