ちゃおっす、筆者だ。
皆さんは「劣等感」というのを感じるだろうか?
筆者は幼少期の頃から周囲と比べて「自分はなぜできないんだろう?」そう自問自答して枕を濡らした日もあった。
社会人になると、特に営業職だと、営業成績が見える化されたり、個人の業績表彰式などがあり、「人と比較する」環境が整えられている。
これが劣等感を引き起こすキッカケとなっていることはないだろうか。
では、ここで考えて欲しいのだが、そもそも”劣等感”というのは、必ずしも「必要なもの」なのであろうか?ということを読者の皆さんと一緒に考えられたら良いと思い、今回は「劣等感は必要なのか?」ということについて考察したいと思う。
もし今、劣等感を強く感じてしまっており、傷心しているのであれば、その傷を癒すために参考にしてみて欲しい。
この記事でわかること
・劣等感を感じるのはなぜか
・世の中には劣等感が感じやすい仕組みがあること
・優生思想からみる劣等感

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験
- 吃音症歴20年
- 元オートローン営業マン
- 元オーダースーツフィッター
- 元百貨店販売員
- 現Webマーケター
- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味
- 酒は飲めない、よく体調崩す人
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
劣等感ってどうして感じるんだろう

まず、皆さんに問いたいのは、「劣等感」というのはどうして感じると思うだろうか?
「なんで感じるのか?」って考えると難しい。
感じるもんは感じるんだから。でも、”どうして感じるんだろう?”っていうことを考えて答えを仮定してみると、劣等感を感じた時にどう対処したら良いのか?、そもそも劣等感を感じなくなることができる、と、”劣等感”に対して的確にアプローチをすることができると思う。
とは言っても、普段感覚で感じていることを深く考えるっていう行為はとても大変な作業だ。
例えば、パイナップルのあの厚い皮を手でむこうとするようなものだ。
それを踏まえて、筆者がしばらく劣等感について考えたことをこの記事では仮定したいと思う。
長く時間はかかったが、劣等感っていうのは「今の自分を変えたい」「理想の自分像に近づけたい」そんな潜在的な”自分自身”の気持ちから生まれるものなんじゃないか?って考えた。
劣等感っていうのは、ついつい「人と比較するもの」と思って、「他者」が原因で劣等感を感じてしまうと考えてしまうんだけど、実は、劣等感っていうのは自分自身の中から生まれているものなんじゃないかって仮定してみた。
だってそうじゃないだろうか?「今の自分を変えたい」「理想の自分像に近づけたい」と思っていなければ、目に見えて比較しやすい”他者”を比較対象として劣等感を感じてしまうことなんてことはないのだから。
例えば
野球の大谷翔平選手に憧れている人は、決して「大谷翔平選手」になりたいわけではないと思う。
”大谷翔平選手になる”っていうのは大谷翔平の体に自分の意識を入れて大谷翔平としての人生を生きるということ。そうではないのではないだろうか?
正しくは、大谷翔平のようなプレーをしたい。周囲から憧れの対象になりたい。それが求めるもの、憧れの対象なのでは?
つまり、「周囲から憧れの対象になりたい」「目を見張るプレーをしたい」これって自分自身の中の「理想の自分」にあたるのではないだろうか。
で、この「自分の中にある理想」っていうのをどう達成しているかみるために、超簡単な方法っていうのがあって、それが「他者と比較する」っていうことだと思う。
他者と比較するのが、自分の現状を自覚しやすいからだ。
そして、この「自分の理想」と「他者の出来栄え」を比較して、他者の方が「自分の理想に近い」場合、「なんで自分は他者のようにできないんだ」って”自分が他者よりも劣っている”と、劣等感を抱く。
こうした仕組みになっていると思うから、劣等感っていうのは実は「自分の中から生まれている」って考えると、結構スムーズに考えられると思う。
世の中には”劣等感”を感じやすくしようとする仕組みがたくさんある
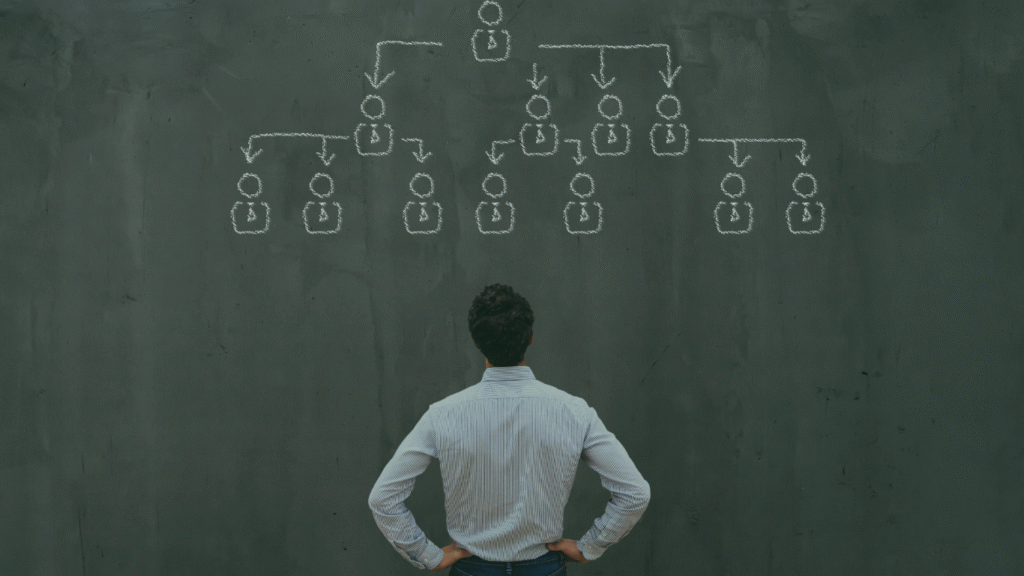
こう考えると、世の中って結構、”劣等感”を感じやすくしようとする仕組みがたくさんあるってことに気がつきはしないだろうか?
「劣等感を感じやすい」ということはつまり、「理想の自分」を構築する仕組みや「自分を変えたい」と思わせる仕組みがあるっていうことだ。
これらの仕組みの例をあげてみると
・インターネットで検索できる環境
・SNSで自尊心を満たせる環境
・多様性を広めようとしている環境
など
ようは、「他者」のことをみやすくなっていたり、職業の選択肢が広がっていたり、価値観が移り変わっているっている現状が、”劣等感”を感じる原因である「理想の自分像の構築」だったり、「自分を変えたいと思うこと」を明確にしたり、それらを作らないといけないという同調圧力ではないけど、一種の義務感にかられたり、強迫観念にかられることに拍車をかけているんじゃないかな。
だから、”劣等感”っていうのを感じやすくなってしまっているというのが現代は特にそうなのかもしれない。
最近の話だけど、会社で「年功序列制度の廃止」などがニュースになっているけど、これっていわば、「実力主義」の会社が今後増えてくるんじゃないかっていう懸念につながると思う。
今までは、学歴とか、年齢が重視されて採用とか、社内異動とかがあったと思うんだけど、今後は学歴・年齢関係なく役職者に就くことだったり、大きなプロジェクトを任せたりしようとしている。
これも、劣等感を感じやすくなる仕組みだと思うんだ。筆者としては。
実力主義ってことは、一定の実績を出さないといけない。で、この実績を出すために会社がやることといえば、ランキング形式で実績を見える化したり、表彰式を行ったりするわけだ。
この施策の背景っていうのは「同僚をお互いライバルとみて、切磋琢磨して実績を作りなさい」ってこと。
つまり、「他者と比較してがんばれ」ってことを会社は言いたいんだ。
ね?劣等感を感じやすくする環境がこれで出来上がってしまうわけだ。
だから、自分が思っているよりも、「劣等感を自然に感じやすくする環境」っていうのは、無意識のうちに整っているってことを知っておけば、劣等感と向き合いやすくなるんじゃないかと思う。
世界には”劣等感”を強く感じることとなった出来事があったのではないか

”劣等感”というのは、世界において、あるタイミングで強く感じるようになったんじゃないかと筆者は考えた。
というのも、「優生学」というのを皆さんご存じだろうか?
「優生学」とは
イギリスの科学者である「フランシス・ゴルトン」が学問として提唱したもの。
ゴルトンは進化論を提唱したダーウィンの従兄弟であり、ダーウィンの自然淘汰の考えに影響され、「人間の繁殖の仕方次第で、より優れた人間を増やせる」という、”優生思想”を基にした学問だ。
「優生学」では、「知能や才能は遺伝する」「優秀な人同士が結婚すべきだ」という思想が欧米を中心として広がっていった背景がある。
参照元:Wikipedia 優生保護法
と、こんな感じの思想が20世紀初頭のアメリカや北欧諸国で「優生政策」として広がっていった。
これ、まさに「劣等感」に強く結びつくと思わないだろうか?
簡単にいうと、「劣っている人」を否定している思想だ。
で、この思想、海外だけじゃないの?って思うが、実は日本にもあった思想なのだ。
1940年、国民優生法というのが制定された。これは、「悪質なる遺伝性疾患の素質を有する者の増加を防遏するとともに健全なる素質を有する者の増加を図り、もって国民素質の向上を期することを目的」という目的のもと、制定されたものだ。
後に、これが「優生保護法」に改正されるのだが、根本的な思想は「劣った人はダメだ」というゴルトンの思想を基にしたものだ。
結局、優生保護法は現在、「母体保護法」として名前と内容を改定されて残っている。
このように、世界ではもともと、「劣っている人と優秀な人を選別していく」という思想が広まってしまった背景がある。
なので、「劣等感」を感じてしまうというのは、前項で書いたように「自分の中からでてきたもの」の他に、「優生思想」のような世界に広まってしまった思想が影響しているのではないかと思う。
だから、「自分は他者と比べて劣っているからダメなんじゃないか」と感じてしまいやすい。そういう政策をしてきて、「優生思想」が広まってしまい、そう思わないとダメなんじゃないかと思ってしまう現実が出来上がっているのではないかと考える。
参照元:Wikipedia 優生保護法
”劣等感”というのはそもそも必要なのか?

ここまで「劣等感」は、なぜ感じてしまうのだろう?ってことを考えてきたが、本記事のテーマである「劣等感というのはそもそも必要なのか?」について考えていきたい。
筆者は、”劣等感”について、「必要でもあるし、不必要な場合もある」というなんともハッキリしない答えを仮定してみようと思う。
”劣等感”というのは、そもそも、自分の中から生まれてくると説いたが、結局のところ、「他者と比較してしまう」こと、「現実と理想のギャップをみてしまうこと」から生まれるわけだが、これっていうのは、良い方向で考えると、「現状と理想の距離感をつかめる」ことが言えると思う。
つまり、ざっくばらんにいうと、夢の実現までの進捗を確認することができるのが、”劣等感”というものだと思う。
だから、夢や目標を持っている人にとっては、”劣等感”というのは必要になってくるんじゃないかと思う。でも、必要とは言っても、100%絶対必要というわけではないと思う。
だって、劣等感で心身を壊してしまうことがあるからだ。
ここからいうと、ただただ自分を卑下するための劣等感(自分でそうしようとは思っていないかもしれないが)に関しては「必要ない」と考える。
他者と比較して「自分はダメだ」とは考えないで欲しい。自分は自分だ。他者は他者の人生を生きている。
実際、他者と自分の人生というのは、”比較”するものではない、比較しようにもできないものだと考える。
自分の人生は、誰にも阻害されない、阻害できない素晴らしいものであって、他者の人生も同様に素晴らしいものだ。
ダイヤモンドと宇宙に散らばる星々、どちらが美しい?と聞かれてもどちらも美しいんだから比較しようがない。と思うのと同じだ。
ここに無理やり、他者と比較して、自分の人生なんてダメなんだと劣等感で卑下するのは全く必要ない。
まとめると、「自分を成長させるための劣等感」は、そこそこ必要であり、「自分を卑下する、自分の価値を低くしようとする劣等感」というのは不必要と言える。
で、覚えて欲しいのは、人にどれだけ否定されたとしても、それをキッカケにして劣等感を抱くなんてことはやめた方が良い。
もちろん、倫理的、道徳的に外れてしまって、他の人から批判されてしまったら、それは真摯に受け止め、改める必要があるが、人生を一生懸命、辛いことがたくさんある中で懸命に生きている中で、他者から思いやりのない否定されたとしても、そんなものは無視していいと筆者は思う。
社会ではそういう、「出る杭を打つ」ようなことを平気でやってくるような人がいる。
そういう人から身を守るためにもこのことは、おさえておくと良いと思う。
まとめ
ここまで長々と「劣等感というのは必要なものなのか」ということについて書いてきた。
簡単にまとめると
・”劣等感”は他者との比較で生まれるものだと思うかもしれないが、実は”自分自身の中からくるもの”と仮定できる。
・「優生思想」という思想が世の中で広がったことがあり、そこで”劣等感”というのを強く感じやすくなってきたんじゃないか。
・”劣等感”は「自分を育てる」時にはやや必要だけど、「自分を卑下する」時には必要ない
特に会社の中で働いていると、「なんであの人みたいにできないんだろう」と他者と比較してしまうことがある。
でも、よく考えてみると、その比較対象の人が持っていないものを自分自身が持っている。それを自覚できていない、信じきれていない状態なんだと思う。
だから、他者と比較してしまい、自分を卑下してしまう。
だけど、覚えといて欲しいのは、人はそれぞれ皆素晴らしい何かをもっていること、他者はと比較できないこと、自分を信じない奴は努力する資格がない(これはナルトのマイト・ガイの言葉)ということだ。
後半何言ってるかわからないけど。
もし今、劣等感を感じて辛いという人は、その劣等感が「自分を成長させるためのもの」なのか、それとも、「ただ単に自分を卑下するものなのか」をもう一度考えてみて欲しい。
それを考えることが、劣等感を感じて辛いという気持ちから脱却する方法の一つだと筆者は考える。
この記事も役立つかも
何かの参考になるかも

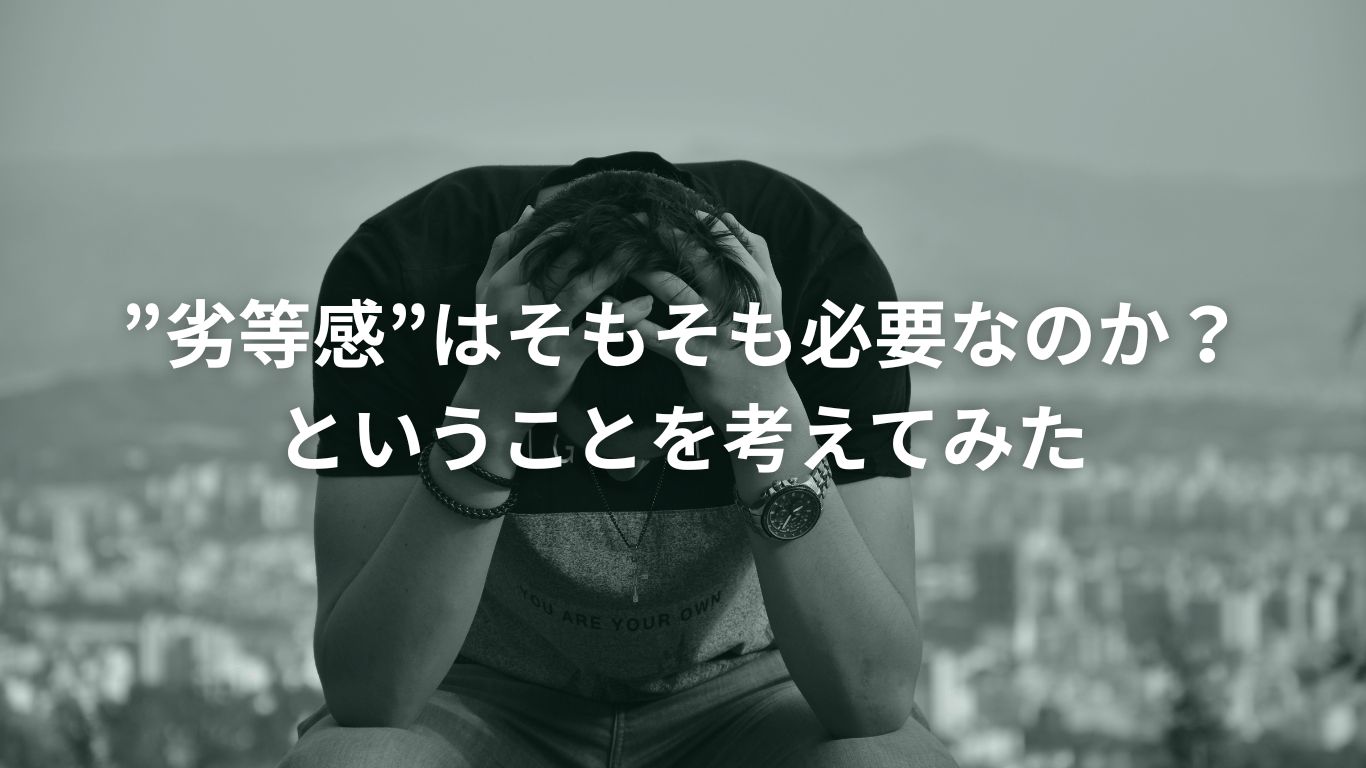
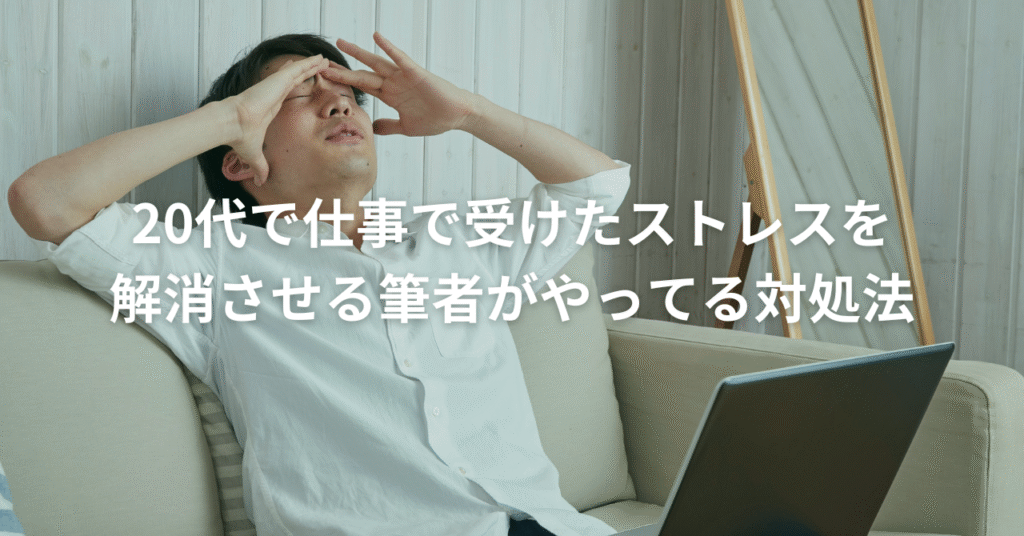
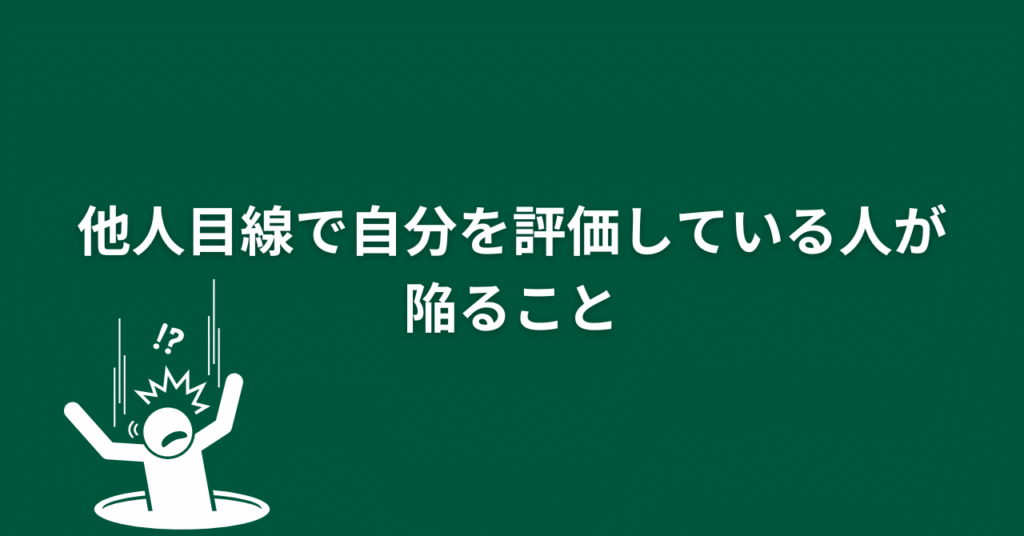
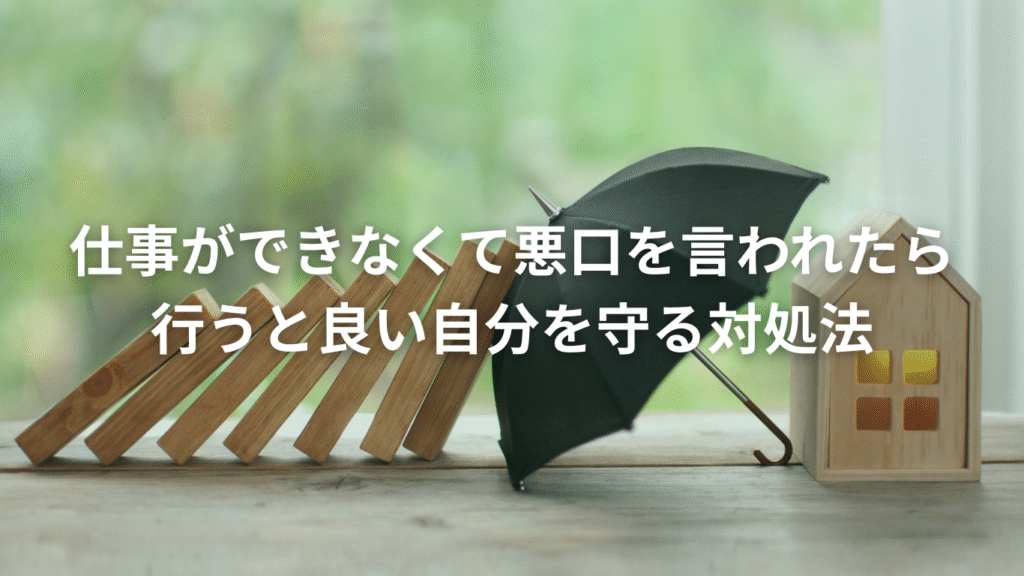
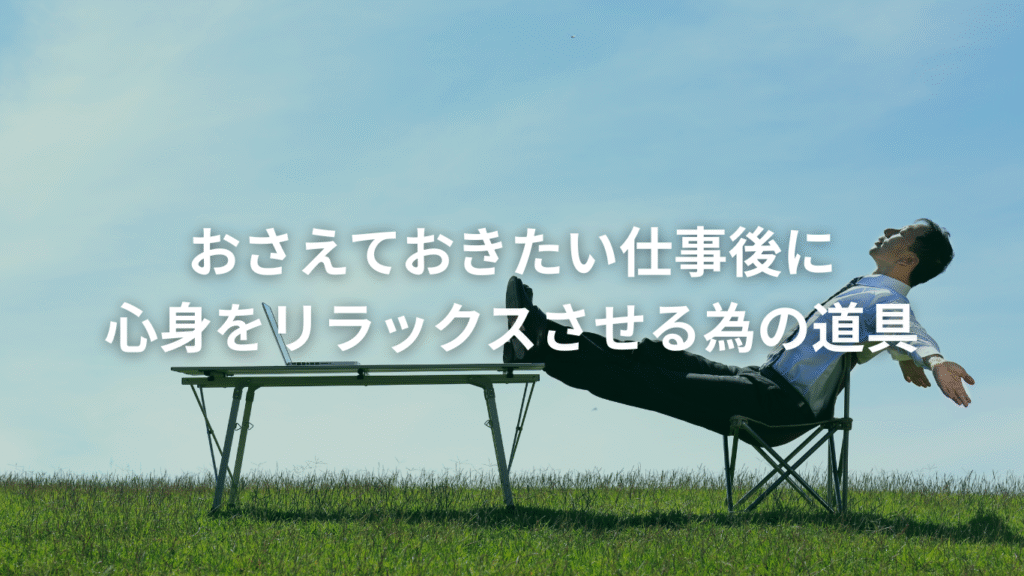
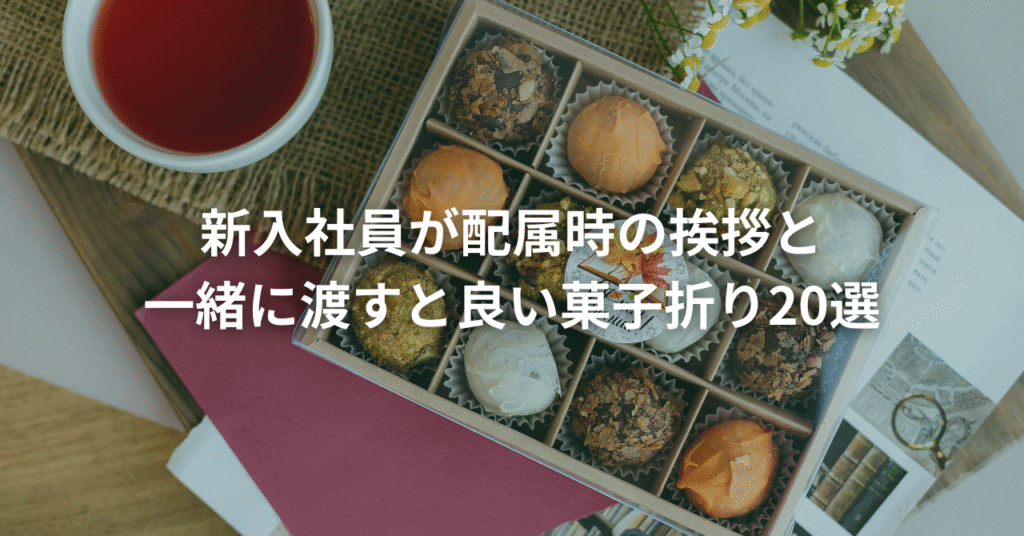
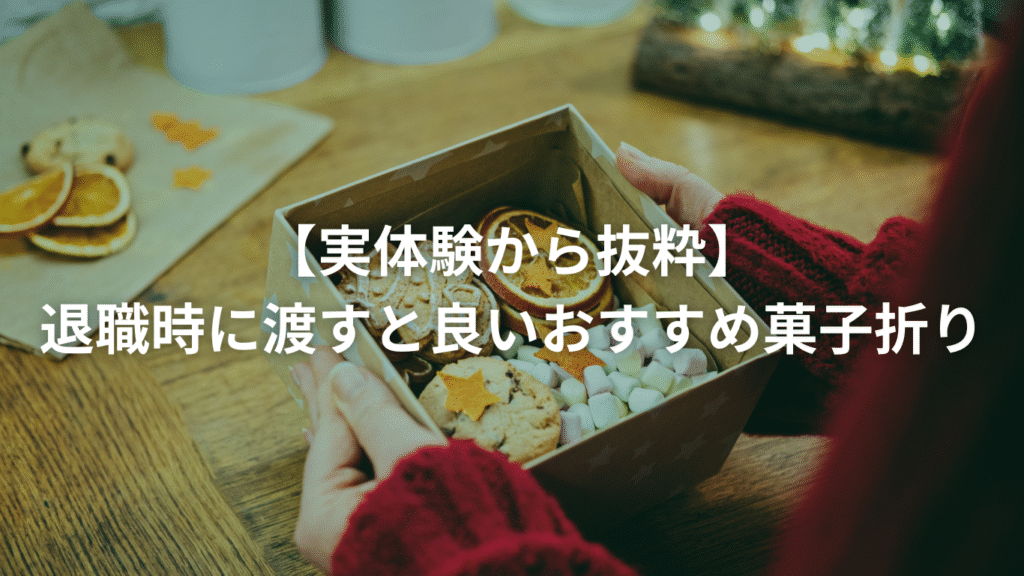
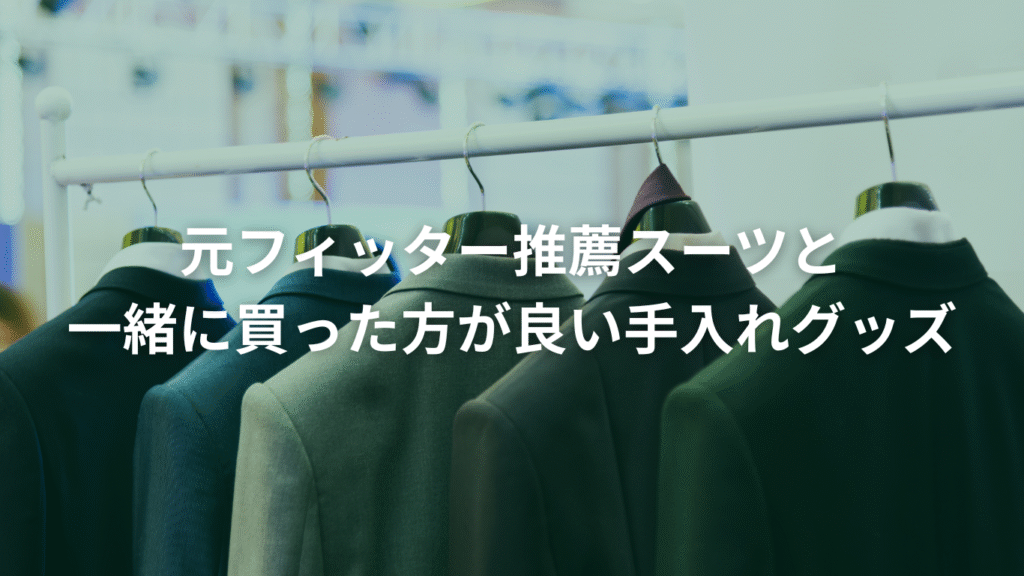

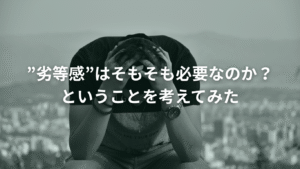

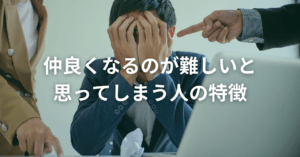
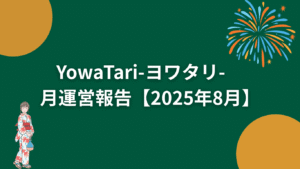
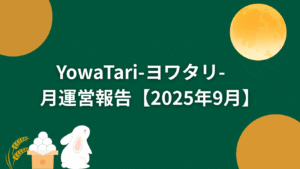

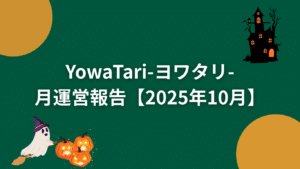
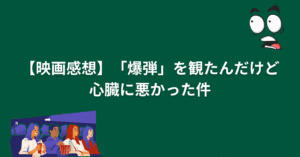
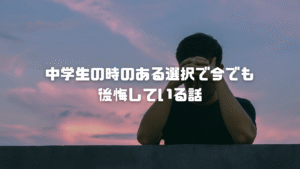
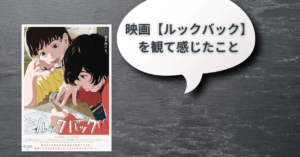
コメントする