筆者です。
仕事上で取引先やお客様と電話をしている時に、相手の声が聞こえなくなってしまったり、そもそも何も聞こえないといったトラブルに見舞われてしまうことはありませんか?
そんな時、あまりそのような経験が浅いうちの時は特に、「どうやって対応していいのか」わからなくなってしまう時がありますよね。
このような電話のトラブルの際、相手に失礼にならないような対応をする必要があります。
今回は「仕事の電話で相手の声が聞こえない時の失礼のない電話の切り方」を解説していきたいと思います。
相手の声が聞こえない時の電話の切り方・切る際の注意点など「どうやって切るのか」だけではなく、プラスアルファの情報も盛り込んで解説していきたいと思うので、ぜひ参考にして見てください。
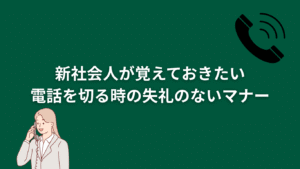
この記事でわかること
・相手の声が聞こえない時の電話の切り方
・電話を切る時の注意点
・より良い印象を与える電話の切り方
・相手の声が聞こえない時に電話を切った際のその後の対応

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験
- 吃音症歴20年
- 元オートローン営業マン
- 元オーダースーツフィッター
- 元百貨店販売員
- 現Webマーケター
- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味
- 酒は飲めない、よく体調崩す人
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
相手の声が聞こえない時に言うこちらからの問いかけの回数
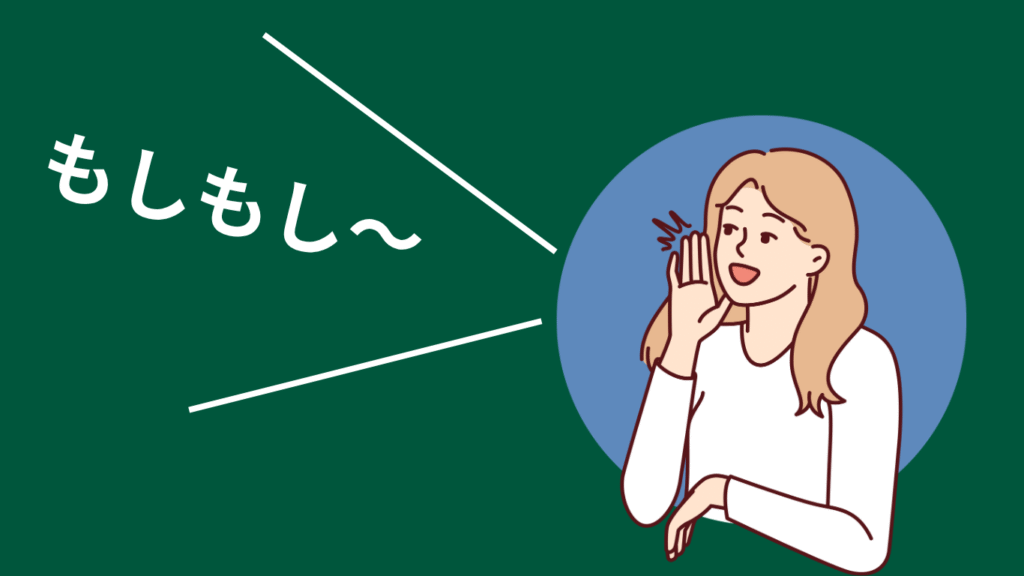
仕事の取引先やお客様相手の電話の際に、相手の声が聞こえない時、電話を切らなければいけませんが、その際に「ちゃんと通信が切れているのか」ということをどれだけ確認しなければいけないのか気になります。
一般的には、電話は繋がっているのか?という確認の際に言う「もしもし」の回数は2〜3回ということを目にしますが、筆者の経験上、3〜5回は言った方が安心だと考えます。
電話の話の最中に相手の声が聞こえなくなったのであれば、電話通信が切れてしまった理由の他に、相手に急用が入ったのかもしれず、一時的な離席かもしれないからです。
3〜5回の確認回数を取ることで、相手が離席から戻ってくるまでの時間稼ぎにもなります。この時に一度の「もしもし」を発する間隔は2〜3秒ほどあけてあげると、そこそこの時間稼ぎにもなりますし、しっかりと電話が繋がっているか確認することもできます。
以上より、「電話がちゃんと繋がっているか」「相手が一時的に離席しているだけか」を確認するための「もしもし」は3〜5回ほどが良いです。
その後、それでも「相手の声が聞こえない」のであれば、万が一こちらは相手の声が聞こえない状況で、あちらからはこちらの声が聞こえている状況であった時に相手に失礼にならないように電話を切ることが大切です。
次項で「相手に失礼にならない電話の切り方」をみていきます。
仕事の電話で相手の声が聞こえない時の電話の切り方

仕事の電話で相手の声が聞こえない時、万一にも取引先やお客様といった方々に失礼に思われないように電話を切るには2つのポイントがあります。
①声が聞こえないことを伝える
②一言添えて電話を切る
以上をおさえてみて電話を切ってみてください。
①声が聞こえないことを伝える
取引先やお客様の声が聞こえず、電話を切らないといけない時、「相手の声が聞こえない」という”なんで電話を切るのか”という理由を念の為言ってあげると良いです。
もし、あちら側からはこちらの声が聞こえている状況であったのであれば、「電話を切る理由」をいわず突然電話が切れてしまうと、「何かあったのか」と不安感を与えてしまいます。
相手に不安を与えてしまうと、電話が切れた後に「折り返しをすれば良いのか」「待っていれば良いのか」とどうしたら良いのかわからないという状況に陥ってしまう恐れがあります。
以上のことから、電話を切る際は「声が聞こえないから電話を切る」ということを伝えてあげると良いです。
②一言添えて電話を切る
相手の声が聞こえない時に電話を切る際、「相手の声が聞こえないから電話を切る」という理由のみだけではなく、”相手に配慮する”一言を付け加えると、もし、相手にはこちら側の声が聞こえている時に失礼に思われることが少なくなります。
次の6つの一言を使ってみてください。
お声が聞こえないみたいですので、一度お電話を切らせていただきます
「相手の声が聞こえない」+「だから電話を一回切る」ということを丁寧に伝えた文言です。
「お電話を切らせていただきます」という敬語の謙譲語表現を用いているのも相手に敬意を示していることになり、失礼に感じ取られにくくなります。
お声が聞こえにくいようなので、一度お電話を切らせていただきます
もし「お声が聞こえないみたい」という文言が言い辛い・失礼に感じるというのであれば、この「お声が聞こえにくいようなので」という文言に変えても問題ありません。
「声が聞こえない」ということを相手に伝えることと、「一回電話を切る」ということが、もしこちらの声が相手に聞こえていた時に伝わることが大切です。
お声が届いていないようですので、一度お電話を切らせていただきます
これも「相手の声が聞こえない」を意味する文言です。
どのように言えば「相手の声が聞こえない」という状況を相手に失礼なく伝えられるのか、それはその時の状況や相手との関係性にもよりますので、参考にしつつ、どの文言を使ったら相手に失礼にならずに伝えることができるのか、を考えて使い分けてみてください。
電波の状態が良くないようですので、一度お電話を切らせていただきます
「電波の状態が良くないようですので」という「決して相手のせいではないよ」ということを暗に伝えるような文言を使うのも良いです。
この文言には「相手のせいで聞こえないのではない」ということと「こちら側から相手の声が聞こえない」ということが含まれています。つまり、二つの意味で”配慮”が行き届いているということです。
申し訳ございません、こちら側の電波不良かもしれませんので、一度お電話を切らせていただきます
「こちら側の電波不良かもしれない」という、これも相手に「あなたのせいじゃないよ」ということを暗に伝えて、相手に余計な心配と手間をかけないようにする”配慮”の意味を込めた文言です。
もし上記のような「相手の声が聞こえない」ことを伝える文言が使いにくいようであれば、この「こちら側のせい」という意味を含めた文言を付け加えることで、相手に失礼なく電話を切ることができます。
一度お電話を切らせていただき、再度こちらからお電話を差し上げます。
「電話を一度切ってどうするのか」ということを電話を切る時に言っておく一言です。
もしあちら側の声が聞こえておらず、こちら側の声だけ聞こえている状況であれば、この一言を付け加えると、「電話の行き違い」や「相手の不安」を防ぐことができます。
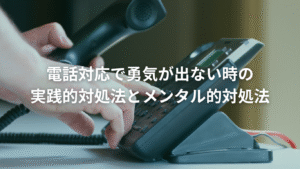
相手の声が聞こえない時に電話を切る際の注意点

相手の声が聞こえない時に電話を切る際、3つの注意点があります。
この注意点をおさえることで、相手に失礼に感じられずに電話を切ることができます。
・無言で切らない
・聞こえないからと言って気を抜かない
・フックスイッチを活用して静かに切る
無言で切らない
仕事の電話で、相手の声が聞こえない時、何も言わずに無言で切るのは避けた方が良いでしょう。
相手の声は聞こえなくても、もし、相手は、こちらの声が聞こえていたら「なんの配慮もせず電話を切った」と思われてしまい、それがキッカケで「失礼だ」と思われてしまう可能性があります。
電話を切る時は必ず上記で紹介した一言などを電話越しで言ってから切るのが安心です。
聞こえないからと言って気を抜かない
何度もになりますが、相手の声が聞こえていないからと言って、こちらの声が相手に聞こえていないかというと、そうとは限りません。
筆者も取引先との電話の中で、向こうからの声は聞こえているけど、こちら側の声が取引先に聞こえない。という状況に何度も遭遇したことがあります。
この経験から、相手の声が聞こえないからと言って、気を抜いてしまい、「聞こえないんですけど」「これ折り返した方が良いですよね」のような周囲との会話などが入らないように、「聞こえているてい」で電話を続け、切った方が良いです。
フックスイッチを活用して静かに切る
フックスイッチは固定電話についている受話器を置くところにある、カチャカチャと動く部分のことを言います。
ここを押すことで、電話回線を切ることができます。
固定電話で取引先やお客様に電話をかけている場合、この受話器をそのままガチャンと置いて回線を切るのではなく、フックボタンを押して回線を切ることで、静かに電話を切ることができます。
これも「相手にはこちらの声が聞こえている」というていを想定し、切る時に相手の耳に大きな音が流れ、不快感を感じないようにするための”配慮”です。
より良い印象を与える一言
相手の声が聞こえない時に電話を切る際に、もし相手には、こちら側の声が届いていた時に、より良い印象を与えることができる、電話を切る際の一言を紹介します。
以下の2つの一言を電話を切る際に付け加えてみてください。
・大変申し訳ございませんが
・申し訳ございませんが
・失礼いたしますが
このように、「相手の声を聞き取ることができないこと」「独断で電話を切らせていただくこと」この二つの行動に対して、相手に配慮した一言を付け加えることで、丁寧な言い回しになり、相手に良い印象を与えることができます。
「相手よりも下手にでる」ということを意識してみると自然にこれらの言葉が出てきます。参考にしてみてください。
相手の声が聞こえない電話のシチュエーション別切り方

実際に、仕事の電話中、相手の声が聞こえなくなってしまうシチュエーションは2つ考えられます。
・話途中で聞こえなくなった時
・最初から聞こえない時
この2つのシチュエーションでどういう文で電話を切れば良いのかを紹介します。
話途中で聞こえなくなった時
もしもし(3〜5回確認後)、お声が聞こえなくなってしまったようですので、大変申し訳ございませんが、一度お電話を切らせていただき、再度こちらからお電話差し上げます。
失礼いたします。
ポイント
・もしもしの確認を念入りに
・途中までは聞こえていたけど聞こえなくなったニュアンスの言葉を使う
・一回切ってまた掛け直すことを伝える
最初から聞こえない時
もしもし(3〜5回確認後)、お声が聞こえないみたいですので、一度お電話を切らせていただきます、大変お手数をおかけしますが、もう一度こちらからご連絡差し上げます。
ポイント
・相手からの電話で電話番号がわからなかったら「大変お手数ではございますが、こちらから電話番号の識別ができませんので、もう一度ご連絡をいただけますと幸いです。」と言う。
・相手の声が聞こえないことを伝える
・もう一度折り返すことを伝える
相手の声が聞こえなくて切った後の対応

もしも、相手の声が聞こえなくて、電話を切った時、その後に相手に誠実感を与えるためのポイントがあります。
こちらもおさえておけば、電話を切った後の対応をすぐに行動に移すことができます。
・電話を折り返す
・折り返しが繋がったら電話を切ってしまった経緯を伝える
・申し訳ない感を出す
電話を折り返す
電話を切った後は、必ず折り返すようにすると、「連絡の行き違い」を防ぐことができます。
もし電話を切った後に、相手からの連絡を待っても、相手も「電話が切れたから待っていよう」となってしまう可能性があり、電話の譲り合い状態になってしまいます。
「電話を独断で切った」という事実もあることから、こちらから電話を折り返すことが、「すぐに相手に連絡をすることができる」かつ、「連絡の譲り合い」を防げる、このようなメリットがあります。
折り返しが繋がったら電話を切ってしまった経緯を伝える
もし、電話を折り返して、相手と電話が繋がったら、「電話を切ることになった経緯」をまずは伝えると良いです。
もし、電話が切れたことに対して不快感を相手が抱いていた場合、冒頭でことの経緯を伝えることで、「そういうことだったのか」という自分の気持ちと事象を知ることで、合点がいき、気を収めることがのぞめます。
相手に自分の「電話を切った」という行為を納得させ、その後の会話を円滑に進めるためにも、まずは冒頭で経緯を説明することが大切です。
申し訳ない感を出す
相手と電話が繋がったら、「電話を切ってしまって申し訳ない」ということを伝えると、相手も「しょうがない」という気持ちになってくれます。
自分の思い通りにならないことが重なると不機嫌になる人もいます。そういう人は、一つ一つの相手の行動をみて違和感を蓄積します。その相手の機嫌を害するような違和感をなくすためにも、「申し訳ない感」を出すことは大切なのです。
言葉、言い方で「申し訳ない感」を意識してみてください。
まとめ
今回は「取引先やお客様との電話で相手の声が聞こえない時の電話の切り方」を解説していきました。
もう一度本記事のポイントをまとめると
切る前に
「もしもし」の確認を2〜3秒間隔で3〜5回
電話を切る時に大切なのは
①声が聞こえないことを伝える
②一言添えて電話を切る
切る際の注意点は
・無言で切らない
・聞こえないからと言って気を抜かない
・フックスイッチを活用して静かに切る
これらを覚えておくと、相手に失礼に感じ取られないように、電話を切ることができるでしょう。
ぜひ参考にしていただければ幸いです。
この記事も役に立つかも

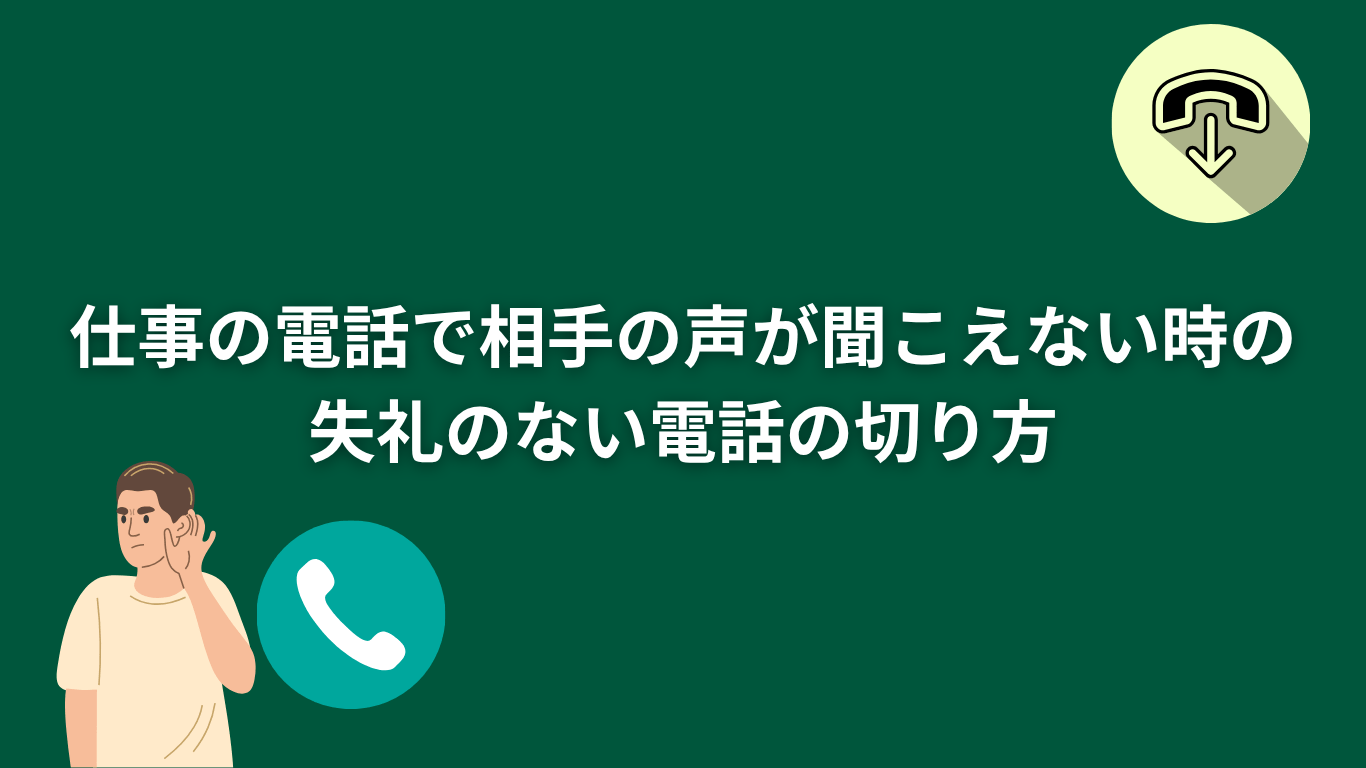
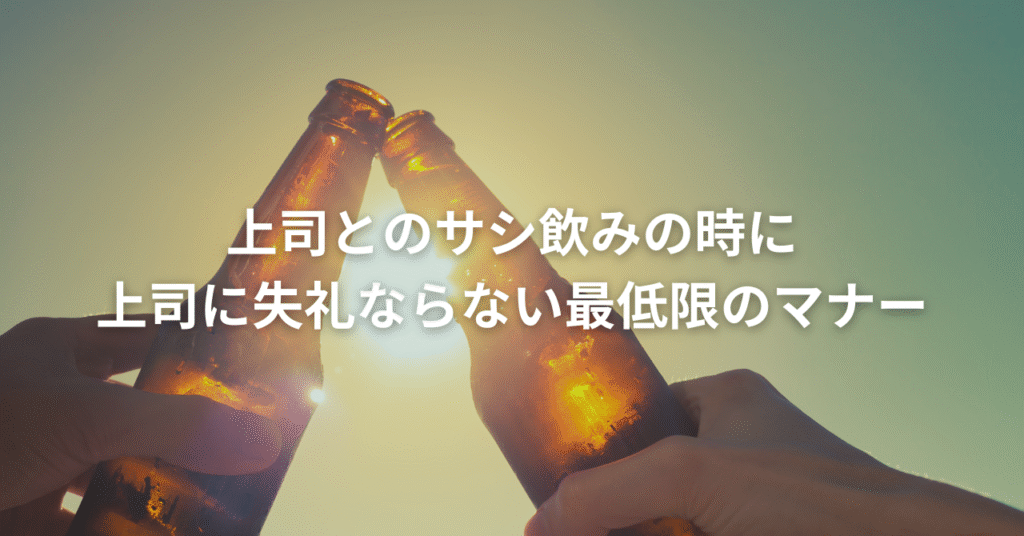
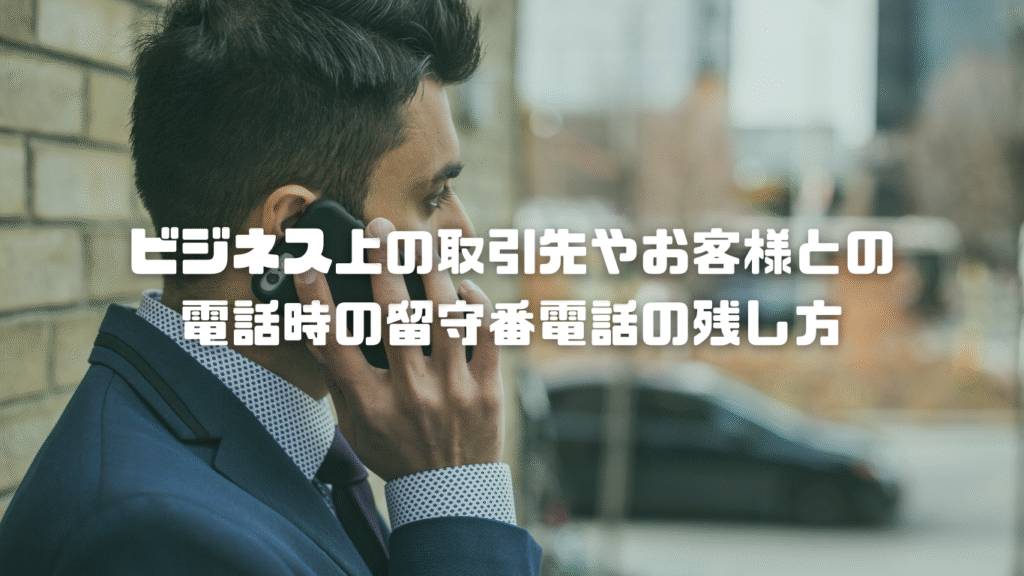
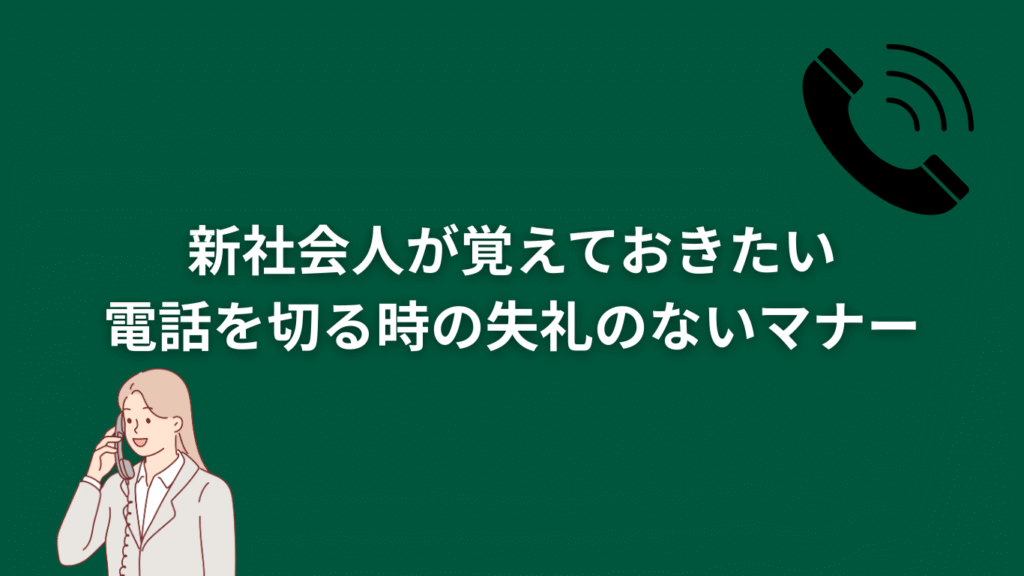
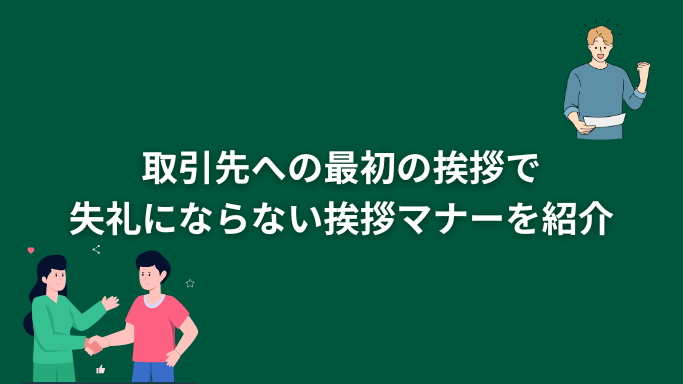
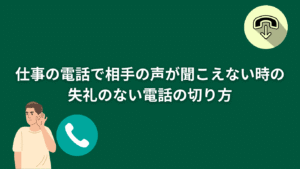

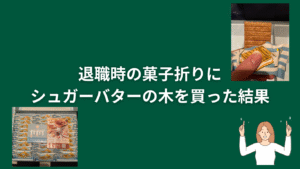
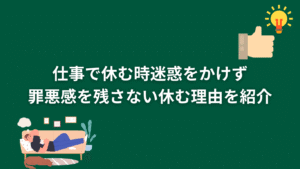
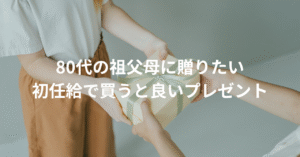
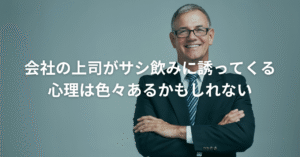
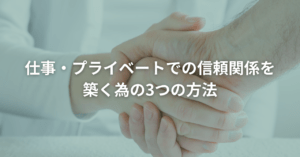
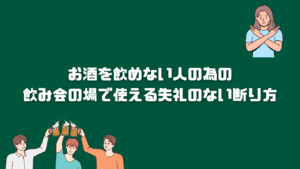
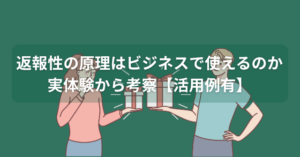
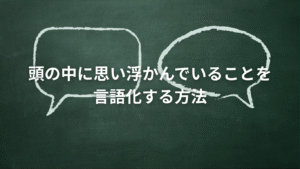
コメントする