筆者です。
・吃音症で仕事が不安
・吃音だけど人と関わる仕事がしたい
・営業での吃りに困ってる
・上司や仕事での吃音不安をなくしたい
・吃音でも営業はできるの?
……など、吃音症でも営業ができるかどうか、不安に思っていませんか?
そんな不安をなるべく解消し勇気づけられるようなお話をしていこうと思います。
結論からいいますと吃音でも営業はできます。
より詳しく言うと、人と接する仕事はできます。
かくいう私も吃音症とは20年ほど人生を共に歩んでいます。
そんな私でも営業や接客業もできました。今日はそんな筆者の実際の体験談もご紹介し、「吃音症は営業職に就けないんじゃないか」という不安を解消していきたいと思います。

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年 小学〜大学まで
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイトを経験
- 吃音症歴20年
- オートローン会社に1年半在籍
- スーツ生地メーカーのオーダースーツ販売店に約4年在籍
- 読書を月10冊ほど
- 筋トレ歴約7年
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
吃音症でも営業職はできるか
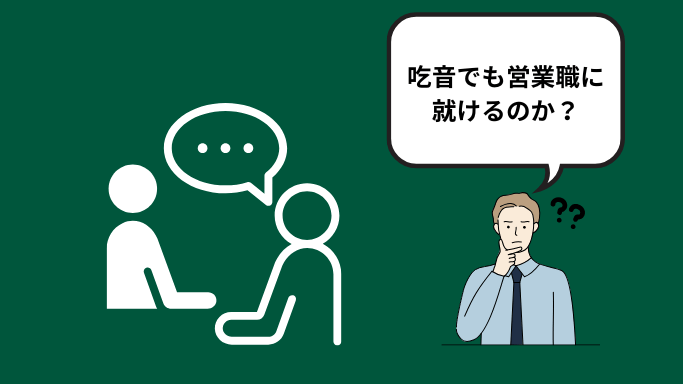
冒頭でもお伝えしましたが吃音を持っていても営業職はできます。
筆者も小学一年生ごろから吃音症をもっています。種類は連発、難発、伸発の3種すべてが発動します。
ちょこっと解説
・連発:言葉が連続してでてきてしまうよ
・難発:言葉が出てこなくなってしまうよ
・伸発:「あーーーーりがとうございます」って感じに言葉を伸ばしてしまうよ
筆者は実際に小学1年生の頃から2年生後半くらいまで吃音が理由でいじめられていたんです。
吃音をマネされたり、そのマネで周囲に嘲笑されたり、どもる言葉を言わされて吃る自分をみて嘲笑されたりと、なかなか嫌な体験でした(笑)
今では難発が主に発動しますが、営業と接客業の人と接する仕事を経験しました。
吃音をもっていても営業職に就けるのは、”吃音の度合い”で変わるんじゃないかと思うのではないでしょうか?
意外とそうではないのです。
筆者も最初に人と接する仕事に就いた時、難発や連発、伸発といったすべての吃音がでてしまい「ほんとどうしよ…」と窮地に陥っていました。ですが、環境に慣れていくうちに自分の心をコントロール(落ち着き、達観する)することができるようになり、吃音を気にせずに仕事に取り組むことができ、結果、吃音を持っていても、営業職や接客業といった人と接する仕事をできると確信をもちました。
私が実際に体験して感じた、吃音でも営業職ができる理由は具体的に3つあります。
・取引先に慕われやすい
・そこまで気にしていない
・相手の気持ちを汲み取ろうとする力が備わっている
取引先に慕われやすい
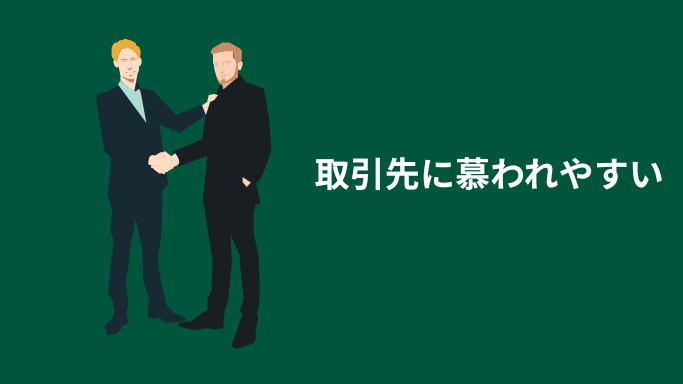
筆者自身、吃音と何十年一緒に人生を歩んでいて多少は吃音の扱いに慣れているとは言っても、初めての環境に身を置く時は必ず吃音がひどくなります。社会人になりたての頃は社内でさえ吃音がひどかったです。
営業配属になり、取引先様へ訪問するようになると、吃音はさらに激しくなりました。
電話でも自分の名前さえ「………、ひっ、筆者です」といった感じでうまく言えないということが続き、営業訪問では吃りながらあたふたしながら忙しなく仕事をしていました。
しかしだからこそ、取引先様に好印象を与えることができたのかもしれません。
手前味噌で大変申し訳ありませんが、一生懸命に仕事に取り組んでいる姿を見て良くしてくれたんだと思います。
吃音であり、他の同期よりも上手く営業活動ができないからこそ、とにかく目の前の仕事に一生懸命に取り組むという姿勢で最初から臨めたことが功を功を奏しました。
ポイント
そこまで気にしない

実際吃りを指摘されたことは一度もありません。
自分でも「めちゃ吃ってるやん…」とわかるくらい吃っているのですが、あくまでも大切なのは伝えたいことが伝わっているかです。
とどのつまり、仕事の中身が大切ということです。
真面目でハキハキ喋っていても内容がちゃらんぽらんだったら相手の頭上にはハテナマークが浮かんでしまいます。
吃っていても、伝えたいことがちゃんと伝わることで信頼は積み重なっていくのです。
そして、吃っても伝えたいことは伝わります。筆者は営業に行く前に何を話すのかを整理してから行っていました。あとは、何度も頭の中でシミュレーションをしたり、パンフレットを持って行って、パンフレットの文言を手でなぞりながら説明をしたり、できるだけ上手く話せる準備と、物事が伝わるように事前準備をしていました。
ポイント
相手の気持ちを汲み取ろうとする力が備わっている
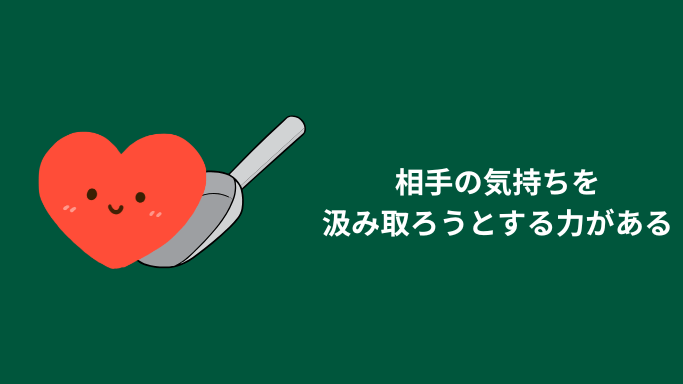
筆者は、相手の反応を伺ってしまうという癖があります。
相手の表情や、仕草から相手がどう思っているのか考えてしまうのです。
これは、幼少期から吃音をもっているということと、吃音を指摘されたり、いじられたりしたという経験からきていると考えます。
ただし、この癖は営業職などの人と接する仕事になると良い効果を発揮します。営業職において「相手がどう思っているのか」を汲み取ることはかなり大事だからです。
相手と良好な関係を作り出すことに繋がります。
ポイント
体験談
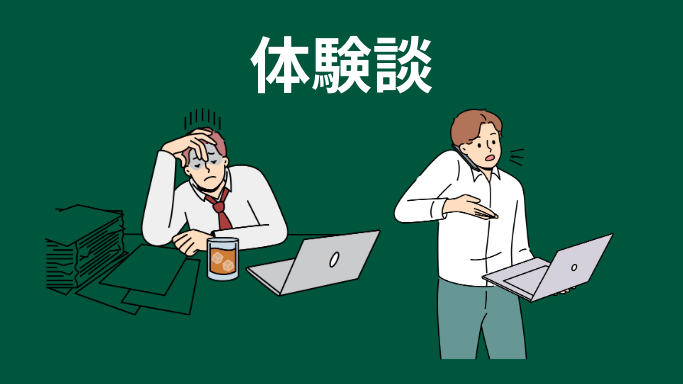
私の実際の営業職での吃音体験談を紹介します。少しでも参考になれば幸いです。
営業での実体験
営業で特に嫌な業務が“電話”です。
対面であれば、ボディーランゲージを駆使して吃りをごまかせていたのですが、いざ電話となると難発がひどく、とにかくあたふたした印象を相手に与えてしまいます。
電話で吃ってしまう理由は2つあると思います。
・電話は相手の声がゼロ距離で届く
・対面はボディランゲージが使える
電話は相手の声がゼロ距離で届く
耳間近で声が聞こえると、圧迫感があり、その圧迫感で喉らへんの筋肉が強張ってしまい言葉が出なくなるのです。
また、圧迫感が「やばい、早く何か話さないと」という気持ちを誘発させ、焦りにより吃音が発生してしまうということもあります。
対面はボディランゲージが使える
上記で書いていますが、対面では言葉が出なくても、表情や動作などのボディーランゲージで想いを伝えることができます。
ですが、電話越しではこれができません。電話越しでは言葉で相手に何かを伝える必要があるのです。
対面では言葉が詰まった時は笑顔で誤魔化すことができたのですが電話ではそうはいきません。
電話業務での対処法
筆者が実際にやっていた電話で吃りにくくする方法が”動作と一緒に言葉を発する”というものです。
「あれ?ボディーランゲージは通用しないんじゃないの?」と思うかもしれませんが、これはボディーランゲージとは別で、吃音には何か動作をやりながらだと言葉を発声させやすいというのが筆者の吃音キャリアの中からわかりました。
ですので、筆者は取引先へ電話をする時に、外だったら歩きながら、車の中だったら空いてる足でリズムをとりながら、または、空いている手で何か動作をしながら電話をしていました。
営業職で辛いこと
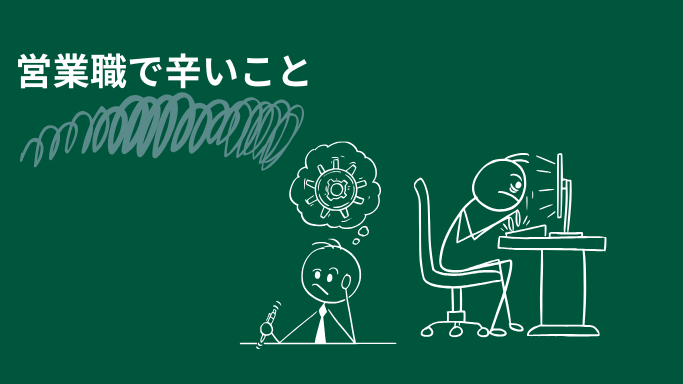
吃音をもっている筆者が実際の営業業務で「辛いなー」と思ったことを共有させてください。
筆者みたいなちゃらんぽらんな人でもなんとかやっているんだなと、少しでもメンタル的に楽になってもらえれば幸いです。
電話で特に吃りが出ること
体験談でもお話ししましたが、電話で話しにくく、普通の人の1.5〜6倍くらいの電話時間がかかってしまうというのは辛かったです。
せかせかしている人と話すと「早く話さなければいけない!」という焦りが生まれ、どもりも比例して悪化しました。
今でもせかせかしている人と話すと焦りで吃りがひどくなりますが、「もうしょうがないや」と割り切っています。
ですが、早く電話を終わらせたいという潜在意識のせいか、電話相手の名前を聞くことを忘れてよく注意されます。
みなさんはちゃんと焦っても相手の名前だけは聞くようにしてくださいね。さいあく、先輩や上司がかけ直してくれますから。(悪知恵)
伝えたいことを伝えられない場合がある
「本当はこう言いたいのに」という言葉を言えないということがあります。
吃らないようにするために言葉を言い換えなければならず、本来伝えたい内容を伝えられず、相手に誤認をさせてしまったり、余計に考えさせてしまったり、「この子に頼んで大丈夫かな?」と不安にさせてしまったということが辛かったです。
例えば…
詳しく伝えたいことなのにも関わらず、言葉が出てこないため「こそあど言葉」など漠然とした言葉しか使えず漠然としか伝えられない。というもの。
これは仕事の質にも関わってくるので、上手くいかないと認識の違いなどができてしまい仕事の失敗に直結するものなので、しんどかったですね。
これは今でもあります。
取り組んだ対策
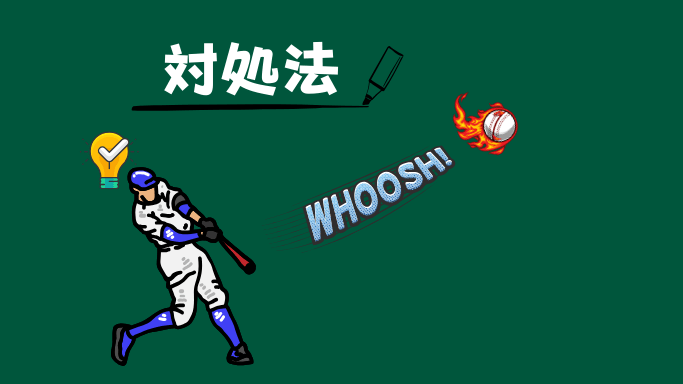
筆者が実際に営業職の時に取り組んでいた対策を紹介したいと思います。
もし、営業職に就くことになった、もしくは、今営業職で働いているという人は参考にしてみてください。
カミングアウトする
カミングアウトに関しては高校生から開始したアルバイトで始めました。
アルバイトでは店長に、仕事では上司に。カミングアウトすることで吃音の理解に繋がります。
ただ、絶対にカミングアウトしたほうが良い!ということではありません。
吃音をなるべく隠したいという方もいると思うので参考程度にとどめておいてください。
カミングアウトした結果、今のところ全員に理解され、自分自身を受け入れていただいてます。(ありがたいことに)
割り切る
吃ってもいいや。自分の価値は失われないからな!というのが私が大切にしている考えです。
自分が吃って、実際に相手がどう感じているのかなんてわかりません。指摘を受ければまだ良い方ですが、何も言われずに心が離れていくことだってあります。何も考えてないかもしれませんし、がんばれっがんばれっと応援してるかもしれません。
自分が吃ることと相手がどう思っているのかを分離して考えてます。
吃ることで自分の価値が下がるわけではありませんし、存在を否定されているわけではありません。
「これが筆者なんだ文句あるか!」くらいの気持ちでいたほうがメンタルが安定します。
グレイテストショーマンの「This is me.」みたいですね。
とはいうものの、悩みの大きさは人それぞれ。
一つ、これだけは忘れないでいただきたいのは、あなたは1人ではないということ。
私も吃音をもっており、世界のどこかで生きてなんとかやっています。
そんな人がいると言うことを忘れないでください。筆者もそんな頑張っているあなたに勇気をもらえます。
話し方のコツ
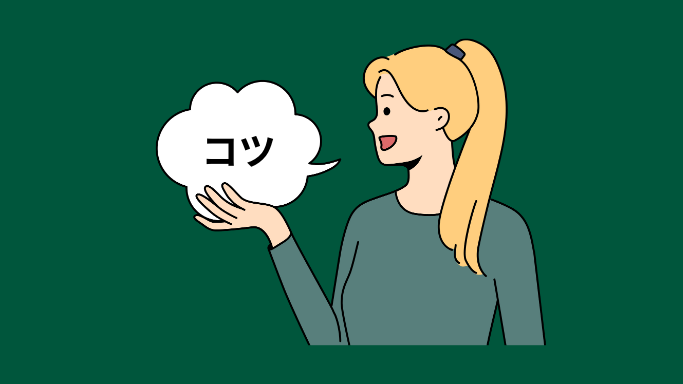
私が行っている話し方のポイントです。万人に受けるわけではないと思いますので参考までにご覧ください。
イニシャルを伸ばす
意図して伸発を出すと言う事です。
「こーーーれはですね」と言葉や物事を考えているように発声する。すると、自然に話しているように聞こえます。
肝心な話しやすさですが、私はとても話しやすくなります。と言うのも筆者は難発がメインなので、イニシャルが出れば勝ったも同然だからです。
文章を区切って話す
選挙で演説を強いる議員に注目してみてください。
文章を細かく区切って話しているのがわかります。
そして、この話し方はとても言葉が出やすく話しやすいことがわかりました。
この中川家のネタで街頭演説というものがありますが、こんな感じです。
面白さの中に学べるものがあります。
例えば…
「今日お時間〇〇時にお伺いします。」
↓
変換後
「今日、お時間(時間)〇〇時に、お伺いします。」
短文で区切ります。
その時にしっかりと感情を込めて言うことです。でないと、ロボットみたいになってしまいます。
吃音症の有名人
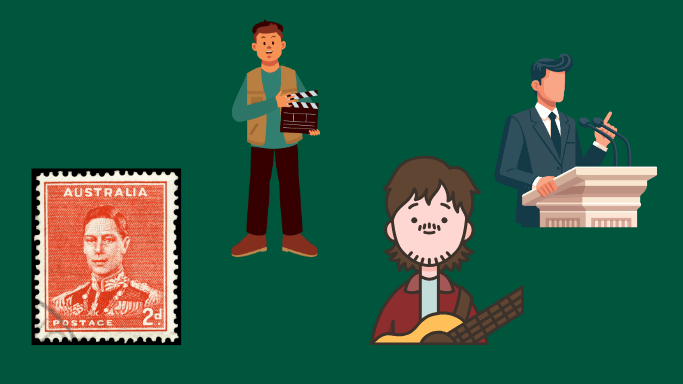
吃音でも活躍している人は多いということに驚きました。「こんな人もいるんだ」と少しでも前向きになれるように紹介したいと思います。
白洲次郎
戦後、外交で活躍した実業家であり、貿易庁長官、内閣総理大臣秘書官を務めた人物です。
ドラマでも生田斗真さんが白洲次郎を演じたことで話題になりました。
「英語の方が話しやすい」と親族に語っていたそうです。
細田守
「時をかける少女」「サマーウォーズ」「おおかみこどもの雨と雪」「バケモノの子」「未来のミライ」「竜とそばかすの姫」でお馴染みの映画監督です。
ちなみに私は「サマーウォーズ」が大好きで聖地巡礼もしてるほどのファンです。
サマーウォーズの栄おばあちゃんの人物像について分析した記事もあります。
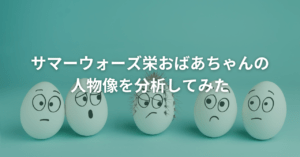
細田守監督は吃音症の映画である「英国王のスピーチ」を観て、
「英国王のスピーチ」観ました。子供のころ吃音者だった者としては(今もまあまあそうですが)、まるで自分がカウンセリングを受けている気分でした。自らのキツい状況に友を得て立ち向かう物語にはとても勇気付けられます。
とXでポストをしていたことから吃音症であったということがわかります。
ジョージ6世
「英国王のスピーチ」で吃音症だったんだと知りました。国王であるジョージ6世は国民の前で堂々たる振る舞いをしたスピーチを何度も行わなければならなかったはずです。
そんな中でも当時、スピーチセラピストのライオネル・ローグさんと二人三脚で吃音症を乗り越えていったとのことです。
映画では同じ吃音もちからみて同感することがたくさんあり、クライマックスのシーンでは感極まって涙が出てしまいました。とても勇気をくれる映画でした。
エド・シーラン
とても驚きでした。
エド・シーランさんの曲はとても大好きでよく聴かせていただいてます。
そんな有名アーティストも幼少期は吃音症を患っていたそうです。
彼はアメリカの吃音協会にもチャリティ参加しており支援もしているそうです。
こんな筆者でも営業成績1位
鼻につく見出しですが許してください。
こんな筆者でもありがたいことに新社会人の1年目に新卒営業成績1位を獲得できました。
決して自分1人の力ではありませんが、吃りながらも目の前のことに一生懸命に取り組んだ結果だと思っています。
例えまわりに吃っていることを指摘されようがあなたの頑張りをみている人は必ずいます。
吃音でも営業職に就くことは可能ですし、新たな自分の可能性に気づく機会になるかもしれません。
周りの声に抑制されるのではなく自分自身の心からの”やりたい”という声に耳を傾けて自分の可能性を試してみてください。
可能性を試すことに成功・失敗はありません。むしろ、成功と失敗でくくるのであれば、試さないことが失敗です。
この記事をみて少しでも希望になれば幸いです。
まとめ
最後にもう一度お伝えしますが、吃音症でも営業職、人と関わる仕事に就くことは可能です。
不安がある人は胸を張ってチャレンジしてみてください。興味がある人はどんどん挑戦してみてください。
きっと大丈夫です。
そして、まだまだ不安だという人はこの記事のコメントでも問い合わせでもXでもなんでも良いです。
相談ください。
そして忘れないでください。
あなたは頑張っていて、1人ではない。少なくても吃音症である筆者もいます。
一緒に頑張りましょう。

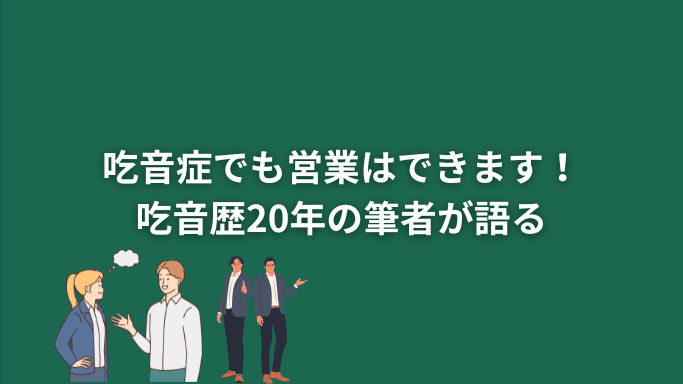

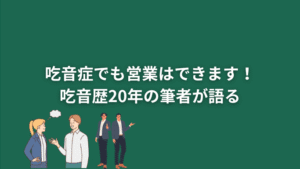





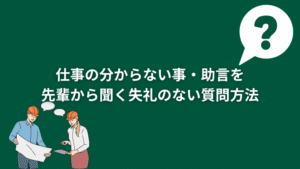
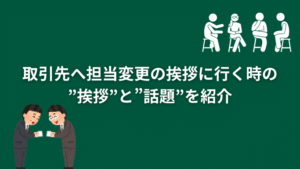

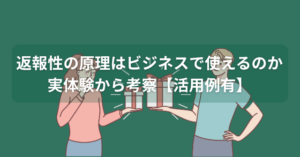
コメントする