やあ筆者だ。
仕事上は「物事を伝える」という機会が多いですよね。
・プレゼンテーション
・報告
・営業活動
など
物事を伝える相手は上司であったり、取引先であったり、はたまた、社内の同僚だったりと、「伝える」ということは仕事において頻繁に行われることであり、大切なことでもあります。
ただ、中には「伝える」という行為が”苦手”という人もいるのではないでしょうか。筆者も新社会人の頃は「人に物事を伝える」という行為が得意ではありませんでしたし、極力避けたいという考えの持ち主でした。
そんな筆者でもガムシャラに働いてきた上で、「自分が伝えたいこと」を相手に伝える技術を筆者なりに蓄積していき、今ではその「伝えたいこと」を文章にして何十万文字という記事を書けるようになりました。
そこで今回は「仕事上で上司や取引先に伝えたい事が上手く伝わる話し方のコツ」を紹介していきたいと思います。
今回の記事を参考にしていただき、仕事上の「伝える」という業務を上手くこなせられれば幸いです。
この記事でわかること
・伝えたいことを上手く伝える基本のコツ
・より上手く伝えるコツ
・上手く伝えるための事前準備

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験
- 吃音症歴20年
- 元オートローン営業マン
- 元オーダースーツフィッター
- 元百貨店販売員
- 現Webマーケター
- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味
- 酒は飲めない、よく体調崩す人
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
伝えたいことを上手く伝えるコツ
仕事上で伝えたいことを上手く伝えるコツは7つあります。
このコツをおさえて、自分の中の「伝えたいこと」を明確にし、相手に話すことで、上手く相手に自分の「伝えたいこと」を伝える事ができます。
ぜひ参考にしてみてください。
①伝えたいことを事前に準備する
②結論+中身+結論
③長すぎないようにする
④相手が理解しやすい言葉選び
⑤相手に合わせた例え話を入れる
⑥”主観”と”事実”を分ける
⑦”曖昧さ”を出さない
①伝えたいことを事前に準備する
まずは自分が上司や取引先に「伝えたいこと」を明確にしてみてください。
この「伝えたいこと」が不明確なとき、「どうやって説明しよう」「どうやって話そう」ということが漠然としてしまい、話の内容が相手に伝わりにくくなってしまいます。
例えば
・取引先に伝えたいことが「商品の値上がり」だったとして、「とりあえず値上がりをしたことを言おう」と思っているだけでは、相手に余計なことを考える隙を与えてしまいます。
→この時、「何で値上げをするんだ」「直前まで報告してこないのはなぜだ!」と不明確要素が多く不信感だったり、「本当に伝えたいこと」が伝わらなくなってしまいます。
事前に「伝えたいこと」を明確にすることが、伝えることに具体性を持たせ、相手に伝えたいことが伝わるという良い結果に結びつきます。
②結論+中身+結論
「伝えたいこと」が明確になったのであれば、次にやることは、相手に「伝えたいこと」を伝えるための「文章」を構成することです。
この時に大切なのが「結論+中身+結論」という構成で文章を作ることです。
この構成をするメリットは次の通りです。
・シンプルで分かりやすい
・「伝えたいこと」に説得力が生まれやすい
・時間がない相手にも時間を取らせずに優しい
「結論」は「自分が伝えたいこと」です。
「中身」はその伝えたいことの具体的な内容であったり、説得力をつけるものであったり、例え話だったりします。
例えば
「取扱商品の値上がり」を取引先に伝えたい時
大変申し訳ございませんが弊社取扱商品の〇〇が来月から〇〇円値上げすることになってしまいましたことをご報告に上がりました。
昨今の物価高の影響もありますが、弊社取扱商品の原材料としている〇〇の値上がり・人手不足による人事採用費の増加、主に2点の理由より、今回大変申し訳ございませんが値上げをさせていただくことになりました。
恐れ入りますが、来月から〇〇円から〇〇円に価格を変更させていただけますことをご了承いただければ幸いです。
まあ、例えの質はおいておいて、こんな感じで「結論+中身+結論」の構成で文を作れば、相手に伝わりやすい文を作る事ができます。
③長すぎないようにする
文章を長すぎないようにするのもポイントです。
長すぎてしまうと、徐々に「伝えたいこと」という趣旨から離れてしまう恐れがあります。ですので、なるべくシンプルに、長すぎずに文を作ってみてください。
ただ、ここでのポイントは「伝えたいこと」に必要な情報を無理に削らないということです。文を短くしようとして無理に必要である情報を削ってしまうと、かえって「伝えたいこと」が伝えられない。という恐れがあります。
ですので、「文を短くする」or「必要情報を入れるか」という二択に迫られたら「必要情報をシンプルに入れる」ということを大切にしてみてください。
④相手が理解しやすい言葉選び
「伝えたいこと」を相手に伝える時にできるだけ「相手が理解しやすい言葉」を選んで伝えてあげることが大切です。
よくカタカナ言葉を使っているビジネスマンがいますが、あれは他者に気を配れていない、自分の能力を誇示したいという潜在的意識が「伝える」行為を妨害しています。
これをいうと「ビジネスマンとして知っておくべき」というポジショントークをしてくることがありますが、仕事は「人と人との繋がりでできている」以上、相手に合わせなければ仕事はうまく回りません。
この”相手が理解しやすい言葉選び”というのは、この「相手に合わせる」ことが目標であり、「伝えたいこと」をうまく伝えて「仕事を円滑に回す」ことが目的なのです。
⑤相手に合わせた例え話を入れる
例え話を入れると、「伝えたいこと」に説得力や想像力が増して、相手に伝わりやすくなります。
そして、ここで入れる例え話は「相手に合わせたもの」であれば、相手も想像しやすく、伝えたいことが上手く伝わることに繋がります。
「相手に合わせた例え話」というのは
・相手がゲーム好きならゲームに例えた話
・相手が野球が好きなら野球に例えた話
など
相手の「経験」「立場」「趣味」などに合わせて、想像しやすい例を付け加えると、「伝えたいこと」が伝わりやすくなります。
⑥”主観”と”事実”を分ける
これは結構やってしまうことなので注意すると良いです。
ついつい主観と事実をごっちゃにしてしまい、相手との認識の齟齬が生まれてしまう可能性があります。
「伝えたいこと」を伝える時には、ちゃんと”主観”は主観、”事実”は事実で分けて話すと良いです。
ここでの「主観」は「自分が感じたこと」です。「事実」は「実際の相手の行動、言動」です。
例えば
主観
・お客様が嬉しそうだった
・取引先の表情が柔らかかった
・特定の商品が最近売れている気がする
事実
・お客様が次の予約をとってくれた
・取引先が新しい契約をしてくれた
・特定の商品の予約注文が何件か入った
主観を伝える時は「あくまでも私の主観なのですが」というと相手に分かりやすいです。
事実はそのまま事実として伝えると良いです。
⑦”曖昧さ”を出さない
「伝えたいこと」を上司や取引先に伝える時に大切なのが「曖昧さを出さない」ということです。
・おそらく大丈夫です
・おそらくこうなります
・たぶん〇〇だと思います
というまだ確定していないことを曖昧に伝えると、これも認識の齟齬であったり、みのなる情報になりません。また、その情報の説得力や想像力が半減してしまう恐れもあります。
つまり、伝えられた方は聞いた情報を完全に信じる事ができなくなってしまうのです。
「伝えたいこと」を明確にすることも大切ですが、伝える時の文章に「曖昧さ」を入れないということも、情報の明瞭性を損なわないようにする大切なことです。
より伝えやすくするコツ
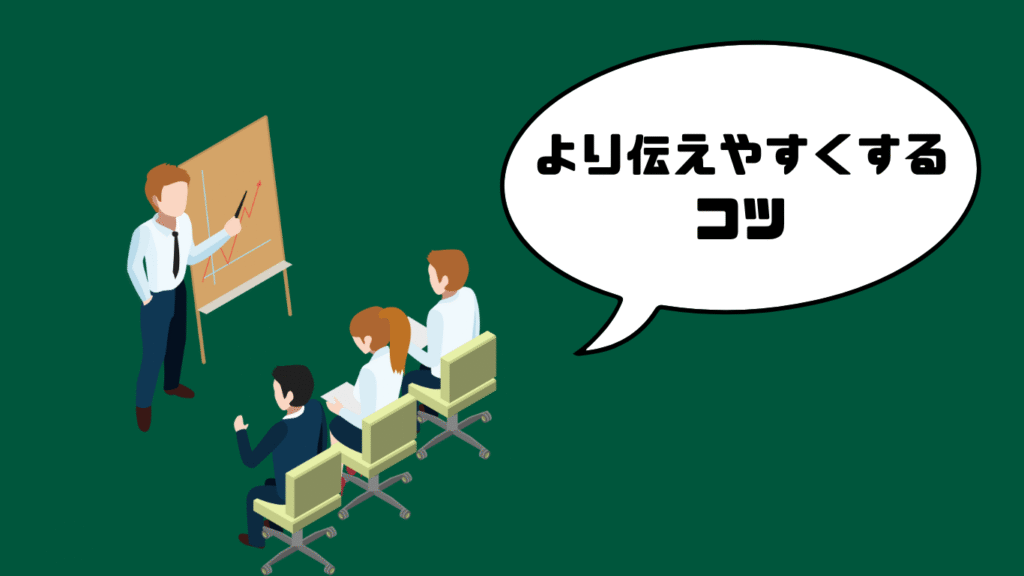
「伝えたいこと」が伝わる話し方の基本のコツを知った上で、次に、「伝えたいこと」を”より”伝えやすくするコツを紹介していきたいと思います。
より伝えやすくするコツは以下の3つです。
・相手にテンポを合わせる
・5W1Hを意識してみる
・非言語コミュニケーションも意識してみる
相手にテンポを合わせる
相手にテンポを合わせるというのは、2つの意味があります。
1つは「相手の会話のテンポ」に合わせるということ、2つ目が「相手の言ったことに対してのテンポ」を合わせることです。
1つ目の「相手の会話のテンポ」について、相手と話すスピードを同じにすることで、良い印象を相手に与える事ができるので、自分が「伝えたいこと」を伝えやすくするという意図があります。
これは、心理学の「ペーシング」という会話の早さを相手と同じにすることで相手に親近感を湧いてもらい、心理的障壁を下げてもらうという効果があることもポイントです。
問題は2つ目の「相手の言ったことに対してのテンポ」を合わせるというのは、相手がもし自分が「伝えている最中」に指摘をしてきた場合、その指摘に合わせて、話すスピードを合わせるということです。
例えば
・伝えている最中に「これは違うんじゃないか?」と言ってきた。
→指摘されたことをすぐに訂正しようとして、早口で捲し立てるように訂正をする。
→これは相手の話すスピードと合っておらず、相手に不快感を与えかねない。
と、このように相手の言葉に対してそれ以上の早さで話すことで、相手にプレッシャーを与えてしまい不快感に繋がってしまうのです。
いつでも冷静にいることがポイントです。
5W1Hを意識してみる
学生時代英語の授業で習ったことです。
・Who:誰が
・What:何を
・When:いつ
・Where:どこで
・Why:なぜ
・How:どのように
このように5W1Hを意識してみると、「必要な情報」が見えてきます。
「誰が」というのはとても大事ですよね。主語になります。
「何を」というのも「何をしたのか?」という内容を話す時に必要です。
「いつ」は内容そのものになったり、内容を補足する役割があります。
「どこで」も内容を補足する役割があります。
「なぜ」は動機や原因を表す時に必要です。
「どのように」これも内容に具体性をもたせる時に必要です。
このように考えると段々と頭の中を整理することができます。
非言語コミュニケーションも意識してみる
非言語コミュニケーションを意識してみるのも大切です。
ここでいう非言語コミュニケーションとは
・表情
・声色
・仕草
です。
これらは、話す内容に説得力を出してくれます。
例えば
「伝えたいこと」が良い内容だった場合
→声色、表情を明るくすることで、相手に「良い報告なんだな」と話の内容があまりわかっていない段階でも判断する事ができます。
さらに、「メラビアンの法則」という心理的作用もあります。これは、「言動と表情、言葉」に不一致が合った場合、優先される情報は「視覚情報が55%、聴覚情報が38%、言語情報が7%」となるという法則です。
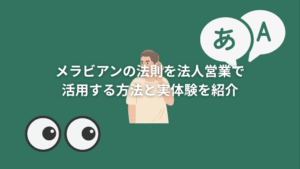
メラビアンの法則は「言動と表情、言葉」が不一致の条件下での心理的作用ですが、もしも、ポジティブな「伝えたいこと」でも暗い表情で伝えることで、100%相手に伝わらないかもしれません。
ですので、なるべく「言動と表情、言葉」、特に意識できる非言語コミュニケーションである表情、声色、仕草などは意識してみると良いです。
伝える前の事前準備

「伝えたいこと」を上手く伝えるには、事前準備も欠かせません。
特に次の5つの準備を行っておくことで、伝えたいことを上手く伝えるように話す基本のコツの一つである「伝えたいことを事前に準備する」を達成する事ができます。
また、「伝えたいこと」の説得力をつけることもできます。ぜひ参考にしてみてください。
・見える化する
・状況の把握
・情報収集
・資料の準備
・知識の蓄積
見える化する
事前準備はかなり大切です。これが上手くできれば、「伝えたいこと」を相手に「上手く伝える」ことができ、認識の齟齬なく伝わることにも繋がります。
その事前準備で大切なことは「何を伝えるのか」を明確にすることです。
明確にするには実際に自分がどう思って、どう感じているのかを「見える化」することです。
「見える化」をすることで、頭の中の情報を整理する事ができ、「自分の伝えたいこと」を明確にできます。
その際には次の2つの方法をやってみると良いです。
・紙に書き出す
・iPhoneのメモ帳アプリに書き出す
紙に書き出す
紙に書き出す時に筆者がおすすめするのは、「なるべく大きな紙に書く」ことです。
なるべく大きな紙に書くことで、上手く空白を作る事ができ、一目で情報をみやすいですし、補足情報も書き入れる事ができ、より頭の中の情報の整理をすることができます。
おすすめなのはA4のレポート用紙です。
筆者も普段からA4のレポート用紙で頭の中を整理しています。
筆者が実際に使っているレポート用紙
iPhoneのメモ帳アプリに書き出す
iPhoneのメモアプリに頭の中の情報を書き出すこともおすすめです。
これは情報の見える化ができるだけではなく、iPhoneがもつ、いつでも持ち歩く事ができるという特性のおかげで、場所を選ばずに頭の中のことを書き出せます。
また、それを見返すことも容易です。
iPhoneのメモアプリで情報を整理する方法は別の記事で解説していますので、そちらも参考にしてみてください。

状況の把握
事前準備の一つに「状況の把握」というものがあります。
これは「伝えたいこと」の質をあげるのにとても役に立ちます。
起こっていることに対して冷静に分析してみるのです。
・誰が関わっているか
・どういう問題が起きているのか
・仕事の進捗はどれくらいなのか
など
このように現状の把握をしてみてください。
情報収集
「情報収集」も「伝えたいこと」を伝える間に行いたい事前準備です。
情報収集をすることで、「伝えたいこと」の質が上がります。
とにかく伝えようとしていることに関する情報はないか?をもう一度確認してみてください。
資料の準備
「伝えたいこと」に説得力を持たせるには目に見える「説得材料」をもつことも大切です。
特にプレゼンテーションや商談など、業務上で”データ”が必要な場面ではなおさらあった方が良いです。
・市場調査
・売上動向
・客足の増減傾向
など
目に見えて説得材料となる資料は事前に準備しておいた方が良いでしょう。
知識の蓄積
知識の蓄積は「自分を守るため」です。
「伝えたいこと」を伝えたい時に、相手から”指摘”や”質問”があるかもしれません。その時に素早く的確に回答することができれば、相手からの信頼感の増加に繋がるかもしれません。
また、この時、もし答えられなく、言葉に詰まってしまったら自己嫌悪に陥ってしまう可能性があります。ですが、事前に知識を蓄積しておくことで、その自己嫌悪を防ぐ事ができるのです。
自分を守るためにも「知識の蓄積」をやってみてください。
仕事上で伝えたい事を伝えるためにやっておいた方が良いこと

仕事上で上司や取引先に自分が「伝えたいこと」を上手く伝えるためには、やっておいた方が良いことがあります。
それは次の3つです。
・良好な人間関係の形成
・読書
・新聞を読む
良好な人間関係の形成
伝える相手と良好な人間関係を形成することで、自分が伝えたいと思ったことを、たとえ上手く伝えられなかったとしても、「汲み取ってくれる」可能性が高まります。
ただ、良好な人間関係を作るには日々コミュニケーションが必要です。
読書
読書をすることで良い事が3つあります。
・知識がつく
・想像力がつく
・言語力がつく
知識については言わずもがなですが、「想像力」と「言語力」について解説すると、
「想像力」
・小説などを読んだ時にシーンの描写を想像することで想像力がつきます。
・ビジネス書などでも「この人は何が言いたいんだろう?」と思考する事で、「相手が考えることを想像する」力がつきます。
「言語力」
・活字を読むことで、文法が自然と頭に入ってきて、その文法が感覚として根付き、日々使う会話の中で意識するか・無意識のうちに本に書かれているような丁寧な文章を作ることができます。
このように読書は「知識」や「娯楽」だけではないということがわかっていただけたでしょうか。
新聞を読む
新聞を読むことも読書と同じように、文章を書くプロが書いた文字列を読むことで、自然と言語力がついてる、だけではなく、主に時事ニュースについて情報種集をすることができ、言語力がつくと同時に「情報収集」も可能になるものです。
筆者個人的にネットニュースも良いですが、ネットニュースだと文章が端的に書かれているものが多く、言語力が上がりやすいのは長文がある「新聞」が良いかなと思います。
筆者は社会人になってから新聞を読み始めましたが、以上のような効果以外にも「日々どれだけ多くの情報が世に広まっているのだろう」という驚きや気付きもあるので、とても良いものだと思います。
最後に
今回は「仕事上で伝えたいことを上手く伝える話し方のコツ」を中心に、「伝えたいこと」の伝え方を解説していきました。
ただし、今回紹介した方法が「絶対的な正解」ではないことを念頭においておいてください。もちろん、本記事で書かれていること以外にも、ネットや本などで書かれているものもそうです。
これらはあくまでも一つの”方法”であって”正解”ではありません。
方法は活用する相手によって都度変わります。今回の方法がはまらない相手もいます。それは人間おのおの様々な人生を歩んできているので仕方がないことです。
ですので、決して以上のような情報を鵜呑みにするのではなく、いったん自分の中で考え、「どの方法が自分に合うのか」ということを見つけ、実際にやってみて試行錯誤して「自分だけの方法」を確立していってください。
今回の記事は、その助けになれば幸いです。
この記事も役に立つかも

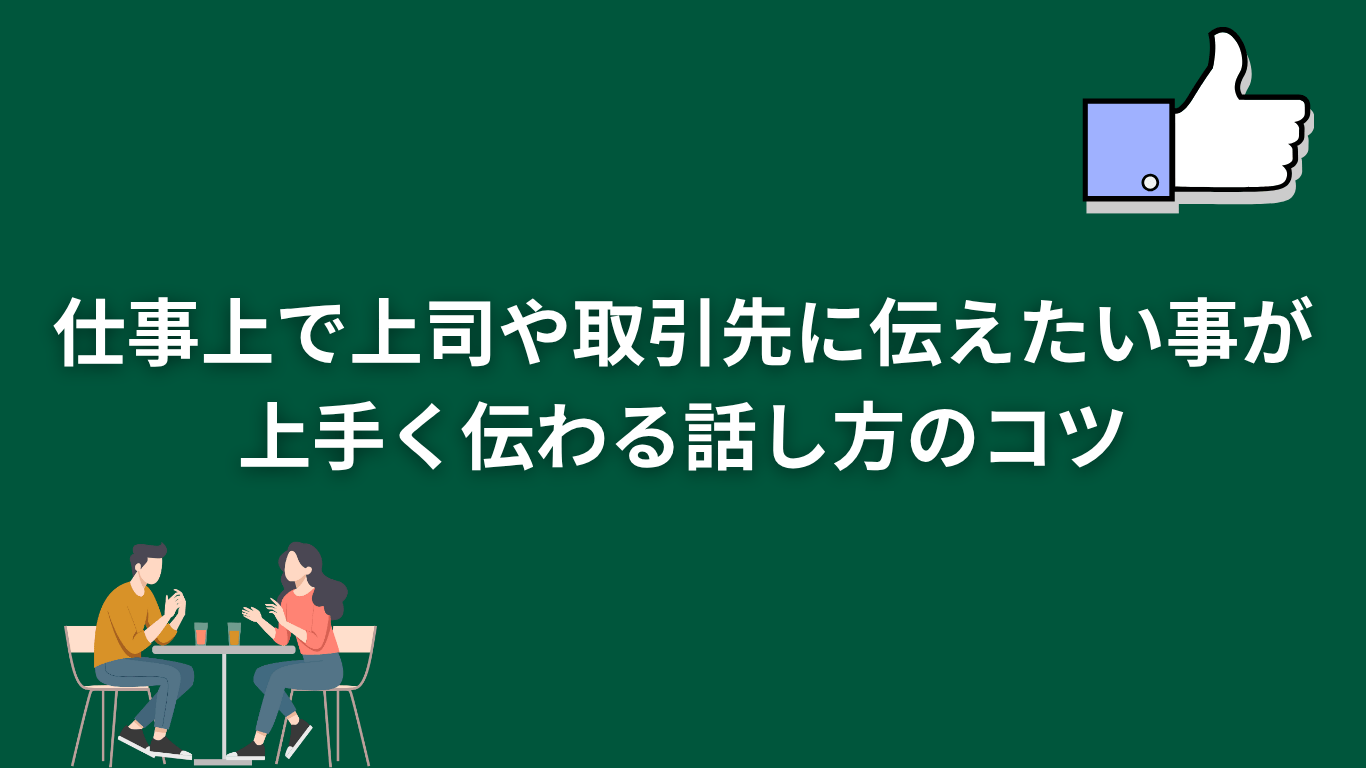

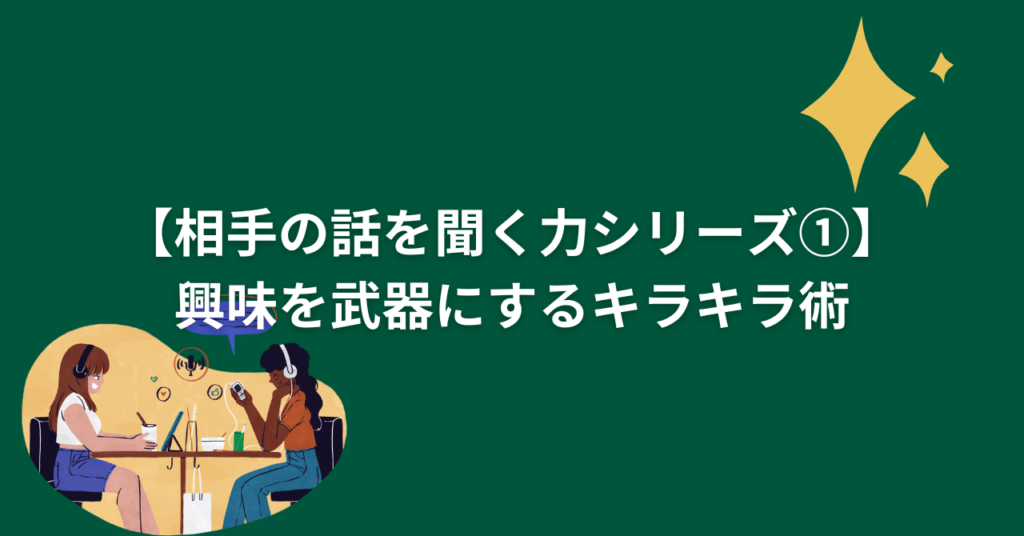
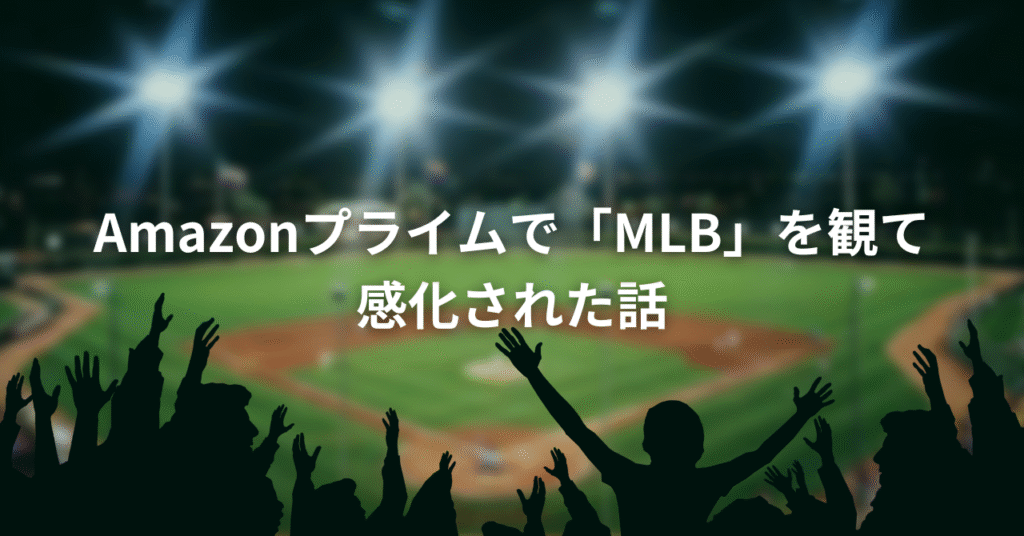
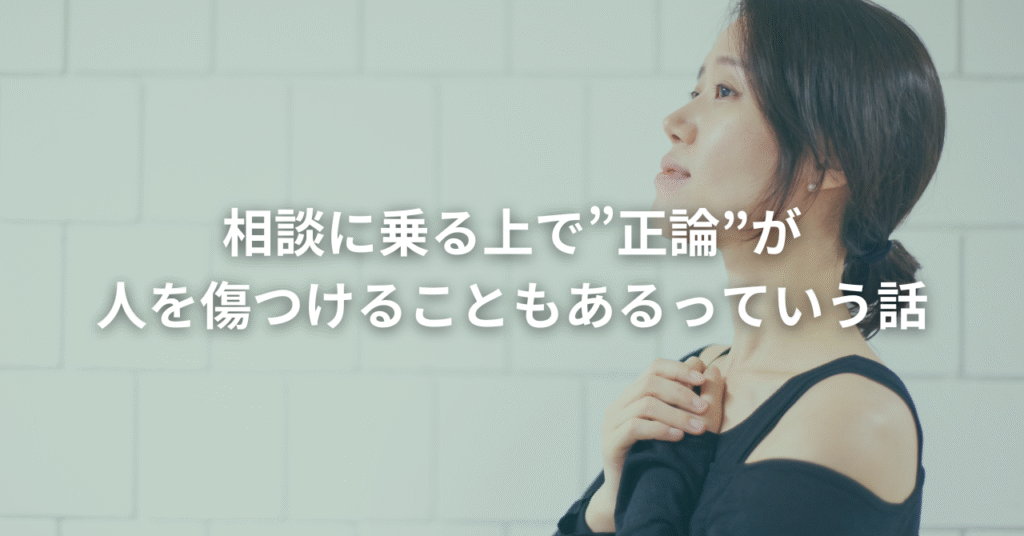
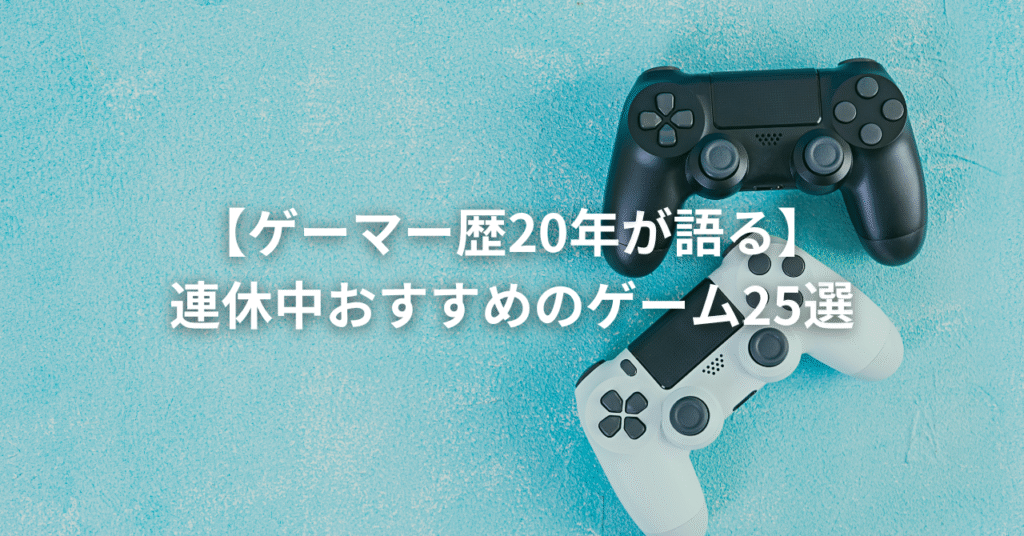
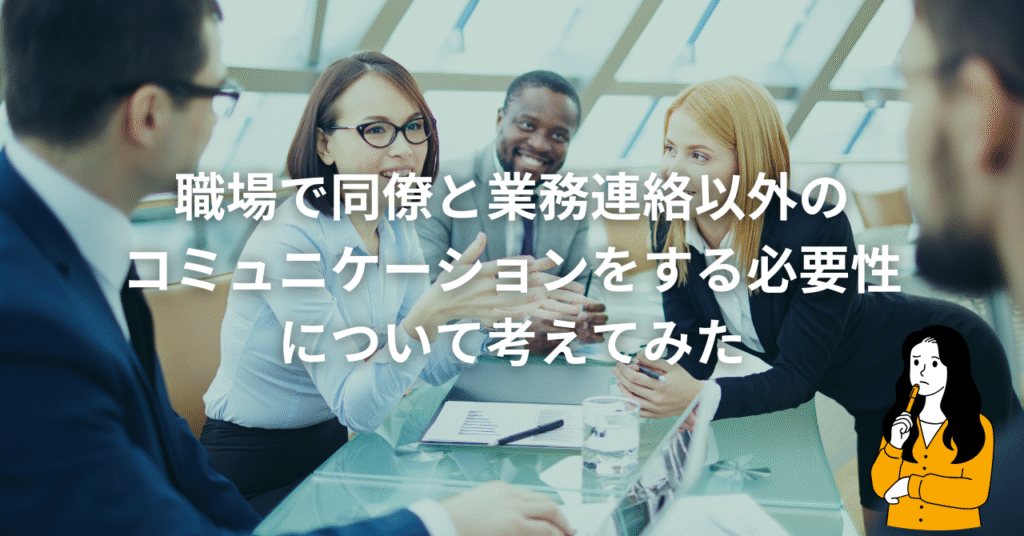
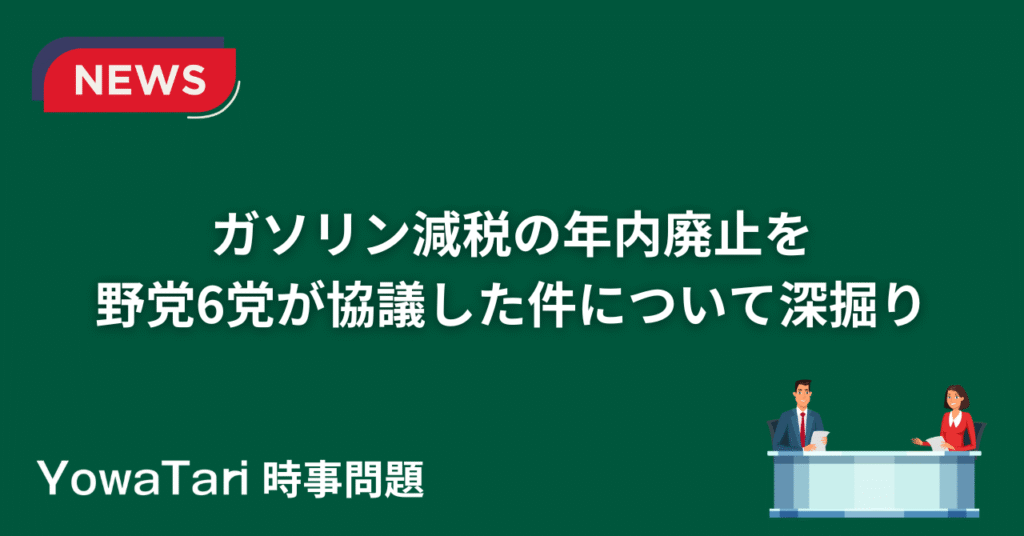
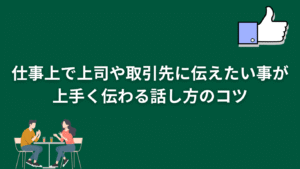

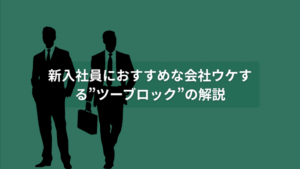
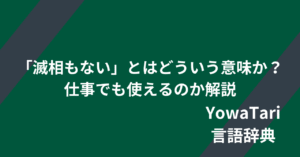
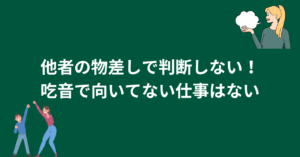

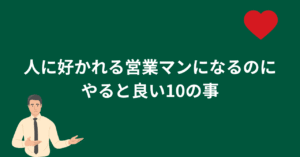
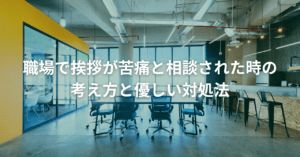

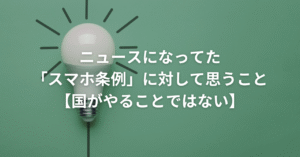
コメントする