職場において、”会話”っていうのは嫌でもしないといけない。
でも、この”会話”っていうのは相手に気を遣わないといけなくてめちゃくちゃ億劫になってしまい、「嫌なこと」っていう認識になってしまいがち。
だから、職場内における同僚との「コミュニケーション」って過度に気を遣わない、つまり、労力がそれほどかからない”業務連絡”だけで良くない?って思ってしまうんだけど、実は職場で業務連絡以外にコミュニケーションをとる必要性って結構高いんじゃないかっていうことを今回深掘りしていく。
筆者もどちらかというと職場というか会社にいる時は極力会話を避けたい人ではある。だけど、筆者の経験上からしても職場内で業務以外のコミュニケーションをとることって結構重要だったりすることを会社で過ごしていて感じたから、今回はそんな筆者の目線からも考えていきたいと思う。
この記事でわかること
・職場で同僚と業務連絡以外のコミュニケーションの必要性
・業務連絡以外のコミュニケーションが必要な理由
・新庄さんとバリーボンズさんの話

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験
- 吃音症歴20年
- 元オートローン営業マン
- 元オーダースーツフィッター
- 元百貨店販売員
- 現Webマーケター
- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味
- 酒は飲めない、よく体調崩す人
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
職場で同僚との業務連絡以外のコミュニケーションは必要か?

職場で同僚との業務連絡以外のコミュニケーションは必要か?ってことについて考えていきたいんだけど、これは筆者の経験からしても、「必要」ってことが言える。
ただし、同僚との業務連絡以外のコミュニケーションが”必須”か?って言われると、そうではないと思う。
別に「絶対に職場内では同僚と業務以外のことを話さないといけませんよ!」なんて決まりはないし、業務以外のことを話さないと人事評価が下がるのか?って考えるとそんなこともない。
それでも、筆者は職場内で同僚と業務連絡以外のコミュニケーションは”必要”だと考えてる。
その理由を深掘りしていこう。
職場での業務連絡以外のコミュニケーションが必要な理由
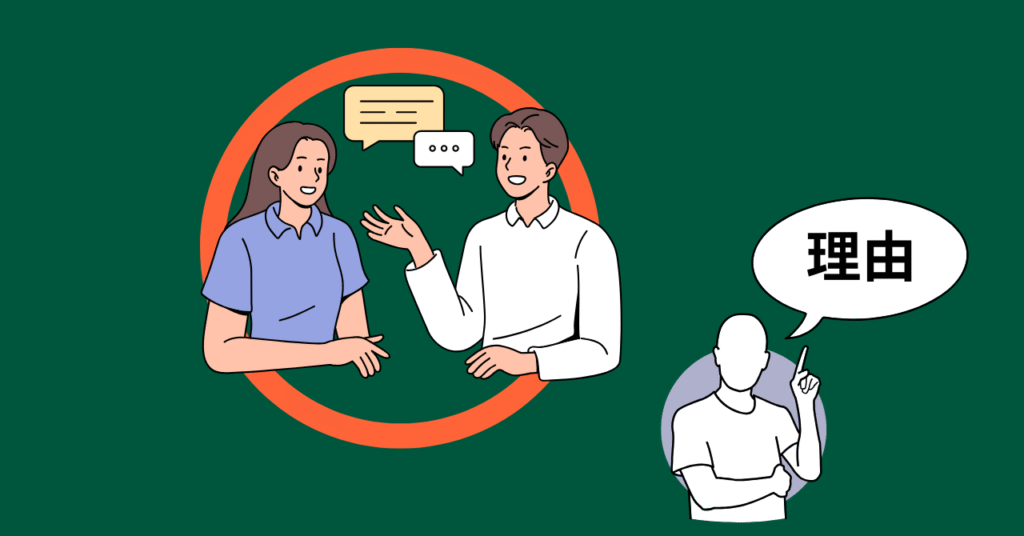
職場で業務連絡以外のコミュニケーションが必要な理由は次の6つの理由が考えられる。
それぞれ詳しく見ていこう。
①業務の円滑性を欠く
②過度に気を使うから
③同僚が信用できなくなる
④話し合いの質が変わる
⑤相談できない環境を自ら作ってしまう
⑥相手の気になったところを上手く指摘できない
①業務の円滑性を欠く
職場内で業務連絡のみの会話をしていると、業務の円滑性を欠くことになってしまう。
「業務の連絡はするんだから仕事には影響ないんじゃない?」そう思うかも知れないけど、確かに比較的業務の手順が決まっていて、その決まっている流れに沿って行う業務では業務連絡のみをしていれば仕事の円滑性を欠くことは少ない。
だけど、業務の流れの中でイレギュラーな対応が考えられるケースであったり、あとから追加で業務を追加しなきゃいけなくなる可能性がある業務などといった、もともと決められた業務の他にも色々な業務が生じる可能性があるものだと、同僚と業務連絡を超えたコミュニケーションが必要になるんだ。
同僚と業務連絡を超えたコミュニケーションをとっておけば、気軽に「もし他の業務が途中で入ってきたらフォローお願いしても良いですか?」といったような業務内における”連携”をとることが容易になる。
これは”業務連絡”というような実務的な話ではなくて、”気持ち的”な話。
簡単にいうと、「事前に同僚とコミュニケーションをとって心理的にお願いしやすい環境を作る」っていうこと。
②過度に気を使うから
職場内で業務連絡のみの会話を同僚としていると、同僚に過度に気を遣わないといけなくなっている状況から抜け出せない。
まず、他人になんで”気を遣ってしまう”のかというと、他人が他人だから。何を言ってるのかというと、”他人のことを知らない”ということを言ってるんだ。
他人のことを知らないから、「相手はこれを言ったら嫌がる」とか「相手はこれを言ったら喜ぶ」とか、そういう「相手に合わせた言葉選び」「相手に合わせたテンション」などがわからない。
例えると、相手の怒りの地雷原がわからないから、慎重に相手と接してしまうっていうこと。これが他人に気を遣ってしまう背景。
”気を遣う”っていうのはめちゃくちゃしんどい。筆者も人見知りだからわかる。会社に入って「疲れるなぁ」って思うのは8割「人への気遣い」だと思ってる。
この”気遣い”の心労から解放されるには「職場内の同僚と業務連絡以外のコミュニケーションをとる」っていうことってこと。
同僚とコミュニケーションをとって同僚を知れば、過度な気遣いをせずに仕事ができるから。
③同僚が信用できなくなる
仕事において”信用”ってのはすごい大事。
取引先から”信用”されて、新しい仕事を貰うことだってできる。社内に上司から”信用”されて職位が上がったり、重要な仕事を任せてもらえたりする。
プライベートでもそう。人から信用されることで、頼られる場面が少なくない。
色々なところで”信用”っていうのは重要視できるけど、職場内の同僚への”信用”も大事。
ここで言いたいのは、「職場内の同僚から信用されるためにコミュニケーションをとろうね」ってことじゃない。「職場内の同僚が信用できるかどうかのコミュニケーションをとる」ってこと。
こっちから同僚を信用することっていうのは結構大事。というのも、職場内で同僚を信用することで、自分が休みの時の仕事を任せたり、業務を連携する時に「自分がどこまでやっていれば同僚は仕事をやりやすいか」ってことがわかって業務の円滑性にも影響してくる。
こうした場合、同僚を”信用”するためには業務連絡を超えた”コミュニケーション”が大事だよねってこと。
カジュアルなコミュニケーションをとっていれば、同僚がどこまでできるのか、どこまで任せられるのか、どういうことが苦手なのかっていう同僚に関することが知れて、それは同僚への信用に繋がるから。
④話し合いの質が変わる
職場で同僚と業務連絡以外のコミュニケーションをとることで、職場で会議などの話し合いの質が変わる。
職場の会議っていうのは発表者が話してただ、作られたレジュメ通りに話が進んでとくに他の人の意見を出さないで終わるなんてことはままあるとお思う。少なくとも筆者がいた会社にはあった。
なんのための会議やねんっていう会議ね。
こうした話し合いっていうのはあとから振り返った時に「あの話し合いやる意味あった?」って疑問をもってしまう可能性がある。
本当の話し合いっていうのは、話し合いに参加した人の色々な意見を収集して全員でより良い結論を導き出して、その結論を目安に行動していくもの。
会社の中の”話し合い”っていうのは、決して職種が高い人の意見に全員が賛同するっていう場ではない。って筆者は思う。そんな話し合いしてるんだったら業務をした方が実りがある。
ちょっと話がそれちゃったけど、同僚と普段から業務連絡以外のコミュニケーションをとっておくことで、これも”心理的な障壁”が取り除けるってこと。
ここでいう、話し合いの場で意見が出しやすい環境を作ることができる。ってことに繋がってくる。
そうすれば、全員の色々な意見が収集できて、より良い結論を導くことができる話し合いができるっていうわけ。
⑤相談できない環境を自ら作ってしまう
職場で同僚と業務連絡以外のコミュニケーションをとらないことで、同僚に相談できない環境を自らつくってしまうことになる。
職場において、「困った時に相談できる環境」っていうのは本当に大事。これは筆者の実体験から言えるんだけど、筆者はもともと新卒で会社に入社した時に、「他の人と協力する」ってことが苦手だった。なぜなら人見知りだし、結構早い段階で他人に対して心のシャッターを締めてしまうから。
だから、仕事上でわからないことがあったら当時は直属のトレーナーである先輩じゃなくて仲の良い同期に主に相談してた。
でも、同期だって新卒で仕事がわかるわけではないから、わからない者同士で話してて結局失敗しちゃうみたいなことをしていてトレーナーの先輩に怒られたことがある。
この筆者の経験から、普段から業務連絡以外のコミュニケーションをとっておかないと、いざ仕事上でわからないことが発生した時に「相談しにくいなぁ」って気持ちに苛まれて、結局業務上の失敗をしてしまい、相談しないことに対して怒られるってことになりかねない。
普段からコミュニケーションをとって、”相談しやすい環境”を作って業務上の失敗を防ぐっていうのは自分でできる仕事のミス防止でもあるってこと。
⑥相手の気になったところを上手く指摘できない
職場というのは”他人”が必ずいる。
で、その他人っていうのは「自分と空気感やテンション、価値観が合う人」だけではないってことが難しいところ。つまるところ、会社って組織は十人十色な従業員がいっぱいいるってこと。
その中で、業務上「それは違うんじゃないかな」って思うことって出てくる。それはしょうがない。他人だし、生きてきた人生だってみんなそれぞれ違うんだから、違う価値観を持っていて、大多数の人があっているだろうって思っている価値観とは違う価値観を持っている人だっている。
そういう時に、「それでも良いんだけど、こっちの方法の方がより良いよ」っていう助言を伝えるにしても、コミュニケーションが十分に撮れていないと、言われた相手からしたら「うるさいな」「なんだよ上から目線で」っていったような”不快感”を感じてしまうかもしれない。
相手に不快感を与えてしまうと、改善してもらいたいことも改善してくれない。で終わってしまう。
こうならないためにも普段から業務連絡以外でもコミュニケーションをとることが重要なんだ。
コミュニケーションをとって、お互いを知っておくことで、どう言えば相手が素直に指摘した部分を改善してくれるのかっていうことがわかり、業務上の改善につながる。
人というのは決して正論をいうだけでは素直になれない。筆者だってそう思う。初めて会った人に正論を言われても「なんだお前」ってなる。逆に親族とか長年付き合っている友人から正論を言われれば「確かにそうだね」って納得する。
これはコミュニケーションがちゃんととれていないと成立しないことなんだ。
確かにコミュニケーションは苦痛
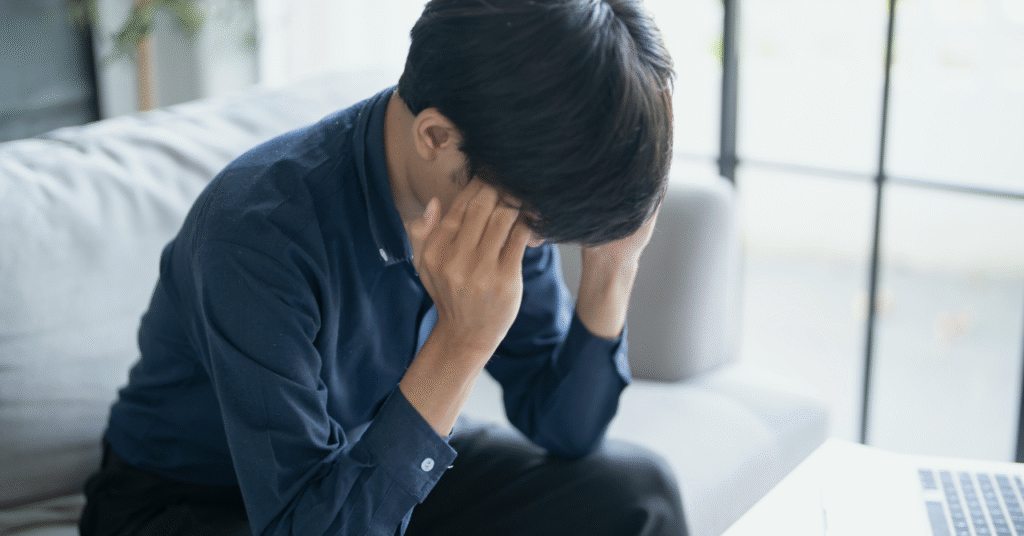
ここまで職場で同僚と業務連絡以外のコミュニケーションをとる必要性について深掘りをしてきたが、実際、職場で「コミュニケーションをとる」っていうことはかなりの苦痛。
自分と全く価値観が違う人と、相手の気持ちを悪くせずに、相手の素性を知って、なおかつ、自分のことも知ってもらう。そして、お互いの感性が一致したら、仲良くなる。ただ、仲良くなるといっても急には無理。
人と人は徐々に仲が良くなっていくものだから、時間もかかる。
こういうふうに考えると、人とコミュニケーションをとるということは一筋縄ではいかないってことがわかる。
ただ、それでも、苦痛な道とわかっていても、職場の同僚とコミュニケーションをとることで得られることの方が筆者個人的には大きいと思っている。
同僚とコミュニケーションをとることで得られること

職場の同僚とコミュニケーションをとることは苦痛だ。苦痛だけど、その苦痛を乗り越えた先には得られることがあると筆者は思う。
相手の人生で得た知見
前述もしたが、会社には色々な人がいる。それぞれの人にはそれぞれの人生があって、その人生で得たことっていうのはみんな違う。
同僚と業務連絡以外のコミュニケーションをとることで、この一緒に働く人間のそれぞれの人生で得た”知見”というものを知ることができる。
この知見っていうのは生きる上で大事だと思ってて、なぜかというと、色々な”視点”をもつことで一つのものの見方、解釈の仕方っていうのが大きく変わってくると思うから。
例えば、同僚の人生の中で吃音をもっていて、その吃音により言いたいことが言えないから相手に上手く伝わるように言い方を変えているっていう知見をもっていたとして、そのことを知った上で、人生の中で他に上手く話せない人がいたら「もしかして、吃音なのかも知れない」っていうように人への見え方、考え方が変わる。
ちなみに吃音症については以下の記事でも書いてる↓
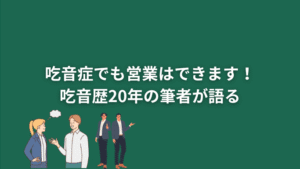
こんな感じで視点を増やせば、受容力っていうのがついて、人としての懐が大きくなるし、自分自身に知識もたまる。
同僚とのコミュニケーションはそういった結構深い部分において重要なんだ。
相手の素性
これは前述した内容とほぼ同じだけど、同僚と業務連絡以外のコミュニケーションをとることで、相手の素性を知ることができる。
・同僚はどんな人なのか?
・同僚からしてやってはいけない行為はなんなのか?
・同僚がもつ正義ってなんだろう?
・同僚の仕事のキャパシティはどれくらいだろう?
など
こんな感じで、同僚がどんな尺度を持っているのか、どういう能力をもっているのかっていうのがわかる。
同僚の素性がわかれば、仕事上での円滑性が上がることにつながるし、気持ち的な働きやすさにもつながるわけだね。
同じ気持ちを抱えているという仲間意識
仕事というのは大変。
何が大変かっていうと、業務的にも、心理的にも。
そういった仕事の大変さを乗り越えるためには、もちろんセルフケアとか、仕事の働き方を変えるとかそういう実用的なことも重要なんだけど、もう一つ、「一緒に働く人と仲間意識をもつ」ってことも大事だと筆者は思うんだ。
例えば
・上司の放任に嫌気がさす
・会社が向かうべき目標がわからなくてイライラする
・無駄な会議ばかりやってる
など
同僚とコミュニケーションをとれば、働いている上で不満に思っていることを共有することができる。だから、「この人も自分と同じように思ってたんだな」って思えて、自分も頑張ろうって自分を鼓舞しやすくすることができ、働きやすさにつながる。
同僚との仲間意識が強まれば、心の安寧を得られるってこと。
無理をする必要はないが無理をして得ることはある

ここまで職場で同僚とコミュニケーションをとる必要性について結構「必要」っていう視点で話しているけど、ここまでいっておいてなんだけど、本当に同僚とコミュニケーションをとるってことは大変なことだし、本当に嫌であれば無理にやる必要はないと思う。
無理にやって、かえってメンタルに支障をきたしてしまうなんてことが起こったら本末転倒。
それでも頑張って同僚とコミュニケーションをとるっていうのであれば、最初は無理してでも、あとから「コミュニケーションとっておいて良かった」ってなることはちゃんとあると筆者の経験から言える。
他にも、ある著名人の話から同僚とコミュニケーションをとることで得られたものをみてみよう。
新庄さんとバリーボンズさんの話
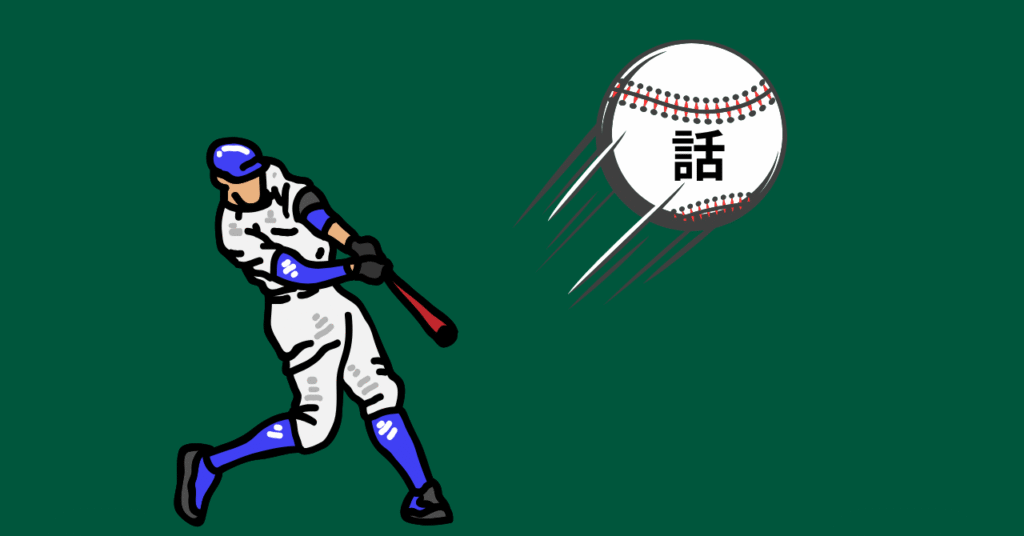
2025/10/25現在では、日本のプロ野球チーム「日本ハムファイターズ」の監督をしている「新庄剛志」さんだが、新庄さんはもともとメジャーリーガーだった。
新庄さんがいたメジャーリーグのチームは「ジャイアンツ」で、MLB史上歴代一位となるホームラン記録保持者である「バリーボンズ」さんとチームメイトだった。
そんな新庄さんはメジャーに渡った頃、なかなかチームメイトと馴染めずに、チームメイトからいじめられてしまった過去がある。ただ、そんな海外でいじめという熾烈な環境を乗り越えたのは「チームメイトとのコミュニケーション」だったそう。
そして、当時のジャイアンツのスター選手であったバリーボンズさんは他のチームメイトに怖がられていて誰も近づかない存在だったそうなんだが、この時に、新庄さんはバリーボンズさんに自らコミュニケーションとり、チーム内で浮いていたボンズさんの信頼を得て、今でも交友関係が続いているっていう話がある。
詳しくはこの記事に書いてある↓
参考元:日本ハム・新庄監督にボンズ氏がエール ジャイアンツ時代のレジェンド同僚
この話からわかることは、やっぱりコミュニケーションの重要性。
新庄さんが自らチームメイトとコミュニケーションをとったことでチームから信頼され、チーム内で浮いていたボンズさんとも信頼関係を得ることができたってこと。
同僚とコミュニケーションをとる時にまずやると良いこと

もし、ここまで読んでくれた読者の方が、「同僚とコミュニケーションをとってみようかな」って思ったら、まずやると良いことを紹介したいと思う。
相手に興味をもつ
まずは、同僚に「興味をもつ」ってこと。
興味をもってくれる相手に対しては自分のことを話したくなるし、興味をもってくれている人に対して嫌な気持ちは湧かない。
相手の話を引き出して、相手のことを知る。相手は自分のことをたくさん話している人に向かって好感を抱くことにつながる。
次第に、相手は自分のことを話しすぎてるなぁって思ったら、読者の方のことも聞こうって感じになって、「〇〇(読者の方)さんはどう思ってますか?」など読者の方を知ろうとしてくる。
これで自然と会話のキャッチボール、お互いの情報の交換ができ、親睦が深まるってこと。
人に好かれることについてはこの記事で深掘りしてる↓
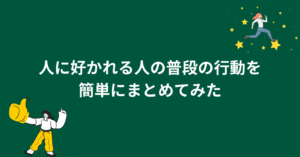
とにかく”聞き役”に徹する
とにかく最初は”聞き役”に徹した方が良い。
最初からベラベラ自分のことばかり話していると、「なんだこの人」ってなりかねない。相手は自分が不要だと思っている情報を投げかけられればられるほど、読者の方にマイナスの印象を抱いてしまう。
これはYouTubeやAmazonプライムでの過剰なまでの広告と同じ。自分が知りたくもない広告が動画の合間合間に流れるとイラっとする感じ。
人は基本的に自分が興味のある話は話したくなるから、その特性を利用する。
まずは、相手の話を良く聞く。自分の話は会話の1〜2割くらいにしておけば大丈夫。あとは、相手に話を振られたら、無理に相手の話題に持っていこうとするんじゃなくて、普通に聞かれた問いに答えれば良い。
情報の交換などで人との親睦を得ることは以下の記事で心理学的に説明している↓
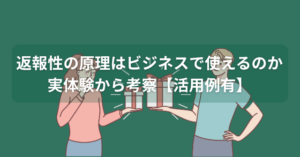
感情を素直に伝える
感情を素直に相手に伝えることはとても大事。
社会、特に会社に入ると「本音と建前」って筆者からしたらくそくらえな慣習を植え付けられるんだけど、「本音と建前」を多用しすぎて現代の社会人は苦しくなっていると思う。
「本音と建前」を多用していると、相手からしたら腹が見えない本当に信用していいのかわからない人間になってしまいやすい。
当たり障りのないことしか言わない人ってなんだか信用できないってことはないだろうか?あんな感じ。
もちろん、過度に苛立ちを見せたりとか、不機嫌さをあからさまにするんじゃなくて、周囲の人に害を与えてしまいそうな感情は自分で管理して、それ以外の「嬉しい」「楽しい」っていうような周囲に良い影響を与えそうな感情は素直に伝えると良いと考える。
同僚との会話であったら、同僚が何かしてくれたら「嬉しいです!ありがとうございます!」というように自分の良い感情を相手に伝えてみると相手には素直さが伝わって、心理的距離が縮まりやすい。
最後に
筆者は実際に業務連絡のみで回っている職場で働いたことがあるが、結構苦痛だった。
業務連絡飲みのコミュニケーションだから、一緒に働いている同僚に変なことを言えないって思って萎縮しちゃって、連携がとれなかったり、アクシデントが起こってもお互いにサポートに入るってこともできないことが多々あった。
この状況はかなりきつい。働く上で支障が出まくり、その上、同僚は何考えているかわからないし、何をしているのかもわからない。
気がついてみると「働きにくい現場」となっていた。
同僚と業務連絡以外のコミュニケーションをとるってことは自分ができる”働きやすい環境作り”だと思う。
今回の記事がそんな働きやすさのキッカケとなれば嬉しいかな。
この記事も役立つかも

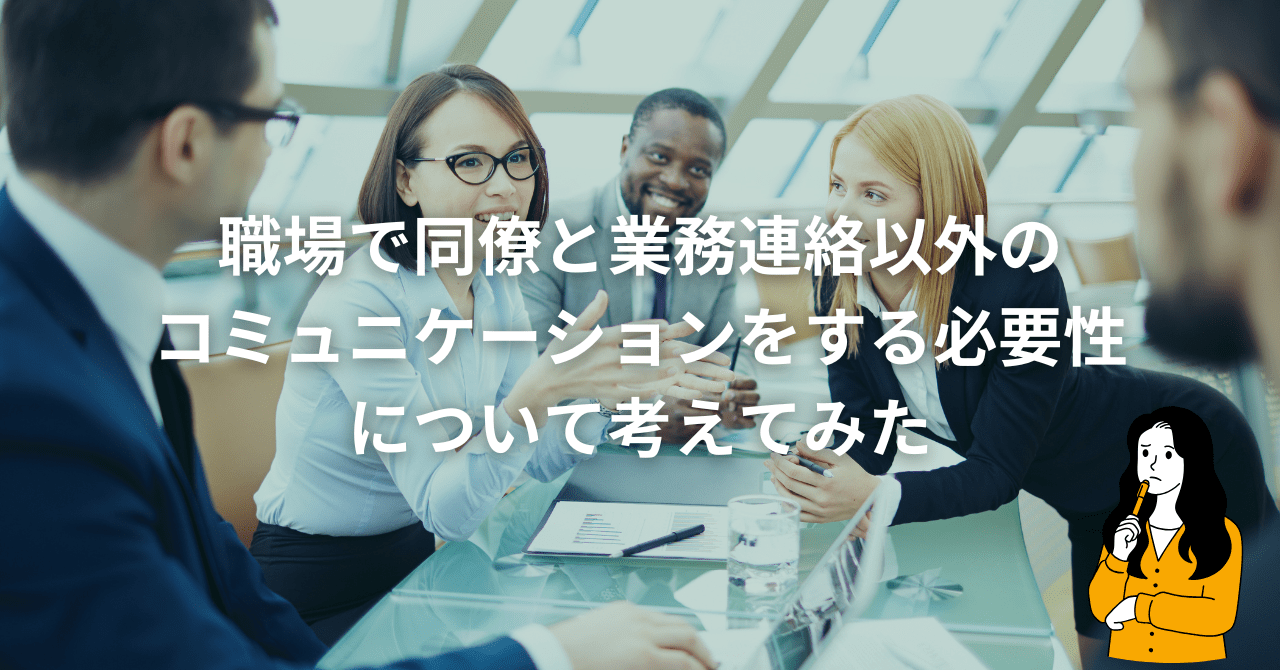
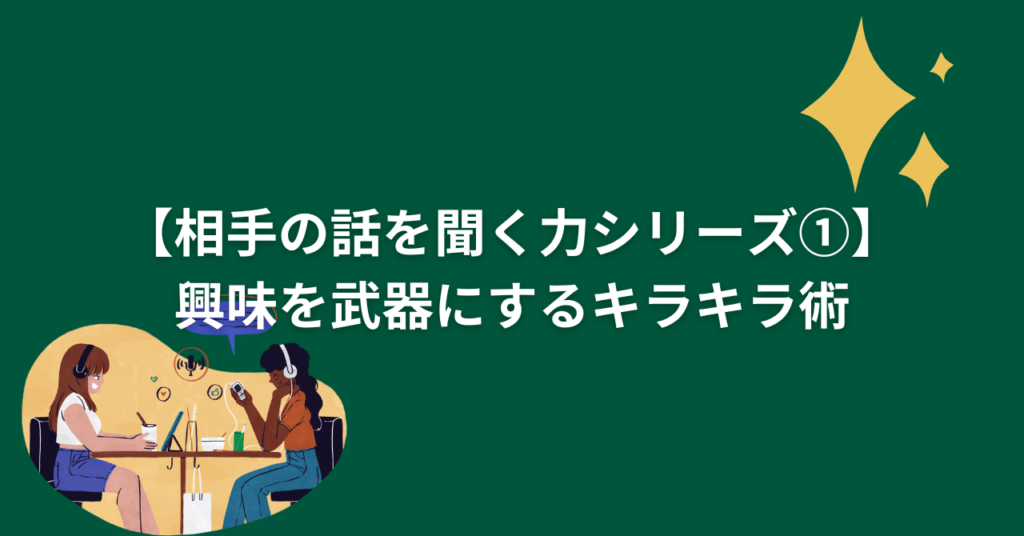
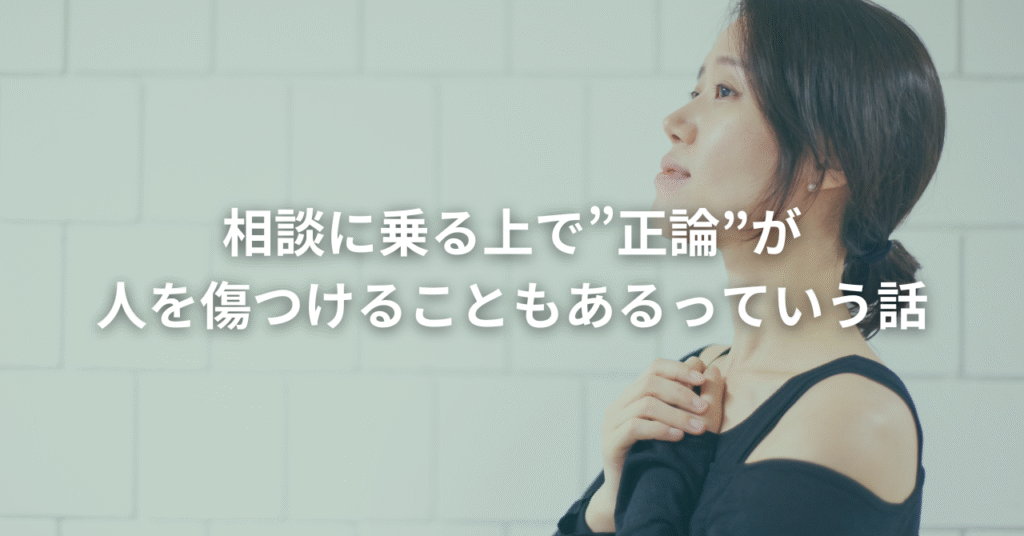
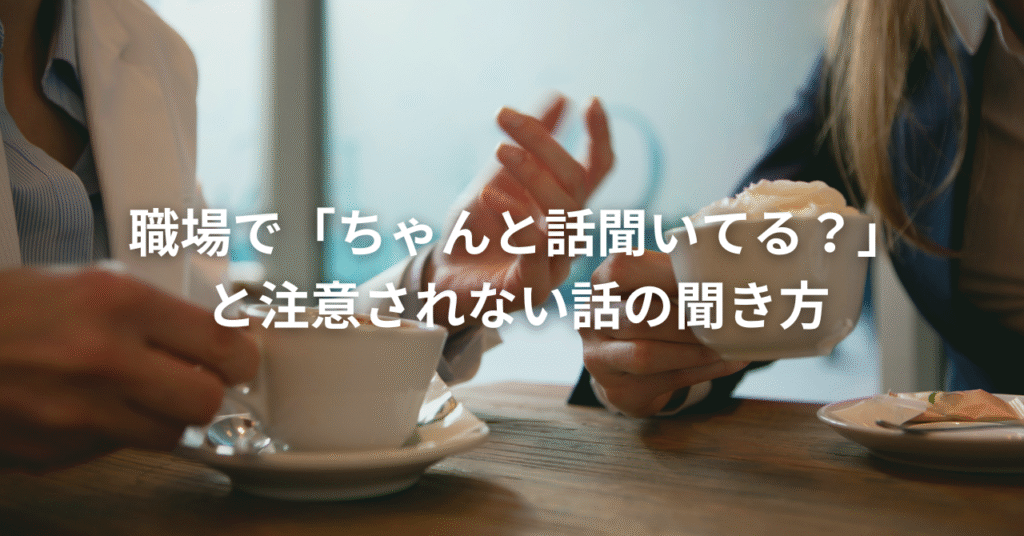
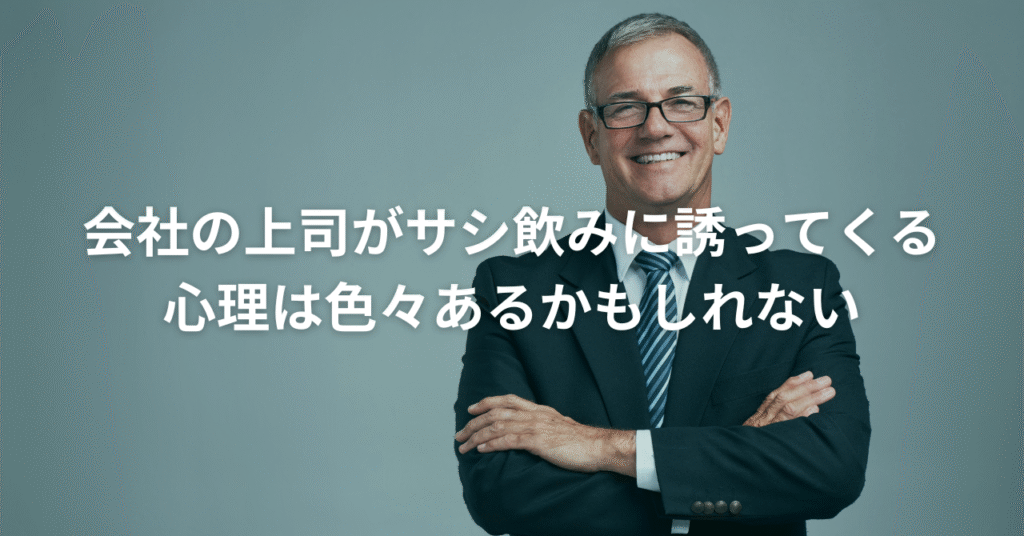
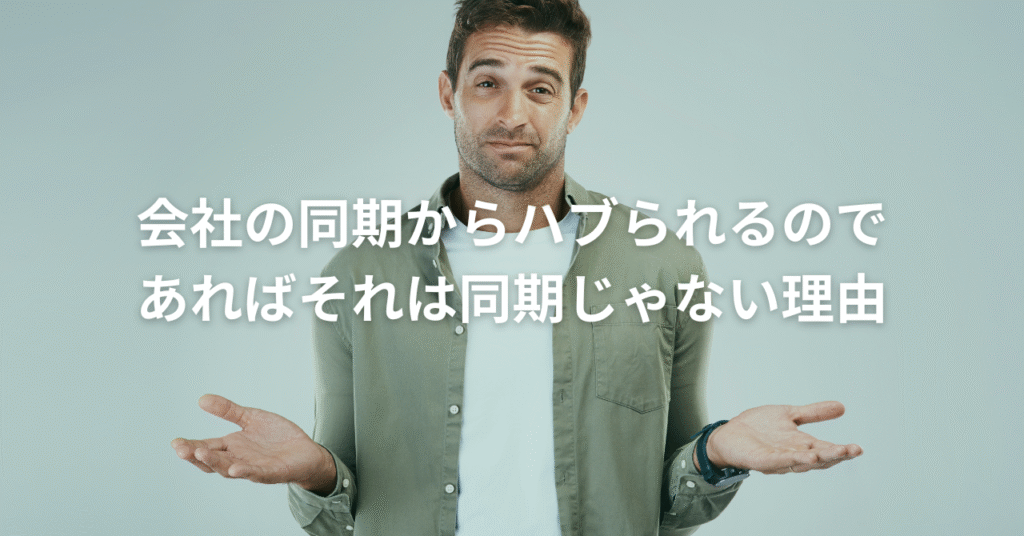
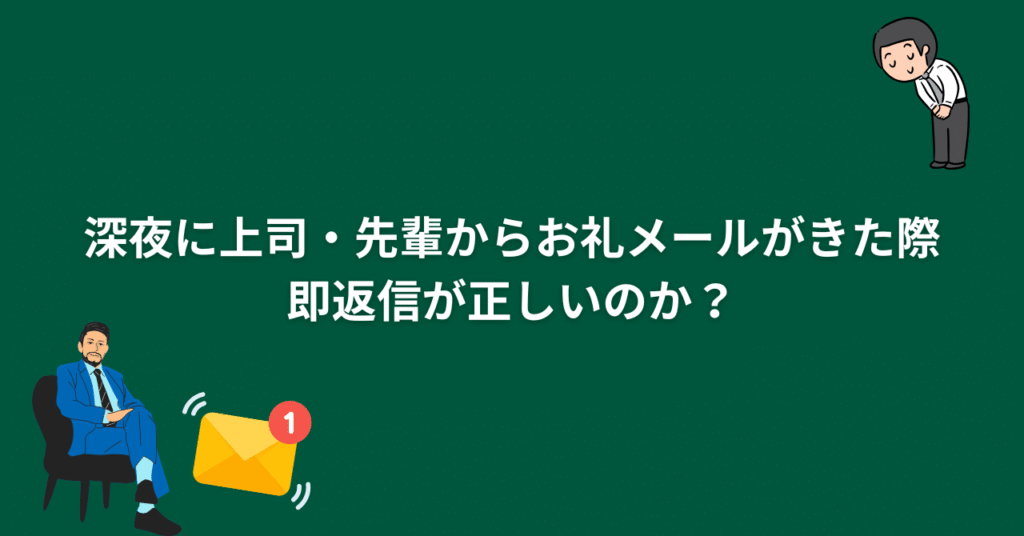
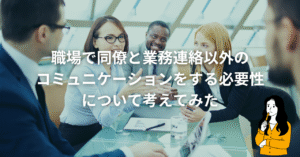

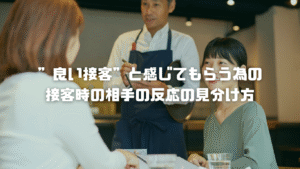
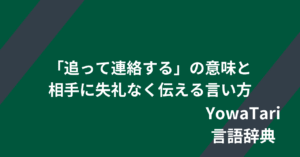
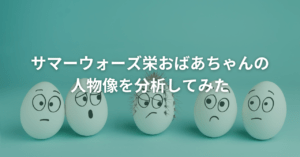
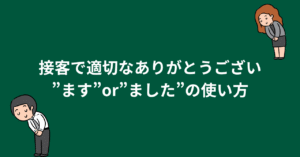
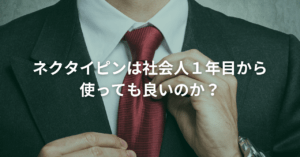
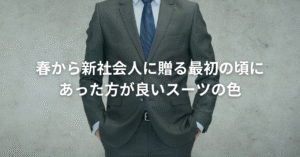
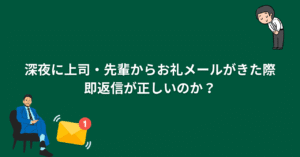

コメントする