筆者です。
読者の皆さんは「返報性の原理」というものをご存知でしょうか?
そもそも「返報性の原理を知りたい」ためにこのページまでたどり着いたと思うので、愚問といえるでしょう。
返報性の原理とは簡単に説明すると、”他者からの何かを受け取ると、その何かに比例するお返しをしたくなる心理的作用”のことをいいます。
この「返報性の原理」という心理的作用は、一般的に「誕生日プレゼントを貰ったからなにかお返しをしよう」や「新社会人になってお世話になった親になにかプレゼントをしたいな」といったときに作用がはたらきますが、”ビジネス”において”取引先、同僚との関係性を深める”ためにも用いることが可能ということをご存知でしょうか?
今回は、ビジネスにおいての「返報性の原理」の活用方法を筆者の経験を通して執筆していきたいと思います。
この記事でわかること…
・「返報性の原理」について
・活用方法
・ビジネスで使ってわかったこと

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験
- 吃音症歴20年
- 元オートローン営業マン
- 元オーダースーツフィッター
- 元百貨店販売員
- 現Webマーケター
- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味
- 酒は飲めない、よく体調崩す人
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
返報性の原理とは

「返報性の原理」とは冒頭での話と重複してしまいますが、「何かを貰ったら何かを返したくなる心理的作用」のことです。
例えば…
誕生日に友達からプレゼントをもらう
↓
友達の誕生日にもプレゼントをあげよう!と感じる
このように、何かを受けとったら「お返しをしなければ」というふうに感じることがあれば、「返報性の原理」がはたらいている証拠です。
返報性の原理の実験
「返報性の原理」について、デニス・リーガン博士が実験した「福引券の実験」を紹介したいと思います。
実験内容
①2人1組(1人仕込み)を2グループ作りました。
②2グループにはそれぞれ作業をおこなってもらいました。
③作業の休憩中に1つのグループは仕込みの人に何もさせません。
④もう一つのグループの仕込みの人にはジュースを同じグループの人の分を買ってもらいました。
⑤作業終了後それぞれのグループの仕込みの人に福引券の購入を同グループメンバーにうながしました。
⑥結果、休憩中何もしなかったグループよりもジュースをおごったグループの購買率が約2倍になりました。
この実験から、「相手の好意にはお返しをしたくなる」という心理がはたらくことがわかりました。
これを”好意の返報性”と言います。
返報性の原理はビジネスで使えるのか?
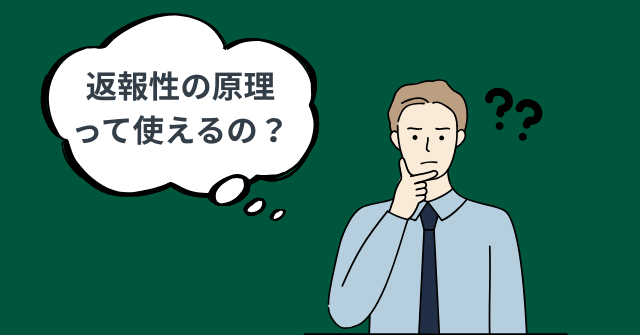
「返報性の原理」はビジネスで使えるのかどうか、という疑問ですが、筆者の経験上、”使える”と言っていいでしょう。
返報性の原理のポイントは、「まずは相手に何かを与える」ということです。このポイントを踏まえて、ビジネスで用いることで、心理的作用がはたらき、相手からお返しをもらうことができ、最終的には良好な人間関係を作ることができます。
言葉で言うのは簡単だと思いますので、筆者の実体験を紹介したいと思います。
筆者の実体験
筆者は法人営業と、個人営業の経験があります。
その経験の中で返報性の原理を用いた経験と、その結果を紹介したいと思います。
法人営業のときの話
ある取引先があり、普段から良い情報を案内したり、取引先からのお願いに答えていました。
ある時、私が利用してほしい商材があり営業で訪問したところ、取引先の担当者さんは快くその商材を利用することを了承してくれました。
分析
返報性の原理の例で述べた「普段から良くしてもらっているから何かお返しをしよう」という気持ちが、はたらいていたのではないかと考えます。
本当に感謝しかありません。
個人営業のときの話
筆者が務めていたオーダースーツの販売店では、普段よく購入してくれているお客様を対象に新作生地紹介会を行っておりました。
その会では、スーツを買ってもらうというのが目的ではなく、日頃の感謝を伝えるためのものであり、そこでは来店してくれたお客様にちょっと良い菓子折りと、スーツに関する用品をプレゼントしていました。
その会に来られたお客様は、新作のスーツ生地をみて帰るのではなく普段購入されているスーツよりも少し良いものを購入して帰る方がいました。
この出来事から、菓子折りとスーツ用品を渡すことによって、「こんなにものを貰ってしまったから何か購入して帰らないといけないな」と深層心理で感じたのではないでしょうか。
つまり、菓子折りとスーツ用品を渡すことで返報性の原理がはたらき、スーツ購入に繋がったと考察できます。
返報性の原理の種類
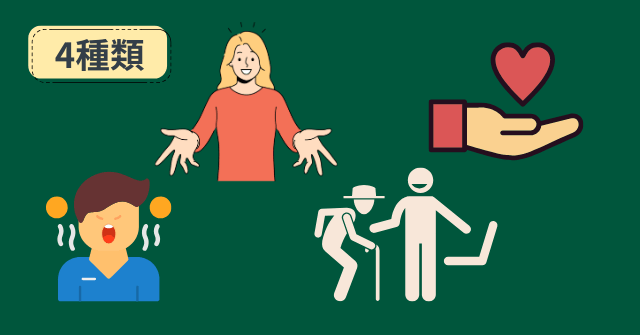
返報性の原理の中で4種類の返報性を紹介します。
・好意の返報性
・敵意の返報性
・譲歩の返報性
・自己開示の返報性
これらの心理的作用を利用することによって、ビジネスの上で取引先と良い関係性を作るのに繋がります。参考にしてみてください。
好意の返報性
好意の返報性というのは、「好意を与えることで、好意を返したくなる」心理的作用のことを指します。
例えば、友達から「友達としてめっちゃ好きだよ」と言われたとしましょう。その時に思うことは「嬉しいな」という気持ちだと思います。「嬉しさ」を感じることで、好きと言ってくれた相手に好意を抱く、このような作用です。
実際に、好意を表す動作をすることで相手から好感を得ることができるかどうか、という実験では、好意を表す動作をしないよりも、好意を表す動作をしたほうが好感度が上がっているという実験結果もあります。
参考文献:早瀬光浩・中村太郎・加納政芳・豊橋創造大学・中京大学 好意の返報性を表出するエージェントが ユーザの親密度に与える効果
敵意の返報性
敵意の返報性とは、好意の返報性とは逆の「敵意を与えることで、敵意を返す」という心理的作用です。
例えば、こんな人はいないかもしれませんが、会議において、「恥をかかせてやろう」と敵意をもった人間がいたとして、その敵意を向けられたときに、「恥をかかせる行為」をした相手に敵意が湧く。といった感じです。
この場面を想像できない方は、「七つの会議」という映画をみてみるとわかります。見てみたい人は一応リンクを貼っておくので参考にしてみてください。映画を観ていると登場人物に敵意を感じることができ、実際に敵意の返報性を体験することができます。
また、敵意の返報性は対人だけではなく、集団においても作用がはたらくという論文もあります。
参考文献:小林智之・及川昌典・同志社大学 メタステレオタイプと集団相互依存観が 外集団に対する反応に及ぼす影響
譲歩の返報性
譲歩の返報性というのは、「譲歩を与えることで、譲歩し返したくなる」心理的作用のことをいいます。
例えば、友達と新幹線で旅行に行く際に友達と自分両方とも乗り物酔いしやすく、窓際の席が良いとしましょう。
その時に旅行に行く際に窓際の席を友達に譲ることで、友達は「譲ってくれたから帰りは自分が譲ろう」という気になり、帰りの新幹線では窓際の席を譲られる。といったものがあげられます。
自己開示の返報性
自己開示の返報性とは、「自分のことについて開示することで、自己開示をされた相手が自分の話もしなければ」という心理的作用がはたらくものです。
例えば、初対面の際に、何も話し始めなければ会話がなかなか進みません。その時に、自分から自分のことについて相手に伝えると、同程度の情報が相手から返ってくるというものがあります。
自己開示の返報性では、誰でもはたらく心理作用ではなく、自己開示をする相手によって、自己開示の返報性の量に変化があると言われているので、どんな場面でも有効になるわけではないということを覚えておくとよいでしょう。
参考文献:安藤清志 対人関係における自己開示の機能
ビジネスでの活用例
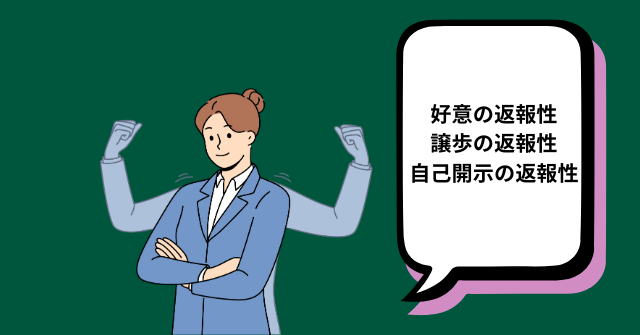
ビジネスにおいて返報性の原理を使うことができるとある程度感じてもらえたのではないでしょうか。では、実際のところどう活用すれば良いかを筆者の実体験をもとに提案していきたいと思います。
ビジネスでの活用例①
「好意の返報性」を活用してみるのはどうでしょう?
例えば…
お客様か取引先にまずは”好意”を与えます。このときの”好意”は例えば、相手に有益な知識や情報を伝えるということがあげられます。
他にも
・販促物をあげること
・料金をサービスしてあげること
が”好意”にあたる行為だと言えるでしょう。好意と行為をかけるなんて粋だなと思ったあなたはなかなかハイセンスです。
このように、お客様や取引先にメリットがあることを行うことで、相手からの好意を引き出すという活用方法です。
筆者の経験
記事の前半でも紹介しましたが、筆者は法人営業を行っていた際に、取引先の依頼をすぐに実行するように心がけていました。
そのような「要望にすぐ答える」という好意を与えることができたお陰で、こちらからの要求を取引先は文句一つなく受け入れてくれていました。
「何かを得たいのであれば、まずは与えること」という考えが大切だとわかります。
ビジネスでの活用例②
「譲歩の返報性」を活用してみるのはどうでしょう?
例えば…
お客様や取引先とのやり取りの中で、こちらから何かを要求したい場合、「譲歩の返報性」の応用である、「ドア・イン・ザ・フェイス」というやり方が有効だと言えます。
「ドア・イン・ザ・フェイス」のやり方は、まず最初に答えるのが難しい要求をします。この要求はあくまでも断ってもらうことが前提なので、変に答えられるかられないかのキワキワな要求をしないでください。もし、そのまま要求が通るのであればこの話はもうおしまいです。
この最初の要求を断ってもらうことで、相手に「申し訳ない」という気持ちを抱いてもらうということが、「ドア・イン・ザ・フェイス」のキモといえる部分でしょう。
「申し訳ない」という気持ちを起こすポイントとしては、「もう少しで叶えられそうなのに叶えられない」といった要求であることです。
一度、断ってもらい「悪いなぁ」という気持ちになってもらったところで、次に本命の要求を行います。この時に一度目の要求よりも大きな要求はいけません。
一度目の要求よりも小さな要求をすることで、一度目の要求と比較して「それなら頑張れそう」という気持ちになり、要求を飲んでもらいやすくなります。
ビジネスでの活用例③
「自己開示の返報性」を活用してみるのはどうでしょう?
法人営業でも個人営業でも大事なのは、お客様と”どれだけ良い関係を作れるか”ということです。良い関係性を作るにはまず、“自分を知ってもらうこと”と“相手を知ること”が大切だと言えます。
その時に役に立つのが「自己開示の返報性」です。特に、初対面のときに「自己開示の返報性」は有効だと言えます。
例えば…
初対面のときに、自分のことについて相手に開示することによって、相手の心理を「自分のことも話さないと」という状態にし、相手からも自己開示を引き出し、お互いのことを知ることで、親密度が増す。
という感じです。
ただし、この関係が初期段階のときにあまり、踏み込んだ自己開示をしてはあまり効果がないと言えます。
1973年にAltmanの提唱により、「関係性が初期の段階では、自己開示の内面性が低い話題が最大の返報性を得る」としていることから、関係性の初期段階である、初対面のときはなるべく踏み込まないような自己開示をしたほうが良いと言えます。
踏み込まないような自己開示
・やっていた部活
・自分の名前
等
参考文献:安藤清志 対人関係における自己開示の機能
返報性の原理の注意点
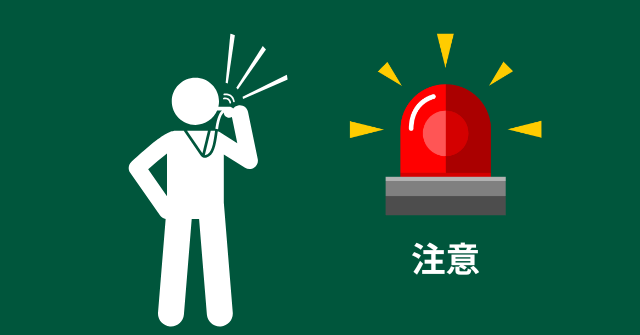
「返報性の原理」を活用するにあたって、注意したほうが良いポイントがあります。そのポイントというのが「相手に悟られないようにする」ということです。
例えば、ジュースを頻繁に奢られたらどういう気持ちになるでしょうか。「わるいなあ」という感情が強くなって逆に距離をとりたくなってしまいませんか?
過剰にgive(与えること)をすることは”なんか重たいな”という感情を抱かせてしまったり、「何か裏があるんじゃないか?」と言った懐疑心が生まれてしまいます。
相手に与えるときは、適度に与える頻度の間隔をあけたり、お返しに困るようなものを送らないようにすることが注意点だと言えるでしょう。
まとめ
今回は「返報性の原理はビジネスで活用できるのか?」というテーマを筆者の実体験から紹介してみました。
最後に、「返報性の原理」はあくまで心理学的に定義されている心理的作用です。「返報性の原理」が正しいんだ!と盲信してはいけません。
実際に、多くの論文でも、返報性の原理の様々な実験結果で、一貫性がある結果は多く残されているわけではありません。この心理的作用を用いる環境や相手によって、効果が大きく変わります。
「返報性の原理は相手に与えて、相手からそのお返しをしてもらうことだ!」と信じ、乱用するのは避け、相手の空気感などを読み、ほどよく参考までに活用していくのが良いでしょう。
この記事も役に立つかも

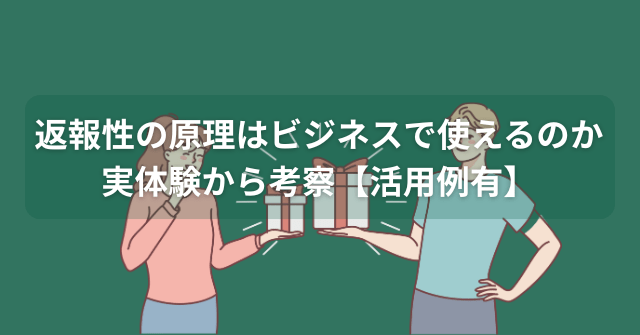


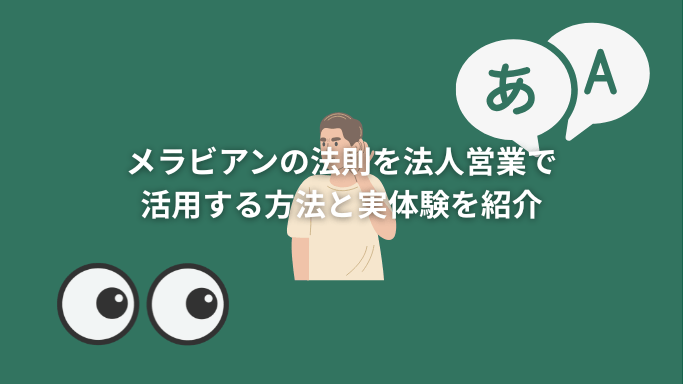

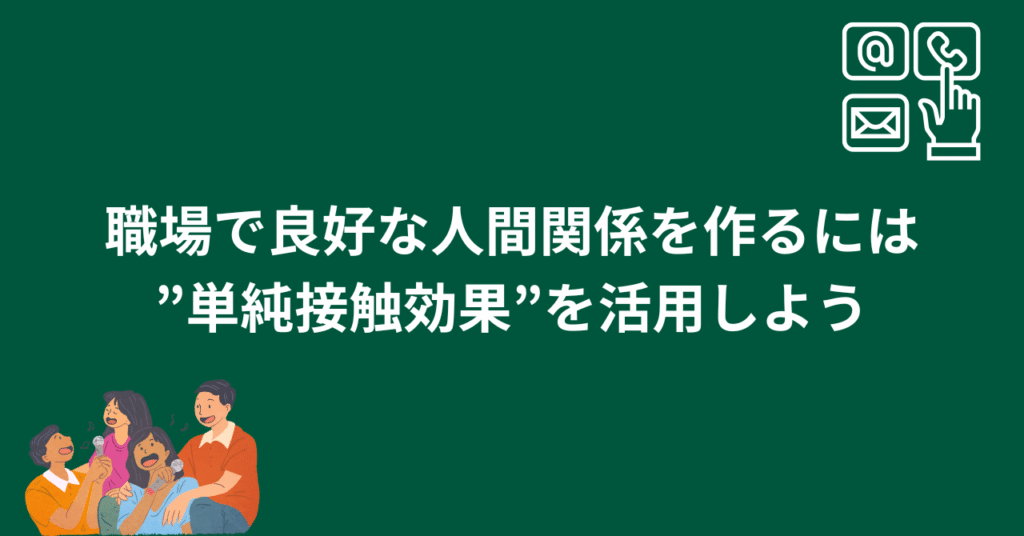
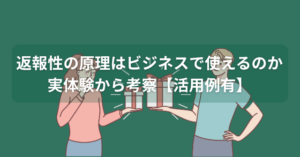

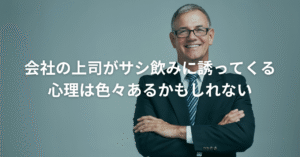

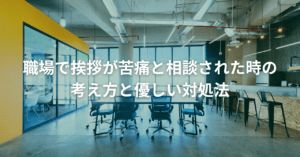

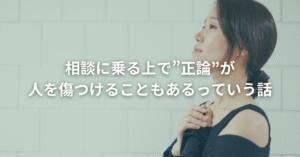
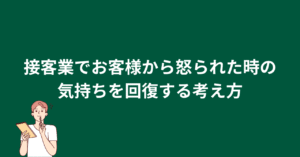
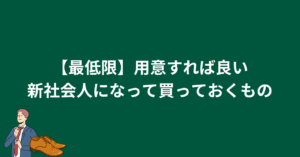
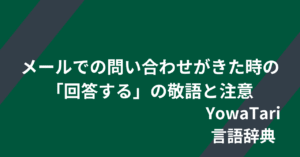
コメントする