社会人2年目ともなると、社会人1年目とは扱いや周りの雰囲気が変化していることをなんとなく感じることがありませんか?
そんな中で、「社会人2年目なのに仕事ができない…」と気持ちが沈んでしまってはいませんか?
今回は、「仕事ができない…」と辛さを感じている社会人2年目の方に“仕事ができないという辛さを乗り越える考え方”を紹介したいと思います。
今回の記事は
・仕事ができないことに対して辛さを感じている人
・仕事ができないことに対しての辛さで打ちひしがれている人
そんな方に「仕事ができないことに対しての辛さを取り除き、社会生活をより良く過ごすことを目標に発信していきたいと思います。
本記事が少しでもみなさんのお役に立てば幸いです。

内向型人間
たくしん
takushin
詳しいプロフィール
インキャ、インドアという2つの”イン”を持つ者。
バリバリ金融営業➡北海道転勤➡第二新卒で転職➡関西居住➡地元に戻る。というムーブをかました5年目社会人。
今まで無事に生きられたのは周囲の”人”のおかげだと本気で思っているので、”人”に関係する悩みが多い社会人(特に新入社員や転職した人)に向けた、自分の経験から”人”に関係する悩みを解決する発信をしてます。
仕事ができなくて辛いと思う原因
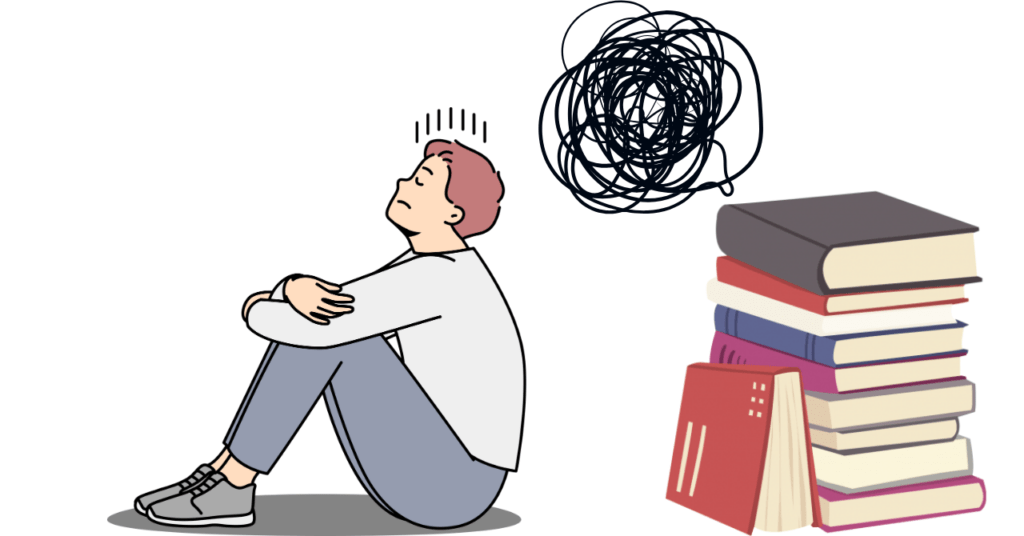
仕事ができなくて辛いと思う原因には、ただ単に仕事ができないことに対しての辛さではなく、様々な要因があると考えられます。
要因
・期待に答えられない
・自分の頭の中ではできると分かっているのに、現実では思うようにいかない
・仕事ができる同僚や後輩と比較してしまっている
…etc
「仕事ができなくて辛い」と思ってしまうことの延長線上に自分自身を否定してしまう場合があります。
 たくしん
たくしん私もアルバイトのときに同じ思いにかられたことがあります…。
そんな辛さを感じてしまう「仕事ができない」という現実は、実は「自分の価値」に影響することはないのです。
仕事ができなくて辛いという気持ちへのアプローチ
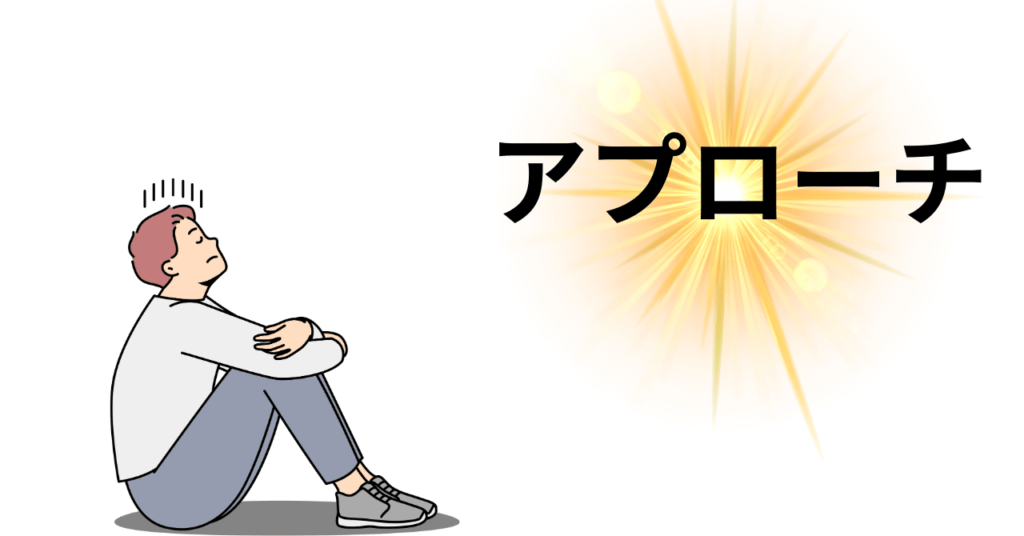

「仕事ができなくて辛い」という現象の辛さの原因について解説していきましたが、実は「仕事ができない」というのは「自分の存在価値」に影響することではないのです。
そして、ここでは「仕事ができなくて辛い」という気持ちにどうアプローチして行けばよいのかを解説していきます。
仕事ができなくて辛いという気持ちへのアプローチの方法の一つにアドラー心理学の「機能価値」と「存在価値」という考え方があります。
これは実際にアドラー心理学の用語ではありませんが、一つの考え方として理解していただければ幸いです。
「機能価値」というのは…
ゲゼルシャフトを基盤とした考え方です。
ゲゼルシャフトというのは「ある特定の目的、利害を達成しようとして集まった集団」のことを指します。つまり、会社です。
「機能価値」というのはどれくらい目的を達成して、どれくらい利益を出したかという指標なのです。



会社で言うところの“人事評価”という感じでしょうか。
「存在価値」というのは…
ゲマインシャフトを基盤としています。ゲマインシャフトというのは自然に発生した共同体。
家族や村落などの共同社会のことを指します。
「存在価値」はそもそも存在している、つまりあなた自身の存在を指したものです。
「機能価値」は「存在価値」とは別物
現代は会社を基盤とした生活スタイルになっています。
なので、どうしても「機能価値」を気にしなければならない状態なのです。
そして、仕事ができないというのは「機能価値」に影響します。
仕事の良し悪しで人事評価が決まり、給与が決まりますよね。これにより、嫌でも「機能価値」というのは気にしてしまいます。



このときに注意したいのが「機能価値」と「存在価値」は別物ということ!
「機能価値」はあくまでも会社内での評価であって、あなた自身の「存在価値」を決めるものではありません。
別物であるにも関わらず、仕事ができないと自分は存在する意味がないんだと後ろ向きな考えになってしまいます。
これは生活の基盤として「機能価値」が身近にありすぎるので仕方がないことです。
しかし、「機能価値」と「存在価値」の話をもとにすると仕事ができないからと言って、自分自身の存在が否定されるわけではないのです。
仕事ができなくても大丈夫、期待に応えられなくても大丈夫、自分の思いどおりにならなくても大丈夫、それも自分自身なんだと“自己受容”することが大切だと言えます。
この「存在価値」を理解し、受容できていれば自身の中の一つの大きな心の土台となるので、仕事ができなくとも気持ちへの影響が減ります。
仕事をできるようにするコツ
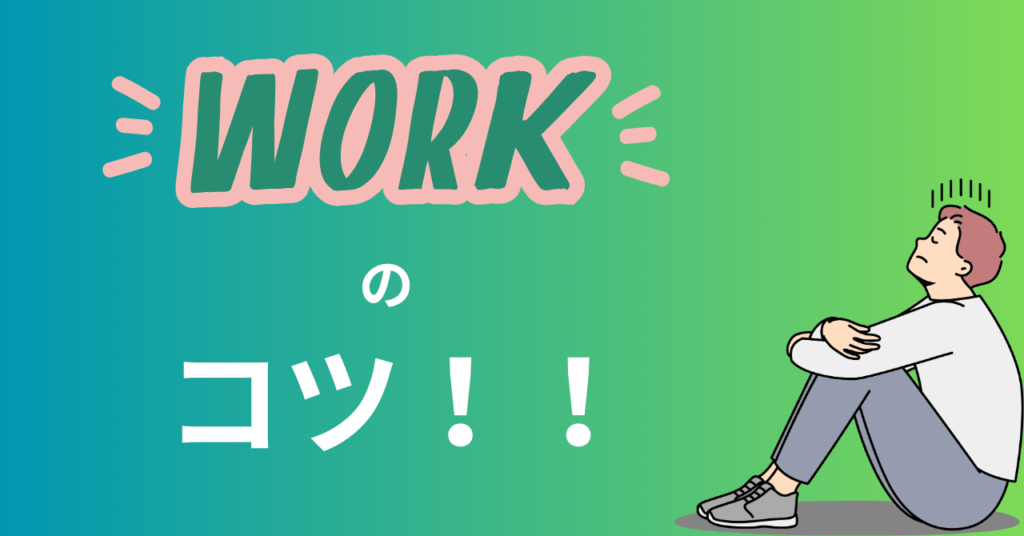

「仕事ができない辛さ」を乗り越えるにあたって、考え方だけではなく少し“仕事ができるようにするコツ”を紹介したいと思います。
全国売上5位の某有名ファミリーレストランでアルバイトをしていた私たくしんにお任せください。
仕事上で何ができないのかによってコツは変わる
残念ながら、これだけやれば仕事が早くなるという簡単なコツはありません。
仕事上で何ができないのかによってコツが変わります。
そこで、3種類の仕事のコツを紹介していきたいと思います。
仕事が終わらない場合
仕事がなかなか終わらないという時の対処法として3つあります。
1 優先順位を立てる
2 気持ちを高める
3 苦手なこと、できないことは任せる
1 優先順位を決める
まず、朝一番に今日やることをまとめて、優先順位を決めます。
優先順位の決め方については下の記事で詳細を解説しています。参考にしてみてください。


仕事に優先順位をつけることで、ミスが減り、進捗が早くなります。
まずは優先順位を立てることを意識してみると良いです。
2 気持ちを高める(簡単な仕事から取り組む)
仕事がたくさんあると何から手を付けたら良いのか分からなくなり、最悪パニックになってしまいます。
そんな最悪の事態を避けるためにも、まずはできるだけ簡単かつ早く終わりそうな仕事から取り組むと良いでしょう。
そして、仕事が終わっている達成感を高めていると自然とモチベーションもアップします。
その上げたモチベーションでどんどん仕事を片付けちゃいましょう。
「簡単な仕事から取り組む」という方法の深堀りをしています
⬇⬇⬇


3 苦手なこと、できないことは任せる
自分が苦手だなぁ、できないなぁと思うことは社会人2年目になってだんだんわかってきます。
そんな苦手分野をもし、他に任せられる人がいればその人に任せちゃうというのも仕事効率を上げる方法の一つです。
得意な人、できる人のほうが仕事の精度も速さも段違いです。
会社なのだから、みんなで力を合わせて仕事できると良いですね。
報連相ができない場合
報連相がなかなかできないという場合の対処法は
一 何かあれば報告する
二 ルーティン化する
この2つが有効です。
一 何かあれば報告する
ほんとに仕事で些細なことがあれば上司なり先輩なりに「こんな事がありました!」「これはどう対応すればよいでしょうか?」などなんでも報告しましょう。
嫌っていうほど報告をしていれば報連相のクセがついてきますし、何よりも「しっかりと報連相してくれる」と信頼度が上がります。
些細なことでも良いでバンバン報連相しちゃいましょう。
二 ルーティン化する
報連相はルーティン化してしまうことが一番楽な方法です。
ルーティンは大体1ヶ月ほど取り組んでいれば身につきます。
「毎日16時に一旦報告する」
「毎朝何をするか報告して、仕事中に進捗を確認してもらう」
など、取り組みやすいルーティンを取り入れるのが良いです。
報連相しないで失敗した話


物事の理解が難しい場合
仕事は日々色々な出来事との格闘です。
上司、先輩、顧客などに言われたことを瞬時に理解して対応しなければなりません。
そんなときに必要なのは“理解力”。
では、この”理解力”はどのように鍛えればよいのか。
理解力の鍛え方はこちら
Ⅰ 本を読む
Ⅱ 紙に書く
Ⅰ 本を読む
読書は何でも良いです。
文学、ビジネス、専門書、小説。
とにかく「文章」に触れることで物事の構造に頭をなじませます。
すると、会話でも「この人は何が言いたいんだろう」「言いたいことはこういうことではないか?」など理解する力が付きます。
もし何を読んだら良いのかわからないと悩む人は以下の記事も参考にしてみてください。


Ⅱ 紙に書く
頭の中のものを紙に書き出すという行為は物事を整理するのに大変役立ちます。
頭の中でバラバラになっている考えを紙に書くことで可視化され、簡単に整理することができます。
なので、もしあまり理解が追いついていないなと感じるようなことがあれば、「紙に書き出す」ということを試してみてください。
もし仕事ができなくて執拗に攻めてくる人がいたら
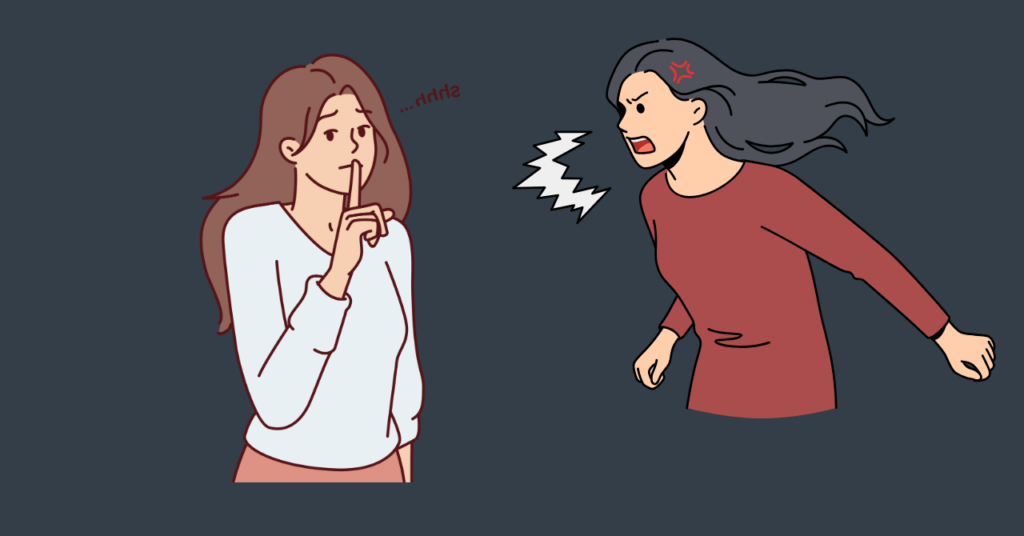

おまけのような項目ですが、少しでも勇気づけができたら嬉しいです。
もし、執拗に仕事ができないことに対して攻めてくる人がいるようであれば、こう思って気持ちを落ち着かせてください。
・無視する
・親切心で◯す
・この記事を思い出して
無視する
もうそんな人は無視してください。
ただ、角が立つと相手も何をしてくるかわからないので、角が立たないように無視することが重要です。
「わかりました」
「すみませんでした」
と口では言って、無視で自分のペースで頑張れば大丈夫です。
一番は心身の健康です。
親切心で◯す
◯の中身は皆さんの想像におまかせします笑
執拗に攻めてくるようであれば、心のなかで「あぁ機能価値と存在価値を分けられていないんだな。可哀想に。慈悲を与えよう…。」と心のなかで憐れみましょう。
執拗に攻めてくる人はおそらく何か悪いことでも起こっているのでしょう。
心のなかの親切心で◯します。
この記事を思い出して
あなたのことを執拗に攻めてくる人がいれば、この記事を思い出してください。
どんな出来事でもあなたの「存在価値」が変わることはありません。
それだけは覚えておいてください。
自分のことを受け入れる勇気さえあれば、仕事ができなかろうが執拗に攻めてくる人がいようがきっと乗り越えられます。
そして、私も「存在価値」と「機能価値」を忘れずに頑張ります。
この記事があなたの”お守り”になれることを祈って。
まとめ
今回の記事は「仕事ができなくて辛い」という気持ちをどう乗り越えるかについて解説してきました。
最後に本記事をまとめると
・「機能価値」と「存在価値」は別物
・仕事ができなくても「存在価値」に影響しない
・なぜ仕事ができないのかを考え、コツを掴む
・執拗に攻めてくる人はアウトオブ眼中
・アドラー心理学をもっと知りたい人は「もしアドラーが上司だったら
もっと詳しくアドラー心理学に触れたいという方はAmazon、楽天のリンクを貼っておきますの参考にしてください。
本記事がお役に立てば何よりです。
以上
たくしんでした














コメントする