筆者でごわす。
会社に入り、仕事をしていると、学生の頃よりも”周囲の人と比較されやすい環境”だということに気が付きましたか?
・月末に営業成績が発表される
・月初めに会議で売上報告
・成績良好な人の表彰
など、日々の社会人生活には”比較”を生み出し、”競争”を根付かせる仕組みが多くあります。
これは、”会社”という社会に価値を届け、利益を生み出し、その利益で社員を雇用し日々の生活を送ってもらったり、会社そのものを成長させ経済活動を行うといった、”資本主義社会”であるがゆえ致し方ない面だと言えます。
しかし、そんな中で社会人として頑張っていると、フッとした瞬間に
「なんで自分はあの人よりもできないんだろう…」
「自分はなんでこんなにもできないのだろう…」
と劣等感に苛まれることがあります。
筆者も劣等感を感じることはあります。どんなに大変かわかります。
今回の記事では、この”劣等感”について筆者なりに考え、これまで経験した劣等感を分析し、いま劣等感に苦しんでいる人へ「劣等感を乗り越える方法」をお届けしたいと思います。
この記事でわかること
・劣等感を乗り越える思考法
・劣等感を乗り越える具体的な方法
・劣等感を抱いてしまうとき

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験
- 吃音症歴20年
- 元オートローン営業マン
- 元オーダースーツフィッター
- 元百貨店販売員
- 現Webマーケター
- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味
- 酒は飲めない、よく体調崩す人
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
劣等感を感じてしまう時
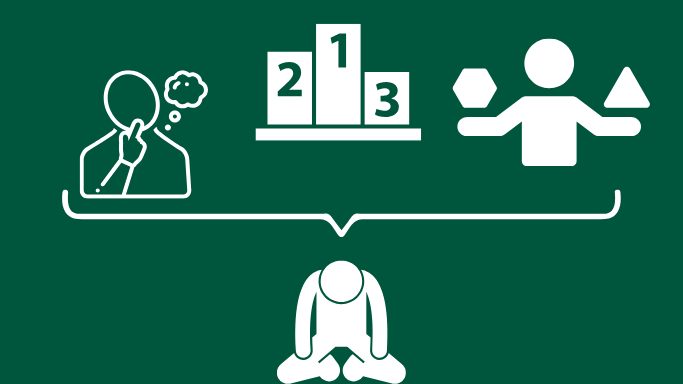
「劣等感」を乗り越えるためには、まず、自分が抱いている「劣等感」を”分析”することがかなり重要なのではないかと、筆者の過去の経験から感じます。
劣等感を抱いている時はどうしても、漠然とした理由で自分を攻めてしまいがちです。この気持ちを抱いている要因が漠然としているからこそ、何をどうしたら良いのかというのがわかりません。
対処法がわからなければ劣等感は募るばかり。しんどさが更に増してしまいますよね。
ですので、まずは今感じている”劣等感”を分析してみましょう。分析することで、的確な対処法が見えてくるはずです。
分析の手始めに「劣等感を感じてしまう時」についてもう一度考えてみましょう。今、どんな場面で劣等感を抱いてしまっているのか、これをみれば明確になります。
筆者が考える「劣等感を感じてしまう時」はこちら
・同僚と比べてしまう時
・自分が求めているレベルに満たない時
・周囲に認められていないと感じた時
・過去と同様の失敗をしてしまった時
・競争環境下にいる時
・後輩が活躍している姿をみた時
・努力が報われないと感じた時
・他者からのアドバイスを否定的に受け取った時
・会社の社内報やSNSで他の人の活躍をみた時
それぞれ解説していきます。
すぐに「劣等感の乗り越え方」を知りたい人はこちらをクリックしてもらえれば自動的にスクロールされます。
同僚と比べてしまう時
仕事の中で、同期や同様の部署で働いている同僚、特に年齢が近い人と、自分をついつい比較してしまいがちです。
近くで一緒に働いているといった”身近な環境”であるがゆえに比較しやすくなってしまっているということが言えるでしょう。
同僚と自分を比較してしまったら劣等感になるのは時間の問題です。
自分が求めているレベルに満たない時
筆者は完璧主義っぽい思考を持っています。何事も自分の中の基準に満たすまでやりきりたいという気持ちで取り組んでいるのです。この思考はときに自分を苦しめます。
特に仕事でこの完璧主義思考が出てきたら大変です。
自分が決めている基準に満たないと、「なぜこんなことも自分はできないのか」と自分を責めてしまい、”劣等感”を感じてしまいます。
劣等感を感じてしまう要因としてこの「自分が求めているレベルに満たない」というものがあるのではないかと分析しました。
周囲に認められていないと感じた時
筆者が劣等感についてよく覚えていることがあります。
それは、「周囲に認められていないと感じた時」に劣等感を感じた出来事です。
キッチンのアルバイトをしていたころ、まだアルバイトに入りたてだった筆者は、初めて土日の忙しい時間に仕事に入りました。そこでは、教えてもらっていたことが全くできずに、周囲の足を引っ張ってしまう結果になってしまい、終いには「皿洗いにいってほしい」という戦力外通告とも捉えられる言葉を受けてしまいました。
このときに「周囲に認められなかった…」と感じ、強い劣等感を感じたのです。
劣等感を感じる要因として周囲への期待に答えることができなかったと自覚したときというものがあると考えます。
過去と同様の失敗をしてしまった時
仕事ではよく「同じ失敗をしないように一度失敗をしたらメモを取りなさい」という教えを受けることがあると思いますが、例えば、一度仕事で失敗があって、メモを取ったにも関わらず、同じ失敗をしてしまったとき、どう思うでしょうか?
「なんで自分は一度言われたのにできないんだ…」と感じてしまう時は有りませんか?
まさに、同様の失敗をしたときに劣等感を感じるということがわかります。
競争環境下にいる時
記事の冒頭でお話しましたが、会社は競争を意識する環境ができています。
”競争”というと”営業職”をイメージしがちですが、決して営業職に限った話では有りません。そもそも会社自体が競合他社と業績やシェア率で競い合っています。
例えば、他部署でも「同期の〇〇さんは活躍しているらしい」「〇〇さん出世したんだって」といった”競争を意識する”出来事が起こっています。
そのような環境下では「あの人はすごいけど、自分も頑張っているのに…」といった劣等感を抱きやすいでしょう。
後輩が活躍している姿をみた時
年齢が下になりやすい後輩の活躍が自分の劣等感につながることがあります。
「なぜ自分よりも入社が遅い人が活躍できるのか」
「なぜ自分よりも年下なのに活躍できるのか」
といった疑問を起点に、自分の立場を見直したときに劣等感は起きやすくなります。
努力が報われないと感じた時
自分では相当頑張っていると感じているのにもかかわらず、なかなか良い結果がでないとき、人は劣等感を抱きます。
かくいう筆者も13年取り組んでいた野球で努力が実らない時期は相当自分を責めてしまっていました。
他者からのアドバイスを否定的に受け取った時
例えば、同様の部署の先輩や上司から「もっとこうしたら良くなるよ」「〇〇という営業の仕方はダメだから気をつけてね」などといった、アドバイスを貰ったときに、否定的に受け取ってしまうことがあります。
こういったアドバイスを受けたときに、「あぁ注意されてしまった」「周囲に言われるなんて、なんて自分は仕事ができないんだ」といった否定的に捉えてしまうことがあります。
会社の社内報やSNSで他の人の活躍をみた時
社内の他の人の活躍を見ることは劣等感に繋がってしまいます。
活躍している社内の人が全く面識がないのであれば、劣等感を感じにくいかもしれませんが、活躍している人と何かしらの接点や共通点があると劣等感を感じてしまう起爆剤となってしまいます。
例えば、同様の部署であったり、同年代であったりといった状況です。
劣等感を感じてしまう具体的な要因
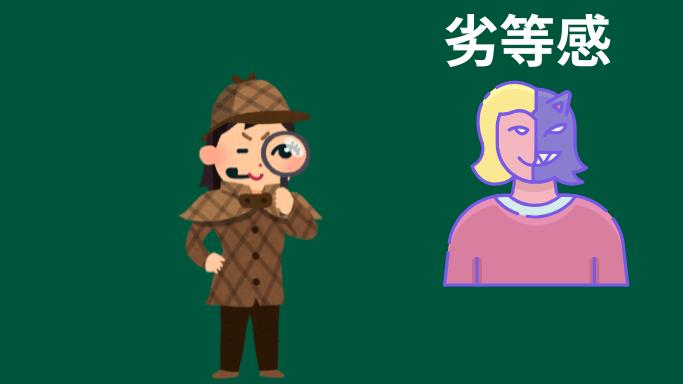
「劣等感を感じてしまうとき」を分析した結果、劣等感を感じてしまうときに共通することが4つあると考えられます。
①他者との”比較”が自分の中の大きな評価基準になっている
②常に高い意識を持っている
③幻想の期待
④自分を過小評価している
これもそれぞれ解説してみます。
①他者との”比較”が自分の中の大きな評価基準になっている
劣等感を抱いてしまう要因の1つに自分を評価するときの基準が「他者と自分を比較する」になっている。というものが考えられます。
これは「同僚と比べてしまう時」「競争環境下にいる時」「後輩が活躍している姿をみた時
」「会社の社内報やSNSで他の人の活躍をみた時」といった劣等感を感じる場面で共通することです。
同僚よりも営業成績が良いから優秀、同僚よりも事務作業が早いから優秀、と自分自身を認める理由に”他者との比較”があると劣等感を感じることに繋がってしまうことがわかります。
②常に高い意識を持っている
常に自分に高い意識を持っている人は劣等感を抱きやすいといえます。
これは「自分が求めているレベルに満たない時」「過去と同様の失敗をしてしまった時」「努力が報われないと感じた時」という3つの劣等感を抱くタイミングで共通する要因だと言えます。
これは意外に気が付かないものです。筆者も「この仕事はここまでやりたい」と会議のときに周囲に言ったときに「意識が高いね」といった言葉をいただいたことがあります。
完璧主義者っぽい性格からこのように自分に周囲から見てレベルの高いと思われる目標を決め勝ちになっていることがあります。
この意識の高さからくる達成難易度が高い目標設定が劣等感に繋がってしまうことがわかります。
③幻想の期待
「周囲からの期待に答えられなかったとき」人は自分の不甲斐なさに劣等感を抱いてしまうことがありますが、意外と周囲は自分が思っている以上に期待をしていないかもしれません。
これをいうと否定しているように聞こえてしまいますが、決して否定的に言っているのではありません。
周囲から「大きな期待」をされていると考えていると、その期待に答えられないであろう状況になったときに劣等感を抱きやすくなってしまうということです。
「期待されている」と感じるのは良いことではありますが、過度に期待されていると考えることは自分の首を自分で閉めることになってしまう可能性があります。
④自分を過小評価している
「他者からのアドバイスを否定的に受け取った時」「努力が報われないと感じた時」といったタイミングで劣等感を感じてしまったときに共通することが、「自分を過小評価している」という要因です。
周囲から観たときにすごいと思われているのにもかかわらず、自分自身では自分を過小評価してしまい、上記のタイミングで劣等感を感じてしまうということがあります。
さらに、自分を過小評価していることから周囲からのアドバイスを自分を否定されたように感じてしまうといったことが起きてしまいます。
劣等感を乗り越える方法

”劣等感”を感じてしまう要因がわかったところで、実際に乗り越える方法を紹介していきたいと思います。
少し多くなってしまいますが、劣等感を乗り越える方法は以下です。
①エピクテトス哲学を参考にする
②アドラー心理学を活用する
③自分の基準を見直す
④”できなかったこと”ではなく”できたこと”をみる
⑤自分を肯定することに抵抗を持たない
⑥主体性を持つ
⑦フィードバックをもらう
⑧自分を助けてくれる人と良好な関係になる
⑨専門知識を得る
⑩人は成長しているということを知っておく
一つずつ解説します。
エピクテトス哲学を参考にする
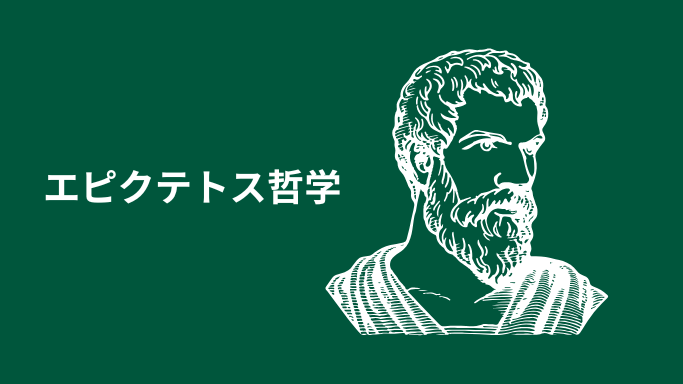
筆者の中で一番おすすめなのがこの方法です。
なぜおすすめであるのかという理由については「すぐにでも取り入れることができる」「他の場面でも適用できる」「メンタルを安定に保つことができる」の3つがあるからです。
まずエピクテトスについてですが簡単に紹介します。
エピクテトス
・紀元1世紀後半〜紀元2世紀前半に生きたローマ哲学者
・ストア派哲学者
・後年片足の自由がきかなかったとされる
・奴隷から哲学教師になった苦労人
参照元:Wikipedia
エピクテトスが戒めたことの一つに「我々次第でないものにとらわれない」という思考があります。
これは、エピクテトスの根底にあるストア哲学の基本的思考法であり、「我々次第のもの」と「我々次第でないもの」を明確にわけ、「我々次第のもの」を自分の欲望の対象に限定する、という考え方からくる思考です。
「我々次第でないもの」は自分がコントロールすることができないもの、つまり他人が介在する評判、地位、財産だったりのことです。
エピクテトスは、この思考にとらわれてしまうと、幸福が遠ざかってしまう、と説いています。
ここで考えられるのは、自分がコントロールすることができない他人の能力や結果つまり、「我々次第でないもの」にとらわれてしまうことが、”劣等感”を抱いてしまうことに繋がってしまうのではないでしょうか。
大事なのは「我々次第であるもの」に注力することです。
「我々次第であるもの」というのは何か仰々しく聞こえますが、もっと崩していうと「思考」「行動」「意識」などの自分でコントロールができるものです。
”劣等感”を感じる時はどうしても「我々次第でないもの」に意識がいってしまっています。この「我々次第でないもの」に関しては他人がもつものであるため、自分たちではどうすることもできないものです。
そのどうすることもできないものに対して意識を持っていくことで、他人と比較し自分を自らの手で追い詰めてしまい、”劣等感”という負の感情に飲み込まれてしまうのです。
この「自分ではどうすることもできないものごと」に意識を持っていくのではなく、「自分でどうにかできそうなこと」に注力する、つまり、今の自分と向き合うことで、”劣等感”という自分を苦しめる感情を遠ざけることができます。
筆者も実際に「自分ではどうすることもできないもの」に労力を使うのをやめることで、劣等感で自分を追い込むことがなくなりました。
いきなり考えをガラッと変えるのは難しいですが、もし今、他人の能力や結果をみて劣等感を感じているのであれば、他人に向いている意識を今の自分に向けて、今の自分ができるのは何か、をもう一度考えてみてください。
見えてくるものがあれば、その見えてきたものに注力してみてください。次第に劣等感を忘れることができるはずです。
筆者はそれで、身だしなみを整えるために深夜に靴磨きをしました、そうすることで劣等感はいつの間にか消えていました。
アドラー心理学を活用する
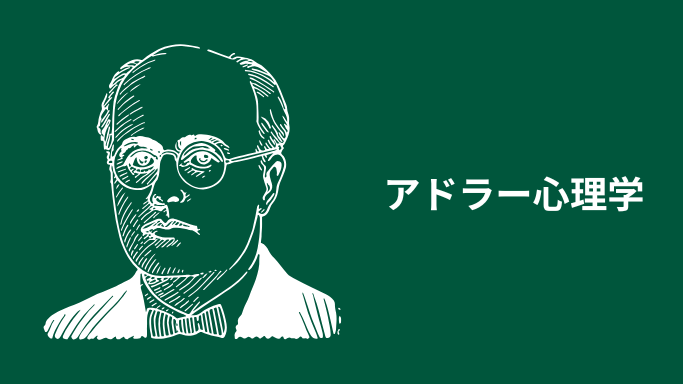
アドラー心理学を活用するのも”劣等感”を乗り越えるのに有効といえます。
筆者が新卒の頃に「もしも上司がアドラーだったら」という本に出会ってからずっと大事にしている考えが劣等感を乗り越えるのにちょうど良いです。
その考えとは、「機能価値と存在価値に分けて考える」というものです。
機能価値・・・仕事ができる、給料が高い、ルックスが良いといった人に備わった能力のようなものを指す。
存在価値・・・人格、存在そのもの。存在価値は全人類平等にあるもの。
劣等感というのは「人と比較」することで生まれることは前項の「要因」で解説しましたよね。この「人と比較」というのは、機能価値を比較していませんか?
劣等感を感じてしまうときの過程で、機能価値で判断して、自らの機能価値だけではなく、存在価値をも否定してしまうのです。
存在価値が意味することをみてみればなんとなくわかると思いますが、存在価値というのは失われることもなければ、価値が低くなるということもないのです。”存在している”ということ自体に価値があるのですから。
何が言いたいのかと言いますと、たとえ他人の機能価値と自分の機能価値を比べて”劣等感”を感じたところで、自分自身にもともと存在する存在価値は減らされることはないのです。
このように、自分の中に絶対的な”価値”が存在するとわかれば、たとえ他者と機能価値に違いがあったとしても感じ方が変わってきませんか?
「もし上司がアドラーだったら」のアドさんはこうも言っていました。
「存在価値が高まれば、機能価値も高まる。」
これはまさにマザーテレサさんの名言である
「思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。」
「言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。」
「行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。」
「習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。」
「性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。」
に重なるものがあるのではないでしょうか。
自分の基準を見直す

劣等感を抱いてしまう要因の一つに「常に高い意識を持っている」というものがありましたね。
これは、自分の基準が高すぎることを意味しています。この基準を見直すことで劣等感を生み出すのを防ぐことができます。
例えば、仕事であれば「昨日上司からやっておいてと言われた仕事のみを今日片付ければ100点」といった、達成しやすい基準をもうけることです。
筆者はその日にやる仕事をB4ほどの大きな紙に書き出して、終わったら横線を引いて達成度を見える化していました。
この時の”その日にやる仕事”は事細かにしてできるだけ達成難易度を低くしていました。
もう一度自分の基準を振り返ってみてください。
”できなかったこと”ではなく”できたこと”をみる
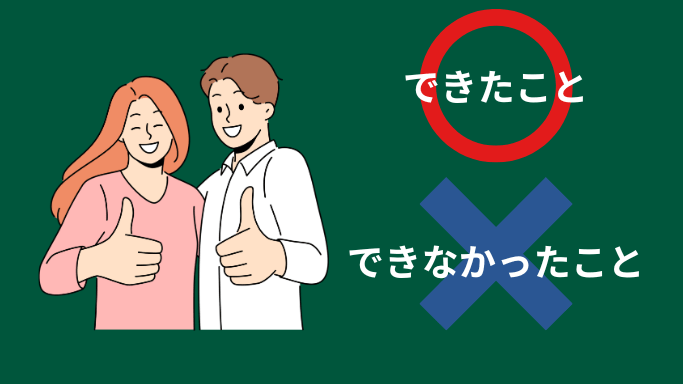
”できなかったこと”ではなく”できたこと”に焦点を当てることで、劣等感を感じても気にならなくなります。
人はプラスよりもマイナス部分を大きくみてしまいがちです。
例えば、行動心理学の一つに「プロスペクト理論」というものがあります。
「プロスペクト理論」とは、人は損失に対して過剰に評価する傾向にあり、現実の損得と心理的な損得とが一致しないということを指します。
参照元:一般社団法人 日本経営心理士協会
自分ができているものは意外と多いものです。それこそできなかったことよりもです。
できなかったというマイナスな面をみてしまうとき、意識して「できたこと」に注目してみてください。
そうすれば”劣等感”を感じてしまったとしても、できていることの多さに気付いた嬉しさが上回り、乗り越えることができます。
自分を肯定することに抵抗を持たない
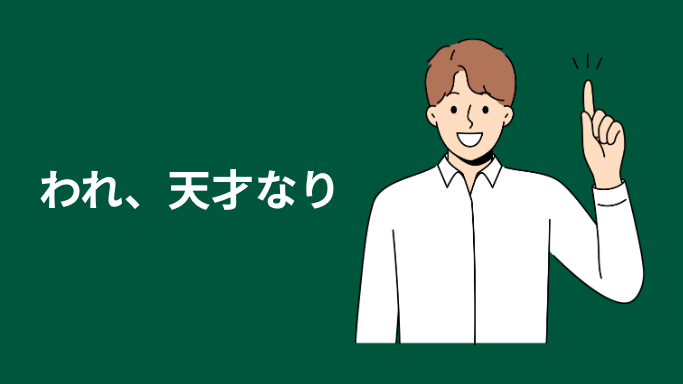
そして、どうか自分を肯定することに抵抗を持たないでください。
自分を肯定することというのは、こっ恥ずかしさもあり、普段肯定することがないと、どうやって肯定したら良いのかわからないなんて言う”気持ちの抵抗”があります。
劣等感を感じているときに、意識的に自分を肯定するクセをつければ、劣等感を感じなくなります。
筆者はよく声に出して「自分って天才だな」と言っています。もちろん一人の時限定ですが。
これを続けていれば声に出さなくても自然に自分を肯定することができ、劣等感をはねのけることができます。
フィードバックをもらう

劣等感を感じてしまう要因に、「自分自身の至らなさ」というものが有りましたが、確かにどうしても自分自身の評価は厳しくなりがちです。
ですが、はたから見ると、自己評価よりもできていること、成長していることはたくさんあります。
これは自分では見つけにくい自己評価であり、他者から得られるものです。
ですので、意識的に先輩や上司、同僚からフィードバックをもらうということが他者から見た評価を得て、自己肯定感を高め、劣等感を乗り越える方法になります。
自分を助けてくれる人と良好な関係になる
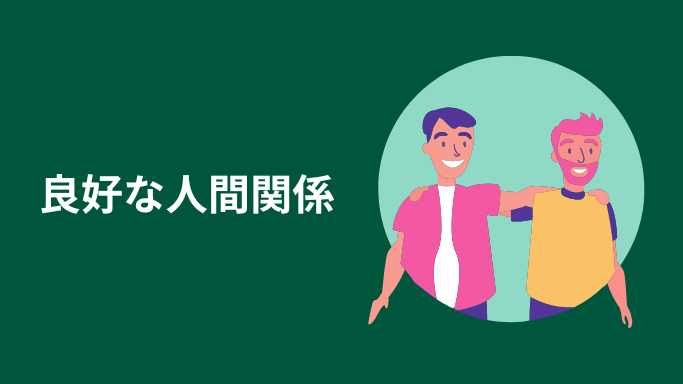
自分を助けてくれる人と良好な関係になることで、的確なフィードバックを貰え、自分自身の価値観で生んでしまった”劣等感”を乗り越えることができます。
上司や先輩、同僚からの良いフィードバックは自己肯定感をあげるキッカケとなり、劣等感を乗り越えることができるとお伝えしましが、まずは、上司や先輩、同僚という自分を助けてくれる人と良好な関係になることが一工程必要です。
上司や先輩、同僚と良好な関係になるヒントとなる記事を添付します。参考にしてみてください。
人間関係を良好にするヒント記事
専門知識を得る
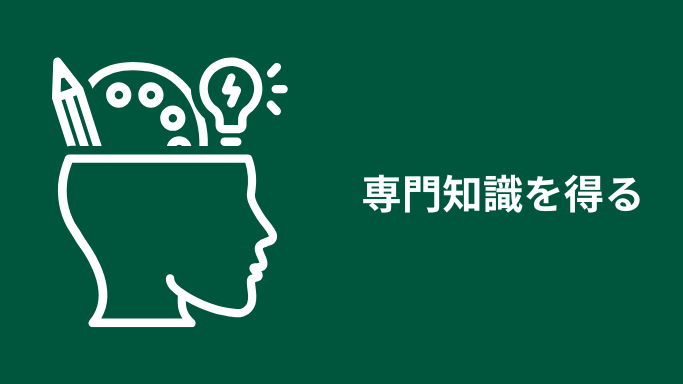
「目に見える結果がなければ自分に自信が持てない…」という方におすすめな劣等感を乗り越える方法の一つに、”専門知識を得る”ということがあげられます。
まさに”目に見える結果”です。
専門知識を持つことで、人や会社から頼られる場面が増えるでしょう。そのような周囲から頼られる環境になることで、劣等感を乗り越えることができます。
人は成長しているということを知っておく

人は意外と自分が思っているよりも気づかぬうちに日々成長しています。
例えば、朝の通勤電車でどこから乗れば会社への最寄り駅の中の出入り口階段に近いのかというのが日々の通勤をしていたら何となく分かってくるように、日々何か無意識に気付き、学んで、できることを増やしています。
ですので、どうか自分に自信を持って劣等感に負けないでください。
劣等感を感じた時にやってしまうNG行為

劣等感を感じたときにどうしてもやってしまうことがあります。
ですが、この劣等感を感じているときの行為が周囲の人を傷つけてしまったり、自分自身を傷つけてしまうということに繋がって悪循環に陥ってしまいます。
以下のNG行為に気をつけてください。
・ネガティブを振りまく
・頑張っている自分を否定する
・上手くいっている人を陥れる
ネガティブを振りまく
劣等感に苛まれ、思考がすべてネガティブになってしまうことで、周囲にもネガティブを放出してしまうことがあります。
ネガティブを放出するというと…
・態度がそっけなくなってしまう
・ついつい否定語を使ってしまう
・行動が消極的になってしまう
といった行為です。
ネガティブを放出してしまうことで周囲が気を使うようになってしまったり、仕事が任せられなくなってしまうといった、さらに劣等感を感じてしまうことになる環境が生まれてしまうかもしれません。
劣等感によりネガティブになっていることに気がつくことが大切です。
頑張っている自分を否定する
劣等感に苛まれてしまうと、頑張っている自分をついつい否定してしまいます。
「なんでこんな事もできないんだろう」
「年下はできているのに自分はできないなんてダメだ」
そんなことはありません。何事もあなたにしかできないこと、できるようになっていることはあります。
劣等感に感情を支配されないようにすることが大切です。
行動が消極的になってしまう
劣等感を感じてしまうと、ついつい行動が消極的になってしまいます。
それは「自分ではどうせできない」と自己否定に陥ってしまうからです。
劣等感を感じているときに上司や先輩から新しい仕事を頼まれても、この自己否定があることによって、受けづらくなってしまい、最悪拒否してしまうということも起こりえます。
このように行動が消極的になってしまうと仕事を任せられる機会が減っていき、周囲へ仕事へ振られているのをみることで新たな劣等感を生んでしまいます。
劣等感を感じても、継続的に感じないように、意識して行動が消極的になっていないかに気をつけるということが大切でしょう。
NG行為をしてしまわないために
上記のNG行為をしてしまわないように、今回紹介した劣等感を乗り越える方法を活用してみてください。
とくにおすすめなのが、エピクテトス哲学の「自分で制御できないことに意識を向けない」という思考です。
この思考法は筆者も普段から仕事で失敗したときや、自分ではどうしようもできないことに打ちのめされそうな時に用いて、自分を責めないようにしています。
そして、今すぐにでも使えるということもおすすめポイントの一つです。
ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
今回は”劣等感”を感じたときの乗り越える方法を解説しました。
今回の内容をざっとまとめると以下になります。
・エピクテトス哲学を参考にする
・アドラー心理学を活用する
・自分の基準を見直す
・”できなかったこと”ではなく”できたこと”をみる
・自分を肯定することに抵抗を持たない
・主体性を持つ
・フィードバックをもらう
・自分を助けてくれる人と良好な関係になる
・専門知識を得る
・人は成長しているということを知っておく
筆者も実際に意識して用いていることですので、参考になれば嬉しいです。
仕事というのは”お金”が発生するものですので、どうしてもシビアになってしまいます。”評価”や”結果”が重要であるという考えも致し方有りません。そんな大変な環境ですが、どんなに周囲の評価が低くても、自分自身の価値は消えることは有りません。
たとえ劣等感を感じても負けずに、逆に劣等感を利用してやる思考で一緒に頑張りましょう。あ、ですが、無理をしすぎない程度に頑張ることが重要ですよ。
筆者の大事にしている考えです。体が資本ですからね。

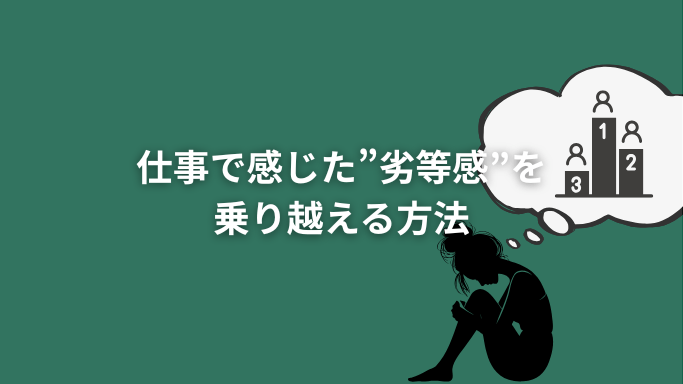

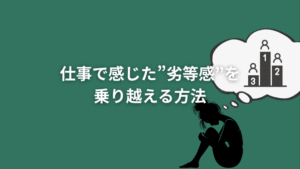

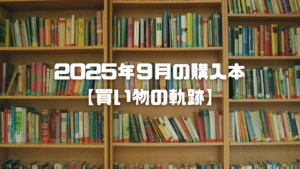
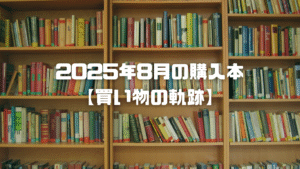


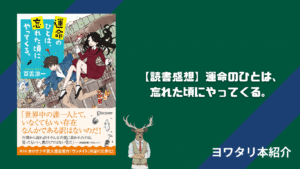
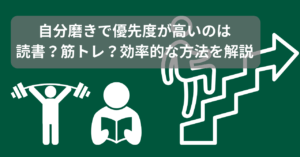
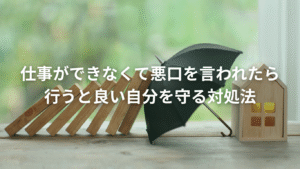

コメントする