筆者だ。
社会人になって、挨拶や名刺の渡し方、電話の取り方などなど様々な研修を受けると思いますが、その数多くの研修の中で、「メラビアンの法則」という心理学の理論を学んだ方もいるのではないでしょうか。
ただ、研修を受けただけでは、いざ実践となった時に頭ではわかっているけれど、実際に上手く扱えるかどうか不安に思いませんか?
今回はその不安を解消すべく、「メラビアンの法則」の解説と法人営業の現場で実際にこの法則を活かして成果を出した筆者の体験をもとに、わかりやすく実践方法をお伝えします。
筆者は実際にこの心理作用がうまくはたらき、”営業が上手くいってしまった”という内向的な筆者にとって驚くべき結果へと辿り着きました。ですので、ぜひ今回の解説は経験則に基づくものであり、かなり実践的なないようなんじゃないかと思います。

文筆家
たくしん
takushin
プロフィール
- 野球歴13年
- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験
- 吃音症歴20年
- 元オートローン営業マン
- 元オーダースーツフィッター
- 元百貨店販売員
- 現Webマーケター
- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味
- 酒は飲めない、よく体調崩す人
- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間
メラビアンの法則は法人営業で使えるのか
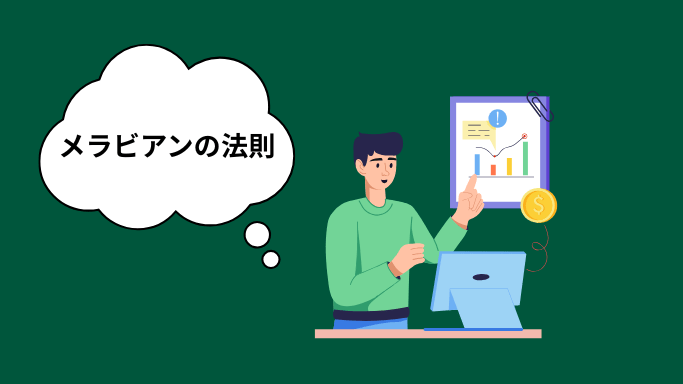
もし、営業の研修などで「メラビアンの法則」を習った方で、「ほんとにこんな小手先なテクニック使えるのかよ」と感じた方がいるのではないでしょうか?
実際に筆者も新社会人での研修のときにメラビアンの法則について講師の方から教わったときに、「なんやねん、この小手先な技術は。実践で使えないやろ」と考えていた一人であります。
ですが、法人営業を経験した今だから言えます。
”メラビアンの法則”という心理的作用を利用したコミュニケーションテクニックは、実践の法人営業で使うことができます。
むしろ、ちゃんと意識して使ったら本当に良い結果に結びつくことがわかりました。
筆者は実際にメラビアンの法則に基づいた行動をしたことによって、「新規契約件数」の営業成績の指標の1つで同期で入社した営業の中で1位を獲得したことがあります。
実際に結果に繋がっていることから、「メラビアンの法則」は法人営業で使えるテクだと言っても過言ではないでしょう。
実体験の話は下で紹介しています。ご覧になりたい方はこちらのリンクから辿ってみてください。
では、「メラビアンの法則」について詳しく解説していきたいと思います。
メラビアンの法則とは
もうすでにご存じの方もいるかも知れませんが、念の為解説しますね。
「メラビアンの法則」とは、心理学者の”アルバート・メラビアン”さんが提唱した、”相手に与える情報の割合”の法則のことです。
簡単にわかるようにポイントを箇条書きにしてみます。
・相手に影響を与える情報の割合は「”言語情報”が7%」「”聴覚情報”が38%」「”視覚情報”が55%」
・言語情報と非言語情報が矛盾した時、非言語情報が優先される
・メラビアンの法則は万能ではない
メラビアンの法則は”視覚情報”が相手に与える情報の中で一番大きいから、”見た目”を大事にしなきゃ!と思いがちですが、実はその認識だと「メラビアンの法則」を上手く使い、法人営業を成功に繋げることは難しくなります。
法人営業でうまく使うにはアルバート・メラビアンさんが本当に伝えたいであろう”メラビアンの法則の本質”を理解しなければいけません。ですので、まずはアルバート・メラビアンさんが行った実験を一緒にみてみましょう。
アルバート・メラビアンさんの実験
アルバート・メラビアンさんが行った実験は2つ。
1つは「言葉と声のトーンの矛盾について」。もう1つは「言葉と表情の矛盾について」という2つのコミュニケーションにおいての”矛盾”について実験で調べました。
「言葉と声のトーンの矛盾について」
実験内容:被験者に中立的な意味を持つ単語(おそらく、たぶん等)を好意的、中立的、否定的な3つの声のトーンで読み上げてもらって、被験者が言う言葉を聞いた人がどう感じたのか?を調べた。
結果:声のトーンが中立的な言葉の意味そのものよりも、感情に影響を与えたことが分かった。つまり、好意的に言ったときは好意的に感じるし、否定的に言ったときは否定的に感じるってこと!
「言葉と表情の矛盾について」
実験内容:被験者に人が写っている写真を見せる。写真を見せるときにその見せた写真と一致、または不一致の好意的、中立的、否定的な言葉を流した。例えば、「表情は笑っていて、言葉は否定的なことが流れている」など。その表情と言葉が一致しているときと、一致していないときに、どちらのパターンのほうが感情に影響しているのかを調べた。
結果:写真に写った人の表情のほうが感情に影響を及ぼすことが分かった。
これらの実験から、メラビアンさんは、行動が矛盾している中で、相手に影響を与える情報の割合は「”言語情報”が7%」「”聴覚情報”が38%」「”視覚情報”が55%」である。ということを示したんです。
さらに、特に感情や好意、嫌悪などと言った人の心情を読み取るときには、人は言葉よりも、見た目や声色からの情報を優先して判断材料とするということがわかります。
この”心情を読み取る時見た目や声色からの情報を優先して〜”の部分は大事なので覚えておいてください。
メラビアンの法則の誤解
ここが特に重要なポイントです。
もしかすると、「営業ではメラビアンの法則というテクニックが有効です。」と研修で教わって、「メラビアンの法則はどこでも使える万能心理テクニックなんだ!」と思ってしまっているかもしれませんが、それはとんでもない誤解でございます。
アルバート・メラビアンさんの実験結果から、メラビアンの法則の大事なポイントを読み取ることができます。
メラビアンの法則は”言語情報、聴覚情報、視覚情報の3つが矛盾しているという条件下で、どの情報が優先した判断材料になるか”というものです。
あくまでも”矛盾している条件下”です。
例えば、竹内直人の「笑いながら怒る人」という芸をみてみてください。(知らない人は検索してネ!)
これをみて「わぁこの人怒ってるな…。」なんて思わないですよね?では、”怒っていない”と判断した材料はなんなのか、それは”笑顔”という表情です。つまり、メラビアンの法則内の「視覚情報」になります。
ですので、「メラビアンの法則万能説」は適切ではないでしょう。メラビアンさんも「あぁ…。ほんとは違うのに…。」と思っているかもしれませんからね。
まとめると…
・メラビアンの法則は「言語情報」「聴覚情報」「視覚情報」の矛盾下でどの情報が優先した判断材料となるのかを示したもの
・特に心情を汲み取る上で人は視覚情報や聴覚情報といった情報を判断材料とする
ということになります。
営業においては、緊張やスケジュールがタイトになってしまったりと様々な環境に置かれることから、この3つの情報が矛盾することは少なくありません。
だから、「メラビアンの法則」というのは営業において重要視されているのです。そのことを踏まえて、活用方法を解説していきたいと思います。
活用するうえでの注意点
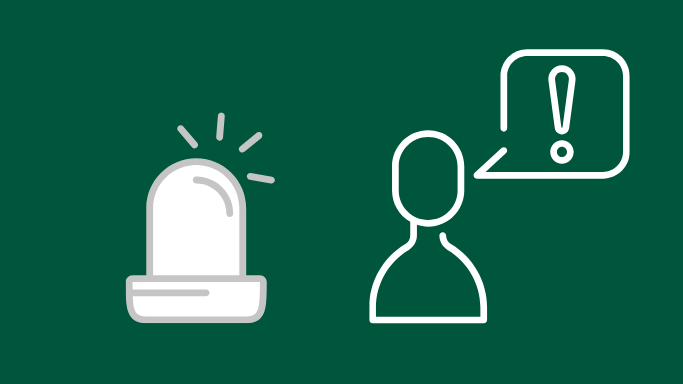
それでは、実際にメラビアンの法則の活用方法を解説していきたいと思います。と、その前に、メラビアンの法則を活用するうえでの注意点を先に紹介します。
注意点を理解しておけば、活用する時にミスが起きにくいので、ぜひ参考にしてみてください。
注意点は4つ
①メラビアンの法則は矛盾下で発生すること
②ボディランゲージを使うこと
③視覚情報に頼りすぎない
④誤魔化そうとしない
①メラビアンの法則は矛盾下で発生すること
何度もお伝えして申し訳ございませんが、「メラビアンの法則は、言語情報、聴覚情報、視覚情報が矛盾しているという条件下」で発生します。
ですので、どこでもかんでも「メラビアンの法則を意識してやるぞ!」と考えてはかえって柔軟なコミュニケーションが営業相手にできず、空回りすることになるのでお気をつけください。
②ボディランゲージを使うこと
視覚情報というのは、表情の他に非言語情報があります。
非言語情報とは、ジェスチャーやリアクションといった行動で相手に感情などを伝えるコミュニケーションの一つです。
つまり、法人営業で、取引先と話す時には会話だけではなく、体を使ったボディーランゲージがメラビアンの法則から言うと大事ということがわかります。
ですので、恥ずかしがらずにボディーランゲージを意識的に行うことにチャレンジしてみてください。
③視覚情報に頼りすぎない
「メラビアンの法則は神だ!!」なんて思っていると、視覚情報にスキルを全振りなんてことをしてしまいます。
視覚情報に頼りすぎて、言葉や声のトーンが蔑ろになり、メラビアンの法則が覆ってしまい、「視覚情報は完璧だったのに、取引先と上手くいかなかった…。」なんてことが起きてしまいます。
なので、決して視覚情報だけに頼りすぎず、言語情報や聴覚情報にも注力してみてください。
④誤魔化そうとしない
筆者もやってしまいがちだったんですが、法人営業中にミスをしてしまった時に、取引先へ説明をするときにできるだけ傷口を浅くしたいがために、変に誤魔化して伝えたりしてしまうことがあるかもしれません。(筆者だけかもしれませんが)
変に誤魔化そうとすると、言葉ではなんとか誤魔化しているのにも関わらず、表情や仕草、声色で誤魔化しが相手に見透かされてしまい、より怒られてしまうというメラビアンの法則が悪い方向へはたらいてしまうということがあります。
ですので、筆者のように何事も誤魔化さないようにしましょう。
法人営業での実践方法
それでは法人営業のシチュエーション別にメラビアンを活用する方法を紹介していきたいと思います。紹介するシチュエーションはこちら。
・法人営業で取引先と初対面時の挨拶
・法人営業で初めて取引先との商談のアポイント電話時
・法人営業のルート営業時の挨拶回りの時
・既存契約店と新しい商品の案内を行う時
・電話で新規契約のやり時を行う時
・電話で商談を行う時
6つのシチュエーションでのメラビアンの法則の活用方法を紹介します。
法人営業で取引先と初対面時の挨拶
法人営業で取引先と新しく契約をし、初めて営業に回るとき、取引先の担当者とは初対面になりますね。
その時にメラビアンの法則をもとに挨拶をすることで、相手へ信頼感を与えることができます。
具体的には、初対面時は誰でも緊張してしまうものです。その緊張から声が小さくなってしまい、元気がないような印象を与えてしまったり、身だしなみまで気が回らなくなってしまう。
そんなことが起きてしまう可能性があります。
メラビアンの法則では、言語・聴覚・視覚の各情報の矛盾により情報の判断材料に優先順位ができてしまうんでしたよね。
ですので緊張してしまう場面だからこそ、相手が判断しやすい視覚→聴覚→言語情報の順に意識を振り分けていくことがポイントです。
法人営業で初めての挨拶の時は「身だしなみが整っているか」「声はできるだけ大きくを意識する」この2つを気をつけることで、たとえ言語情報がうまくいかないという矛盾が生じても、視覚と聴覚情報で相手に良い印象を与えることができます。
法人営業で初めて取引先との商談のアポイント電話時
法人営業は何も対面だけではありません。
取引先との商談は今や電話でも行います。そして、初めて対面する前は取引先と自分のスケジュールを合わせるために合う約束をするというアポイント取りが必要になります。
対面では有りませんが、ここでもメラビアンの法則を活用することはできます。
電話ではボディーランゲージなどの非言語コミュニケーションは通用しづらいです。では、何をどうしてメラビアンの法則を活用するのか。それは、”聴覚情報”に意識を持っていくことです。
初めてのアポイント取りは緊張して話す文が変になってしまう可能性が高いです。それをカバーして相手に良い印象を与えるのは、声色です。つまり、聴覚情報です。
明るく元気よく話すことで、たとえ少し話すことが変だとしても相手が不快になることは少なくなります。
法人営業のルート営業時の挨拶回りの時
法人営業では”ルート営業”がありますよね。日々取引先へ挨拶をして案件をいただくという業務です。
このときにもメラビアンの法則を活用することができます。
ルート営業だとどうしても一日に多くの取引先へ回らないといけない場面があります。そんな時は身だしなみなどの視覚情報が乱れやすくなってしまい、いくら良い情報を取引先へ伝えても信用されにくくなってしまいます。
これはメラビアンの法則が悪い方へ作用した場合です。
悪い方へ作用しないように、視覚・聴覚・言語情報に矛盾がないように注意することが大切です。
既存契約店と新しい商品の案内を行う時
法人営業では既存の契約店に新しい自社取扱商品を案内する必要がある場面に出くわします。
その新しい商品を案内するときに、メラビアンの法則を意識することが大切です。
ルート営業での挨拶周りと同様ですが、いくら良い商品を案内しても、身だしなみが崩れていたり、口調がずさんであったりしてしまうと、取引先は「よし買おう!」とはなりにくいです。
新しい良い商品を使ってもらうためにも悪い方向へメラビアンの法則がはたらかないように、さらには、拙い商品説明だとしても新商品を使ってもらうためにできるだけ視覚情報や聴覚情報をしっかりとすることが大切です。
電話で新規契約のやり時を行う時
電話でのアポイント取りはよくあると思いますが、最近では電話で新規契約をするというのも増えているらしいですね。
筆者が働いていた企業でも電話で新規契約をするという業務が有りました。もちろん筆者も電話で何件か新規契約をとりました。
ここでもやはり、メラビアンの法則に気をつけなければなりません。初めてのアポイント取りと同様、声色には注意です。さらに、”新規契約”ですので、言語情報にも慎重にならないといけません。
声色が暗くならないよう、相手にちゃんと契約内容が伝わるように意識すると良いでしょう。
電話で商談を行う時
既存契約内容の確認や、問い合わせが電話でくる場合があります。
このときもメラビアンの法則を忘れてはいけません。
対応の話の内容はしっかりとしているのにもかかわらず、元気がない口調で話したり、忙しそうな口調をして話したりすると、相手は聴覚情報をもとに「自分の会社はないがしろにされているのか??」と不信感に繋がってしまいます。
相手の不信感に繋がらないような口調で商談内容に取り組んでみてください。
具体的な実践方法

”メラビアンの法則を意識する”というのは具体的にどうすれば良いのか?という疑問に答えるために具体的な実践方法を紹介してみます。
視覚情報、聴覚情報、言語情報の3つのカテゴリに分けてお答えしますね。
視覚情報の実践方法
視覚情報の実践方法では4つを抑えると良いでしょう。
・身だしなみ
・表情や目線
・非言語コミュニケーション
これらを意識することでメラビアンの法則が作用したときに相手へ良い印象を与えることに繋がります。
身だしなみ
メラビアンの法則では言語情報、聴覚情報、視覚情報の矛盾下では、「”言語情報”が7%」「”聴覚情報”が38%」「”視覚情報”が55%」の割合で情報を得るんでしたよね。
この中の視覚情報とはどんな情報なのかと考えた時に瞬時に思い浮かぶのが”身だしなみ”です。
身だしなみを整えることで、3つの情報が矛盾したとしても情報伝達の割合が多い視覚情報で良い印象を与えることができます。
ただし、「身だしなみさえ良ければ大丈夫だ!」とは考えないようにしなければ、言語情報と聴覚情報が悪いときに悪い印象を与えてしまうかもしれませんので気をつけてください。
良い印象を与える身だしなみについては、別記事でも何個か紹介していますのでそちらも参考にしてみてください。
身だしなみに関する記事
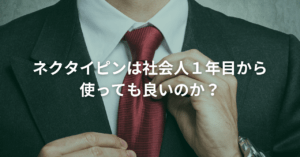
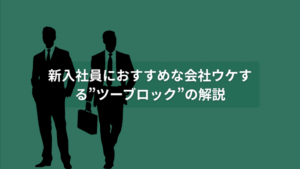
表情や目線
視覚情報では、身だしなみだけではなく、「表情や目線」も重要になってきます。
表情は笑顔であったり、口角が上がっていたりとポジティブな印象を与えるような表情が良いでしょう。
目線においては、伏せ目がちだとどうしても良い印象に映りづらいです。ですので、しっかりと相手の目を見て会話をすることを心がけることで、目線で良い印象を与えやすくなります。
ただ、相手の目を見ることを意識しすぎて睨まないように注意してくださいね。
非言語コミュニケーション
非言語コミュニケーションとは、ジェスチャーやリアクションなどの言葉で表現するコミュニケーション方法ではなく、体などを使って表現するコミュニケーション方法です。
例えば、会話の中で相手が言ったことに反応する場面で、どちらの方が「驚いている」と相手に伝えることができるでしょう。
①絵文字のびっくりのように目を大きく開けて「それは、すごいですね」と言う
②何も動作もせずに「それは、すごいですね」と言う
わかりにくい例で大変申し訳ありませんが、筆者の経験上、目を大きく開くリアクションをした方が、「驚いている感」を相手に与えることができます。
また、会話の時に言葉だけでなく、ジェスチャーを入れることで一生懸命さという良い印象も与えることができます。
聴覚情報の実践方法
聴覚情報の実践方法では2つを抑えると良いでしょう。
・声のトーン、速さ、ボリューム
・話し方
声のトーン、速さ、ボリューム
取引先と会話をする時には、声のトーンや速さ、ボリュームが大切になってきます。
声のトーンでは、暗いトーンで話していると相手に「元気がないのかな」と思わせてしまいますし、速さが速いと、「急いでいるのかな」と思わせてしまいます。
さらに、声のボリュームが小さいと、これまた「元気がないのかな」とマイナスな印象を与えてしまいます。
ここで意識することは、「明るさ」と「相手に合わせた会話スピード」です。
「明るさ」を出すことで、相手にポジティブな印象を与え、「相手に合わせたスピード」で会話をすることで、相手に不快感を与えずにすみます。
話し方
取引先との話し方も重要です。
ちょっと大袈裟な例ですが、見た目は清潔で明るいにも関わらず、話し方がボソボソとしていると、見た目という視覚情報は良くなりますが、聴覚情報である話し方でマイナスな印象を与えてしまい、結果、あまり良い印象を与えることができなくなってしまう可能性があります。
話し方はハキハキと、曖昧さを残さないように話すと相手に良い印象を与えることができるでしょう。
言語情報の実践方法
言語情報の実践方法では3つを抑えると良いでしょう。
・言葉
・ストーリーテリングを使ってみる
・簡潔かつ具体的を意識
言葉
言葉そのものです。
例えば、言葉遣いが軽い言葉ばかり使っていたとしましょう。そうすると、相手に「ノリが学生みたいだな」と感じられてしまい、もし、視覚情報や聴覚情報があまり良くなかった時、不信感につながってしまうかもしれません。
法人営業での取引先との会話では、最低限の言葉使いで臨むことが大切と言えます。
最低限の言葉使いとは、敬語をちゃんと使ったり、「◯◯っす」のようなイナズマイレブンの壁山のような話し方はやめたほうが無難でしょう。(イナイレを知らない人はぜひ観てくれ)
ストーリーテリングを使ってみる
ストーリーテリングとは、相手に伝えたいことを自分の経験などを介して伝えていく手法です。
簡単に言うと、「物語を通して物事を伝える」方法です。
これを使うことで、相手との価値観の共有にもなり、質が高いコミュニケーションがとれます。
ここでの実体験と言う物語で印象が良い経験をベースに相手に伝えたいことを語れば、相手に良い印象を与えることができます。
逆にここで、視覚情報や聴覚情報は印象が良いのに、「昔はヤンキーで先生を10人ぶっ倒して気がついたんです。こんな不毛なことやっても意味ないな。って」という何ともひどいストーリーを相手に伝えることで一気に悪い印象を与えてしまうかもしれません。
なるべく良い経験から伝えたいことを語ると安心です。
簡潔かつ具体的を意識
言葉が長ったらしくては、相手は嫌な気持ちになるかもしれません。
しかし、長い言葉が必要なとき(商談、契約など)は必ずしも当てはまるとは限りません。
ですが、法人営業で取引先とコミュニケーションを図る時には、長い言葉で話しをしていては相手が良い印象を受けるかと言ったら、良い印象を受けないことのほうが多いのではないでしょうか。
ですので、「要点は簡潔に、相手に伝えやすく」を意識することで、言語情報で良い印象を与えることができるでしょう。
筆者の経験
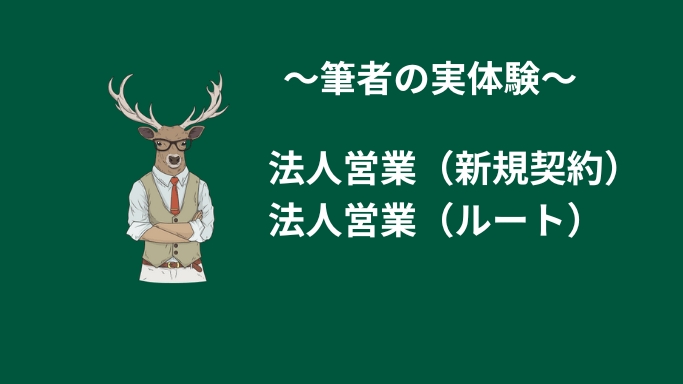
ここまで、「法人営業でのメラビアンの法則の活用方法」だったり、「メラビアンの法則の注意点」だったりをつらつらと紹介してきましたが、実際筆者はどうだったのかを知りたい人のために、筆者の実体験を紹介していきたいと思います。
冒頭でもお伝えしたとおり、筆者はメラビアンの法則が上手く作用して、新規営業契約件数で同期内No. 1を得ることができました。
もちろん、決してこの過去の栄光は筆者自身だけの力ではないことは確かですが、その中でも筆者が実践して効果があったなと思うことの一つが「メラビアンの法則」が上手く働いたことなんじゃないかと思うわけです。
そう思う根拠となる経験を紹介してみたいと思います。
法人営業(新規契約)
筆者は車の販売店さんに対して法人営業を行っておりました。
さらに、新しい取引先も多く開拓していきました。その時の新規契約獲得するための営業で大事に感じたのは、”見た目”です。
メラビアンの法則でいう「視覚情報」です。
当時は、スーツをビシッと着て、カバンもかっちりとした綺麗なものを持って飛び込み営業を行っていました。
※飛び込み営業=会う約束なしで突然店を訪問して営業をかけること
すると、なんの会社なのかは名乗りましたが、商品の説明をしていないにも関わらず、商品の説明を聞いていただけるという機会が多かったのです。
ここだけ聞くと、メラビアンの法則がはたらいているのかわかりませんが、もう一つ新規開拓の時に、新規の契約を取り来ているわけですから、申し訳なさといいますか、控えめと言いますか、なんとも弱々しく営業訪問していたときもあったわけです。
そんな時でも新規の契約の商談まで漕ぎ着けて、契約まで獲得するという結果を得ることができたのは、視覚情報=誠実さ、聴覚情報=弱々しいの矛盾から、誠実さが優先されたことによる副産物なのではないかと振り返ると考えられるわけです。
法人営業(ルート)
メラビアンの法則がはたらいていたのは、新規契約の営業だけではありません。
筆者は法人営業で「ルート営業」を行っておりました。ルート営業とは、既存の顧客に定期的に訪問して商品のアフターフォローや新しい案件の紹介をする営業方法です。
ルート営業は基本的に毎日行いますから、どうしても体の調子やその日の気分なんかで元気がない日や、忙しくて対応が淡白になってしまう日があるわけです。
その中で筆者はいつもスーツをビシッと着て、髪型もツーブロック短髪のおでこ出しtheビジネスマンの格好で営業をしていました。
このように視覚情報である”身だしなみ”に気を使いできるだけ誠実に見えるようにしようとした結果、ルート営業時の訪問で忙しくて淡白な対応をしてしまったとしても、「今日もちゃんとしてるね」などの誠実さという印象をを与えられているであろう言葉を取引先様からもらうことができていました。
とどのつまり、メラビアンの法則は初対面のときでなくとも効果があるのではないかという気付きをこの経験からわかったのです。
メラビアンの法則を身につける方法
「メラビアンの法則について分かったし、実践方法も何となく分かった。だけど、本当に自分で実践で使えるかな…。」と不安に思っている方に、筆者が実際に新社会人時代の営業でメラビアンの法則を実践できるようになったキッカケと、方法をお伝えしたいと思います。
参考にしてみてください。
メラビアンの法則の身につけ方
まず、メラビアンの法則が息を吸うようにできるようになる方法をお伝えします。
簡単に言いますと2つあります。
①何度も意識して行う
②その場その場ではなく常日頃から意識する
この2つです。
メラビアンの法則に限らず、どんな技術においても一朝一夕で身につけることは難しいです。まあ、一番はこの記事を読んで次の日にできるようになった!となってくれるのが一番嬉しいですが、なかなか難しいと言えるでしょう。
ですので、「メラビアンの法則」を日々意識し、仕事だけではなく、普段からも見た目に気を遣ったり、明るさを意識して過ごしたり、言葉使いを正しくして相手に良い印象を与えるということが、無意識下でもメラビアンの法則がはたらくようにすることができる方法だと言えます。
他の場面でも使える
今回は「営業」の中でも特に”法人営業”でのメラビアン法則を活用することを実例を用いて解説しましたが、なにも「法事営業」だけでしか使えないというわけではありません。
例えば…
・個人営業
・社内での人間関係作り
・プライベートでの人間関係作り
・アルバイト
など仕事だけでなく、日々の生活の中であったり、会社に勤めるときだけではなく、学生時のアルバイトの時でも活用することができます。
筆者は法人営業だけではなく、個人営業であったり、接客アルバイトの経験もあります。ですので、法人営業以外の場面での活用法も紹介してみたいと思います。
まとめ
「メラビアンの法則」という心理学の理論は、あくまでも「言語情報と非言語情報が矛盾している時」という条件下ではたらく作用です。
確かに大事な知識ではありますが、何よりも大事なのは「どうすれば自分の伝えたいことが相手に上手く伝えられるのか」ということです。
「相手にどんな印象をもたれたいのか」ということを今一度確認し、今回のメラビアンの法則を意識しつつ、法人営業に臨めば、必然的に何かしらの結果と出会うことができます。
筆者のように内向的な人間でも、この法則を理解し、地道に実践していけば、相手からの信頼を得ることができ、成果を出すことは十分に可能だと言えます。
相手に届く「伝え方」、ぜひ明日から意識してみてください。

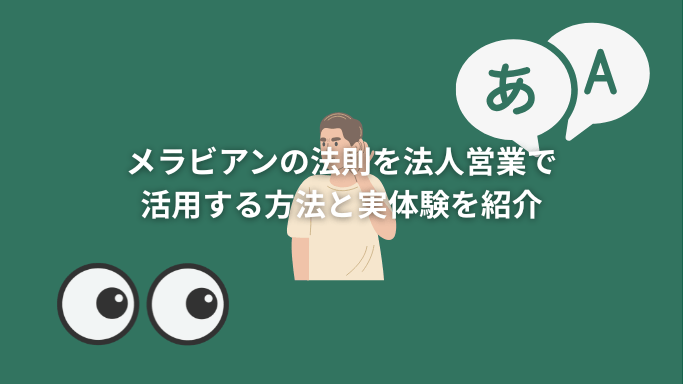
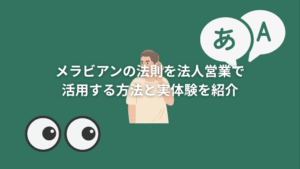


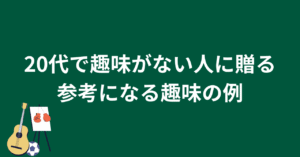

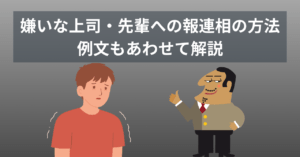
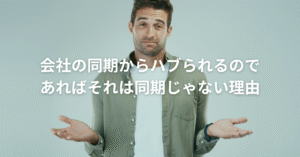

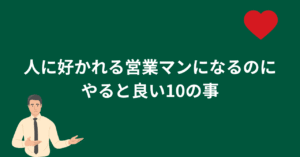
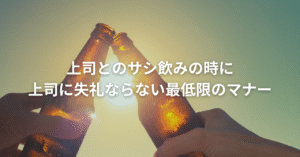
コメントする